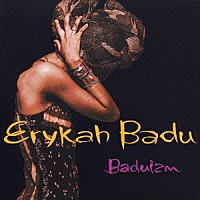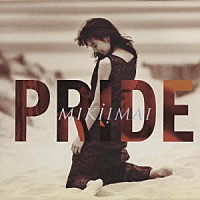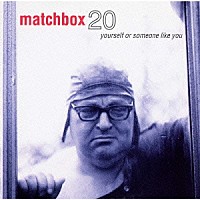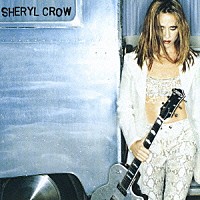FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集
ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!
TOPICS - 1997※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。
ニュースな音楽 TV CM CINEMA ★ WATCHING
エルトン・ジョンの「トゥルー・ラブ」
No.2

Photo: Redferns
やめよう、やめようと思いつつ、このところTVつけっぱなしの生活が続いている。といっても見ているわけにはいかないので、音を消して、耳はCDの方にという状態だ。ひとり部屋にいると、なんだか動く存在がないと寂しいというか、反対に落ち着かなくて。そんな風にTVをつけていると、何が多くスポットに流れているか、自然とわかってくる。最近各局のドラマ戦争がし烈になっており、ドラマの自社スポットが目立つんだけれど、その次に目をひくのが、やはりクルマCM。なかでも音を出している時に耳をひくのがエルトン・ジョンの「トゥルー・ラブ」。車のCMなのに、歌が全面にフィーチャーされていて、まるでエルトン・ジョンのCMのよう。これがかなり大量にオンエアされているのだ。そのたびに“なんておいしいCMなの”と、元レコード会社の社員としてはすぐそんなことを思ってしまう。このほか同じ会社のCMでディープ・フォレストの「フリーダム・クライ」が流れるものも、映像が素敵で音楽ともマッチしていて、見るのが楽しみ。映像にいくつかバージョンがあって、個人的にはフェリー乗り場に車が並んでいる映像が、慕情をくすぐる感じで好きだな。きっとヨーロッパのロケなんだろうけれど、南仏からアフリカへ旅立つのかなんていろいろ想像したりして。エルトン・ジョンに話を戻すと、CM自体はレコード会社にメリットがあるけれど、それに使われたことで、「LOVE SONGS」という今までにはなかったコンピレーションが発売されたことはリスナーに“おいしい”ことなのでは。
(文・服部のり子)

ミッシェル・ガン・エレファント
自分たちなりの"かっこよさ"を追求するゴツゴツしたビートにあふれたバンドここにあり
No.1
ミッシェル・ガン・エレファントの2作目『ハイ・タイム』が業界誌のチャートで13位まで上がったことは、最近の“日本のロック界”のちょっとしたニュースだった。売り上げもすでに6万枚に達しているという。もちろん、ヒットしたことがことさら意味を持つわけではないし、売り上げの数字の大きさがそのまま音楽の価値を保証するものでもない。しかし、このグループが繰りひろげるゴツゴツしたビートにあふれた(ロックを絵に書いたような)歌と演奏を聴けば、このアルバムがこんなにチャートを上がったのか、という驚きに近い感想を持つ人も多いに違いない。
FMfan 24号の「日本のロック特集」でも紹介されていたとおり、ミッシェル・ガン・エレファントはパンクとイギリスのパブ・ロックに啓発された4人組だ。そうした受けとめられ方について、グループの中心人物でボーカリストのチバユウスケは、「それは構わない。実際、ものすごく影響を受けているし、そのことを隠すつもりもない」と言う。「ハイな状態。それも、きれいな青空を見て気分が高揚するという場合だけじゃなく、ずっと下の方ばかり見ていて感情があふれてくることもある。その両方の感じ」。彼は『ハイ・タイム』というアルバム・タイトルについて、そう説明する。収められている12曲はむきだしのビートに貫かれたロック・ナンバーばかりで、熱意と倦怠が入り混じったような彼のボーカルもとても印象的だ。
「もともとはパンク・ロックをやりたくてはじめた」バンドだったが、活動をつづける過程でいまのようなスタイルに変わっていった。そうした音楽的変化について、チバは「ロックン・ロールのかっこよさ、7thコードのかっこよさが徐々にわかってきたんだと思う」と自らを分析する。もちろん、彼らのやっていることは、パンクではないが、パンクがなかったら出てこなかった音楽、という感じだ。
緊張感にあふれたプレイを聴かせるギタリストのアベフトシは、このバンドのもうひとつの核だ。感情が軋(きし)みをあげて突進するようなその演奏は、彼らの音楽をサウンド的にも感情的にも大きく高めている。「こういう音が好きだってことなんですよね、結局は。見た目(の印象)も含めて、そのかっこよさが好きだっていう……」。
彼らは“かっこよさ”という言葉を頻繁に口にする。ステージでアベのテレキャスターとギター・アンプが昔懐かしいカール・コードでつながれているのも、ステージ衣装の細身のスーツも、すべて小文字のグループ名表記も、そして60年代ブリティッシュR&Bに根を這わせようと切望するバンドの方向性も、“かっこよさ” の追求にほかならない。ミッシェル・ガン・エレファントは、新作『ハイ・タイム』を引っさげて、2月まで全国をツアーして回る。夜毎エネルギッシュなライブを繰りひろげ、自分たちの考える“かっこよさ”を観客に見せつけていることだろう。
(インタビュー、文・山本智志)
●PROFILE
チバユウスケ(Vo)、1968年7月10日神奈川県生まれ。
アベフトシ(G)、66年12月16日広島県生まれ。※2009年7月22日、急性硬膜外血腫のため死去。
ウエノコウジ(Bs)、68年3月27日広島県生まれ。
クハラカズユキ(Ds)、69年4月3日北海道生まれ。
91年に結成、渋谷や下北沢を中心にライブを行う。95年秋、インディーズで「wonder style」をリリース。96年2月、ロンドン録音の「世界の終わりに」でデビュー。同年3月にファーストアルバムを、11月にセカンドを発表。現在、NACK5の「MIDNIGHT ROCK CITY」のパーソナリティを担当。
ベイビーフェイス
世界一多忙なプロデューサーが自らの夢をかなえたソロ・アルバム
No.3
『THE DAY』・・・・・・。どこか重みがあるのに、不思議と安堵感を覚える響きのある音楽。新作に付けられたタイトル、そして全10曲に込められた思い、それはマンチャイルド、ディール時代を経て、今日までに至るベイビーフェイスの鼓動を肌で感じることができる、90年代を代表する最も優れたアルバムと言っていい。日中の最高気温が3度という寒さのシカゴの街、朝8時という早朝のインタビュー・スケジュールにもかかわらず、久しぶりに会った彼はどこまでも優しく、もの静かであり、シャイな一面をのぞかせながらも生き生きとインタビューに答えてくれた。
●E・ジョンやR・ストーンズのプロデュースも予定
「シカゴには映画で来てるんだ。『SOUL FOOD』っていう映画なんだけど、僕と妻のトレイシーで設立したEDMONDS ENTERTAINMENTが制作を手掛けている。主演はヴァネッサ・ウィリアムスで、監督は新人のジョージ・ティルマン。彼はシカゴの出身で脚本も書く。ロサンゼルスで会って脚本を読んで気に入って起用したんだ」と、相変わらず忙しいベイビーフェイスは、まさに‘’24時間眠らない男‘’と言われるだけのハード・ワーキング。映画『SOUL FOOD』のサウンドトラックも予定されており、アフター7やジョデシィといった豪華メンバーを起用するとのこと。
今回のシカゴには奥さんのトレイシー夫人と8月に生まれたばかりのブランドン君も同行。リリースされたばかりのアルバム『THE DAY』のタイトル・トラック「ザ・デイ」は、そのブランドン君の子守歌とか。
「そう、この曲はブランドンがトレイシーのお腹の中で動くのを、初めて触ったときに書いたものなんだ。うれしくて飛び上がってすぐピアノに向かって書いたのを覚えているよ」。このほかにもアルバムには、シャラマー、LL COOL J、シャニースを迎えた全米でのファースト・シングルで、シャラマーのカバーでもある。「フォー・ザ・ラバー・イン・ユー」、マライア・キャリーとケニーGが参加した日本でのリード・シングル「クローズ・マイ・アイズ」、そして憧れのスティーヴィー・ワンダーとの初の共演「ハウ・カム・ハウ・ロング」と、多彩なゲスト陣を迎えた珠玉のナンバーがラインアップされている。
「シャラマーのカバーは、LL COOL Jのアイデアなんだ。スタジオで偶然に彼に会って、バック・コーラスをやらないかっていう話になったのがきっかけ。ケニーGとマライアが参加した曲は、ケニーのアルバムにもアダルト・コンテンポラリーのスタイルで入っている。そしてマライアがテープを聴いて、バック・コーラスをやりたいって申し出てくれたんだ。スティーヴィーとの共演は夢がかなったようで素晴らしい時が過ごせたよ。僕の持ってるBRANDON’S WAY STUDIOで録音したんだけど、まずスティーヴィーが歌って、それから後半を一緒に書いた。彼が歌った部分を僕がプロデュースして、僕が歌ったのを彼がプロデュースしてくれた。本当に長年の夢がかなった思いだよ」と、笑みを浮かべながら語ってくれた。
シャラマーは、今回の起用がきっかけで、ベイビーフェイスのプロダクションによる復活という可能性も浮上、さらには今後の予定として、ヨーロッパと日本へのプロモーション・ツアー、3つの新しいアーティストのレコーディング。サウンドトラック『SOUL FOOD』の仕上げと、休む間もないハードワークが待ち構えているという。そして何よりも驚いたのが、エリック・クラプトンの「チェンジ・ザ・ワールド」のビック・ヒットをきっかけとしたロックへのアプローチの可能性について、エルトン・ジョン、ローリング・ストーンズ、フィル・コリンズといった大物アーティストの名前が飛び出したことだ。
シカゴの街を彩るクリスマス・イルミネーションの美しさにベイビーフェイスの人柄が調和した温かい雰囲気のインタビューではあったが、シャイなムードの中にも、音楽のことになると鋭い牙をむき出す天才、それがベイビーフェイスだ。
(インタビュー・文/鈴木しょう治)
メアリー J. ブライジ
ヒップホップ・クイーンの新たな旅立ち
No.11
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
いったい、パフィとの間には何が起きたのだろうか。オリジナル・アルバムとしては3作目に当たる『シェア・マイ・ワールド』では、ショーン・〝パフィ〝・コムズのクレジットは一切見当たらず、デビュー・アルバム『ホワッツ・ザ・411?』、セカンド・アルバム『マイ・ライフ』と、パフィ=メアリー・Jブライジという方程式が成り立っていただけに、最も気になる事であった。
「もう彼らとの関係は完全に私の中では絶った。だから今後パフィやチャッキー・トンプソンと関わるということは絶対にあり得ない」と、強く断言した彼女の表情はそれまでの笑顔とは一転、部屋の空気までもが張り詰めた緊張感で覆われたことが、今でも脳裏から離れない。そして、正直なところその理由は未だ明らかにされていないのだが、心機一転とも言える新作ではジャム&ルイスとの初仕事を始め、ベイビーフェイス、R・ケリー、ロドニー・ジャーキンスといったそうそうたる顔ぶれが参加している。
●偉大なアーティストや作品への敬意もこめて
そのアルバムからのファースト・シングル「ラブ・イズ・オール・ウィ・ニード」は、来日公演も好評のNASをゲスト・ラッパーに迎えた、ジャム&ルイスのプロデュースによるミッド・ファンク・ナンバー。リック・ジェームスの「ムーン・チャイルド」がサンプリングされ、ヒップホップ・クイーンとしてだけではなく、ソウル・シンガーとしてのクイーンにふさわしいメアリーの堂々たるボーカル、さらには新しいメアリー・J・ブライジが発見できる1曲だ。
また、いずれシングル・カットされるであろう「エブリシング」では、スタイリスティックスの「ユー・アー・エブリシング」と、ジェームス・ブラウン「ザ・ペイバック」をサンプリングし、歌い出しには坂本九の「SUKIYAKI」のメロディを使うというインパクトの大きい、奇抜なアイデアが生かされている。
「ジャム&ルイスはキャリアの長い人たちで、いろいろな成功を手にしている。実際に彼らの家に行って、いろいろな賞をもらったディスクが壁にかかってるのを見ると、これだけ長いキャリアを経た今でも成功し続けている彼らの偉大さが実感できたし、私もそうありたいという意味ですごく刺激になった」と、プロデューサーのジャム&ルイスに対する尊敬の思いを打ち明けた。
そして、「今では、昔の人みたいになってしまっているけど、私には彼しか思い浮かばなかった」と語るギタリスト、ジョージ・ベンソンを起用した「セブン・デイズ」や、彼女の母親が家でよく歌い、メアリーが7歳で初めてタレント・ショーに出たときに歌った、思い出のナタリー・コール・カバー「アワ・ラブ」など、メアリーの新しい旅立ちにふさわしい内容のアルバムと言える。
一見、彼女のようなタイプの人間は非常に近づきにくい部分もあり、それはある意味での女王としての風格からともいえるが、インタビューを終えて、たまたまエレベーターを待っていた彼女と遭遇した時に、「気を付けて帰ってね」と優しく声をかけてくれた笑顔を忘れない。
(インタビュー・文/鈴木しょう治)
ホイットニー・ヒューストン ライブレポート
異次元からの電流に打たれたかのようなすスリルと衝撃
No.11
[5月13日◎東京ドーム]
コンサートの開演前、ホイットニーの驚異的な人気の理由を考えていた。古今東西、数え切れない歌手の中にあって、ホイットニーはアルバムの売上で次々に記録を塗り替え、映画までも大ヒットさせる。けれども、照明が落ち舞台下からホイットにーがせりあがってきた瞬間、そんな疑問は霧散した。彼女から発せられた、ビリビリと放電する何かがドーム中に散らばって、4万3千人余りの聴衆はあっという間に征服され、飲み込まれたのだ。デビュー前、母シシーとともにチャカ・カーンのバック・コーラスを務めた、「アイム・エブリ・ウーマン」でこの夜、ホイットニーは“私がディーバよ”と宣言したのである。圧倒的な登場だった。あたかも、後戻りできないジェットコースターが走り出したような、そんなものすごいスリルを感じるショーの開始だった。そして、「オール・アット・ワンス」、「セービング・オール・マイ・ラブ」と続き、夫であるボビー・ブラウンが連れてきた、愛娘ボビー・クリスティーナに向かって、「自分の子供にこの歌を歌う日が来るなんて、不思議な気持ちよ。」と、しみじみと「グレーテスト・ラブ・オブ・オール」を歌い上げる。そのほかにも、ボビーの妹がバックで踊っていたり、甥っ子が出てきたり、旧友であるCCワイナンスがホイットニーとのゴスペル的な掛け合いを披露したりと、ファミリー総出演の観があった。この前の日に、ホイットニーとボビーの間に喧嘩があったと報じられていたが、確かにスクリーンに映し出された彼女の表情が最初変だったけれど、声にはいかなる影響もなかった。それに、ボビーも良きパパぶりを発揮したり、ホイットニーと踊ったり、「ア・ソング・フォー・ユー」を披露したりしていた。 そして、ホイットニーの新旧取り混ぜての熱唱が続くのだが、しかしなんという声なのだろう。この上なくパワフルで、甘くて、その上それ自体に生命が宿っている生きもののように、音と音の間をはいまわりながら、強力にぐいぐいと進んで行く声。それが高度な技巧からなるという事実を忘れそうになるほど、テクニックとエモーションが一体となっている。そして、声の中にリズムが生きたままにすみついている、とでも言いたいような躍動。今宵、ステージの主であるホイットニーは、だれのものでもなく自分の感じるままの、野性味あふれるホイットニー節をドーム中に響き渡らせていく。そして、最後の曲「オールウェイズ・ラブ・ユー」でそれは起こった。聴衆が息を潜めて見守る中、両手を天高くのばしたホイットニーは、まるで避雷針のように見えた。
そして彼女があの一番高い「アンド……、アーイ」という個所を歌いだしたとき、何かが彼女を通して落ちてきて、さく裂して私たちに突き刺さったのだ。それは、鳥肌の立つような瞬間だった。彼女を通して、どこか別の世界の空気が、この世に流れ出した瞬間だった。これがホイットニーの言う、少女のころ神様と交わした契約というものなのだろう。別の世界との橋渡しになること…。 この異次元までもを味方にしてしまうような圧倒的な力で、ホイットニーはいつまでもスターとして輝き続けるのだろう。そして、その彼女と同時代にいられることを喜びたくなる、幸福な夜だった。。
(リポート・門脇由佳)
●SET LISTS
1. Nippy Nine-Seven
2. I’m Every Woman
3. So Emotional
4. Dance With Somebody
5. All At One
6. Savin’ Ali My Love
7. The Greatest Love Of All
8. Queen Of The Night
9. My Name Is Not Susan
10. All The Man I Need
11. A Song For You (Bobby Brown)
12. Exhale (Shoop,Shoop)
13. Count On Me (シー・シー・ワイナンスとのデュエット)
14. (シー・シー・ワイナンスのソロ・パート)
15. I Love The Lord
16. I Go To The Rock
17. I Will Always Love You
―アンコール―
18. Step By Step
(5月13日・東京ドーム)
ニュースな音楽 TV CM CINEMA ★ WATCHING
ブライアン・フェリーの渋めの曲がマッチ。ドラマ「ギフト」主題歌
No.20
海外のニュースではブライアン・フェリーのニュー・アルバムにデイヴ・スチュアートやスクイーズのクリス・デイフォードが参加して、ロンドンでレコーディングされていることが注目されているが、やっぱり日本ではキムタク主演のドラマ「ギフト」の主題歌に選ばれたことが話題。主役高視聴率を稼げる人気者で、しかも選ばれたのが「TOKYO JOE」という、彼のレパートリーのなかでも渋めな曲なので、70年代のロック・ファンも結構驚きなのでは。当然プロデューサーの意向が反映されていると選曲だと思うが、番組のオープニングの映像にマッチしているし、「ロンバケ」と違ってダンディなスーツ姿がクールなキムタクにもこれまたハマっている、なかなかうならせるカップリングだと思う。
TVドラマのタイアップもヒット作りの必須アイテムで、このごろは新鮮味に欠けるけど、今クールは、ブライアン・フェリー以外にもジョン・レノンの「スターディング・オーバー」まで主題歌になって、ヒット戦略以外のところで楽しめる。そして、これは偶然だろうけど、ジョン・レノンも同じSMAPの香取慎吾主演のドラマ、「いちばん大切な人」の主題歌。ということは、若年層とOL層に名曲をアピールできるチャンスなのではないだろうか。実際、OL御用達の銀座のCDショップにはこれが「ギフト」の主題歌を収録したアルバムですと、ブライアン・フェリーの新しいベスト盤『TOKYO JOE~ザ・ベスト・オブ・ブライアンフェリー&ロキシー・ミュージック』がフューチャーされているそうだ。
(文/服部 のり子)
エレファントカシマシ
怒鳴らなくても気持ちは少しずつ届いていくもの・・・だからしっかり歌う
No.20
昨年8月に出た『ココロに花を』で、いきなり支持率を上げたエレファントカシマシ。移籍と言えば聞こえはいいが、要するに前の所属レコード会社から契約を切られ、まるで新人のような奔走の末、新たな契約を得るに至ったのだった。しかし、その経験が生かされた前作の成功は、彼らをまた一回り大きくしたようだ。新作『明日に向かって走れ∼月夜の歌∼』は、どこか余裕も感じさせる仕上がりだ。やはり自信を持ったのだろうか。
「下世話な話になりますが収入絶たれて、オッサン4人という感じになってたのが、まずレコードを出せた。出すことが目標だった。いろいろ新しいこともやって、プロデューサー入れたり曲のサイズを短くしたり、もっと情けないことを歌ってもいいんじゃないかとか、素直なところを出そうとか。そういうのも、自分たちなりにですけど、きちんと出せ
て、今までよりも売れた。というか届いたというのがあったんで、自信にはなったんですよ。」
前作に続きプロデュースには、バンドを数多く手掛けて定評のある佐久間正英を起用、彼の勧めで楽器面での相談役(?)として、そうる透らの協力を得たことも、今回のレコーディングでは収穫だったようだ。
「レコーディングは僕等が中心になってやるんだけど、プレイヤーの脇をサポートしたっていうんですかね。僕は人に言われると逆のことをやるっていう悪い癖があるんで(笑)人の言うことは聞かないようにしてます」
(この発言、少々意味不明ですが、当時の記録がないのでこのままで)
2、3月には続けてシングル・リリースがあったため、結局半年以上スタジオにいたような感じだと言うが、緊張感は保ちつつも和やかにレコーディングは進んだようだ。レコーディング期間が長引いたのは、タイアップ用シングルを依頼されたため、そちらを先行させることになった結果である。
●5枚目ぐらいから僕ら売れなきゃいけないのかなとか考え出して
「アルバムに関して言えば「昔の侍」と「恋人よ」って詞が長いんですけど、そういう曲を前は排除してたんです。今回はわりとヘビーな感じにもとらえられるんですけど、「昔の侍」とか「恋人よ」を入れられたってことで、僕としては変な言い方ですけど、5枚目以降のダイジェスト盤なのかなって。5枚目ぐらいから僕、一人暮らし始めたり学校卒業してたりふられちゃったり、個人的な変化もあったんで、そのへんからプロデューサー入れた方がいいのかなとか、僕ら売れなきゃいけないのかなとか考え出して。結果はでてないんですけど、今回ぐらいまで聞いた感じは全部違うんですけど、気持ち的には5枚目以降としては、これで全部完結したのかなと。」
曲を作る上でも軽やかさや聴きやすさを念頭に、スピーディーに書くことを心掛けたそうだ。その結果か作風が広がり率直さを感じさせる。
「そうかもしれない。大事にして、あんまり傷ついてほしくないなって思いながら出してた曲を、少し突き放しちゃうって言うか、放り投げるっていうか、行ってこいみたいなところで作ってる。歌い方も、前は啓蒙する!みたいのが強かったけど、今は少しずつ気持ちが届いていくものなのかなって。だから怒鳴らなくして、しっかり歌うことを心掛けた」
●このアルバムは売れたいっていうところまででワンセットなんです(笑)
自分の作品に対して少し距離を置けるようになったことも、シングル連発などをこなす原動力になったのかも知れない。
「今は特攻精神ていうか、何でもやろうって姿勢ですから。だって金がないからってバンドを持続できなかったら一番悲しいんだもん。売れたいっていうと脂っこいですけど、僕らは自負してるからアルバムもできるわけで、聴いてほしいと言うのもある。このアルバムは売れたいっていうところまででワンセットなんです」
それでも彼の血に流れているものは変わらない。だから『明日に向かって走れ』と歌う。
「でも、それだけだと猛々(たけだけ)しいんで、僕の中ではロマンティックで静の感じの「月」を、ちょっと入れて見ました」
こう言って、見せた笑顔は透き通っていた。
(インタビュー・文/今井智子)
ジャネット・ジャクソン
久々に発表されたアルバムのタイトルは[ベルベット・ロープ]
No.23
誰の心の中にも張りめぐらされているという、そのロープとは……
●ツアーの後は、自分を見つめることに時間を費やしていたわ
ジャム&ルイスとのコラボレーションによって生み出されるざん新なファンク/R&Bサウンドと、ビデオ・クリップの影響力を最大限に生かしたダンス・エンタテインメントで、多くのブラック/ポップ・ファンを楽しませてきたジャネット・ジャクソン。彼女の久々となるニュー・アルバム『ザ・ベルベット・ロープ』が約4年ぶりに完成した。
これまでも3年から4年のインターバルをとってアルバムを発表してきたジャネットのことだから、4年以上のブランクもさして不思議なことではない。が、前作『janet..』の発表とそれに合わせたツアーを行った後は、話題といえば兄マイケルのビデオ・クリップに登場したことぐらい。その動向があまり伝わってこなかったのも事実である。
ロサンゼルスはマリブビーチにあるジャネット邸を訪ねてのインタビュー。まずは、その〝不在〝について聞いてみた。もちろん軽い話題として、だったのだが……。
「ツアーが終わった後は、自分を見つめることに時間を費やしていたわ。ずっと自分の内面を見つめていたの」
いきなりズッシリとヘビーな答え。これには少々、当てが外れた思いがして、話題を変えようかとも思ったのだが。しかし、アルバムを作り終えたばかりで、この日がインタビュー初日だというジャネットは、慎重に言葉を選びながら、時に言葉を探して考えこみながら、それでも絶えることなく語り続けるのだった。
●人は誰でも特別な存在として生まれてきているのよ
「『ザ・ベルベット・ロープ』。このアルバムがすべてを表しているわ。自己の考察、自分の人生、私に起こった問題、気付いたこと、克服したいこと、そして克服したこと。ちょうどこの4年の間にこれらのことが私の心の中にわき上がってきて、私はそれらを見つめ、対処してきたの。それがさまざまな形でこのアルバムに表現されているの。だから『ザ・ベルベット・ロープ』は、私にとってもとても大切なアルバム。今まで作った中でもっともパーソナルなアルバムになったと思うの」
〝パーソナルなアルバム〝。どこかで聞いた覚えはないだろうか。そう、ジャネットは、前作『janet.』について語った時にも、この表現を使っていた。
「えぇ。でも、今回はより心の奥底から生まれてきたものなの。それに、この4年で私はずいぶん変わったわ。今までもずっと心の痛みを感じてきたの。でも、私は自分を守る方法を心得ていたのよ。心の中にベルベット・ロープを張って、苦痛から自分を守り、辛さを忘れて前に進むことができたのよ。でも、私の心の中の何かが、このベルベット・ロープを張り続けることを拒んでしまって……」
ベルベット・ロープという耳慣れない言葉には、そのような意味が込められていたのか。さらにジャネットは続ける。「それにはいろんな意味があるわ。たとえば私がレストランに行くと、たいてい差別的な扱いをまず受けるわ。でも、私がだれかがわかると、途端に態度がコロッと変わるのよ。そしてVIP待遇(笑)。彼らの心の中にもロープがあるのね。彼らが引いた、普通の人と私を隔てるロープが。そして、その場にいる人たちはロープの外に追いやられ、自分をゴミのような存在と感じてしまうかもしれない。もうロープを張るのはやめましょう。人はだれでも特別な存在として生まれてきているのよ。そのことを、新しいアイデアと革新的なスタイルのサウンドでみんなに伝えたいの」
ジャネットはこのアルバムを「自分のために作った」という。しかし、尊敬するジョニ・ミッチェルの声や、あの「チューブラー・ベルズ」(映画『エクソシスト』のテーマ)のサンプリングを含む多彩なブラック・サウンドが聴き手を受け入れる柔軟さを持っているのも事実だ。彼女は言う。「このアルバムは、多彩な音楽とさまざまな感情の混合体なのよ」と。
(インタビュー・文/染野芳輝)