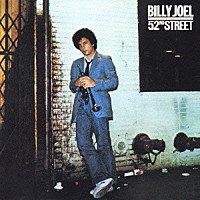FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集
ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!
TOPICS - 1979※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。
キース・ジャレット来日公演
優れた感性の即興演奏
No.2

Photo: Getty Images
キース・ジャレットが東京・日本武道館で行ったコンサートは、この大きな会場で一切のPAを排し、アコースティック・ピアノの美しいサウンドを聴かせようという意欲的な試みである。昨年の2月に、やはり同じ日本武道館でチック・コリアとハービー・ハンコックのデュオ・コンサートが行われているが、この時は補助的にPAが使用されており、その点でも今回のキース・ジャレツトのステージは注目されたわけだ。
さて、キースのコンサートは10枚組のアルバム「サンベア・コンサート」と同様に、全部が即興演奏。アンコールを含めて3曲ほどプレイを披露したわけだが、前半は50分を超える“大作”。いわばキースの心の奥に浮かんできた想い、あるいは彼が通り過ぎじっくりと見てきた風景が、ひとつの音として構成されていく。ある意味ではキースの書き下ろした私小説とでもいえるわけだが、確実なテクニックときわめて叙情的なサウンドの流れは、聴く者それぞれの想いと結びつき、聴く者のイメージを限りなく広げていく。つまり、キースのつくり出す音楽は、抽象絵画が観る者に自由な想像を与えてくれるのに似ているといえよう。
また、エレクトリック・サウンドを主体とした音楽やフュージョン・ミュージックがブームを呼んでいる中で、キースのコンサートがそう快感あふれる演奏を繰り広げたのは印象的だし、3月のトリオによるキースの再来日が楽しみだ。
(共同)

マーヴィン・ゲイ 来日完全密着ドキュメント
MARVIN IN JAPAN/紺野彗
No.7
ソウル界の帝王 マーヴィン・ゲイの5日間を徹底追跡!
晩秋の日曜日、晴れ渡った空の向こうにマーヴィン・ゲイの乗ったJAL71便が姿をみせた。
11月11日午後、成田国際空港ノース・ウイング、2時22分 当初の予定より30分早い到着だ。
マーヴィン・ゲイ、40歳。ステイーヴイー・ワンダーやダイアナ・ロスと同格のスーパー・ヒーロー。
ここ数年相次いだブラック・スターの来日のなかで、最後に残された超大物スターの来日がとうとう実現したのだ。
<マーヴィン、日本上陸>
3時―入国手続きを終え空港ロビーに姿をみせたマーヴィン・ゲイは驚くほどやせていた。
いまから3年前、1976年の全米ツアーに同行、運良く取材できたその時の彼はいかにもスポーツ好きらしいガッチリとした体格その印象からするとふた回り近くも細くなっている。
「やせたね」。レコードにもなった前妻アンナとの離婚騒動が、ここまで彼をやせさせてしまったのかと思いつつそう聞いてみた。
「以前と比べたら30ポンド(約15キロ)近くかな。ダイエットを始めてね。魚を多く食べるようにして肉も脂身の部分はさける。軽くなって調子がいいよ。」
意外にもそんな答えが返ってきた。
「でもね、ぼくは日本料理が好きだろ。食べ過ぎて太ってしまいそうだよ」
“マーヴィン・ゲイ・ツアー'79”。総勢35名。
宿舎のホテル・ニューオータニに落ち着き、まずは東京最初の夜を過ごした。
*
ホテルでのマーヴィン・ゲイの部屋は新館12階の3213号室。スウィート・ルーム。近くに秘書格のオーデル・ジョージとキティ・シアーズが部屋を取り、神経質といわれるマーヴイン・ゲイが静かな時間を過ごせるようにと心配りされている。
翌12日―マーヴィン・ゲイの最初の公式スケジュールは11時から予定されていた記者会見。会場は新館5階りんどうの間。朝早く目覚めたマーヴィン・ゲイの母親は既に買物に出かけてしまったというのに、なかなか起きてこないマーヴィン・ゲイ。記者会見が始まったのは30分遅れの11時半だった。
<日本で初めてのコンサートは「黒い夜」で始まった>
「ホノルルでは1万8,000人ぐらいの聴衆だったけどブドーカンはどうかしら。たくさんの人が見に来てくれるかしら」
マーヴィン・ゲイの身の周りを世話をしているキティ・シアーズが心配していた東京公演の初日。6時半開開演だというのに、3時前には既に数人のファンが会場入り口に姿をみせていた。バック・バンドのサウンド・チェックは3時から。一度ホテルに戻った彼らの会場入りが5時15分。
6時40分― マーヴィン・ゲイ到着。舞台ではオープニング・アクトのパッショナータの演奏が既に始まっていた。
7時15分― 予定通りマーヴィン・ゲイのショウ開始。場内は最上階に空席がみえる程度でほぼ満員。11万人近い数の聴衆。最初の曲は「黒い夜」。アルバム『ライブ・アット・ロンドン・パラディアム』に入っていた曲だ。マーヴィン・ゲイがステージに現れた。ただそれだけでアリーナ席の聴衆は総立ち。長いこと待ち焦がれていたマーヴィン・ゲイの日本公演が、いま、実現したんだという喜びを改めてかみしめているかのように、誰もが笑みを浮かべ、こぶしを握り、声を張り上げていた。
11月12日夜― 初めてマーヴィン・ゲイが日本のステージで歌った。
*
最初のステージを終えたマーヴィン・ゲイ。緊張が解けたのだろうか「トーキョーのナイト・タイムを楽しみたいね。ディスコにでも行こうか」などと言っていた。それでもやはりプロの歌手。ホテルに戻ると「しかし疲れてしまった。明日もコンサートがあるし、やはりのどを休めた方がいいかもしれない」となって、結局は自室に閉じ込もってしまう。
ニューオータニに泊まった3日間、そして大阪グランド・ホテルの1泊2日。合計5日間の滞在の間、マーヴィン・ゲイが彼の自由意志でホテルの外に出たのはただ一度だけ。それもわずか10分ほどのホテル周辺の散歩。ひたすら、コンサート会場とホテルを往復。空いた時間は静かに身体を休めることに専念していた。
本当に優れた歌手はひと一倍健康に気をつかう。そして決してのどを酷使しない。だから本物の歌手の声帯って、驚くほどきれいなピンク色をしているものだという話を聞いたことがある。だとしたらマーヴィン・ゲイ。彼の声帯はたまらないほど鮮やかなピンク色なのじゃないだろうか。
<親日派マーヴィンの日本観>
以前からマーヴィン・ゲイは日本に憧れていたという。そしてその口ぶりから察するに、彼にとっての日本は“冥想”という言葉に象徴されるふん囲気なので、はないだろうか。ストレート過ぎることなく2枚腰の奥の深さをもつ日本人の心情あるいは細やかな心配り。そういったものにマーヴィン・ゲイの,思いは敏感な反応をみせていたようだ。
「神が人間を創られたときに思い描いていた人間の姿――それにいま最も近い形で生きている人々、それが日本人だと思う。例えばぼくが何よりきらいなのは無神経な人間。他人がいやがることを、平気でやり、しかもその柑手の不快な思いにさえ気づかないタイプの連中だ。残念なことにアメリカ人はエゴが強くなり過ぎて、周囲に心を配るということを忘れてしまった人間が多くなり過ぎた。でも日本人はそうじゃないと思う。まだまだ愛ということの本当の意味を忘れていない.人たちだと思う。だからこのまま日本人がアメリカナイズされずにいてくれたらいいなって思っているんだ」
<たった5日の間にマーヴィンが残したもの>
東京・武道館で2回。大阪万博ホールで1回。マーヴィン・ゲイは3度ステージに立ち、そして15日、成田経由のホノルル行きの便で大阪空港を飛び立って行った。 あまりに短過ぎる今回の滞在期間。果たしてマーヴィン・ゲイは彼の思い描く日本人の優しさに、十分接することができたのだろうか。
「5日というのは短過ぎた。フラリと街を歩いてみたかったのに、それさえできなかった。でも、また来たいと思う。1度や2度じゃなく何度も繰り返し日本に来てみたいと思う」
そう語っていたマーヴィン・ゲイ。
だけど……と思う。
確かに短過ぎた滞在期間。マーヴィン・ゲイ自身が、日本の本当の魅力をたんのうするには至らなかったかもしれないが、それ以上に長いこと彼を待ち続けていた数万のファンは、目の前で歌うマーヴィン・ゲイを見、したたり落ちる汗やその包み込むようなまなざしに接したことで、これまで以上に、身近にマーヴィン・ゲイという男の魅力を感じることができたと思う。彼が作り歌ってきた「愛のゆくえ(ホワッツ・ゴ一イン・オン)」や「レッツ・ゲット・イット・オン」「ディスタント・ラバー」という曲をレコードで耳にした時に感じたマーヴィン・ゲイのぬくもり、その優しさを数倍も濃い手ごたえで感じ取ったはずだ。
ありがとうマーヴィン。あなたの歌を知り、惚れ、追いかけてきた自分自身に、今回、生身のあなたに接して、ぼくたちはとても大きな自信を持つことができた。ぼくらはいい男に惚れた。誰もが、そう思っているのではないだろうか。
マーヴィン・ゲイ。陽の落ちた大阪空港から弟のフランキー・ゲイと連れ立って、彼はアメリカに帰って行った。
(紺野彗)
ボブ・マーリー & ウェイラーズ 白熱のレゲエ
コンサートに行ったというより、コンサートを体験したという感じなんだ
No.10
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
「ただ単にコンサートをみに行ったという感じではないんだ。何か目に見えないパワーが体全体を包んで、会場を出た後もずっとその余韻が消えないんだ。コンサートに行ったというより、コンサートを体験したという感じなんだ」
これは昨年のワールド・ツアーの各会場できかれた代表的な意見だと思われるが、初来日コンサートに集まったファンに共通したものではないだろうか。“コンサートを体験する”という言葉がピッタリきたのが、ボブ・マーリー&ウェイラーズのコンサートだ。
「この世にわずか2種類のものしかない。善と悪。陽と陰。悪魔がいて、神がいる。正しく生きている人間はすべてラスタだ。誤った生き方をしている人間はすべて悪魔だ。この2つの要素しかない」(ボブ・マーリー)
記者会見でのボブ・マーリーも、盛んに「悪魔に近づいていく音楽、神に近づいていく音楽」という分け方を強調していた。
ラスタファリ―ジャマイカの思想家マーカス・ガーベイがリーダーとなり、ジャマイカを中心に、アメリカ、アフリカで急速に広まった「バック・トゥー・アメリカ運動」を軸にした宗教・哲学。現在、レゲエ・ミュージシャンの90%がラスタファリアンであるといわれるほど強い影響を与えた。ボブ・マーリーももちろん、その実践者だ。「心の中から生まれてくるもの。日常生活や人生そのものから出てきたのがわれわれの音楽だが、それらに根ざしていない音楽が悪魔に近づいている音楽だ」(ボブ・マーリー)
音楽、宗教とが密接なつながりを持つ状況というのは、日本ではピンとこないが、今回の熱い来日コンサートは、そういったことを抜きにした純粋なコンサートとしても、予想通り、いや予想以上の迫力あるステージだった。音楽というひとつの媒体を通して、日本のファンに、レゲエ、ボブ・マーリーを強く印象づけたことは確かだ。
「音楽は、宇宙の言葉としてメッセージを伝え、言語の異なった国の人々に語りかけるための最良の手段だ。神はひとつであり、宇宙はひとつであることを伝える手段として」(ボブ・マーリー)
(共同)
クイーン 3年ぶりになる来日ステージ
「Not the king. We're a champion.」
No.11
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
クイーンの人気ぶりには全く驚かされる。シングル・ヒットを中心とした番組でも、アルバム中心のロック番組でも、FM局に寄せられるリクエストの中で圧倒的な量をクイーンが占めているという。そして高い評価。最新アルバム「ジャズ」では、人気の高さに比例するような支持を受けた。
3年ぶりになる来日ステージでは、高い評価を受けるにふさわしい自信すらうかがわせた。アルバム作りと同じように十分計算されたステージでのエンターテイナーとして。クイーンの魅力は、ロック界の“キング”というナマの味を感じさせるものではなく、舞台に立ったヒーローを完璧に演じるカッコ良さにある。アイドルという立場は、既に超えたところで。
(共同)
ソ連で大モテ エルトン・ジョン
モスクワ、レニングラードで公演
No.26
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
僕の、いままでのキャリアの中で、最高の出来事だ!」とエルトン・ジョンが興奮気味に話していたそうだ。レニングラードとモスクワで行われた4回のコンサートを大成功のうちに終えた。コンサートに集まったファンも「エルトン!エルトン!」の大声援で迎え、100人を越える警官たちもバック・ステージ・ドアから用意されたリムジンの間に立ち並ぶものものしさ。どこの国のコンサート会場でも見られるような光景が、ソ連でも見られたようだ。若いポピュラー・ファンはどこでも同じ。
「これは僕にとって、強烈なチャレンジだった。だって、アメリカやヨーロッパでは、みんな僕のレコードを聴いているけど、ここの人たちは聴いたことがないわけだからね。実際、彼らはポピュラー・ミュージックを熱望していたんだ」(エルトン・ジョン)
(共同)
特集:日本のフュージョンミュージック
岡崎正通
No.17
FM放送のスイッチを入れると、あらゆる種類の音楽が流れてくる。その中でも、ここ1、2年の間で耳にする機会がめっきり多く.なっているのがニュー・ミュージック、それにフュージョン、あるいはクロスオーバーといわれる種類の音楽だ。
どちらの音楽も、最も“FM的なサウンド”といえるのかもしれない。特にフュージョン・ミュージックは、外国勢に対抗して一歩もひけをとらず、渡辺貞夫の「カリフォルニア・シャワー」のようなベストセラー・アルバムを相次いで生み出している。そこで“燃えるフュージョン”にスポットをあてる―。
<走れ!80年代のサウンドクリエイター>
フュージョン系レーベルをマークしよう
ここ2、3年の間に、日本の音楽状況はめまぐるしく変化し、発展を遂げてきた。一連のニュー・ミュージックの台頭などにしてもそうだが、11本のジャズやロック・シーンにも、80年代に向けての体質的な変化が現れてきている。各地に点在するミュージック・スポットに足を運んだり、毎月発売されるレコードにいつも関心をもっているファンならば、こうした音楽体質の変化を身をもって感じないわけにはいかないだろう。それはひとことでいってしまえば音楽の多様化であり、いわゆるフュージョン世代などと呼んでもいい、新しい世代のミュージシャンの登場である。折からちょうどフュージョン志向をもったレーベルが、日本のレコード各社からも新たにスタートする。CBSソニーが8月に第1回新譜を送り出す“オープン・スカイ”や、9月にキャニオン・レコードが発売する“アガルタ”がその良い例だ。“オープン・スカイ”は佐藤允彦や川崎燎を専属に迎えて、80年代の新しいサウンド作りを
目指す。また.“アガルタ”の方は、永くニューヨークに住んでいる日本人ベーシスト、中村照夫の率いるグループ、ライジング・サンの新しい録音を第1回新譜にもってくるなど、こちらも大した力の入れようだ。このほかにもキング・レコードが昨年夏から発売している“エレクトリック・バード”は、やはりニューヨーク録音を中心に、フュージョン系の新しいサウンドを狙っているし、またもっと前にコロムビアが始めた“ベター・デイズ”レーベルは、当初からこうしたノン・ジャンル指向を打ち出していた。ビクターには、“フライング・ドック”や“Zen”といったユニークなレーベルがあり、またアルファ・レコードは初めからこういう新しいサウンドの作品を多く作っていて、そのうちの何枚かは既にA&Mレコードの手を通じてアメリカでも発売されているといった具合である。とにかくここへきて、フュージョン系のレーベルも各社出そろった感じだ。
フュージョンはジャンルではない 音楽形態だ
そもそもフュージョン・ミュージックとは、一体どんな音楽を指すのだろうか。僕の考えをいえば、フュージョンないしクロスオーバーというのは、音楽のひとつの形態を示す言葉であって、特定の音楽ジャンルを指すものではない。例えば、レコード店では便宜上、フュージョン(またはクロスオーバー)という棚を作ってレコードを仕分けするかもしれないが、いままで、ジャズだとか、フォ-クだとかと呼んで区別してきたようには、もともといろいろなものが混ざり合っているフュージョン・ミュージックは区分できない。
冨田勲は、シンセサイザーでストラヴィンスキーの「火の烏」を演奏する。これはクラシックとポップスのフュージョンだ。あるいは最近のサウンドでは、ジャズとロックをミックスしたようなものが多いようだが、その中にもラテン音楽の影響が入っていたり、あるいはソウル・ミュージックに近いようなものがあって、実にさまざまなのである。つまりいろいろな要素が、あるサウンドの中に並存している音楽の形態をフュージョンと呼ぶのであって、フュージョン・ミュージックに一定のスタイルやジャンルは存在しないのだ。このような音楽を演奏するには、いままでのジャズだとか、ロックだとかいうように既成のジャンルにこだわりをもっていては演奏出米ない。良いと感じたものを何でも積極的に吸収していくような、柔軟な精神が要求される。そして今、日本のフュージョン・ミュージックは、そういった新しい世代のミュージシャンたちを中心に進められている。
ナベサダ、ネイティブ・サンはなぜ売れる?
そうしたフュージョン・シーンのトップに立っているのは、やはりジャズ・ミュージシャンの大御所、渡辺貞夫だろう。渡辺貞夫は、年齢的にみれば今の若いミュージシャンたちよりも、ふたまわりくらい上になる。しかし、彼がロサンゼルスで、デイヴ・グルーシンやリー・リトナーと吹き込んだ「カリフォルニア・シャワー」が30万枚を越える超ベストセラーになり、次いでニューヨークで吹き込んだ「モーニング・アイランド」も、現在それに迫る勢いで売れ続けている。この種のタイプのレコードがこんなに売れたというのは、過去に全く例のないこと恋のだが、これもヒューマンなナベサダ・サウンドと、現在のアメリカを代表する一流ミュージシャンたちのとの音楽が、美しいブレンドをみせた結果といえよう。
渡辺貞夫に続く世代のフュージョン・グループが、このところめきめき人気を上げているネイティブ・サンである。グループを構成している本田竹曠、峰厚介、川端民生、村上寛は、いずれもジャズ畑で活躍を続けてきた中堅ミュージシャンばかりだが、これにギターの大出元信を加えたネイティブ・サンの音楽は、もっと開放的で、リズミックな楽しさにあふれている。彼らは豊富なジャズの経験からソロをとらせたらすばらしいプレイを聴かせてくれるが、ネイティブ・サンの音楽では、それがトータルなグループのサウンドにまで高められているのがポイントだろう。昨年春に結成されたこのグループは、まだアルバムを1枚発表しただけだが、このレコードもテレビのCFや雑誌広告にグループ・が使われたりして、いま凄い勢いで売れている。彼らは8月 25日、東京・田園コロシアムで、ワン・マン・コンサートを開くが、野外のライブ ・コンサートだけに、いまから楽しみだ。大野雄二や佐藤允彦、鈴木宏昌らは、やはりジャズ・ミュージシャンとしては既にベテランの領域に入っており、しかもいまなおフュージョン・サウンドにも意欲を燃やすなど、前向きな姿勢を崩していない。彼らが若いミュージシャンたちを刺激しながら、どのような音楽を演奏していくかはまだこれからだが、いずれにしろ彼らはオーソドックスなジャズを演奏してきて、それからフュージョンにも目を向け始めたあたりが、次の世代のミュージシャンたちとは一味違うところ。
「ジャズとフュージョンを区別したことなんかないさ」
もうひとり、もう10数年にもわたってニューヨークを舞台に活動を続けている日本人ベーシスト中村照夫は、ニューヨ-クの一流ミュージシャンを集めてグループ、ライジング・サンを結成している。彼の名前は日本よりもむしろニューヨークで知れわたっているが、ちなみに彼のバンドが一昨年発表したアルバム「マンハッタン・スペシャル」は、米国でジャズ・チャートのベスト・テン入りしした(アメリカのジャズ・チャートは大半がフュージョン系サウンドで占められている)。間もなく発売になる彼のニュー・アルバム「ビッグ・アップル」では、ゲストにランディ・ブレッカーやヒューバート・ロウズも参加しているというから大いに楽しみだ。アップルとは、もちろんニューヨークのニックネームで、中村照夫がこのレコードに賭ける心意気を、タイトルからも読み取ることが出来る。「従来からのジャズと、フュージョン・ミュージックとを僕は自分の中で区別しない。僕は、自分の音楽をフュージョンだと思って演奏したことはない」と中村照夫は述べている。おそらくそんなところが、日本の新しい世代のミュージシャンと共通する感覚でもあるのだろう。
<渡辺貞夫、ネイティブ・サンに続くもの>
それでは日本の新しい世代のミュージシャンでは、どんな人が活躍しているのだろう。そして80年代の日本のフュージョン・サウンドはどうなるのだろうか。
80年を示唆する渡辺香津美
まず、若手ギタリストの中て、既にスターの座についているのが、渡辺香津美である。彼は、つい最近、新しいLP「キリン」を発表したばかりだ。このところ海外のミュージシャンとの共演アルバムが多かった渡辺香津美だが、ここでは久しぶりに日本を代表するフュージョン・プレイヤーを総結集して、豪華なサウンドを作り上げている。このLPあたりは、80年代の新しいサウンドを示唆するものだといっていいかもしれない。ジャズ・ナンバーの「マイルストーンズ」をご存じのファンだったら、このレコードで彼らがあまりに新鮮な感覚で演奏しているのに、びっくりすることだろう。
活動範囲の広い坂本龍一
「キリン」をプロデュースしている坂本龍一は、いま最も期待出来る若手アレンジャー、キーボード奏者である。彼の場合はニュー・ミュージック界のアーティストとの交流が多いが、やはり最新アルバム「サマー・ナーブス」では、キーボードとボーカル、それにプロデュースと編曲を担当し、カリブ風のさわやかなリズムをバックに、ポコーダーも駆使してなかなか凝ったサウンドを聴かせてくれている。これも葱かなか聴き応えのある1枚だった。坂本龍一の場合は感覚的にポップだし、活動範囲も幅広いので、これから彼の音楽がどう展開するかわからない面白さがある。
アメリカに“逆上陸” 増尾好秋、川崎燎
ギタリストとして渡辺香津美に劣らない人気と実力をもっているのが、増尾好秋と川崎僚のふたりだろう。ふたりともアメリカで生活を続けているので、生演奏に接する機会はほとんどないわけだが、レコードでは彼らの健在ぶりを十分接することが出来る。増尾好秋は“エレクトリック・バード”からの第2作「サンシャイン・アベニュー」を発表したが、彼は自身のナイーブな感性を今日的なサウンドの中に、うまくブレンドさせている。彼は最近作「マンハッタン・フォーカス」でもフイーチュアされており、年内には帰国してライブ・スポットなどに出演する計画を立てられている。一方、川崎燎もアメリカでは、ギル・エヴァンス・オーケストラに参加するなど多彩な活動をしてきた。そして、米RCAから「ジュース」というリーダー作を出したこともあったが、彼が従来のジャズにこだわることなく、自由な発想で制作したのが“オープン・スカイ”から発売された「ミラー・オブ・マイ・マインド」である。以上3人のギタリストは、もはやトップ・クラスに位置しており、彼らが80年代の音楽をリードしていくであろうことは、ほぼ間違いない。しかし、ギターという楽器は、ロックの花形楽器だから、ロック畑の優れたプレイヤーを挙げないで、80年代のギター・ミュージックは語れない。
ロック・ギタリストに注目 高中正義、山岸潤史
例えば高中正義などは、かなり早くからこうしたサウンド志向をもっていたギタリストのひとりだろう。彼はついこの間、第一級のスタジオ・ミュージシャンを集めてバンドを結成し、LP「チャ・チャ・ミー」を発表したばかりである。四人囃子やプリズムのメンバーだったころからずば抜けたものをもっていた森園勝敏は、「バッド・アニマ」に続く第2弾がロス録音で、間もなく発表される。彼のギターもあくまでロックをベースにしながら、しかもいままでのロックというワクを超えてしまっている。もうひとり「ディグ・マイ・スタイル」で衝撃的なデビューを飾った秋山一将も、若手のホープである。ジョージ・ベンソンにも通じるメロウな表現力をもった彼は、この1作で多くのファンを獲得したけれども、つい最近出たセカンド・アルバム「ビヨンド・ザ・ドア」を聴くと、ナイーブな彼がさらに柔軟な表現を身につけてきていることがわかる。このほかにも個性的なギタリストは数多い。鈴木茂や大村憲司、松原正樹、そして元ウエスト・ロード・ブルース・バンドのギタリストで今回イギリスからゲイリー・ボイルを迎えて「リアリー」を完成させた山岸潤史などは、これからも大いに注目していかなければならないだろう。さらにロックやニュー・ミュージックの分野で、トータルなサウンド・クリエイターとして、山下達郎、細野晴臣、そして多彩なキーボードを駆使する深町純などがどのように音楽を展開させてゆくかは、80年代の大きな楽しみのひとつでもある。
期待の新人2人 本多俊之、清水靖晃
ホーン・プレイヤーをみてみると、この分野にも優れた新人はたくさんいるが、何といっても光っているのは、本多俊之と清水靖晃のふたりだ。どちらもライブ・ハウスやレコーディング・セッションではひっぱりだこの人気ミュージシャで、しかも短期間にぐんぐん実力を伸ばしてきている。本多俊之は、シーウィンドと共演した「バーニング・ウェイブ」1作で脚光を浴びたサックス奏者だが、2作目の「オパ・コン・デウス」ではセルジオ・メンデスのバック・メンバーとし共演し、ブラジリアン・サウンドをとり入れたポップな演奏で、また新しい境地を切り開いた。清水靖晃の方は、ユピテルからの初リーダー・アルバム「ゲット・ユー」でファンから注目されたわけだが、第2作「マライア」では、秋山一将などと一緒にさらにフュージョン志向を強めている。本多にしても清水にしても、まず楽器の音色が抜群に良く、フル・トーンで朗々と鳴り響いているのがすばらしい。彼らの演奏はいつもエキサイティングな興奮を失ってはいないが、2人とも心の底からのびのびと彼らの歌を歌い上げていくのが気持ちいいのだ。
充実した活動 向井滋春、大野俊三
「ヒップ・クルーザー」をこの春出したトロンボーンの向井滋春は、今日的なリズムのなかに、トロンボーンという楽器がもっている豪快で野性的な味を生かしたプレイをおこなっている。彼の音楽の中にもラテン的な陽気さがみられるが、いままでのジャズがもっていたブルース・フイーリングだけにとらわれないで、ハッピーで屈託のないサウンドを生み出していくあたりは、フュージョン・ミュージックの新しい方向を示すものだ。
管楽器ではもうひとり、ニューヨークにいるトランペッター、大野俊三も頑張っている。彼はこの8月に「クォーター・ムーン」を出すが、このLPではカーター・ジェファーソンなど、すべてニューヨークの若手ミュージシャンでバックが固められている。このLPに限ったことではないが、いまやフュージョン・ミュージックの世界では、日本人プレイヤーが世界の一流ミュージシャンと共演するのは、ごく当たり前のようになっている。壮々たるバック・ミュージシャンを使って、内容的にも海外ミュージシャンの作品に少しもひけをとらない、充実したアルバムが生み出されているのだ。
多彩なキーボード 益田幹夫、松岡直也
キーボードでは、かつて日野皓正グループでピアノを弾いていた益田幹夫が、年内に「コラソン」に続く“エレクトリック・バード”からの2作目を出す。これは前作と同じくニューヨーク録音になる予定で、現在進行中とのこと。ラテン・ピアノのベテラン、松岡直也は、サンバやサルサなど、ラテン音楽のもつ色彩的なリズムを、現代的なサウンドの中に巧く溶け込ませている。高中正義、大村憲二、村上秀一などとことし初めに吹き込んだ「ザ・ウィンド・ウィスパーズ」は彼の代表作といえるだろう。もうひとり、ユニークな活動を続けているアレンジャー、三木敏悟の名前はここで落とせない。彼は昨年、インナー・ギャラクシー・オーケストラというリハーサル・バンドを結成して、「海の誘い」という意欲作を発表したわけだが、彼の音楽もまた従来のビッグ・バンドというワクをはるかに超えた大胆なアレンジに特色がある。オーケストラの楽器編成もちょっと変わっていて、さまざまな手法を導入する彼の発想そのものが新しいフュージョン世代の感覚といえるのではないだろうか。
(岡崎正通)
パティ・スミス さすがニューヨーク・パンクの女王と思わせる貫録
Rain, Park, And…
No.22
 Photo: Getty Images
Photo: Getty Images
79年の夏、ニューヨークでも数多くのコンサートが行われた。なかでも、約2カ月にわたって開かれた「第3回ドクター・ペッパー・フェスティバル」には、前回までとは異なりパティ・スミス、トーキング・ヘッズ、サウスサイド・ジョニー&アズベリー・ジュークスと、地元出身のニュー・ウェーブ・グループが出演、集まったニューヨークっ子を狂喜させた。
なかでも注目を浴びたのがパティ・スミス。さすがニューヨーク・パンクの女王と思わせる貫録をみせた。
パティが登場したのは8月11日。コンサートのスタートは午後6時30分の予定だったが、その日は昼間からあいにくの曇り空。そして5時ぐらいになるとドシャ降りの雨になった。満員の客席は、あまりにもすごい降りに大混乱で、コンサートが中止にでもなれば暴動も起こりかねない雰囲気であった。
コンサートは定時を少し遅れてスタート。興奮気味の観客を抑えるように、はじめはスロウでユッタリと。しかし、いつの間にか彼女の歌にひき込み、すっかりノせてしまうのはさすがだ。観客もドシャ降りの雨を忘れてしまっているよう。
衣装もごく普通のものだし、化粧もほとんどなし。どうみても美人とはいえないが、ステージでの存在感を感じさせ、いい女だな、と思わせる。
約2時間のステージに、観客は傘もささずに立ちっ放しの、魅了されっ放しだった。
コンサートが終わり、フッとわれに返った時には、降り続いていた雨のために全員ビショぬれとなったが、心には大いなる満足感があふれていた(ニューヨークのセントラル・パークで)。
(共同)