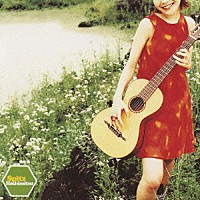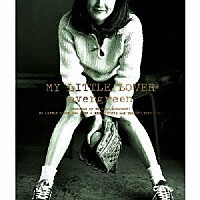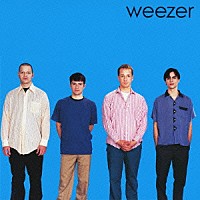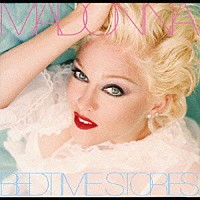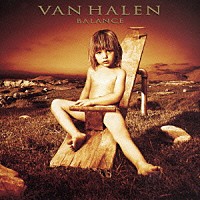FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集
ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!
TOPICS - 1995※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。
ヴァネッサ・ウィリアムス 自らの目標を努力で勝ち取るのが人生
ブロードウェイ・ミュージカル「蜘蛛女のキッス」の成功と3年ぶりの新作
No.1

Photo: WireImage
どんと崖っ淵から突き落とされるかもしれないし、宝くじに当たるかもしれないし、今日と変わらない明日が来るかもしれない。ほんのちょっと先の人生にどんな出来事が待っているかわからない。だけれども、もし突然、失意のどん底に陥ったら自分だったらどうするだろう。全米でNo.1ヒットになった「セイブ・ザ・ベスト・フォー・ラスト」の歌声とともに、セクシーでチャーミングな彼女自身が登場するシオノギのCFを見るたびにそんなことを思っていた。ヴァネッサ・ウィリアムス。黒人女性として初めてのミス・アメリカの栄寛を1度は手にしながら、それを剥奪されるというスキャンダルに見舞われ抹殺されそうになりながら、這い上がってきた人である。
「今、私はブロードウェイの舞台に立ち、レコードを出し、企業からスポークスパーソンになってほしいとオファーがくる。こんなこと10年前には考えられもしなかったわ。みんな私のダークなイメージを気にして、絶対あり得なかったことよ。それが、3人も子供を産んでからセックス・シンボルと言われるようになったのよ、おかしいでしょ?」
障害を乗り越え夢を実現させるために
ジーンズに黒のタートルネックのセーター。素顔に近いナチュラルメイクでNYのブーロードハースト劇場の楽屋に現れたヴァネッサは、穏やかな表情で話し始めた。93年の上演以来ブロードウェイで一番人気のミュージカル『蜘蛛女のキッス』で舞台を務める。その一方で、ロマンチックでハートフルな歌声とジャジーな雰囲気が心地よくブレンドされた3枚目のアルバム『スウィーテスト・デイ』を完成させたばかりの10月中旬。
初めてアルバムの半分以上をセルフ・プロデュースしただけに、どの曲にも思い入れがあるけれど、とりわけ印象的なのがファースト・シングルのタイトル曲だったという。「以前、詞を書いてくれたフィルに、自分のこれまでのことや、恋愛について、子供たちのことを話したんだけれど、彼はそれを覚えていたのね。『僕は君の話を詞にしたんだ。そう、君がこの曲を生み出したんだ。』って言ってた。だからなんだかこの曲には自分の指紋についているような気がしているの。人生は厳しいものかもしれないが、二人が一緒にいれば最高のものになるという内容のラブ・ソングなのだけれど、その歌詞は確かにヴァネッサ自身とオーバー・ラップする。「ペントハウスの表紙に”ミス・アメリカ・オー・ゴッド・シーズ・ヌード”とデカデカと出た6カ月間のことだったけれど、自分の意見なんかまだ残っていない20歳の娘が突然アメリカ女性を代表するようになったの。これはすごく大きなことだった。でも自分の人生の目標を考えてみると私はミス・アメリカになりたくて歌やダンスや演技の勉強をしてきたわけじゃなかった。だから人生はこれで終わりとは思わなかったの。」ずいぶん苦しんだし、混乱もした。ただこの時にヴァネッサは王冠とともに失ったものを考えるのではなくて、そのことによって見えてきたことをプラスに受け止めたのだ。そして幸いなことに、傷ついた彼女を丸ごと包み込みサポートしてくれている家族がいた。「人はだれでも人生において何かを証明しなければいけないときがある。もしビューティー・クイーンとして注目されたら知性を、シンガーであれば歌えることを、2枚目、3枚目とアルバムを出すのならただの一発屋ではないことを証明しなくちゃいけない。人生にはいつだって乗り越えていかなければならない障害があるんです。私にはいつもこの山に登りつめるんだという夢がある。ある人はこんな私のことを野心家ね、というかもしれない。だけど夢を実現したいから、私は一生懸命はいつくばって登っているの。」
ポジティブな気持ちを忘れないで生きていたら、夢が実現する明日が待っているとヴァネッサは言う。彼女自身がそうしてきたように。春からのツアーや、ジャズを歌う次のアルバム、子供たちのためのアルバム・・・これからのヴァネッサの夢はいろいろあるけれど、一番の望みはと言えば、「声がわかって、歌詞が聴き取れて、みんなが一緒に歌えて結婚式や卒業パーティみたいな場で使われるような抒情的な歌を歌い続けたい!」
(インタビュー、文・金沢英子)

Gラヴ、ジェフ・バックリー、BECK [コーヒーショップ・カルチャー]の旗手たち
ライブ・ハウスに代わる新時代の音楽発信地
No.1
![Gラヴ、ジェフ・バックリー、BECK [コーヒーショップ・カルチャー]の旗手たち](/common/special/time_machine/img/photo/1995-glove-redferns.jpg)
Photo: Redferns
コーヒー・ショップ・ムーブメントという言葉がささやかれている。ちょっと聞くとなんのことかわからないが、スピーカーズ・コーナーのあるコーヒー・ショップが、新しい音楽の発信地として、今、ニューヨークやロサンゼルス、またはパリやロンドンといった大都市で話題を集めている。ラップ・ミュージックを、会話をするのと同じ感覚で聴いて育ってきた世代にとって、ライブ・ハウスがバンドの情報交換や発表の場となってきたように、コーヒー・ショップがそういう集いの場になってきている。アメリカの新聞記事によれば、Gラヴ&スペシャル・ソースやベックをはじめとするアーティストたちが、この新しいムーブメントの代表格として取り上げられている。Gラヴことギャレット・ダットンは、トニ・モリスンといった作家の抒情的な文章に感銘を受けやすいと話し、ボストンでギター1本でソロ活動していたころは朗読に近い形の作品が多かったという。もちろん、今でも歌詞に重きを置いた曲作りに努め、歌う口調もトーキング風のスタイルになっている。ニューヨークで活躍中のソウル・コフィングのボーカル、マイク・ドーティも、ヒップ・ホップと詩の朗読を合わせた音楽を作りたくてグループを組んだと話している。パリのMCソラーは、もともとジャーナリストを目指していたが、彼の詩に友人が音楽を付けてみたのがきっかけとなり、今ではドゴール大統領が演説でやっていたという3文節で言葉をまとめて区切っていく方法をラップに用いるなど、言葉とリズムの融合を楽しみながら曲作りをしている。公衆の面前で実験的に詩を朗読することはJ・ケルアックやW・バロウズが行ってきたように、いまさら珍しいことではない。作者が自作を読み上げることで、言葉に表情を付けることができ、創作した世界に聴き手を自在に誘引していくことが可能になるからだ。そして今、“バロウズの子供たち!と呼ばれる若い世代が、ケルアックがチャーリー・パーカーの音楽に合わせて詩を発表したように、自分の詩のイメージに合った音楽や効果を上げるノイズを探しては言葉とミックスする手法に興味を示し、新時代のスタイルを築き始めている。それらのショップはSin-çやNuyorigcan Poets、Café Canal Brasserieなど、まだ限られてはいるが、海外に行った際にはのぞいてみる価値は十分にありそうだ。
(文/伊藤なつみ)
●Gラヴ&スペシャル・ソース / 生き方にこだわるのと同じくらい音楽にもこだわる
たとえばモノトーンの映像に、街角で自作の短編小説を朗読していた若者が映っていたとする。Gラヴ&スペシャル・ソースの音楽は、その若者が小説にリズムをつけて歌いだし、ふいに映像から飛び出してきたような、そんな立体感のあるリアルなサウンドなのだ。ストリートの匂いも、通りゆく人々の息づかいまでも含んでいるような、一瞬にして空気の色も変えてしまう特別な音楽なのである。Gラヴことギャレットは、まだ22歳。今から2年前に故郷フィラデルフィアから、自分を見知らぬ環境に置いてみたいと一人でボストンへ渡り、ギター1本でソロ・パフォーマンスをはじめる。そこへドラムスのジェフリーとアップライト・ベースのジミーが続いて参加し、グループが結成された。
「歌詞で影響を受けたのは、(黒人女流作家の)トニ・モリスン。彼女の文章はインスピレーションをすごく喚起させる。あふれるような、抒情的で詩的な言葉使いが好きなんだ。場合によっては、彼女が生み出した言い回し一つをもとに曲を書いてしまうことがあるほど。そのくらい影響されている。それから、ブルース。これも詩的で同時にシンプルで、何かを訴えるのに口数多くまくしたてる必要はないことを証明している。どう言うかの方が大時な場合もあるからね」
好きなアーティストは、ボブ・ディラン、ボブ・マーリイから、KRS-ONEと幅広い。共通点としては、どれも言葉の勢いがメロディラインに影響を与えているような歌詞を重視した音楽であること。バンドが曲を作る際には、ギターがブルースを、ドラムがファンクを、ベースがジャズを基盤に演奏し、「曲のテーマを各自が自分なりのアートに取り込み、3つの違ったアングルから端を発して何かを生み出していく」という手法によって行うというが、彼らの場合もギャレットのラップ的なボーカルも欠かせない要素となっている。最低100回は演奏して、言莱と音楽を次第になじませて完成させるというから、ちょっとした気だるいフレーズからも彼らの生活を垣間見るような、そんな小説を読むような味わい方もできるのだろう。
「たとえば<コールド・ビバレッジ>は、冷たい飲み物の歌。それがこの曲のテーマで、みんながそれぞれテーマを解釈して、各時の楽器で冷たい飲み物を音に、僕は歌にする。だから歌詞やテーマを各自が自分なりのアートに取り込んでいく感じだね」
楽器はオールド・スタイルのものを好み、レコーディングもライブ一発録音、できればデビュー・シングルがEPだったように、アルバムもレコード盤でリリースしたかったそうだ。「自分たちがどう感じているかをきちんと表現したいだけなんだ」と話す彼らは、生き方にこだわるように音楽にもこだわっている。他人に命名される前にと、自ら自分たちの音楽を"ラグ・モップ”と名付けたのも彼ららしい。これは「イカれてて、ファンキー」という意味なのだそうだ。
(インタビュー、文/伊藤なつみ)
●ジェフ・バックリー/カフェでのライブは聴衆との真剣勝負だった
94年の夏に『グレース』でアルバム・デビューを果たしたジェフ・バックリーが、それ以前はソロ・アーティストとして、ニューヨークのさまざまなコーヒー・ハウスやクラブなどで熱心にライヴ活動を行っていたということは、すでによく知られている話だ。正確に言えば、ジェフは92年の春頃からソロ・アーティストとしてエレクトリック・ギター弾き語りのライブ・パフォーマンスを開始しそのすごさが評判となって、レコード契約が彼のもとに殺到した。そしてジェフを獲得したコロンビア・レコードは、ファースト・アルバムのレコーディングのプレッシャーを取り除くためにと、まずは彼が活動の根拠地にしていたセント・マークス・プレイスにあるシネ(Sin-ē)というカフェで、2日間、5時間半にわたってライブ・レコーディングを行った。
そのセッションからの4曲が収められたミニ・ アルバム『LIVE AT SIN-Ē』(アメリカで93 年暮れに発売)を聴くと、彼がそのカフェで いつもどれほど強烈なライブを行っていたのかを窺い知ることができる。 「ぼく自身の歌があれば、あるいは自分が手懸けている何かがあれば、頭に浮かんだとたんすぐにやっていたね。次から次へと新しい 歌を増やしていき、それで何とか一晩やってのけることができたんだ」とジェフはシネで歌い始めたころのことを思い出して語っている。
「ぼくはゼロから始めたよ。それ以前の歌は、全部捨ててしまって、一曲もストックしていなかった。ソロになる以前にニューヨークで参加していたゴッズ&モンスターズの曲はやりたくなかったし、やりたくてもできなかった。新しい曲しかやりたくなかったけど、最初のギグまでには時間の余裕がほとんどなかったんだ。」
とはいえジェフは何とかソロ活動をスタートさせ、やがてニューヨークのライブ・シーンで話題を集めるようになっていく。そしていつしかシネの顔にまでなってしまったのだ。「そのうち2時間のショーがやれるほどのレパートリーが溜り、ようやくシネのメインを務められるようになった、というのもシネのゴールデン・アワーは夜の10時から12時までと決まっていて、途中で休憩をとってもいいし、2時間ぶっ統けでやってもいい。ぼくは2時間ぶっ通しでやることにしたよ。それ以上やったこともあった。もっと短く、でもうまくやることを覚えたのは何か月も経ってからだった。みんなすごいのりようだったね」「ソロは一人の勝負だから聴衆の気持ちをしっかりつかまなくちゃならない。そうるすには音楽に身を委ね、グルーブを見失わないことだ。感情や言葉から生み出されるグルーブをね。その中に入り込んで歌を歌うのさ」ソロ時代に培われたジェフのこの姿勢が、3人のバンドメンバーと一緒に演奏する現在にもしっかりと引き継がれているからこそ彼のライブはますます強烈で圧倒的なものとなっているのではないだろうか。
(インタビュー、文/中川五郎)
●BECK/ギター1本だとすぐに歌えるからありとあらゆる所で歌っていた。
94年のアメリカの音楽シーンのベスト・ニュー・アーティストということになると、やはりベックの名前を挙げる人がいちばん多いのではないだろうか。異色のラップ・ナンバー「ルーザー」で一躍時代の寵児となった異色の存在だが、彼の原点というか、出発点をたどってみれば、フォークというところに落ち満きそうだ。日本で発売された彼のアルバム『メロウ・ゴールド』を聴いても、フォークの気配がわずかに感じ取れるし、バンドを従えてのとんでもなくアナーキーだった8月の来日公演でも、フォーク・シンガー、ベックの姿が垣間見られたりした。
実はベックは『メロウ・ゴールド』だけでなく、94年のうちに、ほかにも2枚のアルバ ムを発表していて、しかも全部別のレーベルからほとんど時期を同じくして発売するという、ふつうではまず考えられないことをやってのけている(やっぱり異色の人物だ)。メジ ャーのゲフィン・レコードから発売された『メロウ・ゴールド』は別として、ほかの2枚の アルバム、『STEREOPATHETIC SOUL MANURE』と『ONE FOOT IN THE GRAVE』は、いずれも小さなインディ・レーベルから発表されているので、日本盤はリリースされていないが、それを併せ聴くと、ただでさえつかみ切れないベックのまた別の姿を確かめることができる。特に後者のアルバムは、直に(?!)フォークを歌うベックの作品が数多く収められていて、なかなか興味深い。
「今のようにバンドで演奏する前、アコースティック・ギター一本での弾き語りを6~7年やっていたよ。1週間に5回なんてざらさ。それこそ1000回はやっているんじゃないかな。ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、シアトル、ありとあらゆるクラブやコーヒー・ハウスに出演した」とベックは言う。「バンドとバンドの間にちょこっとやらせてもらったりとかね。ギター1本だから、すぐに歌える。お金がなくて、どこかのクラブにしょっちゅう潜り込んでいたよ。」「フォーク・ソングは今も大好きだ。だれでも演奏できるし、曲にしたってみんなの共有財産のようなものだから、エゴイスティックな部分から最もかけ離れた音楽だと言えるね。」ストリート・ミュージシャンとしてブルーグラスを演奏していた父親の影響で、ベックはフォークやブルースに興味を抱くようになったのかといえば、そうではないらしい。「好きな音楽はプッシー・ガロアやストゥージス、ラヴ&ロケッツなんかだった。たまたまレコード店でミシシッピ・ジョン・ハートのレコードを見つけて、ジャケットの彼の汗まみれの顔にすごく感動して買ってしまったんだ。」
94年はツアーに忙殺され、レコーディングをしたくてもできなかったとぼやくベックだが、彼の次なるアルバムが(もう4枚目だ!!)フォークやブルースからますます遠ざかった作品になるのか、それともまた出発点に戻ったようなものになるのか、実に楽しみだ。
(インタビュー、文/中川五郎)
発祥の地アメリカの本家本元ラップとは
内輪話が中心の内省的ライムから、ギャングスタ・ラップの時代へ
No.14
●ラップが誕生したばかりのころのライムはメッセージ系と快楽系に大別された
RAP-俗語扱いで“喋る”という意味である。そのルーツを探ってみると、古くからアフリカン・アメリカンの子供たちの間で行われてきた“dirty dozens”なる言葉遊びにたどり着く。リズミカルな言葉で相手をやり込める、言ってみれば“売り言葉に買い言葉”的なケンカ遊びだ。その“dirty dozens”が進化したものがラップだと言われている。70年代後半、ニューヨークはサウスブロンクスで産声を上げたとする説が最も有力だ。当時、ラップも含めて、ブレイクダンス、DJがターンテイブルを操る妙技、そして地下鉄の車体等に書かれたスプレイ・アートをひっくるめて、人はいつしかその新しいストリート・カルチャーを“ヒップ・ホップ”と呼ぶようになった。ラップ・ナンバーとして初のヒット曲となったシュガーヒル・ギャングの「Rapper’s Delight」(79/シックの「Good Times」のバック・トラックをそのまま再演奏して使用し、ラップしたもの)のライム(ラップの詞)に、”Hip-Hop”という言葉が登場しているが、この言葉が最初に登場した曲が「Rapper’s Delight」だと言われている。
ラップがこの世に誕生したばかりのころは、ライムの内容はシリアスなメッセージと快楽的なそれに大別されていた。70年代後期から80年代初期にかけて活躍したラッパーたちを、俗にオールド・スクール・ラッパーズ“と呼ぶが、その代表格であるグランドマスター・フラッシュ&ザ・フューリアス・ファイブは、「The Message」(82)でサウスブロンクスの現実を生々しく暴いてみせた。また、先述の「Rapper’s Delight」は典型的なパーティ・ラップである。80年代半ばになると、サウスブロンクス以外のニューヨークの各地からラップのスターが続出。エアロスミスの「ウォーク・ディス・ウェイ」のバック・トラックを従えてラップし、世界的大ヒットを記録したRUN D.M.C.、彼ら同様ニューヨークはクイーンズ地区出身のL.L.クールJはラップ界初のアイドル的存在になった。当時のラッパーの特徴は、マッチョなイメージを前面に押し出し、太いゴールドの鎖をジャラジャラさせ、ひたすら自己顕示欲の塊のようなライムを口にしていたことである。そうした“自我の強調”に、多くのストリート・キッズが憧れた。
●内輪話が中心の内省的ライムから、ギャングスタ・ラップの時代へ
80年代後半ともなると、ニューヨークのみならず、全米各地からラッパーが登場し、ライムの内容も多様化。自己顕示欲的ライムは廃れ、代わりにデ・ラ・ソウル、ジャングル・ブラザーズといった、俗に言うニュー・スクール・ラッパーズが台頭し、内輪話が中心の内省的なライムが好まれるようになる。そうした傾向は、ニュー・スクールの次の世代のネクスト・スクール・ラッパーズ(ア・トライブ・コールド・クエスト、リーダーズ・オブ・ザ・ニュー・スクール、ブランド・ヌビアン等)の出現と共に、一層強まる事に。その一方では、ジャジー・ジェフ&ザ・フレッシュ・プリンス、スリック・リックらのような、漫談を彷彿とさせるコメディ・ラップを得意とするラッパーズも人気を博していた。
90年代は、何と言ってもギャングスタ・ラップ(またはG-ファンク)全盛の時代。主にウエストコースト出身のラッパーズーアイス・キューブ、ドクター・ドレー、スヌープ・ドギー・ドッグら―が、犯罪、殺人、麻薬などに関することをストレートにラップし、全米のストリート・キッズを熱狂させている。文字通り、猫も杓子もギャングスタ・ラップ、というのが現状だ。
ライムの命は、押韻(ライムはもともと語尾で韻をふむの意)である。そのため、多くのラッパーズは造語を作り出すことをも辞さない。また、彼らはスラングを生み出す天才だ。ラップの誕生から15年以上経った今も、たった26文字のアルファベットを用いて、身近な問題から世界情勢に至るまでを、リズミカルにラップすることに腐心している。ライムの内容が多様化しようともRAPの定義(“喋る”という行為)は昔も今も変わらない。
(文/泉山真奈美)
シェリル・クロウ
土の香りから都会の一場面までアメリカのエッセンスを投影した明るさ
No.13
 Photo: Getty Images
Photo: Getty Images
●アメリカの伝統が育てあげた音楽
身も心も引きずりこまれるように聴いてしまう歌との出合いは、そうあるものではない。シェリル・クロウのデビュー作「チューズデイ・ナイト・ミュージック・クラブ」は、オープニングの「ラン・ベイビー・ラン」をはじめ、久々にそんな思いで聴いた作品だった。アメリカの音楽界に登場した大きな才能——。彼女の歌を聴いた人ならだれもがそう予感したはずだが、93年11月の発売当初はさほどの話題にならず、内心やきもきしていたのは私だけではなかったと思う。しかし約1年後、「オール・アイ・ウォナ・ドゥ」が大ヒットし、グラミー賞の3部門で受賞という栄誉に輝いた。デビュー以前はソングライターやバックコーラスなどでキャリアを積み、走り続けてきた彼女は、ようやくひとつめのゴールに到着したようである。
「アルバムが出たときは正直言ってそんなに売れなかった。1年間ツアーを行って、ライブ・バンドとしての実力が認められつつあるときに、<オール・アイ・ウォナ・ドゥ>がヒットしたので、2回も評価されているような気分。それがうれしいわ。」
彼女の音楽にはロック、R& B、カントリーなどアメリカが長いあいだ培ってきた音楽のエッセンスがブレンドされている。その歌からは、広いアメリカの土の香りが漂ってくるかのようだ。さらにその音楽を素晴らしくしているのは、南部経由を思わせるリズムのノリだ。初期のボニー・レイット、またはかつてボビー・ジェントリーがその歌で匂わせた、泥臭いリズムのグルーブが彼女の歌にはある。
「私が生まれたのは、アメリカのど真ん中、ミズーリ州の農場です。メンフィスのR&Bが大好きで、子供のころはバンドで、モータウンやスタックス・レーベルの歌をレパートリーにしていたわ。その当時から今でも好きなのがヴァン・モリソン、ローリング・ストーンズ、デレク&ドミノス。子供のころはカントリーは嫌いだったけど、いまにして思うと私に大きな影響を与えているわね」
●自分の存在意義を見い出すことが大切
90年代のロサンゼルスのスナップ・ショットと語る「オール・アイ・ウォナ・ドウ」、クリントンが大統領に当選した時にインスパイアされて書いた「ラン・ベイビー・ラン」、MTVというメディアについて考えたときにできた「ナウ・ソング」など、彼女の歌には現代のアメリカが投影されたものが多い。しかもその姿勢は明るくポジティブなエネルギーに満ち、聴くうちに彼女のパワーを貰った気分になる。
「だれかを励まそうと思って曲を書いたわけではないけど、女性に対するフェミニスト的なテーマは、アルバムのなかにさまざまな形で盛り込んであると思う。音楽ビジネスにいると、男性社会のなかにいるということをしばしば実感するので、それが歌になっていることはあるわね。ただ、アルバムを通して言えるのは、どの歌の中の人物も自分は何物なのかというアイデンティティを探している。それを探す課程で困難を乗り越え、打ち勝っていく、ということがひとつのテーマとして流れています。」
自ら本の虫という読書家。マーク・トウェイン、オー・ヘンリー、ジョン・アーヴィング、そして、スタインベックとフォークナーの名を好きな小説家として挙げた。「私が好きな作家は強烈なキャラクターを描いている人です。困難な状況に立ち向かっていく本物の人間を描いている作家が好き。」そんな小説の主人公は様々なキャリアを経てデビューに至ったこれまでの彼女の人生に重なるようだ。「私が育った農業のコミュニティでは、必死で働くことが最良のことだった。自分を失わず、自分自身であり続ける。そういう人たちが私の手本です。成功できたのは運もあるけど、自分のアイデンティティが、音楽を作るところにあったからだと思うわ。」
インタヴューの最後、次に目指すゴールは?と聞いたら「私にはゴールがないの」と笑顔で答えてくれた。「ラン・ベイビー・ラン」——その歌のように彼女は走り続けるのが好きなようだ。
(インタビュー、文/中安亜都子)
日本の夏、レゲエの夏
空前の盛り上がりを見せる‘95夏のレゲエ・シーン
No.16
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
さあレゲエの季節がやってきた。もはや“夏だけのシーズン物”という時代は過ぎ去り、一年中どこでも耳にするリズムとして定着したレゲエ。とは言ってもやっぱり旬は夏。今年もCDショップにはビッグ・ネームの復刻版から話題の新人のデビュー作、カバーの企画アルバムからヒット曲を集めたオムニバスまで百花繚乱。さて95年のレゲエ・シーンは果たしてどんな傾向にあるのだろうか。
PART 1
ロック&ポップス・ファンの心をつかんだレゲエ・ヒット。
●この夏を代表するレゲエ・ヒットは?
昨年を代表するレゲエ・ヒットと言えばビッグ・マウンテンの「ベイビー・アイ・ラブ・ユア・ウエイ」がある。映画「リアリティ・バイツ」のサントラにも収められた、ご存じピーター・フランプトン76年のヒット曲のカバーである。アーティスト、曲ともに今でもその人気は高く、昨年に引き続きレゲエ・サンスプラッシュで来日。今年もトリを務める予定だという。しかしこの曲が、レゲエというジャンルでのベスト・チューンかというとらえ方になると、いささか話が違ってくるように思う。
FMから流れる心地よいサウンドに耳を傾け、「おっいいな、この曲」と感じたら、たまたまそれが後乗りのリズムであった。つまり、特にレゲエにこだわらない、音楽ファンの心をつかんだナンバーだったということだ。
考えてみれば、92年はシャインヘッドの「ジャマイカン・イン・ニューヨーク」、一昨年はUB40「好きにならずにいられない」、そして昨年はビッグ・マウンテンと、毎年、その年のレゲエ・シーンを盛り上げるためのけん引者的楽曲が存在している。そしてその多くがカバー曲であるというのも興味深いとこだが、今年はというとカバーはもちろん、いまだにこれといった強力なヒット曲が現れていない状態だ。まさにレゲエ戦国時代といった様相を見せており、ならばとばかりに日本のレコード・メーカー各社も、こぞってオムニバスなどの企画アルバムをリリースしている。
たとえば人気の“MAX”シリーズに『ラガ・マックス』が登場したり、マンスリーでテーマ別にラバーズ・ロックを聴かせる『ラバーズ・スタイル』があったり、カバーにおいても人気アーティストが歌った曲を集めたアーティスト・オリエンテッドなものから、選曲のコンセプトに重きを置いたソング・オリエンテッドなものまで実に多種多様である。
●ルーツ・レゲエよりも洗練された作品に人気
日本でレゲエがブームであるとは言っても、そこにはやはり特徴があり、すべての音が受け入れられているとは正直思えない。この数年の間に急成長したこのレゲエというジャンルにおいて、必要とされる大きな要素は耳当たりの良さだったとも言える。ジャマイカ本国の、言葉は悪いが泥臭い、土着のサウンドよりも、ソフィスティケイトされた西洋寄りの音づくりをされた作品の方がチャートを賑わし、多くの支持を得る。ジャマイカからアメリカ、あるいはイギリスへと渡り住んだミュージシャンや、その音作りをニューヨークやロンドンへ持ち運んだアーティストたちの音だ。
今年の例で言えば、マキシ・プリーストの「クロース・トゥー・ユー」を思わせる「ミシェール」がヒットとなったアンドルー・ドナルズ。彼もジャマイカ生まれだが、その活躍の場を欧米に求め成功した1人だ。日本のFMから頻繁に流れていたのも記憶に新しいところだろう。そして同様にホットな動きを見せたといえば、昨年暮れの全米No.1アイニ・カモーゼの「ヒア・カムズ・ザ・ホット・ステッパー」や、ヒップ・ホップとの融合とニューヨーク色の濃い、ダイアナ・キングの「シャイ・ガイ」といったところか。いずれも頭1つ抜けた感こそあれ、「95年を代表する」とまでは行っていないのが現状だ。
長年にわたってレゲエに親しんできた人、特にラスタの思想(エチオピアのハイレ・セラシエ皇帝を生き神とあがめ、黒人のアフリカ回帰を説くもの)を歌う、ルーツ・レゲエを追求してきた人の中には「そんな軟弱な。レゲエはもともと南の小さな貧しい島の闘う音楽なんだ」と言う人もいるだろう。 しかし、そのルーツ・レゲエの、いや、レゲエ全体の神様とされるあのボブ・マーリイでさえ、ジャマイカ生まれの白人、クリス・ブラックウェルが主宰するロンドンのアイランド・レコードと契約を結ぶことによって、ラスタの嫌うバビロン(搾取する権力側、西側諸国を指す)のサウンド・エッセンスを取り入れることがあった。本国お失意の声に悩みながらも、それが結果として自らの存在や主張を、さらにはレゲエというものを世界中に知らしめていくことになったのだ。
PART 2
レゲエも今年はなぜか70年代のヒット曲ブーム
●ロックやポップスからの影響を反映
ボブ・マーリイの名を一躍世界へ知らしめるきっかけとなったのが、エリック・クラプトンが歌ったボブのカバー、「アイ・ショット・ザ・シェリフ」の大ヒット。これは、ロック・シンガーがレゲエの曲をカバーするという、今の流れとは逆のパターンだ。それにしてもレゲエにはカバーが多い。本誌のアーティストインタビューで何人かのレゲエ・シンガーに話を聞いたが、その理由として一番多かったのが「自分が影響を受けたアーティストや楽曲だから」という答え。特にメロディを大切にする歌もののミュージシャンは、リアル・タイムで聴いてきたR&Bシンガーの名を口にする。古くはマイアミあたりから流れてきたアメリカの電波をキャッチして、今なら最新の全米チャートを楽しみながら、レゲエのリズムに乗せたらどうなるのだろうと、ジャマイカンの遊び心が実験的方向へ走らせるのだろう。
また、面白かったのが「カバーだとは思ってないよ」という声。ジャマイカにはヒット曲のリズム・トラックをそのまま使う、ワン・ウェイ(またはワン・トラック)という手法があるが、そんな伝統が影響を与えているのだろうか、興味深い答えではあった。機械的ではない手作りの音が再び注目を集めるようになってしばらくたつ。『ホワッツ・ザ・411?』で70年代のサウンドとヒップ・ホップを組み合わせたメアリー・J・ブライジに始まる70’s重視の傾向は、最近ではポーラ・アブドゥルの最新作『ヘッド・オーバー・ヒールズ』にも見られ、70年代的アプローチの楽曲が詰まっている。またクラブでも“ダンス・クラシックス”と称して70年~80年代初めの、エレクトリック・ダンス直前あたりまで の音が人気を博しているらしい。この70年代的傾向は、レゲエのカバーにおいても例外ではない。
今年のカバー曲のオムニバスを見ても、E.W.&F、スティーヴィー・ワンダーはもちろん、ウエストコースト・サウンド、オーリアンズ、オーストラリアのエア・サプライ、さらにはキッスにスーパートランプと、意外とも思えるアーティストのカバーを発見することができる。また、ラバーズ・ロックの女性シンガー、キャロル・トンプソンがグローヴァー・ワシントンJr.の「ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス」をマキシ・プリーストと共演したり、UB40のリード・ボーカル、アリ・キャンベルがソロとして、ジャクソン・ファイブのアルバム『ベンのテーマ』から1曲カバー、「僕たちの夏物語」としてシングル・カットをしている。ジャネット・ケイの「ラビング・ユー」がミニー・リパートンによる75年の全米NO.1ヒットのカバーであることを思えば、もともとメロディ・ラインのしっかりしたところに題材を求めるのは以前からの方法でもある。とは言え、今年は特に70年代的(多少の幅はあるものの)傾向は顕著であるようだ。
●完全に定着した夏のレゲエ・イベント
今年も大小さまざまなレゲエ・イベントがやってきている。アニバーサリー的ライブといえば、アスワドの20周年記念のジャパン・ツアーが6月1日、日本武道館で行われた。ゲストにジャネット・ケイ、マキシ・プリーストを迎えた豪華なステージは、仲の良いレゲエ仲間のバースデイ・パーティに参加して、ひと足早く夏気分をも満喫したような楽しいものだった。ちなみに今年、彼らのデビュー・アルバム『アスワド』がCD化され、リリースされている。
そして、レゲエ・ジャパンスプラッシュ’95にレゲエ・サンスプラッシュ’95といった、例年通り大きな規模で行われるイベントも待っている。特にジャパンスプラッシュには、昨年この来日のために再結成したとも言われる、アイ・スリーが出演する。彼女たちはボブの生誕50周年記念、トリビュート・トゥ・ボブ・マーリイ・フェスティバル~ナチュアル・ミスティック・ツアーのメイン・アクトとして、5月末から30公演にも及ぶヨーロッパ・ツアーに行ってきた。その余韻もさめやらぬままに、日本のファンに今年もどんな歌を聴かせてくれるのか、そしてまた、ボブのどんな言葉を伝えてくれるのか、興味は尽きない。
ルーツ、ダンス・ホール、ラバーズ・ロック、その他実に多岐にわたり変化をとげているレゲエ・シーン。進化、発展するものもあれば、逆に衰退していくものもある。しかし、その時その時に与えてくれる感動はどの音楽にも言えることだが、ずっと心の中に残るもの。ジャマイカのサウンド・システムをそのままを運び込んだライブから、何万人と膨れ上がるコンサートまで、95年だから聴ける、観られる、そして感じられる、そんなレゲエを逃がさないように。今年の夏も、レゲエが熱い。
PART3
この夏はボブ・マーリイを聴かずにいられない。
●生誕50年を迎えたボブ・マーリィの足跡
今年は“キング・オブ・レゲエ”、ボブ・マーリィの生誕50周年にあたることから、CD、ビデオ、書籍など、彼に関する作品が続々と発売されている。ボブの妻、リタ・マーリィを中心とし、彼の活動には欠かせない存在だった女性コーラス・トリオ、アイ・スリー。彼女たちがボブのカバー集『蘇る魂~ソングス・オブ・ボブ・マーリィ』を発表。また、ボブと同じ年のベテラン・シンガー、マックス・ロメオがウェイラーズの音源をそのままに、それも同時期にボーカル・ダビングをしたものを集めた1枚、『マックス・ロメオ・シングス・ボブ・マーリィ』などの面白い作品もリリースされている。95年のレゲエ・シーンにおける大きな柱は、このボブ・マーリィの生誕50周年にあることは明らかだ。
1945年2月6日ボブ・マーリィはジャマイカ北部の教区、セントアンの小さな村、ナインマイルスに生まれた。父は白人のイギリス陸軍大尉、ノーヴァル・マーリィ、母はジャマイカ人女性、セデルラ・ブッカー。父親とは10歳で死別。とはいえ両親の国籍の違いもあって、生前から多くの愛を注がれていたとは言えない彼は、貧困の中に育つ、ごく普通のジャマイカ人少年であった。しかし幼少のことから歌に対する非凡な才能を発揮、14歳で初めてタレント・ショーに出演するなど徐々に才覚を現し、62年、17歳でシングル「ジャッジ・ノット」でデビュー。セールス面では不発に終わったものの、レゲエ界のスーパー・スターへの第一歩は、この時確実に印されたことになる。
それから3年後の65年には、ピーター・トッシュ、バニー・ウェイラーとともに、ウェイラーズを結成。ジャマイカ国内で数々のヒットを飛ばした後、72年にはアイランド・レコードと契約。アルバム『キャッチ・ア・ファイア』を発表した。翌年、続く『バーニン!』をリリース、イギリス、アメリカへのツアーへと出るが、グループは分解。オリジナル・メンバーのピーターとバニーが脱退してしまう。そこからはボブと彼のバンド、ウェイラーズとしての活動が始まる。妥協を許さないボブの元で、何度もメンバーの入れ替えがあったものの、ボブの魂は貫かれ、1981年5月11日、安息の地ザイオンへ旅立つまでに、残した10枚のアルバムとその後発表された数々の作品群、そして数多くの伝説のステージは、今でも燦然と輝き続けているわけだ。
彼の主張は徹底したラスタファリズム。思想的部分があまりに濃厚で、その歌の多くはジャマイカ国内のラジオには乗らず、逆に時として政治の宣伝手段としても利用された。その結果、反対勢力からと思われる狙撃にも合い、一命はとりとめたものの、ジャマイカを去り、アメリカへの亡命を余儀なくされる事件も起こっている。76年のジャマイカ総選挙の時である。しかしそのパワーは、当然良い方向にも力を及ばしている。62年のジャマイカ独立以降対立していた2つの政党、JLPとPNPが、78年、ボブを仲介として手をつなごうと平和コンサートを計画。首都キングストンで行われたそのコンサートのステージ上で、ついに両党首の握手を実現させた。またその年には長年の夢だったエチオピア訪問を果たし、その体験をたっぷりと反映した9枚目のアルバム『サバイバル』を翌79年に発表。その中に収められた1曲「ジンバブエ」は西アフリカの多くのミュージシャンによってカバーされ、戦うアフリカのテーマとしてそれぞれの民族グループに受け入れられ、後の独立運動に多大な影響を及ぼしたという。
そのほかにもネイティヴ・アメリカ・インディアンの部族などにも浸透していき、ボブの歌は、迫害を受ける人々の心を支えていくことになる。そして1980年、ジンバブエが独立した際、その記念式典にボブは公式に招かれたのだ。こうした出来事が、彼の予言的主張への自信を深めさせ、そのカリスマ性は自身の内外から一層強まっていくことになる。
●ロック・シンガーとも共通するカリスマ性
しかし、彼を支持した西欧各国の人々が、彼の主義主張を心から受け入れていたかというと疑問である。なぜなら白人層はもちろんのこと、第3世界といわれるジャマイカとはまったく異なる環境に生きる黒人層に、さほどのアフリカ回帰願望があるとは思えないからだ。もちろん個々のアイデンティティとしてのアフリカの血の尊厳は抱いているはずだが、ボブの言うバビロンに対しての彼の魂力は、1つの主義を貫き通す、その一貫した徹底性をステージで見せる、神をも思わせる神秘的な姿と巨大なカリスマ性にあったのではないかと思う。
これはボブに限らず、大衆がこれまでにあがめてきた数々の偉大なるロック・シンガーたちに共通する部分である。ボブの魂力がどこにあったにせよ、彼が世界にレゲエという、小さな島国の音楽を紹介したことに間違いはない。それがさまざまの国の音楽にも影響を及ぼし、最新の音やリズムに貪欲な一流ミュージシャンたちが取り入れることで、レゲエはさらにその範囲を広めていった。R&Bがレゲエに大きな影響を与えたのと同様に、今度はレゲエがロックを感化していき、やはり同じように互いにその良さをフィード・バックする。
この繰り返しが現在の“気がつけばレゲエのリズムだった”的な、ジャンルを超えた状況を作り上げてきたのではないかと思う。昨年“ロックの殿堂”入りを果たしたボブの、とても大きな功績の1つである。
(文/長谷川雄啓)
THE RED HOT CHILI PEPPERS
精神的ダメージから立ち直るための時間
No.21
Welcome Back! われらのレッド・ホット・チリ・ペッパーズが待望の新作『ワンホット・ミニット』を引っ提げて帰ってきた。彼らの人気、評価を揺るぎないものとした前作『ブラッド・シュガー・セックス・マジック』から実に4年ぶり。4年は長い。生まれたばかりの子供は、もう4歳の立派な子供になってるし、その間時流や流行も変わってる。
しかし、そんなことは彼らには一切無関係のようだ。今回も聴く人皆が満足するであろう、とてもリアルでプリミティブなロック・アルバムに仕上げた。フロントマンのアンソニー・キーディスが語る。意外に思うかもしれないが、インタビュー中の彼はとてもシリアスだ。
「確かに4年は長いよ。でも、今回新作を作るに当たり、そういう長い期間がオレたちには必要だったんだ。いろいろなことがあってオレたちは精神的ダメージを受けていて、まずそこから立ち直るのに長い時間を要したし、知っての通りギタリストも交代した。新ギタリスト、デイヴ・ナヴァロとうまくやっていくことができるのか? ということに確信を持つまでに、また長い時間がかかった。でも、それは決して無駄なことじゃなかった。なぜならその成果が新作にはっきりと出てるからさ」
彼らは92年初頭の再来日公演中からまさに不運の連続だった。その最中に前ギタリストのジョン・フルシャンテが脱退、2公演が中止になった。その後、後任を迎えて92年度の米ロック界最大の出来事と言われた“ロラパルーザ・ツアー”に参加し、各地で大絶賛された。が、終了後にまたもギタリストが脱退、後任決定も難航した。そしてアンソニーとベースのフリーの親友であり、俳優であるリバー・フェニックスの突然のドラッグ中毒死がさらなる追い打ちをかけた(新作で聴ける「トランセンディング」 は、リバーに捧げられた曲)。そんな彼らが新ギタリスト、デイヴを迎えて復活したのは昨年夏のことだった。『ウッドストック'94』でのロック史上に残る、あの仰天パフォーマンスでだ。
「頭にどデカい電球乗っけて、銀色のジャンプ・スーツに身を包んでライブをやるバンドがどこにいるよ。オレたちしかないじゃん。久しぶりのライブだったし、精神的にヘビーなことばかり続いていたから、皆を驚かせたいということや厄払いということも兼ねてあれをやったんだ。あれこそ究極のエンタテイメン卜だよ。そういう素晴らしいアイデアは、皆オレさまが考えるんだ(爆笑)」とドラムのチャド・スミスが豪快に笑い飛ばす。確かにあの姿には腰を抜かしたし、見た瞬間「やるねえ、さすが!」と思った。そう思った人は少なくないはずだ。「今だから言えるんだけど、あの電球すごく重くてさ、演奏中首がもげる~って何度思ったことか(笑)」とチャドはその時のエピソードも話してくれた。
●苦難の4年間を象徴する「精神的」メロディ
新作はそんないかにも彼ららしいエンタテイメントが満載されている作品であると同時に、長きにわたって彼らが味わってきた悲しみや憂鬱が顔をのぞかせる作品でもある。この4年間の彼らの真の姿が、激しいビートを基調としたファンク・ナンバーやゆったりとしたアコースティックのバラード・ナンバーなどに乗って見えてくる。乗り応え、聴き応え十分のロック・アルバムだ。アンソニーが言う。
「新作は感情的にヘビーな作品だと思う。もちろん、明るめの曲もあるよ。そうなったのは、曲を書いている時の心境がそうだったし、その時バンドが置かれている状況がそうだったからさ。もし、そうじゃなかったら今回聴いてもらえる精神的なメロディには出合わなかっただろう。もちろん、デイヴの貢献度も大きいよ。」アンソニーが言う精神的なメロディは時に突き動かされるほど刺激的であり、時に包み込まれるほど優しい。今回もまた彼らは突き抜けた。長いこと待ったかいがあった。
(インタビュー・文/有島博志)