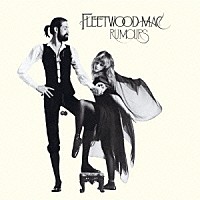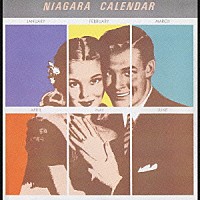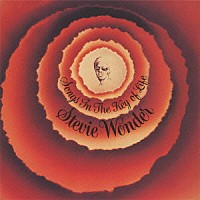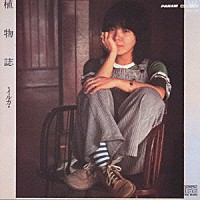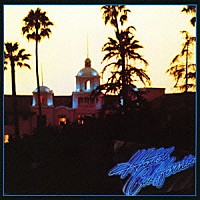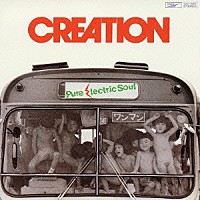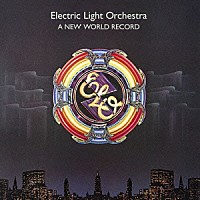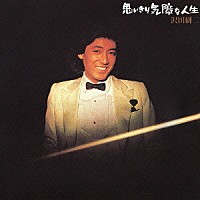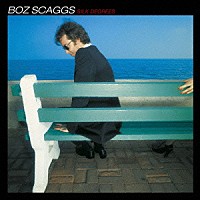FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集
ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!
TOPICS - 1977※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。
ワイルド・ウィークエンドの復活 パンク・ロック
パンクはキミ自身の中に存在するエネルギーの再発見だ/大貫憲章
No.3

Photo: Getty Images
パンクはライフ・スタイル
新年を迎え改めて1976年のロック界を振り返ってみると、やはりいろいろな出来事があったなぁ、って月並みな感慨におちいるけれど、その中でも、ぼくにとって最も印象深かった事件は、パンク・ロックとの出会いだった。
パンク・ロックとはどんなものなのかを、ひと言で説明するのはとても難しい。少なくとも、パンク・ロックは、ハード・ロックだとかプログレシブ・ロックとかいったような、音楽のスタイルを示す言葉ではない。もともと、パンク(PUNK)というのは、アメリカのスラングとしてずい分古くから使われていた言葉だ。字引きをひけば、そこには、「ヨタ者」、「こども」、「チンピラ」、「たわいないこと」、「オカマ」といった訳語がいくつか並べられているだろう。どうも、あまり良いニュアンスは持っていないようだ。バンク・ロックは、したがって、そういったパンクな個性を備えたロックということになる。
パンク・ロックという言葉そのものは、すでに60年代の終わりころから使われていたという。少なくとも、今日、パンク・ロックがブームのような状態になる以前から、その言葉は使われていた。
ちなみに、ぼくの持っているイギリスで発行された、みかけの安っぽい〝ヒストリー・オブ・ポップス〟に載っているパンク・ロックの項には、およそ次のような紹介文が戦せられている。
それによれば、パンク・ロックとは、60年代中期のアメリカのサイケデリック・バンドのいくつかを指すもので、例えば、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオス、クライアン・シェイムス、バーバリアンズ、スタンデルス、ナッズ、シャドウズ・オブ・ナイト&ザ・ミステリアンズ、シーズ、サーティンス・フロア・エレベーター、チョコレート・ウォッチ・バンド、ザ・リーブス、ストレンジラブス……などのグループが紹介されている。「ウーリー・ブーリー」の大ヒットを放ったファラオスやトッド・ラングレンのいたナッズ、「96粒の涙」の大ヒットを放ったミステリアンズなどは別として、あとはほとんど無名のローカル・バンドばかりだ。彼らは、主としてローカルなディスコやダンス・クラブを活動場所としていたセミ・プロ的なバンドで、同じサイケデリック・バンドでも、ジェフプーソンやデッドなどのスタ-とは、まるで別の世界で活動していたわけだ。もちろん、今ロのパンク・ロックと彼らとは同じではないだろうが、発想としては大差がない。
〝怒れる若者たち〟の〝理由なき反抗〟
それでは、今日のパンク・ロックのブームは、いつ、どこから火の手が上がったのかと言えば、75年の末ごろからで、場所はニューヨーク。表面化した最初の出来事は、パティ・スミスのレコード・デビューだろう。パティ・スミスは、ブルー・オイスター・カルトに詞を提供していたことで一部に知られていた女流詩人だが、いつの問にか自らバンドを従えてステージに立つようになり、そんな彼女にアリスタ・レコードが目をつけ、レコーディング契約を結んだ。これがキッカケとなり、彼女の周辺にマスコミのライトが集中し、にわかにニューヨークのアンダーグラウンドなロック・シーンが脚光を浴びはじめることになった。そして、面白いことには、同じころ、ロンドンの町でも、ドクター・フィールグッドがパブ・ロック・ブームの中から注目され出し、同じように、ロンドンのアンダーグラウンドなロック・シーンが関心を集めるようになっていたのだ。
こうした流れの辿りついたところが、パンク・ロックのムーブメントだった。現在、パンク・ロックは、若者のライフ・スタイルや意識、文化、風俗をも飲み込んで、ものすごいスピードで世界中に広がりつつある。そして、重要なのは、これが、単にロックという音楽領域内だけのムーブメントではないという点だ。これは、70年代の〝怒れる若者たち〟の〝理由なき反抗〟であるのかもしれない。50年代のビートニク、60年代のモッズと底流は同じだとぼくは考えている。
アメリカン・パンクとブリティッシュ・パンク
パンク・ロックとは、特定の音楽スタイルを指すものではないから、ひと口にパンク・ロックと言っても、十人十色というか、個性はさまざまだ。ただ、どちらかというと、ニューヨーク産の方は、インテリ臭が強く、やはり、かつてのベルベット・アンダーグラウンドやイギー・ポップなどのセンスを強く感じさせる。パティ・スミスやトーキング・へッズ、テレビジョンなどはその代表的な存在だ。また、ラモーンズ、ハートブレーカーズ、ウェイン・カゥンティ、ダフ・ダーツなどは、むしろ肉体的で、アンチ・インテリ的な様相を呈しているものの、どこか醒めている部分があり、いくら暴力的なハード・サウンドを叩き出していても、気軽にホイホイ乗れないような冷たさがあるような気がする。
一方、ロンドン産の方は、明らかにエキサイティングで、ちょうど60年代のモッズ族時代のビート・ミュージックがそうだったように青臭いふてぶてしさが濃厚だ。その旗頭は、EMIレコードとかなりの高額で契約したといわれるセックス・ピストルズ。ジョン・ロットンをリーダーとするこの4人組は、現在のロンドンの〝怒れる若者たち〟を代表する。すべてのエスタブリッシュメントにツバを吐き、襲いかかる。しかも、彼らはロンドンにふさわしく、いかにもファッショナブルだ。ちょうどモッズ時代のザ・フーやスモール・フェイセスがそうだったのと同じだ。このピストルズに続けとばかりに、ロンドンの町には、ザ・クラッシュ、ダムド、テイラ・ギャング、エディ&ホットロッズなどの若いグループが、毎夜毎夜、各地のパブやライブ・ハウスで興奮の渦を生み出している。
この他、ヨーロッパ各地にも、このパンク・ムーブメントは波及しており、フランスからは、リトル・ボブ・ストーリー、ピンク・フラミンゴスなどが現れ、デンマークからはガソリンが早々とレコード・デビューしている。
自己表現のロック、パンク
要するに、このパンク・ロック・ムーブメントは、すべてが管理されてしまったロック・システムに対する反抗であり、ロックに原点回帰をうながすとともに、現代の若者たちに、もっとエキサイティングになれとアジっている地下からのメッセージなのだ。だから、パンク・ロックのレコードを聴くことは、ただのキッカケにすぎない。より積極的に自己を表現し、状況を打破することこそ、パンクなのだ。3,000円払って、コンサート場に行って、その場限りの要求不満解消をして満足してしまうのは、ロボットと同じだ。もっと違う状況を自分から働きかけて作ろうという婆勢が重要だと、ぼくはパンク・ロックに出会って、改めて感じている。
(大貫憲章)

‘77ロックはトリプル・ギターで幕開け レーナード・スキナード
アンコールの「フリー・バード」まで大熱演のステージ
No.4
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
1977年のロック第一弾は、レーナード・スキナード、1月14日の東京・中野サンプラザホールを皮切りに計5回のコンサートを行った。サザン・ロックの第一人者というよりも、もはやアメリカン・ナンバーワンといっても過言でない彼らの演奏は、今年の幕開けにふさわしい大熱演だった。
アルバムを発表するごとに、そのスケールが大きくなっていくレーナード・スキナード。最新作「レーナード・スキナード・ライブ」では、トリプル・ギター・スタイルが復活、ライブ・レコーディングが彼らの本拠地アトランタのフォックス・シアターということを加味しても、予想以上に素晴らしいレコードとの評価を受けた。そして今春早々の来日コンサートは、日本のファンからそのライブ・レコード以上の賞賛で迎えられ、彼らもその期待にこたえファンを完全にノック・アウトした。
このグループは、アレン・コリンズ、ボブ・バーンズ、ロニー・ヴァン・ザントの3人がハイスクール時代に結成した小バンドが母体となってスタート。すぐにエド・キング、ゲイリー・ロッシントンなどを加えた3人ギターという異色の7人編成となった。
今はもうないアトランタの小さなロック・クラブ「フノチオズ」で演奏していた。レコーディングのために当時来ていたアル・クーパーが、彼らの演奏に圧倒され契約をかわしたという。これがサウンド・オブ・サウス・レーベルに至る彼らの歩み。
3枚目のアルバムを最後に「酒が飲めないため」(?)にエド・キングが脱退(真相はわかっていない)。鬼才トム・ダウドをプロデューサーに迎えた4枚目のアルバムでは、ツイン・ギターで演奏していた。昨年春に、スティーヴ・ゲインズと会い意気投合、待望のトリプル・ギターが復活。女性コーラス3人を含めた10人編成で来日。
「荒野の7人」のメロディに乗ってメンバーが登場。オープニングは、「ワーキン・フォーMCA」選曲は最新のライブ盤とほとんど変わりないが、やっぱりナマの迫力はすばらしく、グイグイと聴衆を引っ張っていく。アンコールの「フリー・バード」まで大熱演のステージは、日本のファンにも人気・実力ナンバーワンのアメリカン・バンドとしてはっきりと印象づけた。
第1部のアイドルワイルド・サウスも本場に負けるなと大ハリキリ、なかなかの好演奏を見せつけてくれた。
(共同)
甘さから力強さへ……スタイリスティックス
おなじみとなったスタイリスティックスの正月公演
No.4
もうおなじみとなったスタイリスティックスの正月公演。まだおとそ気分もさめやらぬ1月6日、会場の東京・渋谷公会堂には熱心なソウル・ファン、スタイリスティックス・ファンがつめかけた。昨年末、いままでのものとは少々毛色の違うアルバム「想い出のジュークボックス」を発表し、微妙な変化をみせるスタイリスティックス。その印象はステージにもうかがえた。一つは、典型的な聴かせるグループだったスタイリスティックスが、今回のコンサートではかなりステージ・アクションに気を使っていたこと。それともう一つは、〝甘く美しい〟を売りものにしていたコーラスが、かなり荒く力強くなってきたこと。この変化を日本のファンが歓迎するかどうかはわからない。しかし、スタイリスティックスが今新たな転換期を迎え、従来のイメージからの飛躍を目指していることを確かに感じさせるコンサートではあった。
(共同)
カルロス・サンタナ・プロフィール 人間的成長を物語る円熟した演奏
小倉エージ
No.5
 Photo: Getty Images
Photo: Getty Images
日本でも人気の高いグループ、サンタナのリーダー。官能的な泣きのギターで人気を集めている。
1946年、メキシコのアウトラン・ド・ナバロの生まれ。マリアッチ・ミュージシャンを父に持っていたことから幼いころから音楽に親しみ、やがてはティファナのクラブで活動を開始。その後、サンフランシスコに移り、66年にサンタナ・ブルース・バンドを結成し、クラブなどで活動を続けた後、ラテン的要素をグループの音楽に反映させ、マイク・キャラベロ、チェピート・アリアスらラテン・パーカッション奏者を加えたラテン・ロック・バンドとなり、サンフランシスコにおいて絶大な人気を獲得し、69年にレコード・テビューを果たした。
デビュー間もなく数多くのヒットを相次いで放ち、ウッドストック・ロック・フェスティバルへの出演を契機としてその存在は広く知られ、日本でも情熱的な親しみやすいサウンドが受けて、たちまちのうちに人気を獲得。
カルロス・サンタナは、そうした時期まではB・B・キングらブルース・プレイヤー、さらにはジミ・ヘンドリックスなどの影響もうかがえたが、その後グループがメンバー・チェンジを繰り返し、洗練されたサウンド作りを見せはじめるとともに、カルロスのギターにはJ・コルトレーン、マイルス・デイヴィスの影響が見られるようになった。さらによりリズムを重視し、ソウル/ジャズ色濃い洗練された音楽性を持つとともに、スティヴィー・ワンダーらの影響を見いだせるようになったのである。
それらからも明らかなように、カルロス・サンタナは、単にギタリストより他の分野のミュージシャンから多くのものを学びとっているところが注目される。そして、テクニックよりも、ナイーブな個性を反映した独特の味わいのある演奏、ギター・スタイルを持っているといえよう。最近では、人間的な成長ぶりを物語るかのように、ゆとりある熟した演奏を聴かせるようになっている。
(小倉エージ)
熱唱!泉谷しげる
ロサンゼルスでジャクソン・ブラウンらと共演
No.7
4月8日から3日間、東京で「The Sea Must Live!」を合言葉に開催される「ローリング・ココナッツ・レビュー・ジャパン」。内外のミュージシャンが多数参加し、音楽を通して「海洋汚染を救え」と訴える。ところで、この一大イベントに先立ち、泉谷しげるが2月5日から26日まで渡米。サンフランシスコ、マイアミ、ニューヨーク、ロサンゼルスで記者会見を行うとともに、2月9日にはこのイベントの資金調達のためのベネフィット・コンサートにゲスト出演した。
コンサートは2月9日、サンフランシスコのサンホセ芸術センターで行われ、出演はジャクソン・ブラウン、ジョン・デイヴィッド・サウザー、ウォーレン・ジヴォン、泉谷しげるの4人。メインはジャクソン・ブラウンだが、泉谷はJ・D・サウザーに紹介されて登場、「野良犬」を歌うとともに、カタコトの英語で「The Seas And Whales Must Live And People Too!」とやり、観客から「サイコー(最高)」の大喝采を受けた。
(共同)
ジャニス・イアン 「日本で私のコンサートができるということは驚異的なこと」
日本公演初日は9月2日、横浜の神奈川県民ホール
No.20
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
8月24日、午後1時58分、ジャニス・イアンを乗せたパンナム801便は、日本の空の玄関、羽田空港に着陸した。日本のファンの前に初めて姿を見せた彼女は4フィート0.5インチ(約149cm)、104ポンド(約47kg)という小柄だが、ちょっぴり太りぎみ。そして意外なほど気さくで明るい。しかし、その明るさはレコードで想像していた彼女の自閉症的繊細さのイメージとは若干のズレがある。
「13歳でデビューし、いま26歳。人生の半分来てしまった。(背と比べて考え方の)根本的な点では変わらなくても、人生に対するアプローチは変わってきたと思う」
『l7才の頃』から2年、その前の話題作『ソサエテイーズ・チャイルド』からは11年。時の流れは、一人の少女を明らかに変貌させていった。それはコンサートの中にもうかがえた。
日本公演初日は9月2日、横浜の神奈川県民ホールで行われた。
「日本で私のコンサートができるということは驚異的なことです。確かに言葉のギャップはあるけれども、ほんとうにいい歌手というのは、音楽それ自身が通訳になってくれるのではないでしょうか」
コンサートは彼女の演奏する楽器により、3パートに分かれていた。アコースティック・ギター、ピアノ、エレクトリック・ギターと各パートごとに彼女は4~6曲を歌う。各パートごとの選曲をみていると、彼女のサウンドの変化、ひいては生活の変化まで読みとれるような気がする。アコースティック・ギターの部では、主にアルバム『スターズ』と『愛の回想録』から。ピアノの部で、大ヒットした『ラブ・イズ・ブラインド』が登場する(『ラブ・イズ・ブラインド』はアルバム『愛の余韻』から)。そしてエレキの部では、最新アルバム『奇跡の街』が中心となる。これは完全に彼女の出したアルバムの順序と並行する。初期のクリスタル・グラスのようなキラキラと輝く、それていてどこかモロさをもったジヤニスの音世界が、『愛の余韻』あたりから、いつの間にかエネルギッシュでワイルドな音世界へと、その色彩を変えてきている。冬の部屋でひざを抱えてうずくまっていた少女が、いまは自分の城を飛び出し.ダイナミックに躍動している。
「デビューした時は両親と一緒に住んでいて貧乏だった。でも今は違う。お金も持っているし、好きなことができる」
こういった生活の変化は、一人のアーティストが有名になっていく過程でだれでも経験する。そして、それがそのアーティストの音楽に大なり小なり影響を与える。しかし並外れてとぎすまされた感性の上に築き上げられたジャニスの音楽が、その生活状況の変化によって感性を鈍らせていくとしたら……エネルギッシュでワイルドなジャニスを見ていると、そんな危険性をはらんでいるように思えてならなかった。
(共同)