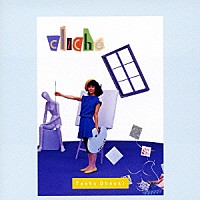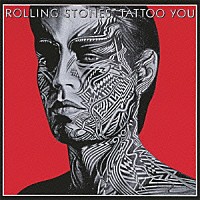FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集
ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!
TOPICS - 1982※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。
海外特別取材!アース・ウィンド&ファイア レポート
新作アルバム「天空の女神」が以前に劣らないペースでセールスを記録
No.4

Photo: Redferns
アメリカでも、日本でも、アース・ウィンド&ファイアのニュー・アルバム「天空の女神」が素晴らしいセールスを記録している。グループ内での評価としては「今でもあれは非常に音楽的にうまくいっている」(ヴァーデン・ホワイト)と語っているが、前作「フェイセズ」が、従来のアルバム・セールスから見ると決して成功したとは思えなかっただけに、このアルバムの成り行きが大きく注目されていた。
キャッシュボックス誌が「単に6枚連続プラチナ・アルバムの後に、ゴールド・アルバムが出ただけのことである」と、アッサリかたづけているように、新作アルバム「天空の女神」が以前に劣らないペースでセールスを記録している。
アル・マッケイがグループを抜け、ローランド・バウティスタが8年ぶりに復帰した新生アース・ウィンド&ファイアは、ニューヨークのナッソー・コロシアム、マジソン・スクエア・ガーデンのコンサートも超満員の大成功を収めた。なお、昨年のローリング・ストーンズの全米ツアーと同じく、このアース・ウィンド&ファイアのコンサートにも大企業のスポンサーがついている。
「今ではほとんどの大型グループがその種のサポートを受けていると思う。業界全体が変わって、レコード会社は、もうツアーにお金を出してくれないんだ」
このコンサートのスポンサーはパナソニック(ナショナル)。
「ずいぶん長い間、コマーシャル的なものとは遠ざかっていた。それが“パナソニック”と組むことになったのは、僕もよくカセット・レコーダーを使うからさ。だから、バドワイザーのコマーシャルをやろうとは思わない。ビールは飲まないからね。」
今年からは、興味を持っているサウンドトラックはもちろん、フィルム自体の方にも進出して行こうという彼らは、アルバムも既に13枚だ。モーリスのプロデューサー業のほか、最近では、シンガーパーカッションのフィリップ・ベイリーが近々ソロ・アルバムを発表するなど、個々の動きも目立つが、グループとしてのチームワークもガッチリ固まっている。「メンバーの姿勢も、時がたつにつれて、最初のころよりもグッと近くなった。今はもう完全な家族のようだ」(モーリス・ホワイト)。
(共同)

ビートルズ解散のきっかけを作ったのはリンゴだった!
解散に積極的だったのはジョン・レノン、逆にグループの存続を強く望んだのはポール
No.4
 Photo: Getty Images
Photo: Getty Images
ポール・マッカートニーとリンゴ・スターが11年前のビートルズ解散の事情をそれぞれ新聞、雑誌に語った。ポールはイギリスのタイムズ紙、リンゴはアメリカの音楽専門誌モダン・ドラマーのインタビューに答えたもので、それによると解散のきっかけを作ったのは意外にもリンゴだったようだ。また解散に積極的だったのはジョン・レノン、逆にグループの存続を強く望んだのはポールだった。
ビートルズ分裂にはこれまで、直接の責任はポールにあるとする“非難”が一部に根強くあったが、この点についてポールはまず「4人の中でグループの存続を最も望んだのは、この僕にほかならない」と反論。コンサート・ツアーを続け、団結を図るべきとの立場をとり、「解散やむなし」の結論に達したのも一番最後だったという。
しかし解散が避けられなくなった時点では「離婚する夫婦がそうであるように」早くきれいさっぱり終わらせてしまいたいと考えた、とポール。いずれにしても「分裂の直接の責任は僕にはない」と強調している。
ポールはまたジョンとの不仲説にも触れて解散後の、ポールに対するジョンの批判にはショックを受けたと述べながらも、そのことはポールに、ひとりでも成功できる力があることをジョンに見せてやろうという気を起させたにすぎない、と語った。リンゴは一方グループの中にあって創作活動の面ではいつも疎外感を味わっていたと、興味深い事実を明らかにしている。リンゴによると、ほかの3人は彼の名声を保証してくれ、彼もビートルズ神話を信じたこともあったが「ビートルズとはとどのつまりポール、ジョンそれにジョージ・ハリスンのことでしかなく、私の周囲にその偉大な3人の友人がいたというだけだった」という。結局は自分を「グループのお荷物」と感じるようになり、脱退を考えた。そして最初にジョン、次にポールに会って気持ちを伝えた。4人が解散を決めたのはそれから2週間後、話し合いの結果「それぞれが心に独自の音楽観を抱いている」と、ジョンがそのことをすぐ口にしたそうだ。
ビートルズの解散に対しては、マネージャーのブライアン・エプスタインが自殺しなければくい止められたかもしれない、との見方がある。しかしポールは「当時、既にブライアンの時代は終わりつつあり、影響力はなくなっていた」と指摘している。
(大貫憲章)
ゲーンズブールが仏国歌の原譜落札
「ただ自宅のピアノの前に飾って眺めたいだけ」
No.5
女優の細君ジェーン・バーキンとのエロチックなデュエット「ジュ・テーム」で日本のファンにもなじみ深いフランスの反骨歌手セルジュ・ゲーンズブールが、このほどベルサイユのオテル・ラモーで行われた競売で、作曲家ルージュ・ド・リルによるフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」の原譜を3万ドル(約660万円)で落札した。
ゲーンズブールの落札が決まると、会場はやじと不満の声で満ちたという。
というのも、ゲーンズブールには“国歌冒とく”の前科があるため。日ごろから国歌は民衆の声を反映しなければならないという主張を持つ彼は、2年前ストラスブールで行ったコンサートでこれを実践「ラ・マルセイエーズ」をレゲエに編曲して披露した。これに腹を立てた“愛国者”らは、ゲーンズブールに対する脅迫やいやがらせを行い、特にストラスブール駐屯の陸軍部隊は“レゲエ版国歌”を公演からはずさなければ実力でも公演を中止させると申し入れ、ゲーンズブールもしぶしぶこれに同意したことがある。
今回の原譜落札について、ゲーンズブール自身は「ただ自宅のピアノの前に飾って眺めたいだけ」とすましているが、周囲には、何かこんたんがあるのではないかとの声が強い。
(共同)
アメリカン・ミュージックのルーツ ライ・クーダー インタビュー
山下憲子
No.6
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
エリック・クラプトン、ジミ・ヘンドリックス、デュアン・オールマンetc…とロックの分野に限っても、ギターの名手といわれる人は数えきれないほどいる。が、そんな中でも、ちょっと特異なところに位置する“名人”がライ・クーダーだ。なにしろ彼がこれまで演ってきた音楽といえば、黒人音楽、前衛からハワイアンまでと実に多岐にわたっており、ジャンル分けは不可能に近いし、そのうえローリング・ストーンズのLP「レット・イット・ブリード」などにも参加しているから、ロック・ファンももちろん目が離せない、とういう人なのである。
そんな彼の音楽をあえて一つの線で結ぶとするなら、“ルーツ・オブ・アメリカン・ミュージック”ということになるのだろう。これまで発表された9枚のソロ・アルバムを眺めてみても、そのどれもにアメリカ音楽のルーツである、フォーク、ブルース、カントリーが極めてオーソドックスにかかわっている。しかも、それを少しも古くさく感じさせないところに、このライ・クーダーの存在価値があるのだ。
今回この“ボトルネック・ギター”の名手が、『荒野より=ハードタイムスへようこそ』の新パーソナリティになるという。同番組スポンサーのCFキャラクターとして既におなじみだが、そのヌーボーとした表情同様に興味深い、彼のおしゃべりを少し紹介しよう。
―幼児期のことをまず話してください。
R 1947年にカルフォルニアのロサンゼルスで生まれ、今34歳です。一人っ子で、父母と3人で西部のサンタモニカという海岸にちかいところに住んでました。父はいつもフォーク、クラシック、ボーカル、ピアノ曲などあらゆる音楽をかけていました。3歳くらいの時、父がもらってきた4弦の小さなテノール・ギターを、子供の割には手の大きかった私は、父に学んで弾いてみたのです。今でもこのギターは大切に持っています。ギターは弾くのも聴くのも好きで、学校をさぼってはヒルビリーやらブルースやらを、ラジオで一日中聴いていたものです。
―一番最初に持っていたギターは。
R シアーズという大きなデパートで売っていたもので、約3フィートの長さの木製の4弦だったので10歳まで使いましたが、そのころになって父が6弦のスティールのマーチンを買ってくれました。
―8歳の時にジョッシュ・ホワイトのレコードをもらったそうだけど…
R あまりよく覚えてないんだけど、ジョッシュ・ホワイトというのは当時白人によく知られている黒人のエンターテイナーだった。彼はブルースを口あたりよくアレンジして、ディープ・サウスについて何も知らない白人にも分かりやすくした。うまいミュージシャンだし、力強い歌い方をするし、彼のレコードを買いあさったこともある。彼のようにうまく弾きたかったが、私はまだ12歳だったので彼と同じようには弾けなかったけどね。
―16歳の時にアッシュ・グローブというクラブで初めて演奏したんだよね。
R ミュージシャンのたまり場だったのでしょっちゅう行ってたね。ある日、店のオーナーがそこでうたっている女性歌手のバックをやらないかっていう話をもってきた。彼女はポップ・シンガーでフォークを中心に歌ってたんだけど、ジャッキー・デシャノンという、けっこう売れたロックン・ロール・ライターらしかった。
紹介されて会ってみるととてもいい人だった。このクラブの仕事をしばらくして、それからディズニーランドで演奏したり、テレビに出演したこともある。彼女は有名だったし、仕事の用もあって、ある日レコード・スタジオに連れて行ってくれたこともある。とってもいい経験になった。当時、高校生の普段することといえばサーフィンや映画を見ることぐらいでしょ。それよりはよっぽど楽しかったと思うよ。
(山下憲子)
KINKS来日レポート 拍子抜けするほどストレートなロックン・ロール
伊丹由宇
No.9
 Photo: Getty Images
Photo: Getty Images
“恋に恋する”という言い回しがあるが、ぼくのキンクスに対する思いは、そんな風だった。60年代半ば、リバプール、サウンド群の一グループとして登場したキンクスは、その時に異彩を放っていた。
ちょっぴりヒネクレ、ちょっぴりシニカルで、ちょっぴり破壊的で。つまり、イカしてたのだ。気がつくと夢中になっていた。キンクスに関しては誰にもなにも言わせないぞ。リリースされるレコードを追う度にキンクスへの思いが強まり、彼らの悪口は“禁句”・・・・・10年を過ぎた頃から、僕は自分の幻想を愛していたに違いないのではないか、そんな風に思ったりしたものだ。そこで、ついにというか、とうとうというか、キンクス(私の中では即ちレイ・デイヴィスなのだが)を眼前に見ることになった。
伝説のレイ・デイヴィスは、驚くほど若々しく、しなやかだった。昨年見たライブ・フィルムでは、ちょいと老けて渋い感じがしたのだが、「彼はもう次のステップに完全に足をかけていた」。最新アルバム「ギブ・ザ・ピープル」のサウンドが、現在のレイ・デイヴィス自身なのだと理解され、ぼくは、それをオンナのせいではないか?…強く肯定の気持ちで推測したのだが、ステージは、拍子抜けするほどストレートなロックン・ロールに終始した。「ロウ・バジェット」「ギブ・ザ・ピープル」からの曲が多く、そして突然・・・・「ローラ」。ギター・コードひとつで胸がしめつけられるように感じたのは、ぼく一人ではあるまい。続いて「ユー・リアリー・ガット・ミー」「オール・オブ・ザ・ナイト」。ただ涙ナミダのホールド・アップ。そして、「ツイスト・アンド・シャウト」の大サービス。“キンクスだ、ああ、レイ・デイヴィスだ、ホンモノのキンクスだ・・・・・・”
頭の中がキンモクセイの香りで一杯になりそうな瞬間、「ワイは、ミーナーなんや、それでエエンヤ」なぜか大阪弁でつぶやくのでありました。
聴きたい古い曲があまりにも多すぎてもんどりうちそうになりながら、ぼくは現在のキンクスに何のためらいもなく期待感をキープし続ける。充足感と飢餓感を同時に受け入れ、ぼくは、現実にため息のOKサインを送った。何年後でもあろうと、また音楽がどう変わろうと、“われらの時代”を語るに、キンクスこそ“われらの味方”なのだ。コンサートの終わりぼくは久しぶりにジンのストレートを体に流し込んだ。
(伊丹由宇)
特集:次の時代を走り抜ける日本のロックバンドたち
大野祥之
No.7
時代はいま、シェイプアップといったなまやさしいものではなく、もっとハードでパワフルでエキサイティングな肉体を要求している。理屈をこねくりまわすよりも、汗をかき、ダンスをし、叫び、ファイトするロッカーたちが、日本のロック・シーンの中で浮上しようとしている。ここで紹介するバンドたちは、RCサクセションや甲斐バンドといったスーパーグループを追いつめ、次の時代を走りぬけようとするロックバンドたちである。
■プロローグ■
いろんな意味で、今年は日本のロックが浮上し、注目を集めるようになるに違いない。
それは、ここ2、3年ロックは質的に変化し聞く側の耳に素直に入ってくるようになったことが一番の大きな理由だ。例えば、ほんの2年前ほど前に、気味悪がられていたRCサクセションが、今ではライブハウスから3,000人以上のキャパシティをもつホールでコンサートをうてるようになったし、テレビにまでその活動の輪を広げられる状況になってきた。YMOの海外ツアーは、イギリスの音楽シーンを日本のロックに注目させ、一風堂の土屋昌己や、イギリスでは“ニューズ・ビート”というバンド名でコンサートをおこなったモッズなど日本のバンドが、海外に進出できる状況を形成しつつある。
こうした日本のロック・シーンを築いてきたYMO、クリエイション、柳ジョージ&レイニーウッド、甲斐バンド、RCサクセションなどは、既に自分たちの地位を確固たるものにしたといってもいいだろう。
ライブ・バンドとしては最高の動員力を誇りながら、今までチャート・インしなかったRCサクセションも、YMOの坂本龍一とリーダーの忌野清志郎が共演した資生堂のCMソング「いけないルージュ・マジック」で、ヒット・チャートの上位に進出し、次に出すシングルさえヒットすれば、一般のファンからの幅広い支持を得られるはずだ。
さて、ひと口に日本のロック・シーンといっても、そこには多種多様なバンドがひしめき合っている。ジャンルとして分けられるものもあれば、どんなジャンルにも属さずに、自分たちのポリシーを貫き通し、独自のサウンドを持っているバンドンもある。
いわば混然一体となって突き進んでいる日本のロック・シーンだが、前記のようなベテランや中堅どころのバンドに続く、次の時代を形成しそうなバンドが、ここ1年ほどの間に急成長している。これには、ニュー・ウェーブと呼ばれ、異端視されがちだった時期にデビューしたバンドや、石井聰亙監督の「バースト・シティ(爆裂都市)」に出演したロッカーズやルースターズなど、かつて“めんたいロック”と呼ばれた連中―みんながかつては何らかのムーブメントとしてひとまとめにされていたバンドばかりだが―その中からしぶとく生き残り、自分たちの方向を定め確実に頭角を現しつつあるこれらのバンドたちを見過ごしていたら、今の時代のロックの最もオイシイ部分を食べ残すようなことになる。
しかも面白いことに、これらのバンドの多くが、鮮明なリズムに裏打ちされた躍動感と、他のバンドとは少しもにていることのない独特の存在感を持っている。
頭でこねくりまわすよりも、汗をかき、踊り、叫ぶ・・・・。まさしくフィジカル・エイジの申し子たちだ。時代はシェイプアップといったナマやさしいものではなく、よりハードな肉体を要求しているかもしれない。
これから紹介するバンドたちは、既に名前は知られてはいるが、そのネオ・フィジカルなパワーで、RCサクセションや甲斐バンドを追いつめる、次代の、そして時代を走り抜けるロック・バンドたちである。
■TENSAW■武骨で、それでいてやさしい“ハマ”の裏街のにおいを漂わす
東京と横浜。近いようでいて、全く違った匂いを持った街。バイタリティにあふれ、スリムでファッショナブルな表通りから一歩路地に踏み込めば、バタ臭くギラギラと脂ぎった汗が飛び散る町。そこが横浜(ハマ)だ.
セイボーこと田中聖一(Vo)と鈴木享明(Bs)が初めて出会い、グリコこと富岡義広(Ds)そしてギターのタケこと横内健亨が知り合ったのもハマだった。
柳ジョージを初めとして、ハマの連中はひとくクセふたクセもある臭みを持っている。テンソウの連中がこんな街で育って、バンドを始めた時、この街が彼らに与えたものは、持ち前の粘り強さと、パワフルなガッツだった。
80年、テンソウがデビュー・アルバムを引っ下げてハマを旅立った時ごく一部の早耳のファンだけが彼らを支持していた。ちょうど、ニュー・ウェーブ。ブームが一段落しかけていた時期に、古典的とも思えるオーソドックスなロックを伝える彼らは、次のファッショナブルなブームを探し求めるシティ・ボーイズたちには見つからずに済んだ。その代りにテンソウの、体中で表現するパワフルな感情に共鳴したファンが、横浜を中心にガッチリとテンソウをプッシュし始めたのだ。
「最初はさ、ただカッコイイって思えるバンドがいなかったからね。でも、それだけじゃヤバイと思って考えたのね。ばかも少しは勉強するようになったとういうか…」と田中聖一が当時を振り返ってこう語る。
4月に来日するジャーニーとの共演を控えてテンソウのボルテージは、今まさに爆発せんばかりに高まっている。ひとりのスターがいて、バックに付いているような形のバンドなら、それこそ掃いて捨てるほどいるが、メンバー全員がひとつのかたまりとなってパワフルなビートと大きなウネリを発散しているようなバンドは少ない。
テンソウの持ってる魅力をひと口で表現するならば、このバンド全体がローリングする躍動感であり、包み込むような大きなウネリを持った余裕といえるだろう。
「テンソウの役割っていうのは、ロックのかっこ良さを知らしめたいっていうのかな。うまく言えないけれど。」と自分たちの基本姿勢を田中聖一が説明してくれる。いかにも武骨で、それでいて優しいというムードが彼らから漂っている。ハマの裏街と同じニオイ。
70年代の英米からのロック攻勢を受け、それを真正面から見すえることによって、自分自身のロックを探し、それストレートに表現する。だからこそテンソウはロックにこだわり続けているのだ。ヤワなロックではなく、鋼鉄の歯ごたえのロックを求めて、横浜のハンパ少年たちは“男”になってきた。
■子供ばんど■子供のエネルギーそのままに歌い、踊り続ける底抜けの明るさ、楽しさ
「楽しくやりたね!だんだん楽しくないことが増えてきたからね。楽しくやりたいよぉ!」
本人達がそう言うだけあって、どんなに落ち込んでいる時でも、子供バンドのライブを見たら、だれでもハッピーな気分になれる。
大人じゃできないから、子供のままでやるってワケだ。年間ステージ数300回を下らないという子供ばんどのタフネスぶりには、外国のバンドもびっくりするだろう。だけど、元気にはねまわるのが子供の特徴。楽器車にバンドの楽器と4人のメンバー、それにマネージャーという身軽さで、子供ばんどは日本中のライブ・ハウスを走り回ってる。
リーダー、ギター、ボーカルのうじきつよしがステージに登場すると、場内はワキにワキ、その姿に笑い転げる。頭にはヘルメットをかぶり、小さなアンプがその上にのっている。手には普通のギターより、二まわりも小さなミニチュア・ギター。こんな姿でハードなブギをキメるうじきは、今までになかったタイプの“底抜けに明るいロック・ミュージシャン”だ。今や全米ナンバー・ワンのAC/DCのアンガス・ヤングと比較されるほどの個性は、隣の家のお兄チャンがステージにいるみたいで、ポストRCサクセションとの呼び声もチラホラ。
谷平こういち(G)、湯川トーベン(Bs)、山戸ゆう(Ds)という他のメンバーも、ユニークなことにかけては、うじき以上だ。親しみやすさと“パワー・ロック・ジェネレーション”と、自らがこう呼ぶガッツなステージングで子供ばんどはこの1、2年のうちにライブ・ハウス超満員の状況を作ってしまった。
また、その発想も実にユニークそのもの。昨年11月、12月、今年の1月と、3か月続いた17インチ4曲入りのコンパクト盤を出した。そのタイトルも、「ホップ」、「ステップ」、「ジャンプ」と3段跳び。3枚のコンパクト盤を集めると、全部で2,600円になり、それを1枚のアルバム「ジャイアント」にするというアイディアを実現させた。
流行の貸しレコード屋対策という意味もあるだろうけれど、それよりも子供のおもちゃの超合金合体ロボットを思わせる。こんなバカげたアイディアも子供ばんどならでは。
次のアルバムは待望のライブ・アルバムになるし、夏から秋にかけは、今まで日本でやっていた活動の延長線でアメリカに殴り込みをかける計画も練っている。
楽しさイッパツで、暗い世間をぶっ飛ばす子供ばんどの勢いならアメリカの連中の目を白青(?)させられることだろう。子供だからこそ、子供の心情そのままに歌い、踊り続ける。こんなヤツらのステージを見たら、それこそこっちまで楽しかった子供のころに戻っちゃうかもね・・・・・。
■モッズ■ぜい肉ゼロパーセントの言葉とサウンドを武器にして世界を見据える
世界を見つめる目は、何も東京や大阪などで育つとは限らない。九州・博多、かつてサンハウスの、シーナ&ロケットを生み、そして映画「バースト・シティ(爆裂都市)」に出演して、その話題をさらいそうなロッカーズやルースターズを生み出した街だ。 博多っ子の、こうと思い込んだら何が何でもやり遂げてしまう粘り強さと、良い意味でも悪い意味でも強情な性質からか、博多出身のバンドは強固な意志力でサウンドを創り上げる。
森山達也(Vo,G),北里幸一(Bs)、茶ノ木<地先>裕之(G)、梶浦雅裕(Dr)の4人のモッズは、そんな街から世界を見つめ、ファースト・アルバム「FIGHT OR FIGHT」をロンドンでレコーディング。セカンド・アルバム「NEWS BEAT」発売後、昨年の12月には夢にまで見たロンドンのマーキー・クラブでのコンサートを行った。
次のアルバムはその時のライブ・アルバムになる可能性もあるという。現在、YMOや一風堂によって、ロンドンはその目を日本に向けようとしている。そんな時、エレクトロニクス・ミュージックではない、日本のビート・バンドがロンドンに出現したのだから、モッズがロンドンっ子の注目を集めることになったのも無理はない。
最近、とくにモッズは脂がのって来ている。ライブ・ハウスで収容しきれないファンたちがあふれ、コンサートで騒動が起きることもある。
「仕事がイヤやけん、音楽をし始めた部分もあるしね。それが音楽まで仕事だとか、やらなくちゃいけないってなったら、オレ関係ねぇよってなっちゃう。ただ、最近オレたちを客の方が“モッズはオレたちの代弁者だ”とか祭り上げるけど、それはとんでもないカン違いだと。オレたちそこまでえらくないし、まだまだ青二才だし、そこまでオレたちに圧力をかけられたら、子供たちのための仕事になる。それはゴメンやと・・・・」
森山自身、かつては家出少年だった。だからこそ、ファンの気持ちは分かるだろうし、ファンから代弁者と思われるのも当然だが、「楽観的に一人なんだという事を考えてほしい。一人っていうのはどうにでもなるし、二人になる時もあるしね」という森山の言葉は、簡単でいて真理を語っている。
モッズの在り方は、表面ではなく内面に語りかける性質のものだ。難しい言葉を並べたてられ、理屈で説得されるよりも、簡単明瞭な言葉で、しかも切れの鋭いビートとともにぶつけられる方が、スッと心に入ってくる。
ぜい肉ゼロパーセントの言葉とサウンドこそ、モッズが生まれながらにしてもっている武器だし、この時代に生きている人たちの心のどこかにある内面と共鳴するものだ。また、イギリスに行ってツアーを行うという話もあるというが、博多から世界を見据えたモッズの戦いが、そこから始まるといえるだろう。“闘うか、ブッ飛んじまうか”モッズの宣戦布告が聞こえる。
■A.R.B.■振り上げたこぶしにシンボライズされる 飢えた魂と不条理への怒り
ボクサーとロック・ミュージシャンはハングリーな方が良いといわれる。犯罪者もある意味ハングリーなのかもしれない。A.R.B、つまりアレキサンダース・ラグタイム・バンドは、ハングリーだと囁かれ、熱く燃えるバンドと噂されてきた。魂が飢えているからハングリー。不条理に怒るからこそ燃え上がる・・・・。
A.R.B.は振り上げたこぶしに似ている。こみあげてくる激情の中には、怒りと憎しみもこもっているだろうし、ひとかけらの口惜しさと涙も同時に込められている。
かつて、A.R.B.のオリジナル・メンバーは5人だった。そしてキーボードとベースが抜けて、A.R.B.はバンド活動を停止せざるを得ない状態に追い込まれたこともある。今から2年前のこの時こそ、A.R.B.の最も苦しかった時期であり、彼らが心底から闘志をもやした時でもある。
ベースをギターの田中一郎が弾き、ボーカルの石橋凌とドラムのキースだけの3人で作ったシングル「魂こがして」を、この時期に発表したことによって、普通のバンドならば落ち込んでしまう状況を、自分たちのコヤシにしてしまった。
そして、セカンド・アルバム「BAD NEWS」から、現在のベーシストのサンジがA.R.B.に参加し、苦境さえも克服してしまうバンド体質が出来上がった。
「自分たちの実感として、『BAD NEWS』で固まったというか、これをやらなければっていうのはありましたね。」
と、田中一郎が言うとおり、A.R.B.の現在のスタート・ポジションとなったのが、このアルバムだった。
田中一郎の研ぎ澄まされたギター・ワークは定評が高く、甲斐バンドのアルバムでも、彼のギターを聴くことができる。
同じ九州の出身なので、昔からの知り合いだったというが、田中のギター・サウンドが甲斐バンドを強力にサポートしていることも事実だ。
最新アルバム「指を鳴らせ!」ではドラムのキースが病気で倒れ、アナーキーの小林高夫、元ダウンタウン・ブキウギ・バンドの相原誠、浦田賢一という3人の仲間がドラマーとして参加して、アルバムを完成させてしまった。危機を危機として考え込まず、とにかく動く。立ち止まることを恐れるかのようなそのバイタルな活動ぶりは、何か自虐的なまでの迫力を持っている。
「1、2年前は“壊す”のではなく、“創る”時期やったと思うね、日本では。今もそうやけど、向こうのものをそのまま日本でやっても何もでけんと思ったし。オレたちは今でもそうだけど、否定するところは肯定するし、壊すよりも何かを創っていきたいですね」 こう言いきる石橋凌の詩は、あくまでも前を見つめている。後退した姿勢は決してみせない。自分の手で何かをつかみ、それを育てことに熱中していれば、後ろを振り返ったり、立ち止まったりできないはずだ。
次のアルバムでは、他の人に詩を依頼するとういう冒険もやってみるというが、彼ならば間違ったものは歌わないだろう。どんなことが起きてたとしても立ち止まらないA.R.B.の新しい局面がそこに開けているかもしれない。後を振り向くな、A.R.B.よ!
■ラウドネス■十分なトレーニングでプレッシャーをはねのけ、ヘビー・メタルの最高峰に立とうとする
昨年12月17日、東京の浅草国際劇場は異常な熱気に包まれていた。オープニング・ナンバーが始まる前、場内照明が消えた瞬間に、場内を埋め尽くしていた2,700人の観客がどよめき、1階席の通路は、少しでもステージに近寄ろうとして走るファンの群れに占領されてしまった。
このオーバー・ヒートな空間を創ったバンドがラウドネスであり、なんとこの日が彼らのデビュー・コンサートだとは、だれもが信じがたい思いだったに違いない。
アイドル・グループだったレイジーの解散後、ギターの高崎晃とドラムの樋口宗孝が、山下昌良(Bs)と二井原実(Vo)とともに、ラウドネスでデビューしたのは、昨年11月のことだった。レイジ―時代に溜まりに溜まった欲求不満を解放し、彼ら本来の音楽性をアルバムにした時、ラウドネスは既に日本のヘビー・メタルの最高峰に立っていた。
ギターが大好き少年たちは高崎のハイテクニック・ギターを待ち望み、海外のヘビー・メタル・バンドだけでは満足できないファンたちは、ラウドネスの登場を夢見ていた。
これまで日本のバンドの最大の弱点とされていたボーカルも、日本人離れしたノドを持つニ井原の参加によって、ラウドネスはその弱点を克服している。
レイジーの解散から、ラウドネスのデビュー・アルバム「誕生前夜」をレコーディングするまで、1日に10時間もスタジオで練習していたという。新しい世界に旅立つ前に、ラウドネスは十分な準備をしなければならなかったのだ。
そして、レコードとコンサートのデビューは大成功だった。もうスージー、デイビーと呼ばれるのではなく、ギタリスト高崎晃、ドラマーの樋口宗孝として、彼らはロック・ファンの熱い視線を浴びるようになった。
デビュー・コンサートから2,700人ものファンを集めたラウドネスは、ごく普通のバンドと違って、ライブ・ハウスでコンサートを開くことが既に不可能なのだ。
デビュー・アルバムを一度聴けば分かるように、ラウドネスのサウンドはヘビー・メタルと呼ばれるハードな音創りだ。しかし、もちろんそれだけがラウドネスの音楽というわけではない。
「前から、ヘビー・メタル・ギタリストっていわれるとヘンな気分がしてたんや、ボクは絶対に自分は違うと思ってる。」という考えをもつ高崎晃はソロ・アルバムをこの4月1日に発表する。ラウドネスのメンバー、マライアの笹路正徳が参加したこのアルバムで、ラウドネスのアナザー・ワールドが表現されている。ポップな曲から、ギターのインストゥルメンタルまで、高崎のソロ・アルバムとはいえ、はっきりとラウドネスが浮き彫りにされた音創りがなされていることから、彼らが単なるヘビー・メタル・バンドでも、ヘビー・メタル・ギタリストでもないことが理解できるだろう。
ラウドネスは海外のフェスティバルなどにも、積極的に参加する意欲を見せているが、この日本が生んだスーパー・バンドにかかる期待が大きいだけに、彼らにとってもプレッシャーがかかっているに違いない。しかしそれを吹き飛ばすだけのパワーとテクニック、若さで、ラウドネスは日本のロック史上に一歩一歩伝説を築いていくことだろう。
■エピローグ
「オレたちは、オレたちに本当の興味をもっていないのに、プロモーションで取材に来るようなヤルら、会いたくない」―おや?と思った。デビューしたての暴威(ボウイ)というバンドのボーカリスト、氷室狂介が言い放った時、初めてこのばんどの本質に触れたように思った。これはナマイキというのではなく、ロック・バンドならだれでもが持っている本音の部分だ。3月の卒業式を怖がる教師や、子供の側からみた金属バット殺人事件を題材に歌っている彼らを“エエカッコしい”かもしれないと思っていたが、暴威の連中は本気だったのだ。
今、こういったバンドが続々と登場の機会を狙っているといえるだろう。”歌うポルノ・ロック・ミュージシャン“と異名をとる遠藤みちろうが率いるスターリンにしても、横浜から出て来たCONX(コンクス)、そして、復活したカルメン・マキがバンドとして取り組んでる5X(ファイブ・エックス)、大阪からデビューも間近のヘビー・メタル・バンド、アースシェイカー。
自分自身の肉体からロックを通してブーストされるものを信じ、そしてそのためには本音でいきなければいけないことを、頭ではなく体で知っているヤツらだ。
ラウドネス、A.R.B.、テンソウ、子供ばんど、モッズたちが、それぞれのスタンディング・ボジションを勝ち得ようとしている今、彼らのすぐ後ろには、こういったバンドがファイティング・ポーズを取っているのだ。
戦国時代を迎えたロック・シーンから、こういったバンドが出現し、本音とストレートな生きざまで、音楽ファンをノックアウトする日は近い。頭で考えるよりも、動いた方が早い。ネオ・フィジカルのマニフェスト(宣誓書)が、今、目の前で開かれようとしている。キミはそれを読み取れるだろうか?
(大野祥之)