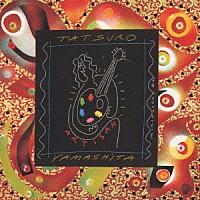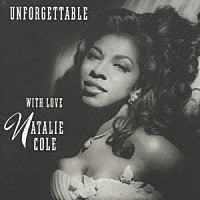FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集
ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!
TOPICS - 1991※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。
セルジュ・ゲーンズブール
フランスの反骨の芸術家 3月2日、パリで死去
No.7

Photo: Getty Images
一番目がメイク・ラブ、二番が酒、三番がタバコ…、そして6番目が死を待つこと。「人生の楽しみは?」という質問にこう答えていたセルジュ・ゲーンズブールが、3月2日、心臓発作のためパリで死去した。62歳だった。歌手、作曲家、俳優、作家、映画監督と、その活動は多岐にわたり、フランスはまたひとつ財産を失ったことになる。
(共同)

ジョージ・マイケル
深刻化する湾岸戦争 チャートやコンサートに影響が
No.6
長期化の気配が漂う湾岸戦争が、いろいろな面でミュージック・シーンにも影響を与えはじめている。まずチャートで目を引くのがジョージ・マイケル。現在、アメリカでは第3弾シングルの「ウェイティング・フォー・ザット・デイ」が快調に上昇中なのだが、その後を追うようにチャートを駆け上がっているのが「マザーズ・プライド」。この曲はいわゆるB面扱いとして同じシングルに収められているのだが、その歌詞が徴兵される息子と母親を描いているだけに注目を集めたというわけだ。それだけにイギリスBBCあたりでの反応が気になるところだ。
また最近、顕著なのがコンサート・ツアーのキャンセル。特にヨーロッパ方面ではシンデレラ、ダニー・オズモンド、アルバート・コリンズらがライブをキャンセルしている。
ほとんどがテロなどを恐れての決定でアーティストよりは、マネージメント側の意向が大きいとのことだ。
(共同)
グロリア・エステファン 来日
絶望と落胆の淵からよみがえった不死鳥
No.9
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
すばらしいコンサートだった。
85年の初来日以来、もう何回となく内外のステージでグロリアを見て来たけれど、今回の彼女は特に光り輝いて見えた。まさしく不死鳥のように、絶望と落胆の淵から自力でよみがえったからだろう。
どれほどの事故だったのか。まずグロリア自身の口から語ってもらった。
「本当に大変な事故だったの。ちょうど一年前の3月20日、私が乗って停車していたツアー・バスに大型トラックが突っ込んで来て、車は大破したわ。私の体もメチャクチャに叩きつけられて、肩甲骨ふたつが背骨から離れて体にめり込んで、粉々に砕けてしまったの。それで骨髄がその砕けてとがった骨の上に乗っているという状態で、あと1ミリ狂っていたら完全に骨髄を切断してしまって、私は一生下半身マヒということになっていたでしょうね」
それで、もう一度ステージに立って歌えると解るまでに、手術後5カ月から6カ月を要したという。
「手術して、幸いなことに背骨の神経本体は切断されていないことが解って、歩けるようになると知ってホッとしたんだけど、脊椎を支えるためにメタルの棒やネジで固定しているから、しばらくの間は腰から下の皮膚という皮膚が焼けるような痛さだったり、椅子から立つのも座るのも大変という状態で、お医者さまにもだれにも、私が果たして舞台に復帰できるかどうか解らなかったの。もちろん違う形で歌い続けるということはできたでしょうけれど……」
ということで、これで今まで通りに舞台にも立てると解ってからは、必死のリハビリを続け、体と筋肉の回復に努めたのだという。そして今もってメタル棒と、それを止めるネジは埋め込まれたままで背中には18インチ(約46センチ)の傷跡が白く残ってはいるものの、グロリアは5センチのハイヒールをはいて踊れるところまで、めでたく回復したのだった。
「今もレントゲンを撮ると、体に埋め込まれた人工骨が映るのよ。だから、エミリオは私のことをロボ・ポップだってからかうの。ロボ・コップじゃなくて、ポップ・シンガーだからロボ・ポップですって。でも、もう自由に体を折り曲げられるし、空港のX線検査だって、ブーと鳴らないで通過できるのよ」とグロリアは笑っていた。
エミリオもついこの間、突然左手が肩のつけ根から痛んで上がらなくなったのだそうで、私が「そういうのを日本では40肩と言うのよ」と半ばからかうように言うと、グロリアは真剣な顔をして、「でも、本当はあの事故で一番傷ついていたのはエミリオだったかもしれないの。あの事故の時は私が大変だというので夢中で動き回ってしまって、自分自身のチェックは何ひとつしなかったんですもの。これも事故の後遺症だと思うの。だって今一番痛むのはエミリオなんだから」と、とても心配していた。
結婚して12年。いい夫婦だと思う。今回は一粒種の息子ナイーブに両親の新婚旅行先だった日本を見せるために、学校を休ませ、家庭教師付きで連れて来たのだそうである。息子は10歳。やはり事故で軽傷を負ったけれど、すっかり回復している。
「すごく陽気で社交的なエネルギーにあふれた子でね、今はマジックに夢中なの。とても頭の回転もいいし、将来はやっぱりエンターテイナーになるんじゃないかしら」
事故からちょうど一年目の3月20日早朝、グロリアはビルボード誌から「Coming out of the dark」が次の週には全米第1位になるという知らせを受けたのだという。すでに年間チャートではポップ・シングルやアダルト・オリエンテッドの部門で、年間を通して最も売れた女性シンガーに選ばれているグロリアであり、今やヒスパニック系のアーティストとしては、女優のリタ・モレノやフリオ・イグレシアスなどと比べても、アメリカ史上最も成功したラテン系の女性となってしまった。幸せな妻で、あり、母であり、アーティストであるという気分はどんなものなのだろうか。
「すごくエミリオに感謝しているわ。彼が夫としても父親としても、またプロデューサーとしても、本当に50/50の分担をしてくれているからできることですもの。他の人と結婚していたら、こうはいかなかったと思うわ」
とグロリアは語り、「それと同時に、どれほど周囲の人々やファンから勇気やエネルギーをもらっているかわからない。その愛にこたえるためにもいろいろな場面でがんばれたんだと思う」とも言っていた。
今回のステージで、びっくりしたのは、「カミング・アウト・オブ・ザ・ダーク」をはじめとする曲作りで重要な役割を果たしてきたジョン・シカーダが、歌手としても並外れた実力を持っていることと、あの71年に「クリーン・アップ・ウーマン」の大ヒットを飛ばしたレディ・ソウルのベティ・ライトがバック・コーラスの一員としてステージに立っていたことで、これがどれほどグロリアのカラーを多彩に彩ったかは計りしれない。
今回の「カミング・アウト・ザ・ダーク」で聴かれたゴスペル・フイーリングは、グロリア自身の中にも存在していたものなのだろうか。
「もう、小さいころからリズム&ブルースは好きだったし、私自身モータウンを聴いて育ったんだから、ゴスペルを歌うこともとても自然な発露だと思っているわ。それにゴスペルは長い間苦しみ傷ついてきた黒い人たちの悲しみを、決してネガティブなものとしてではなく、光に向かって発散してきたという、素哨らしい歴史を持っている音楽だから、今の私には心から共に歌えるという自信があるの」
そう語ったグロリアは、本当に自然体で、しかも小柄な体に大きな自信をみなぎらせていて美しかった。11月には再び本格的なツアーで来日してくれるそうだから、楽しみに待つことにしよう。
(インタビュー・文/湯川れい子)
91夏UKロック・シーン
燃えるイギリスのロック・シーンの"今"を現地取材
No.15
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
イギリスのロックが燃えている。89年ごろから、あらゆる人が、あらゆる所でそう言い続けてきた。確かに、マンチェスター・ブームやジーザス・ジョーンズのアメリカでの成功など、その勢いは形として現れている。では、そうした勢いは今どうなっているのか?相変わらずに燃え続けているのだろうか?そうした現状を3週間に渡る現地取材をもとに、ロックにこだわってリポートしてみることにした。
【キーワード1/マンチェスター】
気の早い人たちに言わせれば、「マンチェスター・ブームなんてもう終わり」だし、ミュージシャンの中には「マンチェスター・ブームはマスコミの作り出した虚構」とまで言う人もいる。果たしてそうか? 現在のイギリスのロック・シーンの盛り上がりの口火を切ったマンチェスターは、もはや終わってしまったのだろうか?
その疑問に答えを出すためにも、日本になかなかやって来ない、マンチェスター・ブームの中核を成し、今やイギリスのNo.1バンドとなったハッピー・マンデーズのコンサートを、何としても見たいと思った。そして、ようやく見ることができた。
●Happy Mondays
6月1日、マンチェスターから電車で1時間、ロンドンからは3時間、イングランド北東の街リーズの『エランド・ロード・フットボール・スタジアム』でコンサートは行われた。
前座にはマンチェスターのハイ、ノースサイド、ラップのステレオMC's、リバプールのラーズ、そして同じくリバプール出身で、音楽性としてはマンデーズに近く、そのブームにのる形でヒット・メーカーになったと言われるファーム…といった面々がそろい、コンサートというよりはフェスティバルのよう。一応“夏のフェス”のはずが、気温は12℃!寒風の中、2万人が地元はもちろんマンチェスターやロンドン、スコットランドやバーミンガムから続々とバスで集まって来た。
オープニングはハイ。メランコリックなメロディとギター・サウンドがすがすがしい新人の彼らには、まだまだ閑散としたスタジアムの、サンサンと照りつける太陽の下というシチュエーションが若干不似合い。ボーカルのジョンが歌い終わる度に自分で拍手して“We enjoy!”と言っていたのはかわいそうだった(でもこの後、ロンドンのインスパイラル・カーペッツの前座で見た彼らは上々で、マンチェスターの清涼剤という役目を果たしてくれた)。
しかし、逆にマンチェスターは大丈夫か? と心配してしまうのがノースサイド。マンデーズを抱えるファクトリー・レーベルが一押しする新人で、たった2枚のシングルしかリリースしていなくても大声援を受けていたが、全く面白みを感じられず、持ってきたお菓子を食べまくってしまった。例えマンチェスター出身のバンドでも、バラエティに富んでいて、いいものとそうでないものがあることを、はっきりと理解させてもらったのだ。
そして、ラーズに続いて登場したファームが、良い意味で予想を裏切る素晴らしさ! これまたビックリで、とても良かった。
アルバム『スパルタカス』は、私自身としては?だったが、「Stepping Stone」「All Together Now」とたて続けに全英ヒットを放ったキャリア8年の彼ら、演奏もブレず2万人を踊らせる術も知っていた。このときつくづく感じたのは、2万人という人間とともに作り出すコンサートの素晴らしさ。日本で日ごろイギリスのバンドがコンサートを行う1,000人クラスの会場では決して生み出されない、熱気や連帯感、そしてそれがバンドにはね返ることによって、さらに熟されるサウンドは、2万人クラスのスタジアムならではのものだと思う。
そうした“連帯感”をずっと大切にしてきたハッピー・マンデーズにとって、2万人を熱狂させることは、そのファームの何十倍も得意のようで、やっと暮れかかってきた9時過ぎに彼らが「ハレルヤ」で登場するやいなや、会場はあっという間に踊りの渦と化してしまった。それは本当に驚く光景だったが、それ以上に驚きだったのは、彼らが素晴らしく、超一流のバンドであるという事実だ。
日本でのマンデーズのイメージというと、「不良仲間が集まって出来たバンド」とか「ダンサーのベズがマラカスを持って、目をギラギラきせながら踊り狂っている」といったもので、彼らがそれこそフュージョン系かと思うほどのうまさを誇るなんていうイメージは全くない。しかし事実は、彼らは本当にうまいバンドだということだ。
だけど、それだけではない。アシッド・ハウスの持つ気だるい揺れとサイケデリックなムード、それにロックのスピリットを持つ1曲1曲の素晴らしさにも改めて気づけたし、下世話さや、話題のベズのマラカス踊りの切れ具合も十分に楽しめた。
実際、私はこれほどまでに彼らのコンサートを楽しんでしまうとは思わなかった。気がついたら、最初から最後まで踊りまくってしまい、用意したメモ帳はまっ白けだ(まずい…)。でも、しかし、メモを取らずとも、ハッピー・マンデーズの素晴らしさ、彼らを中心にマンチェスターが勢いづき、それがイギリスのロックを盛り上げたことは、コンサートが十分に語ってくれた。かと言って、マンチェスター中にレコード会社のA&Rマンが集まって、どんどん契約してゆくなんていう異常さはもう起こらないはずだ(ノースサイドを見れば「後悔先に立たず」と思うだろうに)。そういう意味では、ブームとしてのマンチェスターは終わったのかもしれない。でも、そこからいくつかの素晴らしいバンドが生まれたことは、これからも忘れられることはないだろう。
●Inspiral Carpets
マンチェスター・ムーブメントの中から生まれたバンドの一つである、インスパイラル・カーペッツのコンサートをロンドンのアレキサンドラ・パレスで見た。その会場は本来はエキジビション・ホールなので音響は最悪。当日の取材で会ったジャーナリストが「おととしのここでやったストーン・ローゼズは、本当に最悪だった」と言うので、こわごわとコンサートに臨んだが、その心配は杞憂だった。確かに彼らにしては少しグルーヴ感が足りなかったかもしれないが、悪条件を思えば、かえって彼らのバンドとしての力がうかがいしれた。
曲目は日本公演のときとあまり変化なく、昨年は全くの新曲として聴いて今一つピンとこなかった曲も、その深い詞をよく理解してから聴くと、胸にひびくものがあった。特に「スリープ・ウェル・トゥナイト」の、メロディと詞の両方から包んでくれる優しさは、彼ら自身の人柄と重なって、何度聴いても涙させられてしまう。
しかし、残念だったのが、まるで東京のコンサートのように、客席の前半分ノリノリ、後ろ半分ダラーッ…となっていたこと。ロンドンの観客はもともとクールだし、今のロンドンを熱くさせるのはネッズ・アトミック・ダストビンのような激しいものなのかもしれないが、ちょっと悲しかった。が、だからと言って、インスパイラルの人気やマンチェスターのバンドがロンドンではだめだと決めつけるのは早計だろう。それに、正直なところ彼らの目は今、あまりロンドンには向いていないと思う。これはインスパイラルに限ったことではなく、ハッピー・マンデーズもLAに移住?のウワサもあるし、現在休業中(を強いられている)のストーン・ローゼズも復帰コンサートはニューヨークでは? と言われている。マンチェスター・ブームは今やイギリスで成熟し、アメリカに移ろうとしているのだ。
インスパイラルは今年2度目のアメリカ・ツアーを年末に予定していて、「どんなに苦しくても頑張りたい」とメンバーも語り、その意欲は並々ならぬものがあった。これから先、アメリカでマンチェスター・バンドがどう受け入れられ、それを経て彼らがどう成長するか楽しみだ。
そしてその3大バンドに続くハイやノースサイド(もっとうまくなってね)、モック・タートルズやスワール、パリス・エンジェルスといったバンドたちが、マンチェスターをブームではなく、音楽都市として変わらずに成長させてくれるだろう。
【キーワード2/中堅バンド】
「確かに次から次へと新しいバンドが出てきているよ。でも、だからと言ってやりにくいとは思わない。僕たちは僕たちなりのらしさを求めてやり続けてゆくだけで、それにファンの人たちがついてきてくれればと思う」
と語ってくれたのは、3枚目のアルバムとなる『Fellow Hoodlums』をリリースしたばかりのディーコン・ブルーのボーカリスト、リッキー・ロス。彼らは1985年に元教師のリッキーを中心に、グラスゴーで結成された6人組で、前作『エンジェル』はイギリスで大ヒットし、今やアリーナ級のバンドの一つだ。しかし、その『エンジェル』は「レコーディングがこま切れで、満足いくものにならなかった」そうで、そこで今作ではデビュー・アルバムと同じプロデューサーのジョン・ケリーを迎え、「心で感じたものを源にさまざまな人生を組み立てて歌っている」(リッキー)。深く心に染み入る傑作アルバムを完成させてくれた。
同様に、バーミンガム出身の5人組、ワンダー・スタッフも『ネバー・ラブド・エルヴィス』という素晴らしいアルバムをちょうどリリースしたばかりだ。今、イギリス中のレコード屋さんというレコード屋さんには、エルヴィス似の大型紙人形ポスターが飾られ、ワンダー・スタッフのディスプレーだらけだ。
88年の『グループ・マシーン』、89年の『ハップ!』発表の後、メンバー・チェンジのゴタゴタがあったが、今作でいよいよ彼らもメイン・ストリームのトップに立って、既にシングル「サイズ・オブ・ア・カウ」はイギリスで5位になっているし、6月下旬のコンサートもすべて3万人クラスのところで行われた。
そして、決して忘れてはいけないのがリーズ出身の4人組、ウェディング・プレゼント。
今回、初めて彼らのコンサートを『リーズ・ポリテクニック』で見ることができたが アルバムよりもボーカルのジェッジの声がソフトでいて力強く、それにウリの超速ギターが歯切れが良くて、さすが6年選手だと思った。しかし、私の正直な感想では彼らは永遠のB級バンド…といったところ。決してアリーナ・バンドにはならず、いつまでもみんなのすぐそばで、いい音楽をやり続けていてくれる、そんな感じだ。だからと言って、彼らの実力はB級ではないし、そうした生き残り方や愛され方もいいものだと思う。ちなみに、ここのジェッジも元教師。イギリスの先生は決して「ロックは不良だ」なんて言いそうにもない。
そのほか、既に中堅で最近活躍しているのが『アンリアル・ワールド』をリリースしたギター・バンドのゴッドファーザーズや、『サウンズ』を発表したマイティ・レモン・ドロップスなど。こうした中堅バンドすべてに共通しているのは、流行に決して流きれたりせずに、着実に自分たちのオリジナリティを追求して完成させていること。だからこそ、こうしてずっと愛されているのだろう。
【キーワード3/アコースティック】
80年代初頭のネオ・アコースティック全盛時代―つまりアズテック・カメラ、オレンジ・ジュース、ロータス・イーターズなどが競ってアルバムを出していたころ―を思い出させるようなバンド、トラッシュ・キャン・シナトラズの出現は、アコースティックの血が、いつの時代にも、どんな流行の中でも、脈々と流れていることを分からせてくれた。でも、よく周りを見まわしてみると、ロンドンにだってアコースティックはいつも生きていて、アコースティック専門のライブ・ハウス“ミーンフィドラー”や、アコースティック・セットが多い、“ボーダーライン”などもあるし、ギターやハーモニカを抱えた大道芸人もたくさんいるんだなあ、と、今回の旅で思い直した。
しかし、今年はそうしたいつもの動きを上回るアコースティックの当たり年(?)で、前述のトラッシュ・キャン…だけでなく、多くのアコースティック・バンドが生まれてきている。そして、それらはまるでグランド・ビートやアシッド・ハウスに対抗するかのようにフワフワとしたものではなく、地に足の着いた、しっかりとしたものばかりだ。
その先頭に立つのが6月に来日したばかりのラーズだ。残念ながら、私は日本公演を見ることができなかったが、代わりにハッピー・マンデーズの前座として見た。ギターとドラムスとベースだけの彼らが2万人以上の観客を前にどうするか? と思っていたが、マンチェスター勢の中、アシッド・ハウス大好きといった観客を、しっかりと自分たちにひきつけていたのは見事!これから先の彼らがさらに楽しみになったのはいうまでもない。
そのラーズとの全英ツアーを経て、「僕はここ」や「青春のジャンプ」といった全英ヒットを生んだのが、マンチェスター近郊(またマンチェだ!)出身のミルタウン・ブラザーズだ。彼らは高校・専門学校時代の友人たちが集まって88年のクリスマスにでき上がったバンドで、『Manchester:North Of England』というコンピレーション・アルバムに参加して注目を集め、今回のデビュー.アルバム、『スリンキー』はA&Mからリリースされているからすごい。それだけでも彼らが有望な新人であることが分かるが、アルバムの持つ前向きな空気や、ボーカルのマットのR.E.M.のマイケル・スタイプにも通じる説得力、それに60年代を素直に受け継ぐ楽曲の素晴らしさなどが、彼らの実力のほどを如実に物語っている。正直なところ、彼らは今年の新人の中では私の一番のお気に入りだ。
そのほかでも、キャリア組の(?)ウォーター・ポーイズが突然の復活大ヒットを放ったり、ピーター・アスターがアルバム『Zoo』を完成させたり、とアコースティック勢は元気いっぱい。このまま、まだまだ打ち込みビートのダンスものが増えれば増えるほど、反動として“生”の響きを大切にするアコースティック・バンドは増えてゆくだろう。
【キーワード4/ニューカマー】
イギリス中で今、一番見かけるのがネッズ・アトミック・ダストビンのTシャツを来た子たち。街中はもちろん、一歩、レコード店やコンサート会場に足を踏み入れると、そこはネッズTシャツの海!…というのは大ゲサだけれど、とにかくそれくらいにすごい。昨年私がロンドンに来たときは「ライブがいい…」いうウワサぐらいはあったけれど、たった1年でここまで大きくなってしまうと驚きを禁じえない。しかし、デビュー・アルバム『God Fodder』はメロディ・センスの良さを感じさせるし、偶然TV(チャンネル4)の人気音楽番組“Friday At The Dome”で2曲だけ見たライブ(口パクではない!)は、ほんの短い時間なのに、恐ろしくエネルギーあふれたもので、あっという間にファンがヘッド・バッキングとダイビングの嵐と化していたのがすごかった。こうなると、一日も早く日本でのライブを実現してほしいと願ってしまう。
そのネッズと並んで人気なのがカーター・ジ・アンストッパブル・セックス・マシーン。彼らはジム・ボブ&フルートバットという二人組で、略してカーターUSMと呼ばれている。現在はラフ・トレードと契約しているが次はクリサリスとの契約が決まっており、日本でも大きくフィーチャーされてくることだろう。
そして、今やアメリカでも大人気のEMF。イギリスでは“ジーザス・ジョーンズの二番煎じ”…の声もあるけれど、人気は負けてはいないし、イアン(G)以外、ジェイムス(Vo)、ミルフ(DJ)、マーク(Ds)、ザック(Bs)の4人は全員19歳で、アイドル的要素も持っているのが強い。
という3バンドがとりあえず今年のニューカマー3本柱だが、三つが三つともたたみかけるような激しさと速さを身上としているのが面白い。これも今年のイギリスのミュージック・シーンの特徴の一つと言えるだろう(それと3バンドともよく半ズボンをはいているのも特徴かもしれない!?
そんな彼らと全然タイプが違うのは、女の子二人組のバンデラス。シングル「ジス・イズ・ユア・ライフ」が全英TOP20に入るヒットとなって、その哀愁漂うボーカルとメロディは、イギリスのラジオでよく耳にした。
そして同じく女の子で、こちらは3人組のミランダ・セックス・ガーデンもいい。透明感にあふれたアカペラはクラシカルな空気もたたえていて、本当に美しい。
ところで、ロンドンの小さなライブ・ハウス“パワーハウス”で、シングルを1枚しかリリースしていないインポッシブルズというバンドのライブを観た。フォンタナという名の知れたレーベルと契約した彼女たちだが、お客さんは30人くらいしかいなかった。ロンドンは何と厳しい街だろう! だからこそ次々といいバンドが育ってゆくのだ。
(文/和田静香)
麗蘭
2大ギタリストの共作アルバムを
No.21
RCサクセションの仲井戸麗市とストリート・スライダーズの土屋公平の2大ギタリストによって結成されたスーパー・バンド“麗蘭”。ライブ・ツアーをドキュメンタリー・タッチで収めたビデオ「ウェルカム・ホーム」も好評で、それはRCサクセションやストリート・スライダーズといった各バンドのファンだけにとどまらず、R&Bファンやロック・ファンにも支持されている。
そして10月30日に待望のアルバム『麗蘭』が登場。彼らのサウンドを支えるミュージシャンはツアーにも同行した早川岳晴(Bs)、鈴木博文(Per)を中心に、村上“ポンタ”秀一、サザンオールスターズや布袋寅泰のプロデューサーとしても知られる藤井丈司(コンピューター)、ボ・ガンボスのKYON(Pf)、ホッピー神山(Syn)、梅津和時(Sax)、片山宏明(Sax)など、超豪華なゲスト・プレイヤーが参加。また、これに先立ちシングル「ミュージック」が10月9日に発売される。
(共同)
モダン・ジャズの帝王 マイルス・デイヴィス逝く
伝説の人はついに帰らぬ人となった
No.23
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
伝説の人はついに帰らぬ人となった
しかし、彼の死によってまた新たなるマイルス・デイヴィスの伝説がはじまる
マイルス・デイヴイスが逝った。65歳だった。9月28日土曜日午前10時46分(日本時間29日午前2時46分)、場所はカリフォルニアのサンタモニカにあるセント・ジョーンズ病院、死因は肺炎などによる呼吸不全。病院のスポークスウーマン、パット・カータが読み上げたマイルスの担当医ジェフ・ハリスのステートメントによると、マイルスは9月初め入院し、約1カ月もの長期に渡り病気と闘い続けたという。臨終には姉弟が立ち会った。
<何よりも演奏することを愛した―>
マイルスの最後の苦闘、そして、唯一の負け戦。最後は呼吸不全というのは、何ともマイルスらしい死因をハリス医師がつけたものだと思う。神は、マイルスに吹くことを辞めさせたのだ。生前マイルスは、自分の墓碑銘に「何よりも演奏することを愛した―」と書くように言い渡していたが、彼は呼吸できなくなり、演奏できなくなり、そうして死んだということになる。
マイルスがトランペットに出会ったのは、13歳の誕生日に父からプレゼントされてからで、自らトランペットから遠ざかったのは1975年から1980年の引退の間で、それでも部屋の片スミにあったトランペットが気になり、ついに復帰したというエピソードを持つ。彼は自らの人生で女性やフェラーリなどの車にも夢中になったが「何よりも演奏することを愛した―」という言葉は本当のことだったにちがいない。
<努力型の天才>
「天才は1%の才能と99%の努力で生まれる」と言ったのは発明王エジソンだが、マイルスの死を聞いた時、まず頭に浮かんだのは、平凡なその言葉だった。このジャズ界稀代の英雄は、決してきらびやかな早熟な才人であったわけではない。むしろ持続すること、強固な意志をもった途方もない努力型の才人であった。理知的で人一倍感受性の強いこの人間は、その努力をほぼ100%適切な方向に向けることができた。これは驚くべきことだった。努力と言っても無能な努力ではないのだ。こうして彼は、モダン・ジャズの偉大な歴史をつくりあげたのである。
<モダン・ジャズの歴史をつくる>
マイルスは、モダン・ジャズの歴史を常にトップに立ってつくっていったが、その表現の歴史で彼にとってもっとも重要なカギになるのは、1950年代半ばに経験したある演奏技能上の達成だったといっていいと思う。セントルイスの裕福な歯医者の息子として育ったマイルスは、チャーリー・パーカーを追って1940年代半ばにNYに進出。彼はNYの都市文化に触れ、ブルックス・ブラザーズの服を着、その洗練された感覚をさらに磨きをかけた。1948年ロイヤル・ルーストにたった2週間しか出演しなかったが、ギル・エヴァンス、ジョン・ルイス、リー・コニッツらとの伝説的な9重奏団(『クールの誕生』)は、まさにそんな新世代の都会的なジャズ・ミュージシャンの新しい感覚を表現した音楽だろう。しかしそれは感覚的なことであり、マイルスのトランペットはまだ未熟だった。おまけにパーカーとの付き合いで、彼は麻薬につかり、一時はポン引きのような仕事をしていたともいう。そうした悲惨な生活を一切清算したのが1954年で、その私生活での壮絶な闘いは、そのトランペット表現においても驚くべき成果をもたらした。もし、マイルスはどういうジャズ・ミュージシャンだったかと聞かれれば、ぼくは即座にこの時期の演奏を時間を追い克明にたどれば分かるといいたい。
麻薬をキック・オフしたマイルスの強固な精神力、その内面のドラマがその表現の深さにまさに直結している。これがこの表現者の圧倒的なすごさなのである。たとえば、ブルーノートの『マイルス・デイヴィス傑作集Vol.1、Vol2』は、その曲順があまりにでたらめなのが残念だが、録音年月日を順に追っていくと、この時代のマイルスの変化がまるでスローモーション映画を見るように、手に取るように分かって面白い。そして、最後のミュートによる「イット・ネバー・エンタード・マイ・マインド」におけるバラード演奏で、彼はついに自分の世界をしっかり捕まえたことが分かり、自ら感動を覚えたのだろう。次のプレスティッジの1954年の演奏は、まさに全編傑作の連続である。「ウォーキン」に始まり、この年末にはセロニアス・モンクとの有名なケンカ・セッションといわれる『バグズ・グループ』に至った。
<トランペットの音色は優しく哀しい“声”>
この翌年マイルスは、ニューポート・ジャズ祭に出演し、ほとんど一夜にして大ヒーローになり、メジャーのCBSレコードと契約するわけだが、一体人々はマイルスの演奏の何に強烈に魅せられたのだろう。このしばらくのちにアメリカの電話会社の宣伝で、「マイルスを聴いていたら、君に電話したくなった」という素晴らしいコピーがあったといわわれるが、マイルスのトランペットは、確かに人の心の奥底の優しく哀しい“声”を思わせる。しかし、それは決して見かけほど甘い
ものではない。むしろ厳しいもので、漠然とした言い方になるが、生きているということの怖さといったものをどこかで伝えているようだと言ったらいいのだろうか。むろん、ほのかな楽しさのような気分も漂う。けれどそれは心を包み込むような温かさではなく、むしろクールなちょっとした笑顔のような表情なのだ。そして、その中にこの人間の本当の優しさのようなものに出会うのである。
<全身の神経をとがらせた演奏>
いずれにせよこの1950年代半ばに、マイルスは自分のハートを十分に伝える方法を手に入れることができた。マイルスはあるインタビューでこう言っている。「自分はいつも自分の音を聴いている。音の次に広がる空間に何が残されていくか、それに耳を傾けるのだ」これはマイルスの音楽が成立する重要な秘密のひとつだろう。音の次に広がる空間に何が残されるかと耳を傾けるというのは、比喩的な言い方だが彼はその緊張した空間の中で、世界の奥行きといったものを計っているのだろう。そこで彼はまた新たな攻撃に打って出る。マイルスはその緊張を壊さないためにあらゆる神経をとがらせる。マイルスはシャイな人間ということもあるが、観客に背を向けて演奏したり、トランペットを下に向けて演奏するのは、そうしたことのための必然的な行為であり、よく言われたように決して彼が無礼な男だからではなかった。晩年彼は、ほかのミュージシャンとほとんどくっつかんばかりに寄りそって演奏したが、それも彼の集中力が生み出す濃厚な世界を若いミュージシャンとともに作り、どうにかそれを伝えたかったのではなかったかと思う。
<クール・ジャズからモードジャズ そしてフュージョンへ>
こうした世界が確立されると、あとは自然に決まってくる。1950年代末のハード・バップ・ジャズの第二弾『カインド・オブ・ブルー』を頂点とするモード・ジャズの新展開も彼の親密で奥深いソロ芸術から、いかにも自然な探求を通して導かれたといっていいだろう。彼にとって重要なのは、常に新しい音楽的刺激を新しい世代から受け、新しい時代の空気を十二分に吸収しながら、彼のソロの内部に広がる空気との親密かつ濃密な対話を通して、その空間をさらに広げていけばよかった。むろん、彼はそのために恐るべき汗を流す必要があったが、しかし、その汗は確実に成果を生んだし、また、そうした努力は、彼の芸術に基本的に組み込まれた宿命のようなものでもあった。そうして彼は、ジョン・コルトレーン、レッド・ガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズの時代から出発し、ウィントン・ケリー、ビル・エヴァンスらのピアノを経て、1960年代にウェイン・ショーター、トニー・ウイリアムッスらヤング・ブラッドを経て、1960年代にウェイン・ショーター、トニー・ウイリアムスらヤング・ブラッドを経て、アコースティック・ジャズのハード・ブローイングの頂点を極める。また、1970年代末にはエレクトリック・サウンドや新しいリズムが耳に入ると、自然にそちらの方に向かった。1969年に『ビッチェズ・ブリュー』の金字塔を打ち立て、彼はチック・コリア、キース・ジャレット、ジョー・ザビヌル、ジャック・ディジョネットらと70年代ジャズもきらびやかに予告することができたし、また、その後ピート・コージー、レジー・ルーカスらのギタリスト、あるいはパーカッションのムトゥーメらと強烈極まりないファンクの嵐を生み出した。いまだにこれはもっともハードでシリアスなファンク・ミュージックといっていいと思うが、そうした坂をのぼりつめたとき、彼はシーンから姿を消した。おそらくそれは肉体的な限界と音楽的な極度な緊張が二重に彼に襲いかかったからだろう。しかし、6年後の1980年に、彼は不死鳥のようにまたぼくたちの前に登場した。復帰後のマイルスは、すでにワウワウ・ペダルを外し、ストレートなトランペッターになった。グループのサウンドも軽く、まさにポップの時代を鏡のように映しとったマイルス・ミュージックになった。それでもマイルスというしかないのはこの時代に向き合い、そのソロ演奏の中で、この世界の奥行きをきちんと計っていたからだ。ハードなマイルスを期待するムキには確かに不満があったが、けれど、以前とは違いどこかでこの時代、重い荷物を背負う必要はないのだと感じたのだろう。とりわけ晩年の数年間は、そんなマイルスのさわやかな表情が印象的だった。絵を描く楽しさを知ったり、西海岸のマリブの生活は、ようやくこの巨匠が“自分”の人生をみつめることができたというべきだろう。
<怒りが創造のバネに>
絶対に後ろを振り返らない、絞切型の音を徹底して嫌ったこの音楽家は、そのことの真実を何よりも自分の即興演奏の展開の中で、自分との対話、前に広がる空間、心の奥底にあるものとの対話の中で必然的に得たに違いない。だから、音楽のジャンルや伝統というもののまやかしにも見事に自由でありえた人だったのだ。彼が徹底して対峙したのは、“人間”というただ一点で、黒人として生まれたという煮え返るような心のドラマが彼のすべての創造のバネになったのだ。それはあえて言えば憤怒に近い怒りであり、同時に生きることの無限のいとおしさ、哀しさ、優しさ、怖さというものだっただろう。だから彼は常に人々の中にいて、人々とともに生きることに自信をもっていたのだ。ジャズの中にいて、およそ彼ほどジャズという枠に無縁だった人はいない。マイルス・デイヴィスは20世紀のアメリカの黒人の英雄だった…
(青木和富)