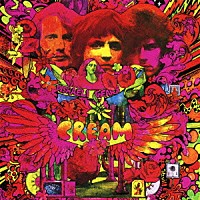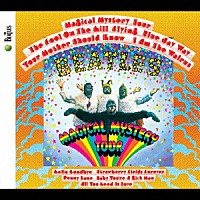FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集
ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!
TOPICS - 1968※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。
バディ・リッチとビッグ・バンド
新編成したビッグ・バンドをひきいて来日公演
No.3

Photo: Redferns
バディ・リッチが新編成したビッグ・バンドをひきいて来日公演。日本のジャズファンを熱狂させている。アメリカのジャズ界にフル・オーケストラの活躍が目立っている。ドン・エリス、サッド・ジョーンズとメル・ルイスなど。その中でもきわだっているのがリッチのバンドだといわれている。
メンバーの中心は若手の無名プレイヤー、それだけにレパートリーはポップス、スタンダード、オリジナル作品とバラエティに富んでいる。だが、日本のジャズファンのお目当は、神技にも近いリッチのドラムソロで、完成と拍手がまるで嵐の海のように会場をのたうっていた。
(共同)

円熟味をましたソニー・ロリンズ
三度目の来日公演
No.5
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
来日のたびに話題をまいているソニー・ロリンズだが、三度目の来日公演で、またまた話題を投げかけている。トレードマークのモヒカン刈りが見られなくなるとともに、エネルギッシュでダイナミックな彼のプレイも、技巧的でややオーソドックスな演奏に変わってきたようだ。うわさによれば、演奏前に精神統一のため、かならずヨガをやるということだが、そうしたことが彼のプレイに一層の円熟味をもたらせたのだろうか。
もうひとつの話題は、日本の若手ナンバー・ワンの菊池雅章の参加だ。これは来日予定のヒュー・J・ローソンのピンチ・ヒッターとして登場したもので、カルテットのメンバーとしてなみなみならぬ名プレイを披露していた。
(古澤武夫)
スティービーとマーサ 熱狂した「モータウン・フェスティバル」
「ザ・テンプテーションズ」の突然の来日不能で、異例の公演
No.6
 Photo: Getty Images
Photo: Getty Images
前人気をあおっていた「モータウン・フェスティバル」は、値打ち格の男性五人からなるボーカル・グループ「ザ・テンプテーションズ」の突然の来日不能で、異例の公演となった。
予定されていたスケジュールは、一足先に来日していた盲目の歌手「スティービー・ワンダー」、女性三人の「マーサとバンデラス」の二組で一応消化された。前売り券は全額払い戻しの「法楽公演」(無料公演)という非常手段がとられた。
ところで変則の「モータウン・フェスティバル」だが、エキサイトしたスティービー・ワンダーと意気の合ったマーサとバンデラスのハーモニーに、熱狂的な拍手があびせられた。
(共同)
黒い魂にかえる アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ
4回目の来日公演
No.21
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
日本のモダン・ジャズ・ファンには、すっかりおなじみになったアート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズの一行がやってきた。数えて4回目の来日公演。
こんどの公演では<黒い魂にかえる>のテーマを前面に強く押し出しているのが特徴。舞台衣装は日本の甚平(じんべい)をアレンジしたアフリカン・スタイル、その演奏スタイルもまるでアフリカの黒い魂をまさぐるようで、満員のファンは黒い旋風にしばし陶酔していた。
メンバーはアート・ブレイキーを中心に、ウィリアム・ハードマン、ジュリアン・ブリエスター、ビリー・ハーパー、ロニー・マシューズ、ローレンス・エバンスの6人のジャズメン、そしてブレイキーのむすこと娘が加わっている。
ブレイキー・ジュニアは1940年生まれ。ジュリアード音楽院卒。ライオネル・ハンプトンやウィントン・ケリー楽団などのドラマーとして活躍、昨年から父の楽団に加わった。エバリン・ブレイキーは1943年生まれ。兄と同じくジュリアード音楽院卒。エロルガーナ、ディジー・ガレスビー楽団などで歌っていた。
(共同)
スイングル・シンガーズ来日
東京公演を皮切りに、日本各地を演奏旅行
No.22
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
ユニークなボーカル・グループとして話題を呼んでいるスイングル・シンガーズが来日。12月6日の東京公演を皮切りに、日本各地を演奏旅行する。
ソプラノ、アルト、テノールが2人ずつの計8人というダブル・カルテット編成で、バロック、ロココ、クラシック、ロマン派の作品をジャズのビートに乗せてうたいまくっており、数年前にレコーディングされた「ジャズ・セバスチャン・バッハ」は、世界的にヒットを放っている。
(共同)
グループ・サウンズは花ざかり
-賛否両論のウズの中で-
No.2
もうさんざん騒がれ、批判され、書かれてきたグループ・サウンズであるが、まだまだことし上半期いっぱいは健在とみなされている。ブームの消長とその反響を新しい年のアングルから診断してみよう。
<コトバの発生>
コトバなどというものは、人間が人間同士意思を通じ合うための便宜的な信号みたいなものだから、相手に通じればそれでいい。たわいのない流行語なども、それはそれでコトバの遊びと受けとれば、日常の会話も楽しくはずんでくるというもの。
してみれば「Soundに複数の“S”をつけるのはおかしい」とか「和製英語さ」などと開き直ってみるのもヤボな話である。それで通用してしまったものなら、別に呼称をつけて「これが正しい」とがんばってみても徒労に終わろうというものだ。 とはいえ、ビートルズを開祖とするこの種の音楽の呼称を、外国の音楽雑誌の中にさがそうとしても見当たらない。グループというコトバはしばしば使われるが、グループ・サウンズというコトバはないようである。和製英語であることは間違いなさそうだ。
<音楽産業の勇敢な戦士たち>
グループ・サウンズというコトバが和製だということは、日本でそのコトバが特別に必要とされたということで、この種の音楽が日本できわだって話題になったことを物語っている。本来は外国からはいってきたものなのに、日本で爆発的にヒットし、そして日本人のグループが本場の外国のグループを圧倒する人気なのだ。毎月楽器店などが発表しているベストセラーをみても、ポピュラー部門で外国盤をみごとにけ落として、日本の若者たちのグループがひしめき合っている。
たとえ一時的なものにせよ、外国の音楽産業の侵入をさまたげている功績は認めてやってよいのではなか
ろうか。英国政府はピートルズに勲章を与えた。日本政府には真似のできない度量である。
<問答無用の“騒音集団”>
ところでこのグループ・サウンズ、わが国においてどんな評価を受けたかとなるとさんざんである。奈良市で演奏会場に殺到したファンが秩序を乱して人身事故を起こしたり、東京では商店会の演奏会場からはみ出したファンが、近所の二階へ無断で上り込んで高みの見物をしたり、そんなこんなで悪いのはグループ・サウンズだということになってしまったようだ。
万事に慎重なNHKでは、さっそくグループ・サウンズ締め出しの方針をとった。そしてそれがまた物議をかもした。マスコミも賑やかに書きまくった。だがヤリ玉にあげたのはファンの狂態であり、長い髪のことであり、おかしな衣装のことである。それらの点について微に入り細に入り、至れり尽くせりの報道が行われているので、いまさら繰り返す必要もあるまい。ただ音楽そのものについては、果たしてどんな評価がされたであろう。十パひとからげに“騒音集団”として片づけられたといっていいだろう。エレキの大音響に驚きの声をあげ、それだけで音楽ではなく音響にすぎないと決めつけられてしまったようだ。「サウンドといわずサウンズというのは、楽音でなく雑音だからだ」などという批評もとび出してくる。
要するに彼らの音楽性にかんしては問答無用、そしてそのカッコやファンの反応をめぐって、社会的、風俗的批判が浴びせられたにすぎないのではないだろうか。
<新しい音楽の追及>
そこでわがFMfanは、音楽愛好者である読者の皆さんと、もう少し彼らに音楽的診断をしてやりたいと思う。彼らの弁護人としてジャズ評論家、福田一郎氏にも登場願おう。
「30以上もあるプロ・グループの中には確かにおそまつなものもある。しかしそれでも若い人に受けるのだ。ということは、若い人たちがこの種の音楽をいかに渇望していたかを物語る。村田英雄や三波春夫が“アンチ・グループ・サウンズ宣言”をしてみたって、若い人たちには通じない。波長が違うのだ。米国であるレコード会社の頭のハゲかかった副社長に会ったら、ロックの新曲のテスト盤をかけながら『私はこの音楽にスリルを感じるよ』と熱っぽく語っていた。新しい音楽を追及する姿勢がオトナたちにもちゃんとあるのを知って大変な違いだと思った。もちろん批判はいい。しかし衣装がどうのこうのじゃ話にならない。三波や村田の衣装だって見方によってはひどいものだ」と、まず演歌ファン、オールド・ファン批判から始まり、さらに次のように続ける。
「音楽は若い人たちによっていつも改革されていく。しかし日本ではそれが遅れた。『ぼくらの音楽はだれも書いてくれない。だからぼくらは自分たちで音楽を作る』と彼らはいう。創作をする彼らは立派にアーチストだ。これはたいへんな進歩だと思う。末しょう的な事柄で彼らをつぶしてしまうような批判は正しくない」
<メロディーが乗った>
ロカビリーからグループ・サウンズまで、ずっと若者たちの流行音楽を演出してきた渡辺プロ社長渡辺晋氏の言いぶんも聞いてみた。「このごろのグループ・サウンズはロカビリーと違ってお茶の間にはいってますね。それからレコードが売れている。これはロカビリー時代には全くなかったことです。見て楽しむという反面に聞いても楽しめるものだという立派な証拠でしょう。ブル・コメの『ブルー・シャトウ』なんか傑作だと思いますよ。それからロカビリー時代の連中よりずっとマジメですよ。へんなウワサを立てるようなヤツはいないでしょう。これはわれわれの努力として認めてほしいのですがねえ…」
レコードも売れることについては前も書いたが、ではなぜ売れるか。渡辺氏はことばを続ける。
「ロカビリーにもグループ・サウンズにも共通するのはビートです。だがビートだけではレコードは売れない。グループ・サウンズにはメロディーが乗ったから売れるのです」
ブルー・コメッツの「ブルー・シャトウ」「マリアの泉」「北国の2人」、ザ・スパイダーズの「夕陽が泣いている」、ザ・タイガースの「モナリザの微笑」、ザ・ヴィレッジ・シンガースの「バラ色の雲」など、ビッグ・ヒットとなった曲は、いずれも少女趣味的ロマンチシズムにあふれたメロディアスなものばかり。
<エレキの悲劇>
ロカビリーとグループ・サウンズを結ぶ花形楽器エレキの存在も忘れられない。渡辺氏は「これは派生的なもの」と軽く見るが、作曲家黛敏郎氏は「宇宙時代の産物で、金属的な無機質な音響は、電子音楽へのあこがれと似たものが感じられる」と新しい世代の楽器としてもてはやなれる必然性を認める。いずれにせよこのエレキのとてつもない音量が“騒音集団”の汚名を着る唯一の原因なのだ。
もちろんエレキだって、静かな音色が出ないわけではない。モダン・ジャズなどでは、そのしぼりこんだクールなサウンドが愛用されていたものだ。しかしいまの若者たちにとっては、指先のひとはじきが、天地をゆるがす大音響となって空間に広がっていくエネルギーと化するところに意味がある。「四畳半的なツマビキ趣味よりよほど若者的健康さがある」と福田氏。「音量だけをとやかくいうならシンフォニーのフォルティシモと変わらない」と渡辺氏。
どうやらグループ・サウンズの悲劇は渡辺氏の指摘する「茶の間にはいった」ところから始まったようだ。茶の間でエレキをかき鳴らされては、古きオトナたちでなくともたまらない。人力車が走っていた道路に、そのまま自動車のコウ水が押し寄せてきたようなもので、若い人たちの生活と、与えられた生活空間とのアンバランスが、ヒズミを生んでいることは否定できない。
<ファンと共に成長を>
このヒズミをどう修正するかにグリープ・サウンズの消長もかかっている。米国では日本のグループ・サウンズと同世代のミュージシャンたちが、モントレーの国際フェスティバルに30日間無料出演、20万ドルの純益のうち15万ドルを黒人の子供のギター教室基金に、4万5,000ドルを黒人学生10人の奨学資金に、5,000ドルをモントレー交響楽団にそれぞれ寄付したという。自分たちの社会的地位を獲得するためにはこんな努力もしているのだ。またビートルズの新曲「ハロー・グッドバイ」や、ビーチ・ボーイズの「英雄と悪漢」など音楽的にも非常に水準が高い。
スターの命は短いが、彼らはファンと共に成長することによって生き残る道を選んでいるのだ。日本のグループ・サウンズの連中は、まだまだそういう自覚がない。世間にオトナとして認めてもらうためには、やはり彼ら自身の努力が必要なのだ。