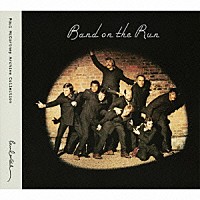FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集
ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!
TOPICS - 1974※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。
ニュー・ソウル・ミュージックの持つ楽しさの要素をすべてそなえているグループ、それがシュープリームスだ
日本でのニュー・ソウル・ブームの火つけ役
No.13

Photo: Redferns
イキのいいリズム感、美しいハーモニー、パンチのきいたボディ・アクション……と、ニュー・ソウル・ミュージックの持つ楽しさの要素をすべてそなえているグループ、それがシュープリームスだ。5月21日、東京・厚生年金会館で開かれたコンサートも、そういったシュープリームスの持ち味が十分に生かされていた。日本でのニュー・ソウル・ブームの火つけ役となったのが昨年のこのグループのステージだっただけに、この日の会場は満員にふくれあがり、開演前から熱っぽいふん囲気に包まれていた。
トレード・マークの真っ赤なマキシをまとったメリー・ウィルソン、シンディ・バードソング、それにシェリー・ペインがステージに姿を見せるとやんやの喝采。昨年の来日メンバーは、メリーを残すだけで他の2人は変わってしまった。しかし、ぴったりと息の合ったチーム・ワークと、ソロ・シンガーとしても一流の実力を持った3人のステージは、相変わらずあざやかに聴衆の心をつかんでみせる。特に、ジャズ、ソウル・シンガーとして人気の高いフレダ・ペインの妹であるシェリーは、小柄な身体から繰り出すややハスキーがかった魅力的な声と、歌のうまさは抜群で今後ソウル界で注目される存在になりそう。リーダー格のメリーは、シェリーに比べて派手さに欠けるがしっとりと歌いあげるフィーリングを身につけたシンガー。シンディは地味ながら長いキャリアを持ったベテランだ。この個性的な3人がひとつにまとまって繰り広げるステージは、その実力のうえにショウ的な面白い要素が加味され人を引きつけずにはおかない。
「ラブ・チャイルド」などの新曲、「ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ」といったおなじみの曲を約1時間半にわたって歌い続けた。休むことなく踊り続け、汗みどろになって歌うステージは、シュープリームスの魅力がじかに聴衆に伝わり、聴衆の反応がシュープリームスの歌を一層盛り上げるという楽しいものであった。
(共同)

注目のブラック・ロック・グループ登場「E,W & F Ⅳ/ブラック・ロック革命」 ほか
CBSソニー・ニュー・リリーズ
No.13
■ポルナレフのライブ!
☆「熱狂のオランピア/ミッシェル・ポルナレフ」
ポルナレフは目下いちばん才能ある若手のフレンチ・ポップスのスターとして大活躍だ。歌手、ピアニスト、ソング・ライターであり、ゆくところ敵なしといったスターだ。また、スターに必要なスキャンダルにも事欠かない。
これは1972年の10月6日に幕をあけたオランピア・コンサートのライブ・レコーディングである。パリの袖舞台の登場なので、ポルナレフも張切っており、すばらしい歌の数々をきかせる。このコンサートは例のおしりを丸出しにしたポスターで、話題を呼んで、前景気も大へんなものだったが、コンサートの方も好評で、彼の代表レコードに数え上げられるものになっている。そして、このレコードは「ポルナレフ・ア・トーキョー」(ECPN-l8)という72年11月録音の日本公演のときのレコードとききくらべると興味ぶかいものがあるが、彼のヒット曲ぞろいで、ピアノもたっぷりきける。
オランピアの舞台一杯にくりひろげられた多彩な芸が目の前に浮んでくるようだ。
■注目のブラック・ロック・グループ登場
☆「E,W & F Ⅳ/ブラック・ロック革命」
いま、ロックやジャズの世界でファンキー・ミュージックやブラック・ロックといった言葉が流行っている。このところ、黒人のフィーリングをダイレクトに力強く表現したファンクな演奏が注目を集めており、“黒人ロック時代到来か?”といった言葉さえきかれるようになった。
アース,ウィンド&ファイアーは元ラムゼイ・ルイス・トリオのドラマー、モーリス・ホワイトが、1969年に宇宙の神の啓示によって結成したという黒人の8人組で、ジャズ、ロック、ソウル、ラテン、アフロ、ファンクなどさまざまな要素が渾然一体となったサウンドをきかせるグループだ。ワーナーを経て、72年にCBSに移籍、移籍第1作が38万枚売れ、73年のこの第2作はなんと76万枚売れてゴールド・ディスクとなった。
つぎの3枚目もビッグ・ヒットしている。エキサイティングなリズムとブラック・パワーがききものだ。とくにラテン・ロック調の「ザンジバル」はまことに斬新だ。
■モンキーズの第三弾
☆「モンキーズ・プレゼント」
いまCBSでは過去に吹き込まれたモンキーズの全アルバムを順次再発売しているが、モンキーズのファンはいまもたくさんいてこのシリーズは好評のようだ。モンキーズといえば60年代におけるもっとも人気のあったポップ・グループでレコードにテレビにと大活躍したが、こういったポップ・グループが今日のロックを受け入れる下地を作ったことも見逃せない。とにかくわかりやすくて楽しく、憶えやすい美しいメロディにみちた曲が多いのである。
この「モンキーズ・プレゼント」は69年10月に発売されたもので、カントリー調ともいえる楽しさにあふれている。この中の「すてきなミュージック」はシングル盤でも出て好評を博したものだ。カントリー・ミュージックといえばアメリカ人の最大公約数的な音楽であり、アメリカ人の若者のアイドルだったモンキーズがカントリー・タッチのレコードを吹き込んだのも当然であろう。
■一年ぶりに発売されるマイルスの待望の新譜
☆「ビッグ・ファン/マイルス・デイビス」
40年代の終りから今日まで、マイルス・ディビスはつねにジャズ界をリードしてきたといえる。それだけに、みんながマイルスのレコードを今か今かと待ちわびるのである。この2枚組は「イン・コンサート」以来、ほぼ1年ぷりの新譜である。吹き込みこそ69年から72年6月と、新吹き込みとはいえないが、いずれも未発売で、しかもスタディオ録音は「ビッチェス・プリュー」から「オン・ザ・コーナー」まででは映画音楽の「ジャック・ジョンスン」を除いてみられなかっただけに、マイルスの発展過程を知る上で見逃すことのできないアルバムといえる。
このレコードをきけば「ビッチェス・プリュー」以後のマイルスの歩みがよく理解できないといっていた人たちも、マイルスの目措していた新しい世界をはっきりと掴みうるのではなかろうか。4曲収められているが、いずれも片面一曲という大作でマイルスの最上の演奏ぞろぃ。「グレイト・エクスペクテイションズ」にはブラック・ファンクヘの第一歩があり、「ロンリー・ファイアー」はマイルスが自分一人の手で作った「スケッチ・オブ・スペイン」であり、「イフエ」は完全なブラック・ファンクだ。マイルスのもっとも重要なLPとして歴史に残るだろう。
カーペンターズ華やかに日本公演
全盛期のビートルズをもしのぐ人気とまで評されるように成長したソフト・ロック・グループ
No.13
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
カーペンターズが「ポピュラー音楽史上最大の注目」をあびて来日した。今回で3度目の日本なのだが、人気の方はアルバム「ナウ・アンド・ゼン」の売り上げに比例してうなぎのぼり。現在では、全盛期のピートルズをもしのぐ人気とまで評されるように成長したソフト・ロック・グループ――それがカーペンターズである。
5月30日、東京ヒルトン・ホテルで開かれた記者会見には100人を越えるカメラマンが、カレンとリチャードの兄妹にむけてカメラの放列を敷き、一斉にフラッシュをたくというにぎやかさ。集まった記者からの質問に、カレンは「私が好きな音楽は兄も好きですし,兄がいいと思う曲は私も気に入ります」と答え、柔らかさに満ちたカーペンターズ・サウンドの中心はリチャードであると語った。またリチャードも『僕たちの音楽は、現在流行している1920年代の音楽からの影響はない』と、彼らの作り出したメロディやハーモニーへ自信のほどを示した。
翌31日、東京。九段の日本武道館には、ファンが長蛇の列をつくりカーペンターズのコンサートを熱っぽく待ち受けた。 第1部のダニー・プルックスに続いて、カーペンダーズは「スーパースター」からステージを開始。「ジャンバラヤ」「イエスタデイ・ワンス・モア」などのヒット曲をたて続けに歌い上げる。「シング」では幼い子供たちと一緒に日本語で歌い聴衆を引きつけた。
兄妹そろってジーンズ・スタイルという軽快な服装で、なごやかな温かさにあふれたふん囲気を満員の会場いっぱいに広げる。特にドラムスもたたくカレンは、歌のうまさを一段と高めたようだ。低音からのびのある高音へ、そして裏声へとナチュラルな響きを伝え、さらにややハスキーがかった声へと、詩情豊かに、あるいは色彩豊かに歌いあげる姿は見事である。
幅広い人気と親しみやすい曲、それに加えたマイルドな味つけ――カーペンダーズの魅力は限り無い。
特集:ポップ・ミュージック界の新しい展開 ― ロック一辺倒から多角時代へ ―
岩浪洋三
No.15
●時代は変わる
ボブ・ディランに「時代は変わる」(The Time They are a-Changin’)という歌があるが、音楽界にも常に変化はおとずれる。振り返ってみると、60年代はその初頭にピートルズやローリング・ストーンズが姿を現し、60年代の終わりには世界的なロック・エイジを迎えた。つまり60年代は大ざっぱにいってホワイト・ロック時代だったといえるが、70年代に入ってニュー・ソウルの台頭もめざましく、さらにはノスタルジックな音楽の流行、ソロ・ボーカルの人気、ファンキーなジャズの進出でボップ・ミュージック界の状況にも大きな変化がみられるようになってきた。これはいったいどうしてなのだろうか。またこれからの音楽界はどう展開していくのだろうか。
この大きく展開しはじめたポップス界の現況をもう少し詳しくとらえてみたい。
●岐路に立つロック
60年代の終わりから70年代のはじめにかけてロックはポップ・ミュージック界の話題を独占した感さえあった。一般の新聞までロックをひとつの社会現象としても取り上げて記事にしたものである。それはロックが音楽であると同時に一種の文化革命でもあったからだ。ロックはアウト・ロウの、ドロップ・アウトの文化、社会変革の一翼をにない、新しい若者の意識を代表し、アメリカではちょうどベトナム反戦連動と結びついて大きな社会変革をめざすエネルギーとなりえたのである。ロックのあの電気増幅によるビッグ・サウンドは一種の破壊を予感させるエネルギーとして若者たちの圧倒的な支持を得たのであった。この時代にはクリーム、クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル、スリー・ドッグ・ナイト、グランド・ファンク・レイルロード、シカゴ、エマーソン・レイク&パーマーなどつぎつぎにロック・バンドが人気を呼び、一時はロックでさえあれば受けたという時期もあり、そのころがロックのもっとも幸福な時代だったといえるかもしれない。ウッドストックのロック・フェスティバルはロックの神話の頂点に立つ事件だった。
しかし、ロックが大人の社会に受け入れられ、ロックが当たり前の音楽になったときにロックの危磯ははじまったといえる。ロックはある程度文化革命の役目を果たし終わったわけだが、そうなると音楽的成長をめざすか、あくまで文化革命的存在であり続けようとするかでロックは岐路に立たされているといえるだろう。ロックはいまや珍しくなくなったというところで壁にぶつかったのだ。アメリカでも一昨年あたりまで一般の新聞をにぎわせたロックの記事が昨年あたりすっかり影をひそめていた。奇妙なファションで売ったグラム・ロックなどは風俗革命に突破口をみつけようとしたロックのひとつのあがきとみられるが、どこまで効を奏したかは疑わしい。
一方、音楽性を追求すると、ジャズの要素を採り入れざるを得なくなり、大先輩のジャズと競争しなければならなくなる。最近のロックにプラスを入れたものが多くなり、ジャズ的要素が強くなってきているのもそのためであろう。シカゴ、タワー・オブ・パワー、サンタナ、マハピシュヌ・オーケストラ、マロなどはそうだし、リック・ウェイクマンの「地底探険」やフォーカスなどにはクラシックの要素が入ってきているし、ソウルやラテンのタッチが加わってきたグループも多くなりつつあるようだ。
ファンの方もこれに並行して次第にロックを音楽的にきく傾向が強まってきており、そうなると、白人のロックがもともと黒人のブルースやR&B、ジャズなどに影響されて生まれた音楽だけに、きき手もそのル-ツとしての黒人音楽に興味をもつ傾向が強くなってきているのが現状だ。これにニュー・ソウルの台頭が拍車をかけ、いま白人ロックの中にもソウル・タッチを加えるものが増えてきている。黒人コーラスを配したハンブル・パイ、ポインター・シスターズをバック・コーラスに使ったシカゴをはじめ、タワー・オブ・パワーのようにファンクなフィーリングを採り入れるロック・グループまで現れたし、サンタナ、マロ、マデュラなどラテン・リズムを用いる黒人よりのグループも人気を得ている。こうなるとサンタナ、マロのようなラテンの血を引く音楽家によるグループは強い。
しかし、白人ロック・グループが黒人色に頼りはじめると、それも白人ロックにとってはひとつの危機に通ずる。事実、ニュー・ファンク・ムーブメントを契機に、ウォー、クール&ギャング、アース・ウィンド&ファイア、スライとファミリー・ストーンといったブラック・ロック・グループが一気にのし上がってきたからだ。これとニュー・ソウルの急激な台頭で、70年代の中期はどうやらブラック・ミュージックの時代になりそうである。
●ニュー・ソウルの台頭
このところソウル・ミュージックの人気と進出ぶりにはめざましいものがある。もちろん、ロックが岐路に立っているといっても、ポール・マッカートニーやグランド・ファンク、エルトン・ジョン、シカゴなどのLPなどよく売れている。しかし、そこへブラック・ロックやファンキーなジャズ、ソウル、女性歌手のレコードなどがぐいぐい食い込んできており、きき手にホワイト・ロックー辺倒という傾向はなくなってきていることは確かなのだ。
ソウルは、R&B、ソウル、ニュー・ソウルという歩みを続けるうちに、より幅の広いポップ・ミュージック的存在となり、すでにレース・ミュージックと呼ばれたR&B時代とはずいぶんちがった形の音楽になりつつあるようだ。現在、あらゆるジャンルの音楽の壁が取り払われつつあるように、ソウル・ミュージックにおいても、ジャズやロック、ポップなどの要素が入り込んできて、ニュー・ソウルと呼ばれる新しいソウルが生まれたわけだが、ロパータ・フラック、ダニー・ハサウェイ、マーピン・ゲイ、スティーピー・ワンダー、カーティス・メイフィールド、ピリー・ポールといった連中は他のカテゴリーの音楽との交流を求め、歌だけで終わるというより、ひとつのトータル・サウンドを求める方向に進んでいる。例えば、今年のグラミー賞において5部門で受賞したスティービー・ワンダーは、このトータル・サウンドをめざす典型的な存在だ。彼は歌だけでなく、インストゥルメンタル・サウンドの構成、演奏、録音も一人でやり、彼は黒人でありながら、その創造する器楽サウンドは多分に白人ロック的なのだが、それが彼の新しさと自由な精神を示すものとなっている。最近のクインシー・ジョーンズは新作「ボディ・ヒート」が示すように、ほとんどの曲がソウル・ボーカルを伴っており、彼の音楽はニュー・ソウルそのものの感がふかい。
この最近のニュー・ソウルのイージー・リスニング化、口あたりのよさを白人への迎合とみる人もいるようだが、それは間違いだ。むしろ昔のように、ソウルが黒人のためだけに終わることの方が不自然だ。なぜなら音楽も社会の状況と無関係ではないからであり、社会は常に動いており、それにつれて音楽も変化することの方が自然ではないだろうか。
アメリカの黒人はいや応なしに白人と一緒に生活しなければならないわけだし、黒人たちも昔のように黒人街にだけ閉じ込もる傾向は薄れてきた。ニューヨークを例にとっても昔は商級ホテル街や5番街に白人は少なかったのだが、現在はニューヨーク中を黒人が所狭しと闊歩している。白人社会も大きく黒人に門戸をひらいているのが現代であり、アメリカの社会はもはや白人と黒人が一緒にやっていく以外になくなってきているのだ。白人と黒人の同化は音楽でもそのまま白人と黒人の同化となって現れる。黒人の解放と黒人の意識を主張する音楽もあるが、同時に全人類的立場に立って歌う歌も増えてきており、黒人も白人の作った歌を積極的に歌うようになったし、ロック・エイジ以降の白人音楽家たちには黒人を差別する意識はなくなってきている。ロックそのものが黒人音楽への共感と黒人に対する一種の同胞感から生まれた音楽だったからだ。また、最近の黒人はパワーをつけてきて、白人に反抗、抵抗するという意識は次第に薄れてきている。抵抗という意識そのものが弱者の強者に対する意識だからだ。それよりも経済的、文化的に黒人がより支配的になっていくことの方が真のパワーの獲得になることを最近の黒人は知りはじめているようである。それはブラック・シネマなどブラック・カルチャーの台頭にもよく表れている。従って、ニュー・ソウルは白人への迎合ではなくて、むしろ黒人の意識の変化、自信、白人文化を黒人が支配し、侵食しはじめた表れとみた方が正しいのではなかろうか。このところのファンクの台頭も黒人が堂々と黒人の日常感覚を主張しはじめたためともいえるだろう。また、最近の黒人は黒人同士が力を合わせて事に当たるという知的な組織活動もさかんになってきた。毎年シカゴでPUSHが主催している黒人博覧会もそのひとつだ。「セイブ・ザ・チルドレン」〈2枚組)はその博覧会の実況録音から生まれたソウル・アルバムである。
ソウルは黒人のためだけの音楽に限定しなくなったとき、それは急速に一般に浸透し、あらゆる音楽の中に根を張りはじめ、ポップ音楽全休を黒く塗りはじめたのである。白人ロックもソウル・タッチを加えはじめたし、ジャズもソウルを素材に使うことが多くなった。日本でも、ニュー・ソウルの幕あけとともにようやくソウルが一般に定着しはじめたようだ。ニュー・ソウルこそ現代のアメリカに生きる黒人たちの生活感覚にいちばんぴったりくる日常音楽なのである。前衛派の黒人ジャズマンのアーチー・シェップも楽屋ではマーピン・ゲイの「ウォッツ・ゴーイング・オン」を口ずさみ、黒人の作家や画家もロをそろえて「ロパータ・フラックを愛聴している」という。一方、ロパータの歌は白人や日本人からも圧倒的な好まれ方をしているのである。もはやニュー・ソウルは新しい時代のポップスと呼ぶべきなのだろう。
●ノスタルジア・サウンド・ブーム
このところのアメリカにおけるノスタルジア・ブームは想像以上のものがある。71年にアメリカに行ったとき、そのブームにはすでに火がつきはじめていたが、その炎は燃えさかる-方で、いまやその頂点に達した感がある。日本でも映画「スティング」の上映などでようやくノスタルジア・サウンドの人気も本格化しはじめているが、今後「デリンジャ一」や大作「華麗なるギャツピー」などの封切りで、かなりのブームになるかもしれない。
今年のアカデミー徴で「スティング」は7つの部門で受賞したが、確かにすぐれた映画ではあったが、現代のノスタルジア・ブームにうまくのったことも確かであろう。「華麗なるギャツビー」も舞台を20年代にとった典型的なノスタルジック・シネマである。この映画のメイン・テーマ曲「ディジーのテーマ」What'll I do? はアービング・パーリンが作詞、作曲したもので、1924年に出版された古い歌である。しかし、こういった歌を本当になつかしいと感じるのは30代後半から上の人たちだろう。しかし、現在のノスタルジア.ブームは中年以上の人たちだけが支えているわけではない。つまり「追憶」だけで成り立っているわけではなく、若者の間でも、こういった音楽や映画が人気を呼んでいるのだ。しかし、こういった20~30年代の風俗や音楽のリバイバルをたんに、流行はくり返す、といった解釈だけで片づけるわけにはいかない。現代はさまざまな意味で未来への希望が失われつつある時代だ。公害、インフレ、食糧難、エネルギー危機などの問題を抱え、未来に希望がなくなると、人々は過去を振り返り、昔に夢を求めはじめるのである。だからノスタルジア・ブームも手ぱなしでは喜べないのだが、特にアメリカ人は振り返りうるグッド・オールド・デイズをもっているだけに、ノスタルジア・ブームが起こるのであろう。ところが、若者がこれを好むのはなぜだろう。彼らにとっては20~30年代はクラシック・カーのモデルを新鮮に感じるのと同じように未知なる世界としてフレッシュに感じ、心をひかれるのであろう。それに「ある愛の詩」が受けたように、現代の若者たちは現代からロマンチックなものが消えているだけに、それに対する抵抗力も弱く、ロマンチシズムに弱いのであろう。そして、ギンギンのロック・サウンドをきいてきた耳には、あの単純でコーニイな20~30年代のピューテイフル・メロディはまことに誘惑的に響くのである。
アメリカでは中年層以上も日本みたいには音楽ばなれしていないのでこのノスタルジックなサウンドに飛びついているが、若者も支持して、これが大きなブームとなったといえるだろう。アメリカの音楽業界誌ピルポードも去る5月4日号でノスタルジアの特集を行ったが、いま大小さまざまなレコード会社がこぞってノスタルジックな音楽を掘り起こしている。ジャズの前身のひとつラグタイムまでが人気を呼び、スコット・ジョプリンの音楽はクラシックのチャートまで制覇したが、このジョプリンの音楽が映画「スティング」に用いられてさらにブームを呼び、こんどは同じラグタイムのジェリー・ロール・モートンの音楽にもスポットが当てられはじめた。
人気コーラスのポインター・シスターズもその半分はノスタルジックなもので売っており、こんどは女性コーラスの戦前派アンドリューズ・シスターズまでミュージカル「オーバー・ヒア!」に引っ張り出され、3人が2人にはなったが大変な人気を呼んでおり、そのオリジナル・キャスト盤はすでにCBSから発売され、彼女たちの古い歌も再発されてこのオールド・シスターズが再び渦中のグループとなっている。これは40年代の音楽映画をミュージカル化したもので、続映を続けている「アイリーン」は1919年のミュージカルをリバイバルさせたものだし、「グリース」は50年代のロックン・ロール・ミュージカルで、「ア・リトル・ナイト・ミュージック」は56年のベルグマンの映画をミュージカル化したものであり、プロ一ドウェイもノスタルジアづいている。
アメリカの本屋には往年のハリウッドの映画スターの写真集がずらりと並び、メエ・ウェスト、ジンジャー・ロジャース、ベディ・デイピス、ハンフリー・ポガート、フレッド・アステアらの主演映画の音楽がLP化されて人気を呼び、ワーナー、MGM、フォックスなどは華麗なスチール写真を掲載したミュージカル映画サウンドトラック集の発売に力を注いでいる。ハリウッドはアメリカ人の夢をはぐくんできたところであり、ハリウッド映画の栄えた時期こそアメリカのもっとも幸せな時代であったことをアメリカ人はよく知っている。だからアメリカのノスタルジア・ブームはハリウッド映画と結びつくのである。シャーリー・テンプルからマリリン・モンローのLPまでがレコード店のノスタルジア・コーナーをびっしりと埋めつくしているのが今日のアメリカだ。
ジャズになると、ラグタイムからグレン・ミラー、トミー・ドーシー、ペニー・グッドマンなどがノスノルジアの対象となっている。今年のニューポート・ジャズ祭にもこのノスタルジックなジャズのプログラムがたっぷりと織り込まれている。
このノスタルジックな風俗を華麗に再現し、表現できるのはやはり女性歌手である。現代は女性歌手時代といわれるが、これもノスタルジア・ブームと無関係ではなさそうだ。
●女性歌手時代がやってきた
ベット・ミドラーはノスタルジア・ブームの中から躍り出した女性歌手のスターだ。レパートリーや衣装にそれを存分に利用してスターとなった。彼女の第二作など多分にアンドリューズ・シスターズのふん囲気を生かしていた。ライザ・ミネリもノスタルジア・ブームの申し子のような存在だ。「キャバレー」というグッド・オールド・デイズをテーマにした映画で彼女は自分のスタイルを確立したのである。そしていま亡くなった母親ジュディ・ガーランドのレコードもノスタルジアの波にのってよく売れているという。
ノスタルジックな音楽の復活は夢へのあこがれを復活させ、女性歌手時代をもたらしたといえる。女性は男性の夢になりうるからだ。こうして、まるで20年や30年代を思わせるようにつぎつぎと女性シンガーが生まれ出ることになった。それも男性に愛と夢を与えるやさしさの象徴のような女性シンガーがしだいに増えてきているのだ。LPトップ100の上位にいつづけているマリア・マルダーの人気はすごい。まさか彼女が男性にとってのマリア様というわけではないだろうが。このほかジョニ・ミッチェル、ヘレン・レディ、カーリー・サイモン、リタ・クーリッジ、アン・マレーら女性シンガーのレコードがよく売れている。目下、各レコード会社が必死で女性シンガーの売り出しに力をそそいでいる。
歌を歌ってやはり華やかで美しいのは女性である。それに女性は音楽の分野では一番歌手に適している。女性はいくらロックを力一杯シャウ卜しても男性にはやさしさを感じさせてしまう。若くして亡くなったジャニス・ジョプリンがそうだった。最近ジャニスの再来などと宣伝されてキャシー・マクドナルドがソロ・シンガーとしてデビューしたが、彼女のアルバム「精神病棟」も、-そのシャウトするボーカルの彼方から哀しさと愛の優しさが聞こえてくる。このところ、ロックでもキキ・ディー、マギー・ベル、スージー・クアトロと女性歌手がふえる傾向がありベテラン、グレース・スリックもソロ・アルバムを作りはじめた。
そして、ポップ、カントリー、ソウル、ジャズの世界でつぎつぎに女性.ソロ・シンガーが名乗りを上げており、一気に女性歌手時代に突入した。「愛の日々」のトニー・ブラウン、独立してソロとなった「パワー・オブ・ラブ」のマーサ・リープス、ドットから登場したダイアナ・トラスク、カントリー調のオリピア・ニュートン・ジョン、ソウルのマージー・ジョセフ、ミリー・ジャクスン、ジャズのデイ・デイ・ブリッジウォーター、フローラ・プリン、など新しい女性ソロ・シンガーは目白押しだ。そして、ダイアナ・ロス、シャーリー・バッシーなどキャリアのある人たちもこの女性歌手時代を支えている。
ホワイト・ロックが、大体男性ボーカル中心だったのをみてもわかるように、ソフトで情緒的で、やさしさを本質とする女性ボーカルの台頭は、それ自身ひとつのアンチ・ロック的な傾向としてもとらえることができるのである。
●ファンキー・ミュージック
最近日本の音楽ジャーナリズムの間で、ファンキー・ミュージックが大きな話題になりはじめている。ロックとジャズの方で少しとらえ方が違うが、ファンキー、ファンクとは黒人臭さのことであり、黒人のソウルや生活感覚、ブルージーなフィーリングから生まれたものだ。ファンキーの台頭は黒人が自分たちのビート、フィーリングをダイレクトに素直に表現しはじめたからで、黒人時代到来を予感した黒人たちの自信にみちた自己主張ではないだろうか。ファンクは黒人たちが気取らず、背伸びせず、自分の感ずるままに表現したものであり、ジャズ、ソウル、ロックを合体させた躍動的なビートに裏付けされたナウな音楽だ。
ジャズでは、ハーピー・ハンコック、クルセイダーズ、マイルス・デイビス、ウェザー・リポート、ドナルド・バード、クインシー・ジョーンズらの演奏にこの50年代のファンクとは違ったニュー・ファンクが感じられ、目下ジャズLPでポップLP100の上位に顔を出しているものはほとんどすべてファンキーな演奏といっていい。
ロックやソウルの部門では、スライとファミリー・ストーン、ウォー、クール&ギャング、アース・ウィンド&ファイア、ダニー・ハサウェイ、バリー・ホワイトなどにそのファンクが感じられ、フイル・アップチャーチ、チャック・レイニー、デビッド・T・ウォーカーなどはファンク・ミュージシャンと呼ばれている。このファンキー・ミュージックの台頭はニュー・ソウルなどブラック・ミュージックの進出と一緒にとらえる必要があろう。
こういったさまざまな音楽の台頭で、ポップ・ミュージック界がロック一色からバラエティに富んだものに変化し、きき手も自分の好みに従ってそれを選択して楽しめるという季節がやってきたようだ。これからもポップ・ミュージックは時代の推移とともに、変化していくはずである。
(岩浪洋三)
新鋭の大型ヘビー・ロック・グループ、クイーン
自他ともに許すイギリスのトップ・バンドに成長
No.17
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
イギリスから新鋭の大型ヘビー・ロック・グループ、クイーンが飛び出してきた。すでにデビュー・アルバムと、それに続く「クイーンII」(エレクトラ)をたて続けに発表、日本でも多くのファンを獲得している。
クイーンはブリティッシュ・ロック・シーンに特有の、また伝統的ともいえる激しく迫るハードなサウンドを踏襲し、さらにその響きを発展させている。それがこのグループの最大の魅力となっている。デビュー当時は、イギリス本国よりも、むしろアメリカで評価を受け人気を博したというが、現在ではミュージック・ツアーなどを経て、自他ともに許すイギリスのトップ・バンドに成長した。
メンバーは、リード・ボーカル担当で、リーダー格のフレディ・マーキュリー以下4人。ギターのブライアン・メイは天文学好きという変わり種だが、特に彼のギター・ワークは注目されそうだ。
(共同)
クラプトンが「再出発」をめざして編成した6人組のグループとともに初来日
ERIC CLAPTON & his group
No.25
 Photo: Getty Images
Photo: Getty Images
あの伝統的なロック・グループ、クリームに参加し、ロックの一方の流れをリードしてきたギタリストのエリック・クラプトン。そのクラプトンが、「再出発」をめざして編成した6人組のグループとともに初来日し、10月31日夜、東京・日本武道館に満員の聴衆を集めてコンサートを開いた。
この29歳の白人ギタリストが、黒人の間に生まれ育ったブルースをどのように吸収消化し、発展させてみせるか、大いに注目されたステージである。まず「スマイル」から、アコースティック・ギターを用いた曲を3曲。かつてのクラプトンを知るファンには、彼の変ぼうぶりに驚かざるを得ないような、さわやかな印象を残すプレイだ。その淡々とした演奏からは実に味わい深いブルースの響きがかもしだされ、あたかも彼自身がサウンドを突き離し、その距離感によってブルースをとらえ直そうとしているかのように感じられた。この出だしだけで、クラプトンは、聴衆をしっかりと引きつけてしまった。
ギターを持ち替えてからは「テル・ザ・トゥルース」「アイ・ショット・ザ・シェリフ」「バッジ」など、新旧さまざまな曲を披露。イポンヌ・エリマン、マーサ・レディの二人のコーラスを得て、クラプトンの声はますますさえる。そして群を抜く彼のギター・ワークや早弾き、グループを統一して曲をトータル・サウンドとして盛り上げていく力強さなど、クラプトンの妙技が十分に発揮された。
パック・コーラスやバック・バンドのうまさはもちろんだが、まぎれもないクラプトンのサウンド、クラプトンのブルースが聴きもののコンサートであった。