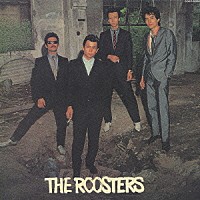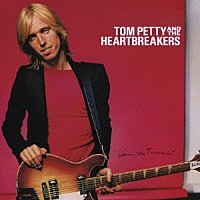FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集
ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!
TOPICS - 1980※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。
ポールの日本公演 また"幻" Hello, Goodbye!
成田で何ともお粗末な逮捕劇
No.4

Photo: Getty Images
待望の日本公演で、華やかな主役を演じるハズだったポール・マッカートニーが、場外成田で何ともお粗末な逮捕劇の主役を演じ、待望の日本公演は、一転、永久に“幻”となってしまった。
「苦労して2回分の切符を手に入れたのにショックです。ステージではポールを見ることはもうできないので、一目見たいとやって来ました。でも、逮捕劇については自業自得の感じもします。(17日朝 東京・中目黒の関東信越地区取締官事務所にやって来たポール・ファンの女子高生)
ファンの反応は、茫然自失というよりも、冷ややかなものを感じる。招へい元のウドー音楽事務所にも、時折思い出したように、コンサートの問い合わせの電話が鳴る程度。前売り開始当日の熱気とは裏腹に、いたって冷静に事態を静観しているようだ。
一方、「鎖につながれたポール、5年の刑か」(デイリー・エクスプレス)なと、東京発の特電がイギリスの新聞でも大々的に報道されたが、ニュアンスの差こそあれ、「何とバカなことをしたのか」というのか一般的な見方のようだ。
イギリスやアメリカでは、確かに日本の法律ほど厳しくはない。売買に関係していれば、もちろん実刑は免れないが、喫っている時に現行犯で捕まる場合は別としても、所持しているだけなら罰金ですまされることが多い。彼らにとってそれは、自分の好きなブラントのタバコを持っているような感覚と大差はないのだろう。
でも、同情されるようなことは、まずないだろう。大量過ぎるし、少し人をバカにしてしてるようだ。一般の生活レベルを知らないスターの甘え、というのが、イギリス人の放送関係者の弁。「自分から日本に来たいといい、日本通ともいわれる男が、日本に麻薬取締法があるのを知らないわけがない。ある国を訪れたいと思ったらその国の法律に従うべきです。グループの責任者が自らこういうことをするとは、日本をなめているんじゃないか。これまでで最も愚劣な事件です」(福田一郎氏)
徹夜までして列を作って、コンサート・チケットを手に入れたファンにとっては何とも後味の悪い“夢”と終わったが“幻の日本公演”チケットとして、貴重なものに変わってしまったのは何とも皮肉な話だ。
(共同)

THE CLASH ON “SIXTEEN-TONS”TOUR
パンクってのは変化し続けることなんだ/大貫憲章
No.6
 Photo: Getty Images
Photo: Getty Images
<クラッシュの生きざまはパンクそのもの>
「オレたちはパンク・バンドだよ。だけど勘違いしてもらっちゃ困るのは、パンクってのは何もイデオロギーをふり回したり、スリー・コードのラフなロックン・ロールだけを演るってことじゃないのさ。常に状況に応じて変化し、挑戦し続ける姿勢が問題なんじゃないかな。オレたちはこれから先も変化し続けるよ」。リバプールからやや南に下った田舎町ディーサイドでのコンサートを終え、次なる爆発地シェフィールドへと数十マイルを移動するマイクロ・バスの車中で、ベーシストのポール・シムノンは僕にクラッシュの在りようをこう語ってくれた。
ともすれば、状況の変容のその激しさに目を奪われ、パンクを単なるムーブメントとしてとらえ、そしてそれを既にとうに過ぎ去った過去の一ページとして片づけてしまいがちな僕らにとって、この発言は衝撃的なまでにズッシリとした重みを持ったものではないだろうか。パンクは決して終わってしまってはいないのだ。
確かに、現在のイギリスのロック・シーンにおいて、サウンドのスタイルとしてかつてのパンク・ロックを強烈に感じさせるバンドは数えるほどしかいない。例えば、UKサブズ、エンジェリック・アップスターツ、ステイッフ・リトル・フィンガーズといったところがそうだ。今さら説明するまでもなく、シーン全体としては音楽的にポップな方向へと流れている。当のクラッシュ自身も、最新アルバム「ロンドン・コーリング」を聴いてすぐわかるように、かなりポップなバラエテイに富んだ音楽性を示している。
そして、こうした状況の変化の中で、かつてパンクとして紹介されたバンドの多くが、脱パンク宣言を行っている。にもかかわらず、クラッシュは今もなお、自らをパンク・バンドだと規定しているのだ。ある意味でいまわしいイメージの“パンク”に、過去のものとされてしまっている“パンク”に、クラッシュは自らのアイデンティティを求めているのだ。これは彼らがパンクの旗頭としてのプライドを持っているからとか、ましてや皮肉やあてこすりを意図しているとかいうものではあるまい。ジョー・ストラマーも言う通り、パンクこそが、クラッシュの生きざまを示す最もふさわしい言葉であるからにほかならないのだ。
たとえ、現在のクラッシュがストラマーの言うように、「もう、暴動はどこだなんてのはヤメにした」としても、彼らが以前と同じように、抑圧される者、搾取される者の側に立って歌い演奏していることは疑うべくもない。ミック・ジョーンズは言う。「ロックン・ロールは若い連中にとって、日々の生活のさまざまなプレッシャーを解決するのに最適だと思う。しかし、肝心なのは、現実から逃げるのではなく、現実に立ち向かうエネルギーをロックン・ロールによって蓄えなけりゃダメだってことさ」。まさしく、クラッシュのロックン・ロールはそのために在るのだ。
クラッシュの音楽がポップ色を強めていることは明らかだ。しかし、それは単に音楽的な装飾をこらすためだけのものではない。そんな意味のないゼイ肉は自らの首をしめるだけでしかないだろう。必要な肉だけをつけるのだ。ポップな音作りを進めて行けば、音楽的な部分でクラッシュに関心を抱く者も増えるかもしれない。そうすればレコードの売り上げもコンサートの入場者も伸びる。現在の彼らには、聞くところによれば、かなりの借金があるらしい。そいつを返済しなければ、活動が思うにまかせないどころか、クラッシュの存続自体が危ぶまれる。幸いにして状況は良化しつつある。レコードは売り上げが伸びているし、ゴタゴタ続きだったマネジメントの問題もうまく片づいた。彼らにとって今がまさに勝負の時なのだ。今回の全英ツアーは、今後の彼らの活動を占う上で、試金石となる重要なツアーといえる。
<勝負をかけた"16トン・ツアー">
さて、彼らにとって初めてといってもいい、"16トン・ツアー"と銘打たれた今回の全英ツアーは、年明け早々の1月5日から2月25日までの、およそ2ヶ月におよぶ長大な巡業だ。"16トン"とは、プラターズなどで知られるポップスの古典的名曲のタイトルを、ジョー・ストラマーのアイデアで借用したものらしいが、僕の記憶が正しければこの歌は確か労働歌のような内容のものであり、実際、今回のツアーでのステージには、背景として工場のシルエットが書き割り風にしつらえられ、そのアイデアがいかにもクラッシュらしいと思わずにはいられない。
当初、このツアーにはサポート・アクト(前座)としてジャマイカン・レゲエ・バンドのトゥーツ&メイタルズが同行する予定となっていたのだが、マネジメント側との金銭的な問題が解決せず結局ご破算となり、その代わりに、プリンス・ファーエら3人のレゲエ・シンガーと、クラッシュが前回の全米ツアー時に知り合ったというアナーキーなカントリー・ロックン・ロール・シンガー、ジョー・エリーとの計4人が交互にサポートを務めるという形におさまった。プロモーターはストレート・ミュージックといい、イギー・ポップのツアーなども手がけている事務所で、ツアー一行は総勢25人前後の大所帯。
僕が見たのはこのうち、1月25日のブラックバーン公演、26日のディーサイド公演、27日のシェフィールド公演の3回で、その間中、彼ら一行と行動をともにさせてもらった。素顔の彼ら、つまりステージ外でのクラッシュの面々を紹介すれば、とにかく4人とも実に静かだということ。大体がロック・ミュージシャンというと、やたら陽気だったり、逆に変屈者で人ぎらいだったりすることが多いのだが、クラッシュはどちらでもない。ノーマルな人間なのだ。もちろん、一部で言われているような、殺気立った無法者といった印象は少しもない。ホテルの部屋をメチャクチャに荒らしたり、女のコを追い回したり……なんてことはないし、ツアーの疲れがあるのかもしれないが驚くほど、そう、ステージでのエキサイトぶりがウソのようにおとなしい。中でもジョー・ストラマーとポール・シムノンはほとんどムダロを叩かないし、行動も4人別々のことが多い。
会場はさまざまだ。ブラックバーンはキング・ジョージ・ホールという街中の立派な公会堂風の建物だったし、ディーサイドは人里離れた郊外のアイススケート・リンク(リンクの上にはもちろん仮床が張ってある)、シェフィールドでは、"トップ・ランク"という2,000人くらい入りそうな大きなダンス・ホールが使われた。そして共通しているのは、どこも立見(1階)でイスがないこと。パンク系のコンサートはイスなしが通例のようだ。
<ハリケーンのような強烈なエネルギーと熱い興奮が体を震わせる>
客層はかなり若い。10歳くらいの少年たちもかなりおり、平均15~16歳といったところか。男女比は7対3くらいで男が多かった。そして、そうした客のほとんどがパンク・ファッション(懐かしい!)に身を包んだ若者たちで、坊主頭の俗にいうスキンヘッドの連中もチラホラ見かけたが、黒人はほとんどいなかった。そういう若者たちが(ビールを飲みながら、クラッシュの現れるのを今や遅しと待っている。その熱気は、一種独特の重さがある。クラッシュが現れるのは9時過ぎで、それまではDJがレコードを鳴らしている。今回のツアーにはブリストルの人気若手DJバリー・マイヤースが同行し、オールディーズ・ロックン・ロール、パンク、レゲエなどのメニューを紹介していた。その後、レゲエ・シンガーがカラオケで40分ほど前座を務め、さあ、いよいよクラッシュの登場となる。
コンサートの演出はほぼ毎回同じで、まず照明が落とされ、ブラターズの「16トン」が流される。湧き上がる大歓声。と、ステージがライトに照らされたと思いきや、いきなり演奏が始まる。オープニング・チューンは「クラッシュ・シティ・ロッカーズ」。ものすごいエネルギーだ。最初からフル・スロットルの全力疾走。向かって左からミック、ジョー、ポール、一段高いドラム・セットにはトッパー。ミックは踊るような軽い動きでギターをあやつる。ジョーは、これがすごい。オフでは死んだように静かなジョーが、別人のような恐ろしい形相で、目をむき、口をゆがめ、体全体をひきつらせるように、マイクに向かってツバを飛ばしながら叫ぶのだ。みるみるうちに吹き出る汗。ポールはといえば、長く細い脚を大きく開き、ヒザくらいに低くベースを構え唇をかみしめながらプレイする。トッパーのドラミングも、その小柄な体のどこに、あんなパワーがあるのかと思うくらい迫力あるプレイを見せる。
何曲かまとめて演奏して、その合間に、ジョーが客に向かってゲキをとばす。若者たちがこぶしをふり上げそれに答える。みんなコンサートを見に、聴きに来ているというより、何やら集会に参加しているといった感じだ。演奏中はステージ上の4人のパワーに負けないほどの勢いで、踊り歌い叫びツバを飛ばす。こいつはやっぱり男の熱気かもしれない。演奏が進むにしたがってその場の空気は熱気を増し、精神的な高揚感が極限近くまで上昇する。ジョーはノドの調子がツアー前からおかしいとかで医者にみてもらってのツアーなのだが、そんなことおかまいなしにかすれそうな声で、しかし、絶唱する。セーブするなんてことはこれっぽっちもないらしい。僕は体の内から熱いものがこみ上げて来て、少年たちと同じようにこぶしを振り上げ、大声をはり上げステージを凝視した。もうクギづけなのだ。ヨソ見などするヒマはない。果たして、この高揚感は一体どこから来るのか。いうまでもない。クラッシュのあまりに強烈で痛ましくさえあるこのステージに凝縮される生きざまに、僕の心が自然に共鳴し、体を震わせるのだ。
ステージはおよそ1時間30分ほど、少しの中だるみもなくハリケーンのようにうなりを上げて展開される。アンコールもある。何というすばらしいコンサート、何というすばらしいバンド、そして至上のロックン・ロール!クラッシュは、まさしくこの時代のこの瞬間を、100%本気に生きている連中だ。4月に予定されていた初来日は、残念ながらスケジュールの都合で7月ごろに延期となったようだが、そのコンサートを体験すれば、僕がここで書いたことが誇張でも何でもない、本当の真実そのものであったことを、キミにわかってもらえるに違いない。本当に、こいつは、一生にそう何度もある体験じゃない。断言する。
(大貫憲章)
Jacksons on tour '79-'80
今夜もドント・ストップ
No.7
 Photo: Redferns
Photo: Redferns
マイケル・ジャクソンとジャクソンズの人気はすばらしい。昨年の10月から12月までの3ヶ月の間、休日は12月1日のたった1日しかなかった。そして、100ヶ所にもおよぶコンサート会場で200万人のファンを集めたという。
そのコンサート・ツアーは、現在も行われている。 その中から、いくつかのエピソードを拾ってみると。
1月11日、ハワイ・ホノルルでのコンサートには、4万人のファンが、2万人収容のNBCアリーナに押しかけ、2万5000人がなんとか入場し、80年代最初の大動員記録となっている。
ちょうど同じ時期、全米ネットのABCテレビの「ABCニュース20/20」のひとつのコーナーで、ジャクソンズを特集した。午後8時20分から始まるこのコーナーで、ジャクソンズを特集した。午後8時20分から始まるこのニュースは、日本ではNHKの「ニュースセンター9時」のような番組で、エド・サリヴァン・ショウに登場するジャクソン・ファイブから、去年11月9日、ニューヨークのナッソー・コロシアムでの演奏までを、インタビューを混じえながらの15分間の特別コーナーを組んで紹介した。なんでも、ジャクソン・ファイブとしての「帰ってほしいの」から、マイケル・ジャクソンの最新ソロ・シングル「ロック・ウィズ・ユー」までのシングル・レコード総売り上げが、ビートルズの記録を抜いたための特別放送らしい。
21歳ながら、もう10年選手のマイケル・ジャクソンと、ジャクソンズ。これからどれだけ大きくなるか、末恐ろしいグループだ。
(共同)
トーキョー・ポップ・ミュージック
増渕英紀
No.15
東京・三百人劇場で、7日間に渡る”日替り”コンサートが開かれたことは記憶に新しい。EX、フリクション、シーナ&ロケット、アナーキー、P-モデルといった新しいグループが続々と登場して、若い観客たちを相手にすばらしく、熱い演奏を聴かせてくれた。その数日前には、彼らは日比谷野外音楽堂に数千人のファンを集めてしまった。こんなことは1年前の音楽シーンでは想像することさえできなかった。イエロー・マジック・オーケストラが、昨年春に東京・六本木のディスコ「Bee」でマスコミ関係者を集めて演奏したステージを今も忘れることができない。単調で無機的なリズム、シニカルにさえ聞こえる彼らの“冗談音楽”は、アッという間に若者たちのハートをとらえてしまい、出すLPがすべてヒット・チャート上位にランクされた。それ以後、ニューウェイブ、テクノ、パンク……とトーキョーのシーンは、まさに音楽のるつぼといってもいい。FAR EAST~トーキョー・ポップ・ミュージックの新しい波が、いま世界へ向かって動こうとしている。僕たちはここで、振り返ってみようと思う。語ろうと思う。そうすることで、80年代の音楽シーンを見つめてみたいと思う。
<東京の新しいロックの波>
東京=シティ・ミュージックといわれたのはもう4~5年前のこと。今は軟弱路線の“ニュー・ミュージック”全盛といわれるが、どっこい都会の片隅では若いしたたかなロックン・ロール・パワーが着実に支持を増やし、地方にまで広がる勢いを見せている。“ニュー・ミュージック”の台頭以来見せかけの優しさと、ゴダイゴのメッセージやアリスの“ハンド・イン・ハンド”に象徴されるきれいごとに日本列島はスッポリ包み込まれてしまった。しかし、さすがに世の中おめでたい人間ばかりではなかったようで、中には“ニュー・ミュージック”という隠れ蓑の裏にある欺瞞と嘘を見抜く人も少なくないようだ。そんな現状に満足出来ない音楽ファンの新しいロックの波といえる。
とはいっても東京からしか出て来ないオリジナリティーかというと、そうでもない。もともと東京はサイクルの早いファッション・タウンで、ロンドンのものでもニューヨークのものでも貪欲に吸収して消化してしまう無節操な所がある。それが東京らしさといえばそうなのだろうが、今回もその例にもれず“東京の新しいロックの波”といっても、やはりロンドン、ニューヨークからの輸入文化的な匂いがあることは否定できない。あるものはパンク、ニュー・ウェイブと呼ばれ、またあるものはテクノ・ポップと呼ばれるように、手法的には海外産ロックの焼き直しには違いないが、それでも大都会が生んだ新しい感性といえるだろう。
<ファッションに酔いしれている ロック世代への警告>
これら新しいグループの多くは既成の表現方法を否定し破壊することによって、これまでの価値感を見事に覆してしまった。ポップで調子の良いメロディ、何かを伝えているようでいて何も伝えていない歌詩。“ニュー・ミュージック”に代表される柔な音楽を聴いて本当に満足できるのか、ハッピーになれるのか?というキツーイ疑問を彼らはダイレクトなロックン・ロールでぶつけてくる。それは"ニュー・ミュージック"に対する一種の反動でもあるが、同時に“ロック”というファッションに酔いしれているロック世代への警告でもある。ヒット・チャートを見渡すと、なるほど日本のロックと呼ばれる種類の音楽は目ざましい躍進ぶりを示している。シングル、アルバム・チャートの上位には必ずロック系のアーティストが顔を出しているし、その演奏スタイルは確かにロック的ではある。しかし、その実体はといえばTVやCFに便乗してヒットした曲がほとんどで自然発生的にヒットした例は探す方が難しい。演奏形態だけロックの手法を使いながら実質はメッセージも何もない“ニュー・ミュージック”と何ら変わりがないというのだから情けない限りだ。結局、60年代後半に派生した日本のロックは70年代前半で立ち消えになってしまったといっても過言ではないだろう。ロックは本来既成の方法論や価値感を否定したところから生まれた音楽だった。それがいつの間にかラディカルな攻撃的姿勢を失い、毒にも薬にもならないヒット・ソングに組み込まれてしまったのである。実際TVに登場して茶の間で支持されればされるほどロックは形骸化し、スピリットを失ってしまうのだ。
近頃、ロックが市民権を得たという事を良く耳にするが、いったいロックに市民権を得る必要なんてあるだろうか?昔、ロックと聞くと顔をしかめた頭の固い大人がいたものだが、今はどうだろう?昔ほどアレルギー症状は見られなくなったことは確かだ。しかし、それは大人の顔が柔軟になったのではなく、ロックの方が軟弱になって社会に適応しようとしてきたからではあるまいか。大人の作った価値感、モラル、社会体制に対して牙をむいて果敢に噛みついたロックが、自らの弱さで牙を失ってしまったというわけだ。
東京に誕生した新しいロックの波は、そうしたロックの原点を見つめ直す上で良いショック療法になったといえるだろう。また、かつて70年代前半に日本のロック・シーンを盛り上げたベテラン・ロッカー達にも、少なからず良い刺激になったようだ。
<街角にはパンク、ニュー・ウェイブがあふれている>
現在、パンク、ニュー・ウェイブと呼ばれるバンドが次々と誕生している。東京に限らずサンハウスを生んだ九州からは“ロッカーズ”、“第四病棟”、大阪からは“犬”、そして名古屋からはスペシャルズより一足先にレゲエ、スカ・ビートを基調にしたスタイルを作り上げた“キャラバン”らが登場している。同時に自主制作レコード作りも盛んで、東京ロッカーズの“S-KEN”を送り出したスタジオ「マグネット」(旧S-KEN STUDIO)では自主制作レコードのレコーディング・スケジュールがギッシリだという。つい最近はリザード初の自主制作シングル“さかな”のレコーディングが行われ、今後も“ミラーズ”のドラマーでリード・ボーカリスト、ヒゴ君が結成したグループ“チャンス・オペレーション”、“絶対零度”らのレコーディングが予定されているとか。一方、渋谷のパンク、ニュー・ウェイブ専門店「ナイロン100%」でも噂の“8 1/2”の自主制作盤を作成して販売している。もちろんグループの数もうなぎのぼりに増加している。PASSレコードからデビューした“グンジョーガクレヨン”(元ミスター・カイトのメンバーが結成)、“突然段ボール”、“ボーイズ・ボーイズ”、加藤和彦のプロデュースで遅ればせながらデビューした“EX”、“シンクロナイズ”、“NON BAND”、“バナナリアンズ”、“連続射殺魔”、“鉄城門”、“PRICE”など、それこそ数え挙げたら切りがないほどだ。従ってその種のイベントも最近は良く目立つ。5月の連休にはスタジオ「マグネット」で“回天'80”なるイベントが開催され、新人11バンドを集めてライブ・レコーディングを行った(後にレコード化する予定とか)ばかりだし、6月には三百人劇場で7日間に渡る“ポップ・ザ・ヒーロー”(シーナ&ロケット、フリクション、アナーキーetc.が出演)が開催された。また、新宿アシベ会館内の“ニューヨーク・シアター”では連日のようにニュー・ウェイブ系のイベントが行われている。
という訳で今や街角にはパンク、ニュー・ウェイブがあふれているのだが、東京ロッカーズが登場した2年前とはだいぶ様相が変わってきた。マンモス・ファッション・タウン東京は何でも呑み込んでしまういわばモンスターだ。アンダーグラウンド・シーンで熱烈な支持を得ていた2年前は別としても、今やすっかりファッションに組み込まれてしまった感すらある。つまり、言葉でアジったり、攻撃的な姿勢を打ち出すこと自体がナウイファッションになってしまったのだ。中にはポーズをとることによってウケようとするグループも出てくる始末だ。テクノ・ポップにしても誰も演奏者になり得るなんていっていると息詰まるのは目に見えている。“ニュー・ミュージック”に対するひとつの反動であったパンク、ニュー・ウェイブもヘタをすれば“ニュー・ミュージック”に替わる単なるファッション・ミュージックに終わってしまう恐れも十分あるといえる。特にあらゆるマスコミが集中する情報都市、東京だからこそその危険性は大だ。そういう意味では支持層こそ広がってはいるが、新しいロックの波は'80年代に入ってひとつの壁にぶち当たったといえるだろう。これまでならただ単純に欲求不満をぶつけるだけでも十分インパクトはあったが、今後はそのエネルギーにドゥーイングに持って行けるだけの方向性を持たせることが要求されてくるに違いない。
もう、ただ単に欲求不満をぶつけ合う時期は終わったのだ。
<グループ紹介>
●RCサクセション
一時のブームが去って以来、ライブ・ハウスは久しく人気グループを送り出せなかったが、RCサクセションは久々にライブ・ハウスから飛び出した逸材だ。再編成後、昨年あたりからライブ・ハウスを中心に活動を再開、あれよあれよという間に人気グループにのし上がってしまった。そして今やライブ・ハウスでは収容し切れなくなって、コンサート・ホールへと活動場所を移している。中でも今年4月に久保講堂で行われたワンマン・コンサートは超満員の盛況でチケットもソールド・アウト、その時に撮影されたビデオも好評だ。現在、RCは初の全国ツアーのまっさい中、東北から九州まで'5カ所回るというのだから、その人気のほどは推して知るべきだろう。'66年にバンド結成されて以来、今年で14年目。歴史の浅い日本のロック・シーンではもう超ベテランの部類に入るが、どんな若いグループよりも今ノリにノッている。読者の中には「僕の好きな先生」、「君かわいいね」といったRCのかつてのヒット曲を知っている人も多いと思うが、彼らがロックン・ロール色を強めたのは'76年に発売されたアルバム『シングル・マン』からだった。現在ステージで人気のある「スロー・バラード」を収めたこのアルバムは、知っての通り昨年末に「再発実行委員会」の手によって自主限定発売されたもののアッという間に売り切れ。その後、ファンからの強い要望もあって8月1日に正式に再発が決定したとか。今RCサクセションの活躍ぶりは目ざましく、話題に事欠かない。
彼らが現在のような完壁なロックン・ロール・バンドへ発展したのは、昨年の初めごろだったと思うが、その演奏スタイルはニュー・ウェイブというよりはむしろシンプルでストレートなロックン・ロールとリズム&ブルースだといって良いだろう。しかし、スタイルは変わってもRCのスピリットは昔から変わっていない。「キミかわいいね、でもそれだけだね。君と話してたら、僕こんなに疲れたよ」とリアルに歌った'72年から、RCの方向性は一貫しているのである。最新アルバムはファン待望のライブ『ラプソデイー』(6月21日発売)。
●アナーキー
日本のロック・シーンも多様化してはきたが、もっとも攻撃的なバンドといえばこのアナーキーをおいて他にいないだろう。昨年の「EAST WEST」に国鉄職員の制服を着て登場、優秀バンド及び最優秀ボーカリスト賞を受賞して一躍注目を集めた新進グループである。平均年齢20才、元暴走族だけにその反骨精神は大変なものだ。歌詞は詩というイメージにはほど遠いほど汚く、しかもストレート、ボルテージの高い演奏は息つく暇もなく一気に盛り上がって1曲2分程度で終わってしまう。まるでアジテーションのようだが、それが観客にとっては快感なのだろう。毒はあるけどスカッとしていていや味はない。ライブ・ハウスはいつも超満員。日本では珍しい位の暴力的なステージが始まるとライブ・ハウスの空間は一触即発のスリル感で一杯になる。
考えて見ればアナーキーというグループ名もセンセーショナルだが、歌詞に目を通せば決して大袈裟ではないことがわかるはずだ。とにかく彼らの周りにある気にくわないモノに対して片っ端からケンカを売る。
警察、政府はいうまでもなく、スーパー・スター気どりのロック・ミュージシャン、「東京・イズ・バーニング」では何と日本の象徴である天皇にかみつくといった具合だ。その辺がアナーキーたるゆえんだろう。こんなエピソードもある。ある公共放送局が4月29日の天皇誕生日に「東京イズ・バーニング」を流したところ、愛国者?や右翼から抗議の電話が殺到したとか……。
●シーナ&ロケット
現在、CFにも使われている「ユー・メイ・ドリーム」を大ヒットさせているシーナ&ロケット。細野晴臣がプロデュースしたセカンド・アルバム『真空パック』も好評、イエロー・マジックに続いて海外進出をねらっているようだ。
シーナ&ロケットのデビューはそう最近のことではない。九州の博多で圧倒的な支持を集めていたワイルドなロックン・ロール・バンド、“サンハウス”でリード・ギターを弾いていた鮎川誠が愛妻のシーナ、浅田孟、川島一秀らと結成したのが約2年前。その当時は確か“鮎川誠&シーナ・ロケット”というグループ名で活動していたように思う。デビュー・レコードはマイナーのエルボン・レコードから発売されたがあまりパッとせず、アルファ・レコードに移籍してからはコンサート・スケジュールも増え、ライブを中心に人気が高まってきたようだ。
音楽誌によってはテクノ・ポップ・グループに分類されているようだが、むしろオールド・ロックン・ロールに今日的なポップ・センスを盛り込んで演奏するロックン・ロール・バンドといった方が正解だろう。シーナのボーカルのふらつきがかつてのミカ(サディスティック・ミカ・バンド)を彷彿とさせるのもミソ!
●プラスティックス
今から3年程前に変な芸術家集団が変てこなグループを結成したというニューを耳にしたことがある。これがプラスティックスだった。それがテクノ・ポップ・ブームに乗っていつの間にかライブ・ハウスなどで大話題となり、昨年11月にはROUGH-TRADEレーベルから日本より一足先にイギリスでレコード・デビュー。そして今年はアメリカ・ツアーを敢行、8月には遂にデビュー・アルバムがアメリカでもリリースされることに決定している。まさにアッという間、トントン拍子のプラスティックス出世物語だ。アメリカで大成功したというニュースを流せば嘘でも売れるご時世だが、こちらは確かのようだ。3月頃、ニューヨーク、シスコのアンダーグラウンドのFMステーションで“コピー・ロボット”が何と1位にランクされていたのだから、プラスティックスの場合は自然発生的なヒットといえよう。
プラスティックスの面白さはイラストレーター、スタイリストなど多彩な分野の集合体ならではの奇抜で豊富なアイディアにある。言葉を音楽の一部として聞かせたり、突如としてモンキーズの「恋の終列車」が飛び出したり、カラフルなまるで玉手箱のような楽しさはプラスティックスならではだ。また東京という精神病棟を認識しつつもジョークで飛ばしてしまう、彼ら特有の“遊びの精神”がこの種の音楽にしては気楽に聴かせてくれる。
●P-モデル
テクノ・ポップ・グループのコンサートといえば一風変わった雰囲気が多いが、このP-モデルの場合はエキサイティングで極めてロックっぽいステージを展開する。“あくまでもロックにこだわりたい”という彼らの意識の現れともいえようが、とにかくパワフルでノリが良いのが特色。表現手段はテクノ風でも姿勢はむしろニュー・ウェイブ的といっても良いだろう。
実際、ステージでもレコードでもテクノ・ポップのグループに見られがちなコミカルさやC調な部分は感じられない。メッセージもラディカルなものが多く、社会分析や批判も実にシビアで前向きだ。ファンもその辺のことは良くわかっているようで、彼らのファンは意外にマジで反骨精神も旺盛のようだ。特に病的ともいえる現代文明に対し、あくまでも挑戦的な姿勢を貫いているところがテクノ・ポップ・ファン以外のロック・フアンにもウケる要因になっている。
一方、サウンドの方はこの種のバンドの中でも最もメカニカルな感触で、メロディよりもディジタル・ビートが主体。他のグループほどポップではないので多少親しみやすさには欠けるかも知れないが、サウンドと詩が一体になって明確な方向性を持っているのがP-モデルならではの魅力だ。今年の4月にはセカンド・アルバム『ランドセル.』をリリースしている。
●リザード
79年に『東京ROCKERS』というオムニバス・アルバムの形で紹介された東京のパンク・ロッカー達の中で、もっとも精神的な活動を行っているのがフリクションとこのリザードだ。
昨年11月に発売されたデビュー・アルバム『リザード』は、ストラングラーズのジャン・ジャック・バーネルが彼らのライブ・テープを聴いてホレ込んだのがきっかけ。ジャン・ジャックのプロデュースによりロンドンでレコーディングされている。ロンドンでの何回かの公演は好評だったようだが、海外進出よりもまず自分達が住んでいる日本をターゲットにライブで勝負していく姿勢を見せている。リーダーのモモヨはかつて“紅とかげ”で活動していたロック界の名物男、彼の強烈なキャラクターと日本の社会に向けた鋭いメッセージがリザードというグループを象徴している。全員が東京生まれで下町育ちということもあって“浅草六区(ロック)”は地元でも大評判、遂には台東区長まで飛び出してくる騒ぎで5月には浅草公会堂で「浅草六区再開発コンサート/三社祭前夜祭」なるユニークなコンサートを行ったばかりだ。
リザードは近々待望のセカンド・アルバム『さかな』をリリースする予定だが、メジャー・レーベルとは違った音作りに挑戦してみたいと、同じ「さかな」の自主制作シングルも作成中だとか。こうご期待!
●パンタ&ハル
日本のロック史上伝説的な存在にまでなっている“頭脳警察”時代を含めて10年、もはやベテラン・ロッカーといえるが、今若いロック・ファンにもっとも人気のあるロッカーでもある。
76年にソロ・シンガーとしてデビューしてからは、かつてのようなラディカルで攻撃的な姿勢はあまり見られなくなったが相変わらずパンダのメッセージはハードだ。特に3作目の『マラッカ』は音楽的には手法に走って軟弱なところを感じさせたが、詩の方はパンタらしい力強さにあふれていた。そこの部分が、パンタの最大の魅力といえよう。新進の石井聡亙のバイオレンス・ムービー「狂い咲きサンダー・ロード」でもパンタの歌が効果的に使われている。
今年の3月に、リリースされた4作目「'980X'」もスピード感のあるストレートなロックン・ロールが人気を集めている。ただ何を勘違いしたのか詩を極めて抽象的にしてしまったため、サウンドから感じられるストレートな伝達力が半減してしまったのが惜しまれる。ともあれ、パンタの魅力はライブ・ステージにある。元々あまり歌もうまくないし声量もない方なのだが、いざライブになると信じ難い程の説得力を発揮する。バッキング・グループ、ハルとの息もピッタリ合って、今年の夏はどうやらパンタがひと暴れしそうな気配だ。
●ヒカシュー
日本のテクノ・ポップ・グループの中でも最もポップで一般ウケしそうなのがこのヒカシューだ。すでにヒカシューの音楽はクラリオン・カーコンポのCMソング(白いハイウェー)に使われており、TVで観た人も多いことと思う。東京オリンピックの日本選手団を思わせる赤と白のツートン・カラーに身を包んだ彼らは、シンセサイザーのピコ・ピコ・サウンドに使い古されたポップス感覚をふんだんに盛り込み、ユニークなサウンドを作り上げている。デビュー・アルバム『ヒカシュー』も近田春夫によってプロデュースされたこともあって、独創的な内容で話題を呼んでいる。シタールなどの民俗楽器を導入する一方、ドラムなしのリズム・ボックスを使う変わった編成。ボーカル・スタイルも日本語の持つ韻を強調した独特のもの、聞きようによっては古典芸能や歌舞伎にも通じる面白さを持っている。そして味つけは近田春夫風の歌謡曲的センスということになる。とにかくテクノ・ポップという輸入音楽ではなく、日本人的なセンスでうまく消化しているところがヒカシューの魅力といえよう。詩もコミカルで、狂気の時代を楽しんでる風なところが何ともしたたかだ。この7月には待望のセカンド.アルバム『夏/ヒカシュー』がリリースされるが、今度は加藤和彦と近田春夫の共同プロデュースというからこちらも期待出来そう。
●フリクション
フリクションはデビューこそつい最近だがグループ自体の結成はかなり古い。現在のレック、ヒゲ、ツネマツの3人が集まったのは70年代の中頃のこと。当時のグループ名は“3/3(3分の3)”という今-や伝説的にもなっているハード・ロック・バンドであった。という今や伝説的にもなっているハード・ロック・バンドであった。彼らはこの3/3時代に自主制作アルバム(75)を作制、その後77年にレックが続いてヒゲがニューヨークに渡って一時的に解散となっている。ニューヨークで彼らはパンク・ロックの洗礼を受け、78年に帰国。東京に戻った彼らはすぐにかねてからの構想通り“フリクション”を結成、東京ロッカーズの一連のコンサート・イベントに参加して、79年にリリースされたオムニバス・アルバム『東京ROCKERS』にも彼らの演奏が2曲収められている。
そして79年の夏、ニュー・ウェイブの専門レーベル“パス・レコード”と契約、今年の4月には坂本龍一の協力のもとにデビュー・アルバム『軋轢』を発表している。 フリクションの魅力は何といっても特徴的なレックのボーカルと、必要最小限のトリオ編成とは思えないパワフルな演奏に尽きるだろう。それぞれにキャリアも長く、3/3時代からのつきあいだけにメンバーの息もピッタリ、数あるパンク・バンドの中でも演奏力はピカ一。リザードと共に東京ロッカーズの中でも最古参、詩も攻撃的なだけでなく意味深だ。
●A.R.B.
昨年デビューした当時はまだまだ力不足を感じさせたものだが、今年に入ってからのA.R.B.の成長ぶりは実に驚くべきものがある。特にコンサートを始めとしたライブ・ステージでの人気はすさまじく、彼らがライブ・バンドとして大きく成長したことを物語っているようだ。デビュー当初は九州、福岡の出身ということもあって多少甲斐バンド的な要素も感じられたが、今年の春リリースされたセカンド・アルバム『バッド・ニュース』では見事にその影響を振り払ってA.R.B.のオリジナリティを確立している。中でもリード・ボーカリストであり、ソング・ライターでもある石橋凌のキャラクターが際立ってきたのが注目されるところだ。ボーカル自体もうまくなった上に、何よりも味が出てきたのが強味だといえる。詩も時代性を見事にとらえていて、「バッド・ニュース」を始めとするいかにもロックっぽい攻撃的な詩がA.R.B.のエネルギッシュなロックン・ロールにひと際映える。ただし演奏力の方は今一歩といった感をまぬがれない。これだけ完成度の高い詩を持っているならば、ことさらニュー・ウェイブを意識することもないような気もしないではない。むしろ、ドッシリとタイトなリズム・アレンジで歌い上げた方がボーカルと詩が生きるのではないかとも思えるが……。ともあれこのI年で急成長を遂げた期待の若手バンドである。
(増渕英紀)
RIDE LIKE THE WIND WITH CHRISTOPHER CROSS
“さわやかなフラミンゴ旋風立ちぬ”
No.16
 Photo: WireImage
Photo: WireImage
マイケル・マクドナルド、ドン・ヘンリー、J.D.サウザー、ニコレット・ラーソン…がコーラスに参加し、フラミンゴをジャケットにしたアルバムが、全米に旋風を巻き起こした。日本でも、ことし初めに輸入盤がベストセラーを記録、そして現在は日本盤がアルバム・チャートをどんどん上昇している。アルバム・タイトルは「南から来た男」。アーティストはクリストファー・クロス。詳しいキャリアと顔が不明なためにミステリアスな男といわれ、親しみやすくシャレたサウンド、高音の伸びがすばらしい美声のために、さぞかしグッド・フェイス…否…とささやかれていた。そして……。
シングル「風立ちぬ」の大ヒットに続いて現在第2弾の「セイリング」が上昇中と、早くも人気者の仲間入り。4月から5月にかけて、北東部をフリートウッド・マックと、6月には南部と中西部にかけてをイーグルスとツアーするなど、デビュー、アルバムに、ツアーにと、ミュージシャンからも大モテ。もちろんコンサートはすべてソールド・アウトの人気ぶりだ。そのツアー中にアッサリと“公開”されたマスクの良し悪しの判断は読者におまかせしよう。
いずれにせよ、この熱い夏に向けて、アメリカで、そして日本で、“さわやかなフラミンゴ旋風立ちぬ”いといったところ。
<華々しいデビューまで>
詳しい経歴はわからないが、70年代の初めテキサスのサンアントニオを中心に活躍していたハード・ロック・ク、ループ、フラッシュのメンバー。フラッシュは、レッド・ツェッペリン、ディープ・パープルなどのコンサートで前座も務めたほどで、地元ではかなりの人気グループだったようだ。73年にクグループを脱退、ロブ・ミューラー、アンディ・サモン、トミー・テイラーと、クラブ・サーキット活動を開始。78年の仮面祭「ハローウィン」の夜、クラブ「アラモ・ロードハウス」で演奏していたところを、ワーナーの関係者がたまたま居あわせて、契約。契約の席上でも、「ハローウィン」の時につけていたマスクをはずさず、ミステリアスな男として、クリストファー・クロスが誕生した。アメリカで、シングル「風立ちぬ」は2位、アルバム「南から来た男」は7位まで上がった。
(共同)
Crystal mood in Japan~デヴィッド・ボウイ
まさかCMに出演するとは…
No.19
髪をキッチリと七三に分け、白で統一された背景の中に、白いスーツで登場、バックに流れるイメージ曲「クリスタル・ジャパン」グラスをかたむけながら、こちらを向いて一言「Crystal」。
デヴィッド・ボウイの音楽を知らない人にも、ブラウン管に登場する彼の姿は、もうかなりおなじみだろう。
デヴィッド・ボウイのファンにとっては、映画出演など他分野への意欲的なアプローチを示していたボウイだが、まさかCMに出演するとは考えなかったかもしれない。
そして現在、彼はアメリカのステージに出演している。バーナード・ポメランス作の「エレファント・マン」で、ビクトリア朝時代、エレファント・マンと呼ばれているジョン・メリックに扮しているという。7月29日から8月3日まで、デンバー・センターで公演し、8月5日からは、シカゴのブラックストン・シアターに公演地を移して、8月31日まで上演される。そして、ニュー・アルバム「スケアリー・モンスター」とタイトルされたこのアルバムでも、ファンの方はかなり驚かされそう。
「シルエットや影が革命を見つめている。もう天国の自由な階段はない」
三浦久の訳詩による日本語のナレーションがいきなり飛び込んでくる。アルバムごとに大胆な実験と変化を見せ、常にファンを満足させていたデヴィッド・ボウイの新たな代表作だ。
焼酎メーカーのCF撮影のため京都に出かけ、京都精華短大の講師で、シンガー・ソングライターでもある三浦久と酒をくみ交わしながら、イギリスのロック、特にニュー・ウェイブの状況から、日本のエタ、非人の話にまで及び、尽きることがなかったようだ。ただし、デヴィッド・ボウイはアルコールの方はあまり強くないとのことだ。