Special
小原 礼(The Renaissance) × 佐藤 竹善 スペシャル対談

“サディスティック・ミカ・バンド”オリジナルメンバーとして、日本のロック黎明期を支え、3月に屋敷豪太とともに噂のロック・デュオ、ザ・ルネッサンスを結成した小原礼と、シング・ライク・トーキングだけでなくソロとしても各方面で活躍する佐藤竹善の対談が実現。日本のロック、ポップスシーンを築いてきた二人の活動から最近のミュージシャンについて、そして6月に行うビルボードライブ公演について大いに語る!
“あぁ、僕らは東洋的だったのかな”
それが受けたのかも知れないって思うようになった
??小原さんと竹善さんは世代的にひと回り違いますが、小原さんがいたサディスティック・ミカ・バンドは竹善さんに取ってどんな存在でしたか?
佐藤 竹善:僕は当時、高校の軽音楽部にいたんですが、仲間がミカ・バンドの『黒船』を持って来て、バンドでやっていて。実はそれが初めて生演奏で聴いた黒船でした(笑)
小原 礼:えぇ?、それは参ったなぁ?(笑)
竹善:日本人なのにイギリスでライヴ活動している人たちがいるというのは、高校生の僕らにはまったくビックリなことでした。
小原:最初のアルバムを作って、イギリス好きだったトノバン(故・加藤和彦)が向こうへ行って宣伝したら、マルコム・マクラーレン(当時は洋服屋)が気に入ってくれて…。そこからブライアン・フェリーやクリス・トーマスに繋がったんです。そのうちクリスが日本へ来てレコードを作る、ということになって、それで『黒船』ができました。今でこそロックがビジネスになっているけれど、当時の日本ではまったくお金にならなくてね。『黒船』も名盤と言われてますが、当時はそういうのができるとは思ってなくて、取り敢えずやってました(笑)。でも、そういうところにいられたのは、すごくラッキーだったと思いますね。
竹善:あの頃のロンドンはどんな感じだったんですか?
小原:すごく活気があった。小さなライヴハウスがたくさんあったし、グラム・ロックも盛んで。トノバンは音だけじゃなく、“バンドたるもの、見た目やファッションも意識しなきゃいけない”という信念があって、カッコ良いものが好きだったから、ミカ・バンドもそうやってました。
竹善:あの時代のロンドンのミュージック・シーンは、日本人のそういうバンドをどう見てたんでしょうね?
小原:何か変わってるなぁ?、って思ってたのかね(笑)。多分、東洋的な印象は持っていたんじゃないかな。メロディとか、ミカの個性とか。その頃は全然気づかなかったけど、だいぶ後になってから、“あぁ、僕らは東洋的だったのかな”と。それが受けたのかも知れないって思うようになったの。
竹善:バンドの形態がヴェルヴェット・アンダーグラウンドっぽいですよね。ルー・リードがいた…。彼らもニコというモデルさんを入れてアルバム作って成功して。彼女が抜けても、独自の活動を続けていくという。ミカ・バンドもミカさんがいないのに、他のヴォーカリスト入れて再生していったでしょ? スタイリッシュでしたよね。
小原:片やニューヨーク、片や東京で、違いはたくさんあるけどね。ヴェルヴェットは当時本当にアンダーグラウンドな存在だったけど、すごくカッコ良かったね。
竹善:パンクとかオルタナ系の人たちは、彼らの詞の世界やスタイルから凄く影響を受けてますよね。それはミカ・バンドも同じで、後進のミュージシャンにたくさん影響を与える。教科書みたいな感じですね(笑)
小原:日本語でロックをやるのが不思議な感覚だったと思うんだよ。みんな洋楽で育っているから、どうやっていいのか分からない。試行錯誤して失敗して叩かれて、みんな一生懸命自分の方法を探してたんじゃないかと思う。
竹善:日本語詞、英詞ですら賛否両論あった時代ですよね。ロックの歴史の本に出てくるような。僕の歳ですら、そんな時代があったんだなって思いますもん。
リリース情報
公演情報
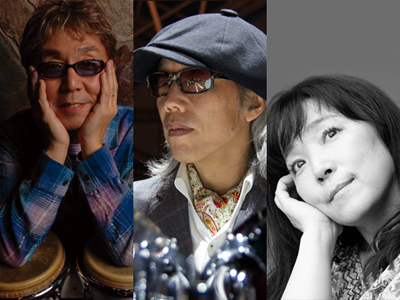
The Renaissance(小原礼&屋敷豪太)
Special Guest 尾崎亜美
ビルボードライブ東京:2014/6/29(日)
>>公演詳細はこちら
ビルボードライブ大阪:2014/7/1(火)
>>公演詳細はこちら

佐藤竹善 × akiko Duo Live
ビルボードライブ東京:2014/6/22(日)
>>公演詳細はこちら
関連リンク
Interviewer: 金澤 寿和
僕らの若い時って、執拗に探さないと何も見つからなかった
でもそこが面白かったんだけどね
??小原さんはそのあと、海を渡って海外で活躍されますよね。元フェイセズのイアン・マクラガンが組んだバンプ・バンドとか、ボニー・レイットとか。
小原:実際はみんな同じスタジオ、同じメンバーで、何人かとレコーディングしてたんだけどね。
竹善:どうやって知り合ったんですか? アメリカで。
小原:たまたまなんだ。僕が向こうへ引っ越して、半年くらい経った頃かな? 女性ヴォーカルの人を2人掛け持ちでやってたんだけど、その一人のリハーサルをロブ・フラボニというプロデューサーが見に来たの。そうしたら、ロブが“明日ちょっと遊びに来ないか”って誘われて。ベース持って彼のマリブの家へ行ったら、みんながセッションしてて、ベースが空いてて。で僕が入って、1時間ぐらいジャムって。キーボードの人が何処かで見た顔だな、と思ったら、イアン・マクラガンだった(笑) それで意気投合して、“明日からレコーディングなんだけど、一緒にやらないか?”と言われて。“そりゃあ、やりますよ!”って返事して。もう本当に偶然。
竹善:出会いですね~。そもそもアチラに行くキッカケみたいなのはあったんですか?
小原:兄貴が住んでた、というのはあったんですけど、キッカケ自体は全然大したコトないの。スピード違反して警察から呼び出されて、行ったその場で急性盲腸になって病院へ担ぎ込まれて緊急手術。その入院中にオンナに振られて、“マジかよぉ?”って(笑) 免許取り消しだわ、楽器運べなくなるわ、スタジオ行けないわ、彼女には振られるわ…。で、じゃあアメリカ行っちゃおうかなって(爆笑)
竹善:それって、いくつの時ですか?
小原:25歳くらいかな。まぁ、いいかってノリで、志なんてなく、ただ流れに任せて行っちゃったんですよ。
竹善:20代の成せる技なんでしょうね、きっと(笑)。
小原:今みたいにビジネスがちゃんとしてないじゃないですか。だから勢いで行けちゃったんだよね。そういう意味では、あの時代で良かったかも知れないね。
竹善:何もない環境だから、逆に何かやっちゃおう的な部分ってありますよね、僕らの世代でもそうでした。小原さんの頃よりはもう全然揃ってましたけど。
小原:今の若い人たちって、もう全然違うよね。考え方もシッカリしてるし、情報もある。もう多すぎるくらいにね。僕らの若い時って、執拗に探さないと何も見つからなかった。でもそこが面白かったんだけどね。
??シング・ライク・トーキング(以下SLT)のデビューは88年でしたっけ?
竹善:はい。東京へ来たのが82年です。
小原:L.A.で亜美ちゃん(尾崎亜美。小原の奥様)に会ったのはいつ? “板前さん?”って言われちゃったという…(笑)
竹善:87年ですね。1stアルバムのトラックダウンの時、スタジオへ行ったら、ちょうどいらしてて。それで覗きに来てくれたんですよ。だけど僕は髪が短くて角刈りにしてたから、ミュージシャンだとは思わなかったらしくて、“何をやられているの? 板前さん?”って(笑) 中学・高校とずっと体育会系だったもので、髪の毛を伸ばす自分がイメージできなくて角刈りでした(笑)
??その一方で、軽音楽部でベースを弾いてたんですよね。
竹善:中1の時にクイーンを聴いて、「ボヘミアン・ラプソディ」が大ヒットして。それでベースのジョン・ディーコンが好きになったんです。だから未だにプレジション・ベースが一番好きなんですよ。
??SLTはしばらく休んでましたが、去年はデビュー25周年で、かなり活発に動いてましたね。ソロ活動と併行して…。
竹善:やっぱりバンドが好きなんです。でも高校くらいの時に、スタジオ・ミュージシャンの音楽に出会うわけじゃないですか、TOTOとかスティーリー・ダンとか。その洗礼を受けているので、どちらも好きなんですね。SLTもデビューからの3?4枚は、どちらかというとスタジオ・ミュージシャン的な構築の仕方でした。バンドとはいえ、僕らは3人しかいないわけだから…。でもそのあとは、どうやったらバンドっぽい音になるか?と工夫するようになって、やっぱりバンド・スタイルに戻っていきました。実はSLTでも小原さんにベースを弾いてもらっているんです。それに僕と沼澤尚が書いたジェフ・ポーカロのトリビュート・ソングとか。小原さんもやっぱり基本はバンドマンのプレイですよね。
小原:スタジオ・ミュージシャン的な仕事もイヤッ!って言うほどやってきたけど、どうしても自分の感覚になっちゃうね。スタジオだと要求されたことだけできればイイんだけど、全体像は見えないでしょ。だけど僕は、アーティストがその曲で何をやりたいのか、どういう意味を持った曲なのか、そういうところを考えながら弾くタイプだから。
リリース情報
公演情報
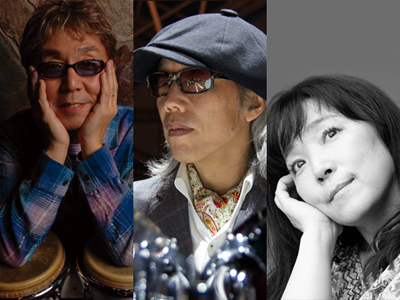
The Renaissance(小原礼&屋敷豪太)
Special Guest 尾崎亜美
ビルボードライブ東京:2014/6/29(日)
>>公演詳細はこちら
ビルボードライブ大阪:2014/7/1(火)
>>公演詳細はこちら

佐藤竹善 × akiko Duo Live
ビルボードライブ東京:2014/6/22(日)
>>公演詳細はこちら
関連リンク
Interviewer: 金澤 寿和
前は探す才能が大事だったけど、
今は選別する才能が大事で、見極めが必要です
??お二人から見て、最近の若いミュージシャンたちをどう思われますか?
小原:さっきも出たけど、情報過多で、それが可哀想だなって。何でもできちゃう反面、何をやりたいのか、どんなものを表現したいのか、その人たちがひとつに集中する妨げになっている気がする。今の日本の音楽の流れって、聴く方も演る方もコドモの音楽ばかりになっていて、情報の垂れ流しみたいでしょ。そんな中で、若い人たちがどれだけ自分で情報をコントロールできるかが重要だと思うんです。アナログが良い音だ、と言われるけど、若い人たちはアナログを聴いてないし、聴く機会さえない。楽器や機材にしても、レコード盤の音にしても、完全デジタルの音しか知らないんだ。本物の良さを知らないまま、分かっているような気になってる。
竹善:昔と今じゃ、状況が逆なんですよね。前は探す才能が大事だったけど、今は選別する才能が大事で、見極めが必要です。逆に今の若い人達のほうが大変じゃないかな?多様なテンプレートがいっぱいあって、便利は便利なんだけど…。
小原:僕らの世代は、試しながら自分の引き出しを増やしていった。
竹善:そうなんですよ。たとえば、僕らはアナログ時代の経験値があるので、シュミレートされたテンプレートの本質を知っている。でも今の人たちは、シュミレートされたものから出てくる音=本物、となりがちなのではと。
小原:元の音を知らず、成立のプロセスや背景も分からない。そのまま使うから軽く聴こえちゃうんだろうね。
竹善:それでも欧米の若い人たちは、ちゃんと個性的な音を創ってるんですよ。最新の機材を使っても、同時に自分たちで安い倉庫を改造して自家スタジオにしたりしながら、古い楽器やマイク、ハードウェアを集めたりして、工夫してますよね。アナログもデジタルも選択肢のひとつなんです。テンプレート的なモノを利用するだけで完成させちゃうのは、もったいないな、と思いますね。
小原:みんな右に倣えだから、もっと好奇心を持って欲しいよね。
??さて、ご両人とも、間もなくそれぞれのプロジェクトでBillboard Liveのステージに立たれますが…。
小原:ザ・ルネッサンスという、屋敷豪太とのユニットで出ます。元々はトノバンの生前最後のバンドとなったVitamin-Qで一緒になったんだけど、その時、何かとても良いマッチングがあったんですね。互いに長く海外でやってたこともあって、ストレスフリーで気が合うんです。それで飲み会から始まったの。ちょうど流行ってたお笑いの人たちが、“ルネッサ?ンス”(c.髭男爵)って言ってて、それでバンド名も決まりで。難しいコトはやらず、ほとんどロックン・ロール。レコーディングも(奥田)民生と亜美ちゃんがゲスト参加した以外は、すべて2人で作っているんです。オトナの遊び、ですね。豪太はプログラマー的なこともできるし、エンジニアリングもやってくれてますけど、それとはまた別に弾きたがり歌いたがりなんですよ。そういうところは2人の共通点ですね。
竹善:豪太さんの歌って、聴いたことないです。
小原:もうね、植木等みたいなの。完全にC調で、スーダラ節の世界。それで僕はちょっとストーカーみたいにね。ポップでロックンロールで楽しくイケてるユニットですよ。
??竹善さんは、ジャズ・シンガーのakikoさんとのデュオですね。
竹善:僕は、いつもシンガーとして、いろいろな人と組んでやりたい、というのがあるんです。Akikoはジャズシンガーですが、今回は二人ともジャズそのものではなく、ポップやロック、R&Bの匂いを楽しみながらjazzyになったらな、と思っています。そんなライヴには、意外にフィットする小屋が少なくて。 いろんな音楽やアンサンブルの組み合わせを、今後も提供していきたいんですが、その一環として今回のライヴもあります。
??akikoさんとの付き合いも、もう結構長いですよね。
竹善:もうかれこれ10年くらいになりますね。最初は僕のソロ・アルバムで、ゲストで歌ってもらって。でもakikoって表向きはジャズ・シンガーですが、永チャン(矢沢永吉)好きだったり、レッチリ(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)・ファンだったりと、実は意外に広い顔を持っている。そういうところを互いに見せ合って、ユニット風に聴かせられたらイイな、と思っています。
小原:バックは?
竹善:ピアノ一本です。その分、歌での自由さが際立つといいなと思っています。
リリース情報
公演情報
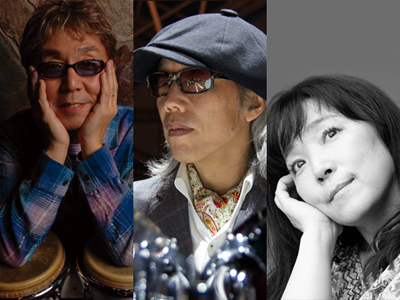
The Renaissance(小原礼&屋敷豪太)
Special Guest 尾崎亜美
ビルボードライブ東京:2014/6/29(日)
>>公演詳細はこちら
ビルボードライブ大阪:2014/7/1(火)
>>公演詳細はこちら

佐藤竹善 × akiko Duo Live
ビルボードライブ東京:2014/6/22(日)
>>公演詳細はこちら
関連リンク
Interviewer: 金澤 寿和
関連商品






































