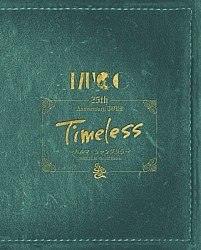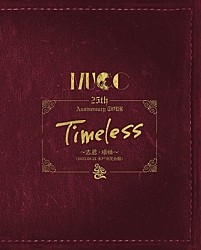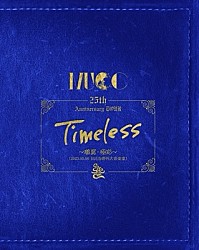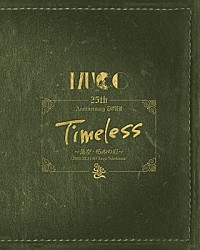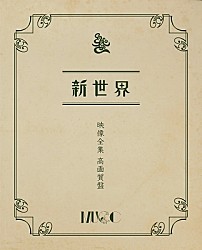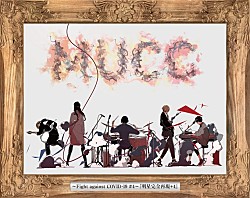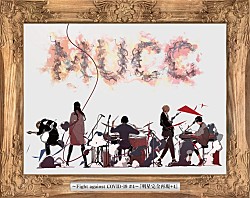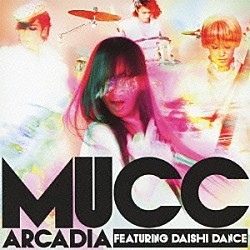Special
<インタビュー>MUCC・ミヤ、「替えがきかないバンドで居続ける」――ニューAL『1997』で表現した、今のバンドだから表現できること

Interview & Text:後藤寛子
2024年に3度目のメジャーデビューを果たし、独自の存在感を極めるMUCCが、待望のニューアルバムを完成させた。MUCCの結成年を指す『1997』というタイトル通り、90年代のトレンドやバンドのルーツになっている音楽を今のMUCC流に料理した楽曲が並んでいる。音作りから、歌詞や歌声、アートワークまで、徹底したこだわりようだ。新しい刺激に満ちた楽曲から伝わってくるのは、どんな音楽性も吸収して自分たちのものにしてしまう柔軟さと、結成28年を前にしてまだまだ未開拓の領域を突き進む貪欲さ。バンドのリーダーであり音楽的支柱を担うミヤ(Gt.)の言葉から、『1997』で表現したかったもの、MUCCの核にあるものを紐解く。
テーマとなった“90年代”
――アルバムを作る段階で、90年代というキーワードがあったんですか?
ミヤ:そうですね。90年代という、自分たちが多感な思春期を過ごした時代の音楽を意識して作ったら面白いんじゃないかなと思ったんです。シングル『愛の唄』(2024年6月4日リリース)を作ったあたりからそういう気持ちが芽生え始めて、そこから『愛の唄』を持って1年間ツアーを回る中で確信に変わり、アルバム制作に入りました。これまでももちろん90年代の音楽からの影響は受けてきたけど、やっぱり直接的なルーツに限定されていたので、時代にビシッと焦点を当てて作ったことはなかったんですよね。うちはメンバーが同い年なので、全員が(90年代を)通ってきているし。
――懐かしさだけではなく、ミュージシャンとして今、90年代の音楽に面白さを感じる部分も?
ミヤ:それは大きいですね。90年代の音楽には、80年代とは違う細やかさや、音楽IQが高いところがあって。子どもの頃はそこまで意識して聴いていなかったけど、大人になって解析してみるとすごく面白いんです。80年代の音楽への反動としてオルタナやグランジが流行っていく流れも、70年代のプログレとかにパンクバンドが反発していたことの繰り返しだったりして、そういう歴史の面白さもありますよね。そう考えると、今また90年代が(カウンター・カルチャーとして)リバイバルしているから、3回目なわけで。1回目はわからないけど、ギリギリ2回目と3回目を体験している世代なりに表現できることがあるのかなと思います。
――たしかに、今の若い世代もY2Kや平成カルチャーのリバイバルを楽しんでいますよね。それとはまた違う感覚ですか?
ミヤ:やっていることは一緒だと思います。でも、今はやっぱりYouTubeやネットにいろいろな情報があるから、もっと知識があるんですよ。昔は情報がないから、むりやり自分で組み立てて説明しちゃう部分があったけど、今は裏付けがないと「間違ってますよ」と言われてしまう。そういう差ですよね。曖昧でもなんとかなった時代と、曖昧だとツッコまれる時代。両方の良さがあると思うし、逆にすべての情報を知っている(今の)世代の人たちに曖昧なものを与えるとハテナになるのも面白いんですよね。あんまり体験したことがないんだと思う。
――90年代は、いろいろな音楽のいいところを再現しようとしてオリジナルが生まれていく雰囲気がありましたよね。
ミヤ:そうそう。音楽でも文化でも、情報がないからおぼろげなイメージを自分の想像で補っていた。最近はそういうことがあんまりないから、逆に面白いんじゃないかな。意外と、90年代のミクスチャーとか、音楽的な新しい流れが日本に入ってきた時をリアルに体験できている世代は狭いんですよ。僕自身、スリップノットやコーンが入ってきた時をリアルタイムに経験できたのはよかったと思います。でも、そういうことを僕らが言い出すと単なる懐古主義だし、そこにこだわるのはくだらないから。今の世代に何かを教えたいというわけじゃなくて、いろいろな経験を含めて自分たちがいかに楽しんで作れるか。結果的に反応してくれる人がいればいいなという感覚ですね。新しいものとしてでもいいし、懐かしいと感じる世代がいてもいいし。

――実際、どういうふうに90年代の空気を取り入れていったんですか。
ミヤ:まずは出てきた曲のイメージをスケッチしながら、「これは○○にしよう」「これとこれを足したら面白くなりそうだから、もっとアレンジを足していこう」みたいな感じでした。基本的にミクスチャーで、「このバンドのサウンドに、あのアーティストっぽい世界観の歌詞が乗ったら面白いよね」「このバンドのボーカルがあの人だったら」とか、そういうイメージがほぼ全曲にあります。いわば、自分の中でドリームバンドを作っている感じですよね。必然的に歌のバリエーションが多くなるので逹瑯は大変そうでしたけど、楽しんでやっていたと思います。
――個人的な印象で言うと、「Boys be an Vicious」にTHE MAD CAPSULE MARKETS、「Guilty Man」にコーン、「蒼」にナイン・インチ・ネイルズあたりの空気を感じました。
ミヤ:「Boys be an Vicious」はMADですけど、俺的に「Guilty Man」はリンプ・ビズキットで、「蒼」はレディオヘッドとマイ・ブラッディ・ヴァレンタイン、ザ・ユーズドでした。
――微妙に違いましたか……。でも、そういうことを考えながら聴くと楽しかったです。
ミヤ:めっちゃいいと思います。解説していくとどうしても具体名が出てきますけど、「やっぱりそうだよね」となる人もいれば、まったくピンとこない人もいるだろうし、それぞれの聴き方をしてほしい。掘っていったら意外なものが出てくるかもしれないですよ。
――具体名は明かしていくスタイルで?
ミヤ:いくらでも言いますよ。それがダメなことだとは思っていないので。特に今回のアルバムに関して言うと、そこから元のアーティストを聴いてみんなの音楽の幅が広がってくれればいいなという気持ちもあります。
Rollin' (Air Raid Vehicle) / リンプ・ビズキット
――参考にするうえで、改めて聴き返したりしたんですか?
ミヤ:作詞作曲している時は聴いていないです。良くも悪くも、自分の頭の中だけで情報が膨らんでいる状態で制作しないと、オリジナリティが出ないので。あとから改めて聴いてみたら「あ、こんな感じだったんだ、ちょっとイメージが違ったな」と思うことも結構ありました。昔の記憶は美化されがちだから、美化されている状態のほうが意外と良かったりするんですよね。いざ当時の曲を聴いてみたら「こんなに音軽かったっけ?」と思うこともあるし、(一般的な)正解がかならずしも正解ではない。だから、基本的に自分のフィルターを通った音のイメージで作っていきました。当時どの楽器を使っていたかは知っているので、同じ楽器を使ってみたりして。
――ミヤさんが他のバンドのカバーやコピーをする時、音の再現性が高すぎて驚くんですが、その感覚とも違うわけですか。
ミヤ:そこはエンジニア脳というか。エンジニアもやっているので、職業柄その音や声がどういうふうに作られているかわかるんですよ。単純に自分が得意なこと、好きな作業のひとつとして、しっかり再現してあげると喜んでくれるかなって。アルバムでは、いくら再現したとて、そこに乗ってくる歌詞がMUCCのものであればまったく違うものになる。ちょっとやりすぎたかなと思うのは、「Round & Round」くらいじゃないですか?
――たしかに、音作りも歌い方もコテコテに振り切っていますね。ライブで披露された時、ZI:KILLオマージュとおっしゃっていましたけど。
ミヤ:ZI:KILLを始め、当時イカツくておっかない人たちがやっていた、女々しくなる前のヴィジュアル系バンドのオマージュですね。D'ERLANGERも入ってるし、いろんなバンドの要素が入っています。それこそ、レコーディングではギターもベースもドラムも当時と同じ楽器を使いました。録音環境はほかの曲と同じですけど、やっぱりその時代の楽器じゃないと出ない音があるんですよね。

――ちなみにどういう楽器を?
ミヤ:たとえば、ZI:KILLのドラマー時代のyukihiroさんはずっとピッコロスネアだから、薄くて高い音のスネアじゃないとそれっぽくならないとか。タムもロート・タムという、表にしかヘッドがないタムを使っているんですけど、当時よく使われていたものなんです。そういうふうに、時代のサウンド感を象徴するような機材が、録音機材も含めてそれぞれのジャンルの中にあって。化石みたいな機材を引っ張り出してきて使って作った音もあるので面白かったです。
――エンジニアのミヤさんとしても楽しめそうですね。
ミヤ:まさに。なんでもパソコンの中で作れるけど、逆にパソコンの中では絶対に作れない音もあるんです。(90年代は)お金をかけて手間がかかることをする時代なんですよね。「Guilty Man」とか、何曲かテープで録音したものもあります。後半はテープマシンが壊れて使えなかったので、半分くらいはデジタル録音ですけど、両方が並んでいるのもいいなと。
――リンプと仰っていた「Guilty Man」は、00年代のMUCCが『是空』や『朽木の灯』で目指していたサウンドでもあるのかなと思って。セルフ・リバイバルというわけではないですが、当時のアプローチとはやっぱり違いますか。
ミヤ:そうですね。当時は思うような音にならなくて四苦八苦していましたけど、今はできるようになったので。それよりも、違うところにどうやって新しい要素を入れるかに重きを置いて作っていきました。たとえば、ジャズのアプローチをハーモニーやギターのコードに入れていたり。「Guilty Man」はアコースティック・ライブでできそうなジャズバージョンも録っているので、何かの機会で出したいと思っています。
当時からなんでも好きな曲をやるバンドだったんですよね
――着眼点が違うんですね。「Boys be an Vicious」は逹瑯さんの作詞作曲で。もともと逹瑯さんからTHE MAD CAPSULE MARKETS的なイメージで届いたんですか。
ミヤ:いや、そういう感じにしたいんだろうなという意志が伝わってきたので、アレンジを任せてもらって、いろいろ組み替えてトラックを作りました。90年代というテーマがあったから、MADっぽい曲が出てきたんじゃないかな。MUCCはコピーバンドから始まったんですけど、コピーバンドの初ライブでMAD、THE BLUE HEARTS、MALICE MIZER、SHAZNAをやってたんですよ。
――幅広い(笑)。
ミヤ:それを思い出したのかもしれない。考えたら、当時からなんでも好きな曲をやるバンドだったんですよね。今回、全体的にそのノリを再現しているところはあります。

――なるほど。
ミヤ:あと、MADは時代によってサウンド感が違うので、1曲の中でいろんな時代のオマージュを入れました。Bメロはデジタル方向に行き始めた90年代だけど、サビはもう少し進んで00年代のイメージ。さらにプロディジーとか、MADが影響を受けたルーツに対するオマージュも入っています。
――ボーカルレコーディングも、オマージュを意識しながら?
ミヤ:曲によって、意識するパターンとまったく関係ないパターンがあって、両極端でした。それこそ「Round & Round」は完全に当時のヴィジュアル系。ZI:KILLのTUSKさんだけじゃなく、D'ERLANGERのkyoさんやEins:Vierも入っていますね。そういう方向性は、逹瑯的には意外とやったことのないアプローチが多くて。90年代のブリティッシュ・ロックに影響を受けている日本人のスタイルは独特だし、かなり低域を効かせるボーカルなので、結構難しいんだなと思いました。
――しかも、テクニックというよりそれぞれのクセが強いですし。
ミヤ:そうなんですよ。結果、MUCCとしても新しいアプローチのひとつになったかなと思います。
――逹瑯さんは、2021年頃からソロ活動を始めていて。ソロ活動からの影響を感じるところもありますか。
ミヤ:ソロをやるようになって、歌うことに対しての向き合い方がすごく柔軟になったと思います。俺としてもやりやすくなりましたね。あいつがソロでやっていることはソロでやればいいことだと思うし、逆にMUCCでやっているアプローチはソロでやっていないので、そのバランスもいいんじゃないですか。
――たしかに。今作のコンセプトによって、逹瑯さんの歌を含め、MUCC全体の表現の幅がさらに広がった気がします。作り終えて、ミヤさんの手応えとしてはいかがですか。
ミヤ:昔よりもちろんスキルもあるし、大人になっているし、自分たちが楽しんでいる空気感をいかにお客さんに伝染させていくかを考えられる余裕もあるので。今のこの年齢感じゃないと到達できないアルバムになったと思います。やっぱり新作を作り続けて、常に今思っている自分たちなりのフォークソングを歌うことが、MUCCが続いていく条件なんですよね。ずっと過去の再現をしていくバンドになったら辞めると思うし、歌詞でも常にその時代のことを歌っていたい。

――音楽的に過去と向き合っても、歌っていることはあくまで“今”の感情だと。
ミヤ:そうです。コンセプトはサウンドや曲作りのきっかけに過ぎないので、基本的には最新のことを歌っています。特に先行して発表した「invader」「October」「Daydream Believer」はオマージュではないので、そうなると結局MUCCの根本にある“フォーク”がテーマになるんですよ。今、自分の隣にあることを歌っている曲ですね。
――「Daydream Believer」はアルバムを締めくくる一曲ですが、MUCCのアルバムがアッパーな曲で終わるのは珍しいので新鮮でした。
ミヤ:そう言われればそうかな。でも、歌っている内容は死にそうなくらい暗いので、あえてこの曲調にした感じですね。まさにフォークソング的な成り立ちで、自分の身近で起きた悲しい出来事から書いた曲です。どうにもならない、どうしようもない、救いがないことって、生きていたら誰にでも起こるじゃないですか。逆に言えば、突然起こる悲しいことは、生きている代償として背負わされている十字架みたいなものとも言える。同時に、やっぱり年齢的に、人の死や避けられない別れに慣れてきてしまっている自分もいる。それでも、夢を見ることが大事なんじゃないのかって……そういうことを歌っています。
Daydream Believer / MUCC
――身近な悲しい出来事を曲にするというスタンスは昔から変わらなくても、90年代の自分と比べると、表現の仕方は全然違いますか。
ミヤ:全然違います。27年やってきただけのことはあるし、やっぱり大人になったし……大人になるのがどういうことかと言ったら、「俯瞰できる」ようになることなんじゃないかなと思っていて。まあ、職業的にあんまり俯瞰で見すぎるのはよくないから、感覚で動いていますけどね。
――〈笑いたいんじゃない 笑って欲しいんだ〉というフレーズは、まさに視野が広がっているから書けた歌詞なのかなと思います。
ミヤ:たしかに、昔だったら「自分が笑いたい」と思っていたかもしれない。歌の内容がどうというより、そういう曲をみんなでどう楽しむかに重きを置いたんですよ。
――悲しい歌でも、みんなで声を出して歌える曲にしたかったと。
ミヤ:そうそう。結局そこに行きつくんですよね。どうしようもないことをどうにかしようとして無駄に時間を使うより、それに対して「ウォー」って歌うことに時間を使ったほうがいいじゃないですか。どうしようもない状況に悩むんじゃなく、じゃあそれをどういうふうに発信するか?みたいな思考になってきていると思います。
――エネルギッシュなエンディングになっていて、今のMUCCのモードが伝わってきました。オマージュが盛りだくさんでも最終的にMUCCのニューアルバムになっているわけで、本当になんでも吸収してMUCCの音楽にしていくところがすごいですよね。
ミヤ:自分ではどうしてなのかわからないものなんですけど……似ているバンドがいないバンドはそういうものなのかなって。だから、これからも替えがきかないバンドで居続ければいいのかなと、そこに尽きますね。そのうえでさっきも言った通り、その時感じているものを曲にするというスタイルでやっていけば、死ぬまでやれますから。

――この先も楽しみです。まずは今作を引っさげてのツアーがありますね。
ミヤ:25周年以降、ここ2~3年は昔の曲をやるツアーが続いていたので、ほぼ新曲だけのツアーは久しぶりなんですよ。新曲たちでどういうふうにライブを作っていくか、お客さんと一緒に作っていくのも楽しいだろうなと思います。最近、ライブでのノリ方が決まってしまっていることが多くてつまらないと感じていて。みんな何をしたらいいか考えすぎだから、逆にどうやってノったらいいんだろう?くらいの状態で来てもらっていいと思う。新しい空気が生まれたら面白いし、むしろアルバムの曲を全然知らなくても楽しませる自信はあるので、安心して来てほしいです。
――通常のライブとは別に、水戸、福岡、札幌ではトークライブも開催されるそうで。去年のツアー(【MUCC TALK TOUR 2024「MC」】)で始まったものですね。
ミヤ:トークライブ、面白いんですよ(笑)。
――どんどんMUCCしかやっていないことが増えていっている気がします。
ミヤ:最近はそれがひとつのコンセプトなんですよね。30周年に向けてやったことがないことにどんどんチャレンジして、30周年で成熟させられればいいなと思っていて。もともと「ほかと違うことをやったら面白いじゃん」から始まったバンドなので、未だにほかと同じことをするのがイヤなだけなんですけど。
――もう30周年を見据えているんですか?
ミヤ:もう2年後ですからね。やっぱり25周年とも35周年とも気持ちが違うというか、30周年は避けて通るわけにいかない。しかも、活動休止を含めて30周年のバンドも多いなかで、うちは休止していない30周年ですし。きっかけや場所はたくさん作るつもりなので、昨今ライブに来づらくなっている人も気にしてもらえたらうれしいです。
関連商品