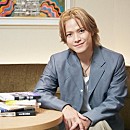Special
稲垣潤一 『男と女‐TWO HEARTS TWO VOICES‐BOX(Special edition)』インタビュー

計35人の女性アーティストとデュエットしたカバーアルバム『男と女』『男と女2』『男と女3』を詰め込んだ豪華BOXを今冬にリリースする稲垣潤一。石原裕次郎の記録をも超えたみせた彼が、このシリーズの話はもちろん、自身のヒストリーや『クリスマスキャロルの頃には』などの代表曲についても語ってくれた。
現実にはドラマティックな雨なんて降らない
--この度『男と女‐TWO HEARTS TWO VOICES‐BOX(Special edition)』をリリースする訳ですが、そもそも稲垣さんが女性シンガーとJ-POPのスタンダードを歌っていこうと思った経緯や理由を聞かせてもらえますか?
稲垣潤一:J-POPがJ-POPと呼ばれる以前からずっと「日本にはデュエットが少ないな」って思っていたんですね。ただ、当時は今よりハードルの高い作業がいっぱいあって。レーベルの壁とか。でも今は実現しやすくなったし、ユニバーサルに移籍したときにスタッフとその話をしていて「やってみましょうよ」と。でもこれは一緒に歌って頂く相手がいないと成立しない訳ですよね。しかも僕もスタッフも初めての挑戦で、歌って頂いた方もほとんどデュエットが初めてだったんですよ。
--なるほど。
稲垣潤一:それぐらい珍しいものだったので、歌って頂く方にお願いして了解をもらうのが一番時間の掛かった作業でした。特に1枚目の『男と女』は前例がないので難しかったんですけど、最終的に11組の方に歌って頂けて。最初のレコーディングが高橋洋子さんと歌った『Hello, my friend』だったんですよ。それを僕も洋子さんも歌い終えたときに「デュエットってこういう形になるんだな」と。やはり声を乗せないと分からないところがあるんですけど、その前に自分が描いていた世界と間違いが無かったなって。
--『男と女』の収録曲は80年代~90年代のヒットナンバーがメインとなっていますが、実際に歌ってみてどんなことを感じたりしましたか?
稲垣潤一:皆さんがよくご存知のヒットチューン。それをデュエット仕様にリメイクするということでプレッシャーはありましたね。ただ、おかげさまで皆さんに良い歌をうたって頂いたし、4人のアレンジャーにも競い合うような形で本当に良いアレンジをして頂いたので、良かったなと思っています。
--稲垣さんがデビューした80年代の音楽シーン。今振り返るとどんな印象を受けたりしますか?
稲垣潤一:ニューミュージックとか歌謡曲、シティポップ、AORなんていうジャンルがあって、まだカテゴラリー的にヒップホップ系は全然いない時代でしたよね。日本語でレゲエを歌うアーティストもいなかった。だから今の方が「J-POP」とひとえに言ってもいろんな音楽性を持ったアーティストが多い。80年代は81年が寺尾聰さんの『ルビーの指輪』で、82年に僕がデビューするんですけど、そこだけ見ても今との違いは明確。僕は今年で28周年なんですけど、その間にすごく変わりましたよね。メディアもレコードからCDになって、カセットからMDになって、アナログからデジタルになった。
--楽曲の作り方も大きく変わっていきましたか?
稲垣潤一:僕はバブルの時代にデビューしているので、曲作りのポイントなんかは今とは随分違っている。僕の曲に対して当時「映像やストーリーがよく見える」ということが言われていたんですけど、そこは意図的に作っていて。例えば『ドラマティック・レイン』という曲がありますけど、現実にはドラマティックな雨なんて降らないんですよ。
--(笑)。
稲垣潤一:それはある種のフィクションだったりして。でもそういう曲でも絵が見えるような詞、というものをテーマにして作っていました。だから「そんなのあり得ない」っていう世界を当時は敢えて歌っていたんです。ただ、90年代になってバブルがはじけると、00年代に向けてだんだんリアリティのある詞じゃないと受け入れてもらえなくなって。時代がそうさせてるんでしょうけど、リスナーが曲に背中を押してほしいと思うようになる。それは今も続いてますよね。
--その今の日本のシーン。他にはどんな印象を受けていますか?
稲垣潤一:昔みたいにお店へ行って買わなくても曲が購入できたり、本当に時代が変わっちゃってて。いろんなものが影響してるんだけど、音楽を聴く人が減ってる。ただ、ライブに関してはそんなに減ってる印象がないんですよね。実際にステージから見ていて、僕と同世代の人が子育てを終えて会場に戻ってきてる。ご夫婦やご家族で来ている方々も見かけるし。で、ライブというものはずっと形を変えていない訳で、これからも変わらないと思うんですよね。
Interviewer:平賀哲雄
日本人に英語で歌ったってしょうがないじゃん
--なるほど。
稲垣潤一:ですから僕もずっと歌っていくつもりなんですけど。ただ、曲が売れないということについては、もしかしたらこちら側が提供している曲に問題があるのかもしれない。皆さんに聴いて頂けるような曲を作れていないことも一因としてはある気がしますね。
--そうしたシーンの流れの中で、稲垣潤一というアーティストはどんな存在で在り続けようとしてきたと思いますか?
稲垣潤一:僕も時代と共にいろんな変化はしているんですけど、変わっていないのは僕のボーカルスタイル。これが変わっちゃったら稲垣潤一じゃなくなっちゃうと思うので、これはキープしていかなくちゃいけない。
--あと、稲垣潤一さんと言えばラブソング。そこに拘り続けた理由って何だったんでしょう?
稲垣潤一:やっぱり「永遠のテーマだった」っていうことですよね。曲の中にはメッセージ色の強いものや人生の応援歌的なものもあるんですけど、大きい意味ではそれもラブソングなんだろうなと思っていて。で、今はこういう時代だからこそ元気を与えられるようなラブソングを歌っていきたい。
--ラブソングを歌い続けてきた歴史があって。例えば、ロックバンドが「ラブソングなんて格好悪い」みたいな姿勢で活躍している姿を見たりして、それに苛立つようなことは無かったんですか?
稲垣潤一:いや、別にそれはないですね。だって僕もデビューする前は「日本語で歌うのってダサイな」って思っていたぐらいなので(笑)。どうもしっくり来なくて、自分が日本語で歌っている姿が想像できなかった。でも今は「日本語に拘りたい」っていう風に変わりましたね。僕が「ダサイな」と思っていた日本語の曲を格好良く歌えないか。っていうことを今は考えていて。だから来年はどういう形になるか分からないけど、日本語でジャズやアメリカンスタンダードを歌うとか。越路吹雪さんや美空ひばりさんもやっていますが、ああいう形じゃないもの。
--具体的に聞かせてもらえますか?
稲垣潤一:僕はよく「AOR的だ」って言われていて。例えば『男と女3』で『また君に恋してる』を歌ったんだけど「やっぱり稲垣さんが歌うとAORっぽいよね」って言われるんですよ。僕は「どこがAORなんだろう?」って思うんだけど、それはきっと声とか歌い方に対しての印象で。それで「ジャズやスタンダードナンバーをAOR的に、ある種ポップに日本語で歌うことが出来たら、まだ誰も形にしていない世界になるかな」って思ったんです。つまりロッド・スチュワートがアメリカンスタンダードをポップ寄りに歌って大ヒットさせましたけど、あれ的なものを日本語で構築できたらいいなって。なので今は日本語に拘りたいっていう。そこは変わっていきましたね。だって日本人に英語で歌ったってしょうがないじゃん(笑)。通じないし、伝えることができないし。
--こんな質問をされるのは久しぶりかも知れないんですが、稲垣さんは音楽的にはどんなアーティストの影響を受けていたんですか?
稲垣潤一:特にビートルズでしたね。親父が洋画好きで物心付く前からいろいろ見せられていたから、映画音楽の影響ももちろんあると思うんですけど、やっぱり60年代、70年代のロック、ポップス。
--自分が子供の頃「ミュージックステーション」か何かで稲垣さんが『僕ならばここにいる』をドラムを叩きながら歌っていて。実にショッキングだったんですが、あれはどういうストーリーや背景があってのスタイルだったんですか?
稲垣潤一:ドラムが中学1年生ぐらいのときから好きで、まず音とかじゃなくてドラムセットの見た目が。昔は楽器屋さんのショーウィンドウにドラムセットが置いてあって「格好良いなぁ」ってよく見てたんです。で、中3で初めてバンドをやるんですけど、僕はドラムもやりたかったし、歌もやりたかったんですよ。だからドラムを叩きながら歌うというのは、その頃からのスタイルなんですよね。誰かの真似ではなく。ちなみに『僕ならばここにいる』でそれをやるのはすごく難しいんですよ。たくさん練習しましたね(笑)。
Interviewer:平賀哲雄
石原裕次郎さんの記録を超えて、日本新記録
--また、その曲のひとつ前のシングル『クリスマスキャロルの頃には』の大ヒットには、当時どんなことを感じていたんでしょう?
稲垣潤一:常にいろんな方へ曲を発注しているので、いろんな曲が集まってくるんだけど、その中で「サビは良い。それ以外はどうかな?」っていうのがあの曲だったんです。初めて聴いたときに「サビは完璧!絶対にこれは良い曲になる」って分かったんですよ。ただ、サビが良すぎる分、他のメロディが見劣りしたんですね。それで作家の三井誠さんと直しの作業を延々とやってて。それだけ手塩にかけて育てたので、作詞を手掛けた秋元(康)くんもすごく気に入ってくれて、ドラマ主題歌のプレゼンに出したらそのプロデューサーの方も気に入ってくれて。それでドラマ「ホームワーク」主題歌になり、クリスマスソングという要望を受けてあの詞が乗っかったんです。それが僕のシングルとしては1番のビッグセールスになって。そこまでの結果になるかどうかは分からなかったけど、最初から「絶対良い曲になる」っていうのは分かっていましたね。
--『クリスマスキャロルの頃には』や『ドラマティック・レイン』のような時代を超えて愛され続ける楽曲を生めたことは、やはり稲垣さんの誇りになっていますか?
稲垣潤一:長年にわたって愛され続けているのは嬉しいですね。だからそういう曲をこれからも歌っていきたい。時代を超えて愛され続ける曲をやっぱり歌っていきたいなって思いますね。ある種のスタンダードナンバーというか。
--『男と女』シリーズでは『ドラマティック・レイン』を中森明菜さんと、『クリスマスキャロルの頃には』を広瀬香美さんと歌われていますが、それぞれ仕上がりにどんな印象や感想を持たれましたか?
稲垣潤一:明菜さんには『ドラマティック・レイン』が絶対に合うなって思っていたんですよ。そしたらやっぱり曲とのマッチングがすごく良くて。あと、僕の声と似てるなと初めて気が付きました。明菜さんがすごく低いキーで歌ってくれてるんだけど、僕が歌ってるのか彼女が歌ってるのか分からないぐらいの瞬間があってね。ビックリしました。で、広瀬さんとの『クリスマスキャロルの頃には』は彼女のキャラクターが全面に出てる。非常にパワフルな声を持っている方ですからね。その香美節が出ていて、あれはあれでまた良いデュエットになったなと思います。
--その『男と女』シリーズで稲垣さんは全35人の女性アーティストとデュエット曲を録音した訳ですが、まずよく実現しましたよね?
稲垣潤一:本当に。デュエットソング数としては石原裕次郎さんの記録を超えて、日本新記録ということなんですけどね。皆さんが一緒に歌ってくれて本当に嬉しく思ってるし、スタッフが一丸となって動いてくれたおかげかなと思ってます。ただ、ギネスに申請したら上には上がいるもんで、ウィリー・ネルソンが100曲以上……あって。
--めちゃくちゃな数ですね(笑)。
稲垣潤一:ありゃ!?ってなって。
--でも3年間でこれだけの人数とデュエットした訳ですから、他の男性アーティストに羨ましがられませんか?
稲垣潤一:よく「俺もやりたかったんだよな」って言われます(笑)。
--あと、このシリーズを聴いているとトキメキが甦るというか、稲垣さんと35通りの女性の声の交わりを聴いてると、ウキウキしてくるんですよね。実際、レコーディングしていてもその感覚はありましたか?
稲垣潤一:自分の中のハイライトは、僕の歌に女性アーティストの歌が乗ったものを聴いたときで。スタジオで聴いてて「やった!」みたいな。いつもいつもその瞬間に感動するんですよ。
--ちなみに今後機会があったら新たにデュエットしてみたい女性シンガーっていますか?
稲垣潤一:いっぱいいます。歌の上手い方はいっぱいいらっしゃるんでね。あと、このシリーズでは主に女性が歌っていたヒット曲をカバーしているんですけど、その点で考えてもまだまだ曲はたくさんありますから。なので「またやってみたい」って気持ちはあります。『男と女4』を出すかどうかはまだ分かりませんけれど。
--で、この『男と女』シリーズも大きなチャレンジだったと思うんですが、11月18日と19日には新日本フィルハーモニー交響楽団とのコンサートを開催。初めてのフルオーケストラとの共演、実際に挑戦してみていかがでしたか?
稲垣潤一:あの編成で歌うのは生まれて初めてだったんですよ。で、どんな形になるのかは本番迎えるまで分からなくて。東京文化会館にはオーディエンスとして1回行っていて「音の良い会館だな」と思っていたんですが、後から“クラシックの聖地”であそこで歌うことは名誉であることが分かって。そんな場所であれだけのオーケストラをバックに歌えたのは、本当に至福だったし、今まで経験したことのないものでしたね。本当に心地良かった。
--お話をいろいろ伺わせていただきましたが、来年もチャレンジの年になりそうですね。
稲垣潤一:そうですね。今年は新日本フィルハーモニー交響楽団とコラボレーションできたり、山中千尋さんというジャズピアニストと箱根の野外でライブできたり、なかなかご一緒できない方とライブをさせて頂いて。なので、来年もそういうミュージシャンの方々と何かできたら良いなと思ってますね。先ほど話した「日本語でスタンダードナンバーを歌う」というのも山中千尋さんとのライブが影響していたりするので。パーマネント的なバンドとのライブだけじゃなく、異種格闘技的なライブもやっていきたいですね。
Interviewer:平賀哲雄
関連商品