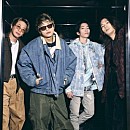Special
<コラム>2025年上半期“ニコニコ VOCALOID SONGS”を振り返る
![]()
Text:小町碧音
2025年上半期“ニコニコ VOCALOID SONGS”が、6月6日に発表された。2022年12月7日より開始された“ニコニコ VOCALOID SONGS”は、ニコニコ動画上の音声合成ソフトウェアで制作された楽曲の動画再生数や、作成数、コメント数、いいね数などのデータに、ビルボードが独自開発した係数を乗じてTOP20まで可視化したチャートだ。今回、上半期の頂点に立ったのは、柊マグネタイトの「テトリス」で、2位のDECO*27「モニタリング」とは接戦だった。
【ビルボード 2025年上半期ボカロ・ソング・チャート“ニコニコ VOCALOID SONGS”】
— Billboard JAPAN (@Billboard_JAPAN) June 5, 2025
1位 柊マグネタイト
2位 DECO*27
3位 サツキ
4位 ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ
5位 吉田夜世
6位 DECO*27
7位 雨良 Amala
8位 はろける
9位 あばらや
10位 大漠波新 pic.twitter.com/7TNwNtDj8b
柊マグネタイトは、2021年以降、シーンで爆発的なムーブメントを巻き起こしたCeVIO AIの音声合成ソフトウェア「音楽的同位体 可不」をフィーチャーしたアンセム「マーシャル・マキシマイザー」を制作したボカロPだ。その柊マグネタイトが2024年11月に投稿した「テトリス」は、黄色の背景を背に回転し続ける重音テトが、〈鬱とか躁とか忙しくて 眠れないわ 今日も〉と自虐モード全開で歌う。ゲーム「テトリス」のBGMとして有名なロシア民謡「コロブチカ」のメロディを軸に、テトとテトリスを組み合わせた語感重視のリズミカルなフレーズや、2024年後半にネットスラングとなった風呂キャンセル界隈を連想させる〈人生キャンセルキャンセル界隈〉など、旬の勢いを最大限に活かした一撃ワードが光る。
▲柊マグネタイト「テトリス」
柊マグネタイトの功績もさることながら、10月にデビュー17周年を迎える古参のボカロPながらも未だにシーンの最前線を走り続けるDECO*27の目覚ましい活躍にも注目したい。DECO*27のブランドは「モザイクロール」や「ストリーミングハート」などが爆発的に歌い手によってカバーされた2010年代から群を抜いていたが、その人気は16年が経った現在も、際限のない青空だ。2024年11月27日にリリースしたアルバム『TRANSFORM』では新調声ミクを取り入れているなど、“変化”をテーマにした作品作りをしていることもその深化に大きく影響しているだろう。DECO*27は、YouTubeやTikTokを通して、2023年5月以降、独自の初音ミクの3Dモデル(デコミク)を使って主に楽曲のプロモーションを行うようになった。このアプローチは、本チャートの動向と実は密接に関わっている。
▲DECO*27「モニタリング」
また上半期の期間中には、1月17日から全国の映画館で上映されたスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク』から派生するかたちで生まれた『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』関連の楽曲が軒並みランクインした。劇中挿入歌「ハローセカイ feat. 初音ミク」をDECO*27が手がけたほか、ユニット&バーチャル・シンガー楽曲に書き下ろした6曲を、kemuやいよわ、煮ル果実などの6人のボカロPのアレンジでそれぞれ完成させた。2月19日公開チャートでは、「ハローセカイ feat. 初音ミク」が1位を飾り、劇場版プロセカ関連の楽曲やDECO*27の過去曲「ヒバナ」などの計11曲も上半期中に登場。さらに、マルチメディアプロジェクト『カゲロウプロジェクト』で知られるボカロP・じんが書き下ろしたエンディング主題歌「Worlders」も、2月5日公開分で最高3位をつけている。2008年10月にデビューしたDECO*27、2011年2月にデビューした、じんと言い、シーンの金字塔的存在が、ドラマチックなストーリーを広げた上半期は、劇場版プロセカが、新規リスナーの獲得源になったことが見て取れた。
▲DECO*27「ハローセカイ」
また、投稿数が過去最大となったボカロシーン最大のイベント「ボカコレ」は、プロセカと並んで、新たな才能を見つけるにはうってつけの場所だ。2月に開催された『ボカコレ2025冬』のTOP100では、これまでもルーキー枠で参加経験のあるボカロP・あばらやが「花弁、それにまつわる音声」でトップポジションを制したこともあり、揺るがない安定感と超新星への期待が走ったことは喜ばしい。
▲あばらや「花弁、それにまつわる音声」
2025年上半期に共通しているのが、初音ミクや重音テトを中心としたバーチャル・シンガーでMVのサムネイルが統一されていること。重音テトをフィーチャーするムーブメントが発生した2024年の流れを引き継ぎつつ、現在増えているのは、サツキの「メズマライザー」を発端にした、初音ミクと重音テトの二人を登場させるパターンの楽曲だ。初音ミクや重音テトというキャラクターの持つ透明性は、フラットに視聴者に受け入れられる傾向にある。二次創作の中には、MVのバーチャル・シンガーが投稿者独自のキャラクターに置き換えられた動画も見られたが、これもミクとテトが持つ透明性に由来した創作の形なのかもしれない。
海外で支持を集めるボカロPの楽曲は、バーチャル・シンガーのビジュアルがシンボルとなっていることが多い。ボカロPそれぞれによる調声でバーチャル・シンガーの声に独自の色が宿っているように、ビジュアル面でもその人らしいバーチャル・シンガーを確立することが、今後定番となることも十分に考えられる。
▲DECO*27の動画に登場する初音ミク、通称「デコミク」は、オリジナルの3Dモデルによる振り付け動画や企業とのコラボレーションなど、さまざまな形で展開されている
「モニタリング」は、1月2日に公開された韓国で聴かれている日本の楽曲チャート“Japan Songs(韓国)”で8位にランクインし、「メズマライザー」はアメリカ、シンガポール、韓国で聴かれているなど、昨今は海外リスナーの流入がバズの強力なブースターとなっている。たとえば、2022年にデビューし、すでにグローバルなファンベースを築いているボカロP・ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ。上半期チャートで4位にランクインした「み む かゥ わ ナ イ ス ト ラ イ」で、MVの画面に日本語と英語詞字幕の両方を、中国の動画配信プラットフォーム「Bilibili」では中国語詞字幕を付けている。2021年にデビューしたはろけるも「キャンディークッキーチョコレート」で、日本語を含めた13言語の翻訳字幕を設定しているのが目に留まる。
▲ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ「み む かゥ わ ナ イ ス ト ラ イ」
とりわけ、海外リスナーの支持が圧倒的に高いボカロPとして名があがるのは、「愛して愛して愛して」がSpotifyでボカロ曲として初の1億回再生の快挙を成し遂げた、きくおだ。2024年1月には自身初の海外公演となるアメリカツアーを開催し、今年2月にはワールドツアー【Kikuo World Tour 2024-2025 “Kikuoland-Go-Round”】のヨーロッパ編を開催した。そんなきくおは、遥か前からアメリカ発の音楽配信プラットフォーム「Bandcamp」を利用していた。こうしたグローバル展開も視野に入れた種まきが、のちの海外リスナーとの接点を作ることを踏まえると、今後、多言語の翻訳字幕やテロップの表示などのグローバル戦略は、一層加速していくと思う。ここで機能するのが、ドワンゴの取り組みである、日本のクリエイターが世界で、世界のクリエイターが日本で、相互に活躍できる機会の創出を目的としたクリエイター連携プログラム「Asia Creators Cross」。その一環として、5月に開催された中国最大級の音楽フェス【Strawberry Music Festival】に、中国でもファンが多い南ノ南、なみぐる、夏山よつぎ、TeddyLoidの4名がDJパフォーマンスで出演した。
それにしても、前回の2024年上半期“ニコニコ VOCALOID SONGS”の振り返りコラムでも感じたことではあったが、ボカロ曲は、主にZ世代が直面する現在進行中の社会問題をリアルに映し出す鏡だ。昨今のトレンドのアップビートなサウンドの存在で気づきにくいものの、底で描かれているのは、LSDやオンラインカジノなどが話題に上がる現代の闇に思える。幻覚症状から勝手な妄想を繰り広げる「モニタリング」や初音ミクの後半のビジュアル転換が不穏な「メズマライザー」などが濃厚だ。その観点で言うと、雨良 Amalaの「ダイダイダイダイダイキライ」も似ていて、サビに突入した瞬間、トリップ状態を誘発する刺激的なサウンドメイクが舞い始めるのが特徴。「メズマライザー」のMVを手がけたchannel(現名:CAST)の作風をオマージュして制作したと本人がのちに告げた「キャンディークッキーチョコレート」にも、思考を螺旋の中に引きずり込んでいくタイプのアニメーションが目立つとともに、タイトルの3つのお菓子の名前はどこか隠語を彷彿とさせる。
▲雨良 Amala「ダイダイダイダイダイキライ」
ゲーム「テトリス」のBGMになっているロシア民謡「コロブチカ」のメロディを引用した「テトリス」やパロディやネットミームを大量に詰め込んだ「テレパシ」からも見られるように、すでに既視感の演出は、ボカロシーンの定石となっている印象だが、前述したトリップ状態を誘発するテーマ性を持った楽曲群の増加の点から着目したいのは、〈ざぁーこ♡、ざぁーこ♡。〉と頻繁に繰り返す「み む かゥ わ ナ イ ス ト ラ イ」や、〈ダイダイダイダイダイキライ OMG 情けない 最早 バイバイバイバイバイしたい〉と繰り返し、韻を踏む「ダイダイダイダイダイキライ」、イントロから〈CANDY CANDY CANDY COOKIE CANDY CANDY CHOCOLATE〉と曲名を堂々とアピールする「キャンディークッキーチョコレート」のような脳内に執拗に残りやすいループするトラック構造。そのなかでも、格別に「テトリス」はイントロから秀逸だ。刻むビートを含め、どこを取ってもサビに聴こえる作りになっている。
つまり、現在のボカロシーンのひとつの大きなトレンドは、脳内に負担をかけすぎない電子ドラッグといえるだろう。これは現代のZ世代をメインとした人々のSOSでもある。そして、昨今アップビートなサウンドが増えているのは、TikTokなどのショート動画プラットフォームとの相性の良さから来ていると思うが、その奥には、きちんと“闇のリリック”を置くーー。ここに鋭い眼光でリアルを語るボカロ曲の真価が生きている。これだから、ボカロ曲の摂取はやめられない。