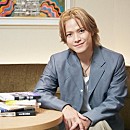Special
<インタビュー>2人組ユニットharhaが届ける、どん底から這い上がれた経験があるからこそ歌える希望

Interview:矢島由佳子
SDR(スターダストレコーズ)が主催する「クリエイターズマッチングプロジェクト」で優勝を掴んだハルハが、インターネット上で見つけたボーカリスト・ヨナベに声をかけたことをきっかけに、2022年より活動を開始した音楽ユニット・harha。「人生オーバー」は、倉持めると、ガチャピン、ばんばんざいなど、多数のアーティスト/インフルエンサーたちの「歌ってみた」動画が上がっている。3月30日に東京・恵比寿CreAtoにて開催される初のワンマンライブは、チケット応募多数のため急遽決定した追加公演も含めて完全ソールドアウトした。
そんな人気を博しているharhaのことを、一言で表すなら、私は「あなたと歩んでいくシネマティック・ポップス」と呼びたい。harhaが生み出す音楽や世界観が今多くの人に希望を与えることができている理由を掴むべく、さまざまな角度から話を訊いてみた。
「お茶の間に届くJ-POPを作りたい」
harha結成のきっかけ
――ハルハさんは、ヨナベさんに声をかける頃、どんな音楽をやりたくて、そのためにどんなボーカルを探していたのでしょうか。
ハルハ:女性ボーカルの方と一緒に、2人組ユニットとして活動していきたいという想いがありました。ヨナベさんは……「お茶の間ウケする声」って言ったらいいんですかね? 自分の声は好きではあるんですけど、ちょっと哀愁を帯びてしまうと感じていて、よりJ-POPらしいものを作っていくには、もう少し温かみのある声色の方がいいなと思っていました。あとは、「余白のある声」を探していましたね。今の歌い手の方って、めちゃくちゃ歌唱力が高くて、技術が秀でている方が多いんですけど、ヨナベさんは歌唱力はもちろん、「楽曲と一緒に歩ける」みたいに感じさせてくれる声だと思ったんです。悪い声色というものは絶対に存在しなくて、その人それぞれの声に合った楽曲が必ずあると思っていて。僕が作り出したかった曲に合っていたのがヨナベさんだったという気がします。
――結成時から「お茶の間に届くJ-POPを作りたい」という想いが強くあったということですよね。お茶の間に届く要素とは何か、クリエイターによって考えが違うと思うんですけど、哀愁ではなく「温かみ」や「一緒に歩ける」といったことが大事だと思っていたというのは面白いですね。
ハルハ:僕がもともと作っていた音楽は、「1対1」みたいな感じだったんです。僕の中の気持ちが自己完結すればそれでいい、と思って曲をたくさん作っていたんですけど、お茶の間にしっかり曲を届けたいと思ったときに、「1対1」ではなくて「1対多数」になる音楽を作りたいということをすごく考えていました。歌詞も誰かが聴いたときに入り込める余地があったり、結末が一個に定まってない物語にしたりすることを、すごく意識して作っている気がします。
――ハルハさんは、もともとラッパーとして活動されていたそうですね。
ハルハ:高校の3年間は本格的にやっていましたね。『高校生RAP選手権』や、地元のMCバトルに出たり。でも初めて出会った人と悪口の言い合いをすることが向いてなくて。地元のMCバトルなんて、ちゃんとしたラップバトルじゃなくて、もうただの喧嘩みたいな(笑)。先輩にボコボコに言われてシュンとして帰るようなことになっていたので、結局バトルに出ることはやめて、楽曲作りをするようになって、高校を卒業してからDTMをどんどんやり始めたことが今に繋がっています。
――そうやってバトルに出ていた頃も、「本当は多くの人に届くJ-POPを作りたいんだけどな」みたいな想いがあったんですか?
ハルハ:僕の初期衝動は、RADWIMPSさんのライブを広島グリーンアリーナで観たときに「ここに絶対立ちたい」と思ったことで。でもラップをしていたときは、それとは違った動機があったんですよね。
――ラップは、どういった動機だったのでしょう。
ハルハ:自分の逃げ場みたいな場所でした。歌詞にすれば、自分の言い表せない複雑な気持ちを昇華できたから、曲をたくさん作っていたんです。でもある程度曲を作ったときに、ふと初期衝動を思い出して、「このままやっていてもグリーンアリーナにはたどり着けないな」ということを強く思って。そこから「もっと人に聴いてもらえる音楽とは」ということを考え始めて、harhaが始まったのだと思います。ラップをしていた頃もヒップホップだけじゃなく、J-POPもJ-ROCKもボカロも聴いていたので、最終的に作りたかったのはそういう音楽だったのかもしれないです。
――amazarashiも好きだったそうですけど、誰かを傷つけるようなバトルではなく、amazarashiみたいに誰かの痛みに包帯を巻けるような音楽を作りたいという気持ちもあったのでしょうか。
ハルハ:そうですね。amazarashiさんには本当に救われました。高校2年生くらいのときに、上手く言い表せない「他者とのズレ」を感じて、「なんで生きてるんだろう」みたいなことまで考えていたときに、「月曜日」という曲に共感して。それ以降、どの曲を聴いても「欲しい言葉をくれる」みたいに感じたんですよね。「頑張っていこうぜ」とかじゃなくて、「つらいよね、わかるわ」くらいの温度感で接し合ってくれるので好きでした。高3の頃にamazarashiさんがツアーで広島に来て、「月曜日」をやってくれたときにはボロ泣きでしたね(笑)。
――ハルハさんが「多くの人に届くJ-POPを作りたい」と思っていた一方で、ヨナベさんはどういったモチベーションで「歌ってみた」の動画をネットに上げていたんですか? プロとしてやっていきたい、といった想いがあった?
ヨナベ:私はまったくそういう意識ではなくて。人生で初めてすごく好きになったアーティストさんがヨルシカさんで、ヨルシカさんを好きになるまでは歌ったことがなかったんです。でも「歌ってみたい」と思って、カラオケに行って練習していたんですよ。その動画をスマホのデータを整理するためにYouTubeに上げていました。
ハルハ:面白いですよね、YouTubeをDropbox代わりにしていたんです(笑)。
――それまで自分は歌が上手いという自覚はなかったんですか? 小さい頃から家族や友達に褒められたり。
ヨナベ:うーん……国語の授業で詩を詠むテストがあって、本当は覚えていないといけないのに私はまったく覚えられてなかったんですけど、先生が満点をくれたことがありました。そしたらみんなから「覚えられてなかったやん!」ってブーイングが起きて、でも先生が「声がいいから」って言ってくれました。それくらいです(笑)。
――詩や言葉を届けるのに合っていた声だったんですね。
ハルハ:ヨナベさんの話を聞けば聞くほど不思議なんですよね。harhaを結成するまで音楽経験がなくて、友達とカラオケに行ったりとかもほぼないし。それなのに、初めて会ったときから「ちょっと試しにハモを歌ってみてもらってもいいですか?」とか言ったら歌えるんですよ。だから謎なんですよね。できちゃうのが不思議でたまらないです。
ヨナベ:あ、ハーモニカだけやったことあるよ。ちゃんとはできないけど。一時期ハーモニカが欲しくて、親にねだって買ってもらって。本当に一時期だけ、フーって吹いてた。
ハルハ:(笑)。実家にピアノはあるみたいで。でも、まったく弾かないらしいです。
――ご家族が弾かれるとかですか?
ヨナベ:誰も弾かない(笑)。
ハルハ:もったいない! 僕が欲しいくらい!
――ハルハさんに声をかけてもらう前は、将来何をしたいと思っていたんですか?
ヨナベ:会社員になって普通の人生を送ろうと思っていました。本気で目指していたものとかもなく、普通にお金を稼いで、ゆっくりして生きようかな、みたいな。
――働きやすい会社に就職して、いい感じのワークライフバランスで暮らしていけたらな、みたいな。
ヨナベ:あ、そうです(笑)。
ハルハ:僕は「音楽で頑張っていきたい」と思っていたんですけど、ヨナベさん自身は特にそういうのがなく、「歌が歌えたらいいかな」くらいの温度感で始まって。ヨナベさんはひとりでふらっとどこかに行っちゃうタイプで、出会った当初も「この前どこどこ行ってきたよ」みたいな感じだったから、気づいたらどっかに行っちゃうんじゃないかなと思っていたんですけど……続けてくれてて嬉しいです。
ヨナベ:そんな心配してたんだ(笑)。
ハルハ:それこそ今はたくさんの方に聴いていただけて、ワンマンもできて、といった状況で。僕はそれを目指してここまで来ているけど、ヨナベさんからしたら、急にいろんな人に曲を聴かれて、いろんな人から賞賛の声もらって、ステージに上がることになったから、「もしかしたらヨナベさんが望んでいるものではないかもしれない」みたいな不安は一瞬よぎる。
――実際、ヨナベさんは今どういう気持ちやモチベーションなんですか?
ヨナベ:今は本当に、ただ歌うのが楽しいってだけですね。携帯とかインターネットがあまり得意じゃなくて、自分でいろんな人のコメントを見に行ったりもしないので。ボイトレしたらどんどん歌が上手くなったり、ステージングの練習をやると表現ができるようになったりするのが楽しい。それが一番のモチベーションになっています。
「一旦、大丈夫」くらいの、ちょっとした希望があればいい
――純粋に歌の楽しさを追求するヨナベさんと、大衆に届けることを意識してクリエイトするハルハさんという、見事なバランスなんですね。しかもハルハさんが綴る詩を、ヨナベさんが歌うことで、「絶望するよね、でも大丈夫だよ、行こう」と、手を引っ張ってくれるところまで表現できているんじゃないかなと思うんです。その部分について掘っていきたいなと思うんですけど……そもそもハルハさんは高校生の頃、どんなことに違和感や絶望を感じていたんですか?
ハルハ:当時は……周りの人らは放課後に部活をしたり遊びに行ったりする中で、自分は部活も速攻やめたし、学校が終わればひとりで帰ってラップする、みたいな生活をしていて。でもヒップホップのカルチャーに入っても、僕は不良でもないし、「高校行ってねえぜ」とかでもなく、どちらかというとJ-POP寄りなラップで、そこでもズレがあって。家族の中でも悩みみたいなものがあったし、腰を落ち着ける場所がなくて悶々としていたんですよね。そういう中で高2のときに、僕が書いた文化祭の劇の台本を美術部の先生が褒めてくれて、「君は絶対に芸術の道に進んだ方がいい」って言われて、気づいたら勝手に美術部に入れられてて(笑)。その恩師が「芸術は鏡だ」と言ってて、それが自分に刺さりすぎたんです。結局自分で生み出したものには自分の思想とかが如実に出るものだから、作品を見ればその人がわかるっていう。そこから音楽のサウンドや歌詞でも、どうしていけば自分の作りたいものに近づけていけるのかをすごく考えて作業するようになりました。高校生のときがいわゆる僕の中での「絶望」で、一回地獄を味わったから、逆に楽観的になった部分があります。その先生に出会って、だんだん吹っ切れるようになったんだと思います。
――芸術で表現する術を知って、楽観的になれたとも言えますか?
ハルハ:そうなんです。悲しいことがあっても「曲にすればいいじゃん」という思想に変わりました。しかもめっちゃいい曲ができたら、すげえ吹っ切れるというか。高校3年生のときも、「この曲ができたから、別に受験落ちてもいいか」と心底思えていました。それがそのまま歌詞にも出ているのかなっていう気がしますね。
ヨナベ:ハルハくんの曲は、ちゃんとハッピーエンドに持っていってくれるなと思うんです。「人生ってそんなに嫌なものではないよ」みたいなことが多いなと思います。
――それは、どん底から這い上がれた経験があるからこそ歌える希望なんでしょうね。
ハルハ:塞ぎ込んでいるところを助長する歌ではなくて、立ち直るまではいかなくても、「一旦、大丈夫」くらいの、ちょっとした希望があればいいなと思ってて。僕がよく言ってるのは、ヨナベさんに「近所のお姉ちゃん」みたいな存在になって欲しいということなんです。つらいことがあったときに、話を聞いてもらったらスッキリする、というくらいの希望があればいい。料理でたとえるなら「最後のひと塩」くらいの希望があればいいかな、っていう感じですね。
ヨナベ:でも(ひと塩)振ろうとして振れるものでもないからさ。個性ですよ。
ハルハ:高校生のときに作っていた曲は鬱まっしぐらだったと思うんですよ(笑)。いろんなことを経て、そういう気持ちになったのだろうなと思います。
――たくさんの人が「歌ってみた」を上げている「人生オーバー」については、「大丈夫、一緒に行こう」までは言ってないんだけど、「絶望するよね」をすごくあっけらかんと歌ってくれているようなテンションが心地よくて。
ハルハ:特にこの曲は、それこそ僕が歌うと暗くなって絶望すぎちゃう感じになると思うんですけど、ヨナベさんの声がちょうど「絶望なんだけど、明るく聴こえる」という部分を担ってくれているなと思います。
ヨナベ:やったー! この曲は「人生終わってるけど、みんなそんなもんやろ」みたいな(笑)。「みんな同じだよ」みたいな感じがある。それが刺っているんじゃないかなと思います。
――ハルハさんも、この曲がここまで広がった要素はそういったところだと思いますか?
ハルハ:大正解だと思う。
ヨナベ:みんなやっぱりしんどいんじゃない?
ハルハ:うん、だと思う。普段生活していてすごく嫌なことが続いたときに、「人生オーバー」を歌ったら、ぴったりだと思ったんだよね。《何も上手くいかないって/誰のせいにしてやろう》みたいな状況が、みんなにもフィットするのかもしれないね。
ヨナベ:そうなんだよ、きっと。
――日本の不景気やいろんな状況の影響もあって、年々「人生上手くいかない系」「鬱系」の音楽が流行ってるなという気がするんですよね。
ヨナベ:わかります。
ハルハ:J-POPは現代を反映する側面がある中で、社会がそっちに向かっているから、曲もそうなるんだろうなという気がしますね。でも「人生オーバー」は、俺の中で明るい曲だから、鬱っぽくはなくて。「無理だよね! バイバイ!」みたいな。みんなにもその温度感で思って欲しいですね。変に抱え込まずに、「しょうがないか!」みたいな感じになって欲しいです。そもそもヨナベさんがそんな感じなんですよ。
ヨナベ:うん、どうにでもなると思って生きている。
――その生き方や性格が、歌声にも出ているんでしょうね。それがハルハさんの綴る歌詞と素晴らしく調和しているのだろうなと思います。最新曲「アンコモンセンス」についてもお伺いしたいのですが、これはどういった発想から作った曲ですか?
ヨナベ:「アンコモンセンス」は、みんなそれぞれの当たり前を当たり前と思えたらいいよね、という曲です。今の世の中、押し付けられる常識も多くて、自分が当たり前だと思っていたものが世の中的には当たり前じゃないなと思っちゃうこともあるけど、「いいんですよ」と。それぞれの当たり前があることは当たり前なんですよ、という歌です。
ハルハ:出羽(良彰)さんにアレンジをしていただいたんですけど、最初に僕からお願いしたのは「とにかく疾走感が欲しい」ということ。当たり前をぶち壊せるくらいのエネルギーが溢れる曲にして欲しいとお伝えしました。
――この曲もそうですけど、やっぱりharhaの音楽は、ボカロ、ロック、J-POPの系譜が交差しているところにありますよね。
ハルハ:そう言ってもらえることはめっちゃ嬉しいです。いろんな要素の匂いが感じられたらベストだなとは思っているので。J-POPにしていこうということは常々たくさん考えていて。特にメロディラインはマジで吟味しますね。サビまでどう持たせるか、サビをどう聴かせるかということを最優先で考えて、カラオケで歌いにくくならないように、ぱっと聴いたときに覚えにくくならないように、といったことも精査するようにしています。ボカロの文脈は自分が世代で通ってきたものでもあるので、意識しなくても出ちゃうんだと思います。
――3月30日には初のワンマンライブが開催されます。追加公演までソールドアウトになっていますが、どんなライブにしたいと思っているかを聞かせてください。そもそもライブは何回目ですか?
ハルハ:harhaとしては3回目になるのかな。でも僕はラップをやっていた頃にライブをしていたので。ワンマンはドラム、ギター、ベース、キーボードと、フルバンド編成でやります。全体のテーマとしては、お客さんと対話することを重要視していますね。コール&レスポンスとか掛け声をありとあらゆるところに詰め込んで、お客さん参加型のライブになればいいなと思っています。映像や照明もそういうことに合わせて作っています。とにかくワクワクさせる、ヘトヘトになって帰ってもらう、この2つを大事にしたいですね。
ヨナベ:私は、ライブが終わったら「また会いたいな」と思うはずだから、みんなも「また会いに来たいな」って思ってもらえたら素敵だなと思います。すごく楽しみです。