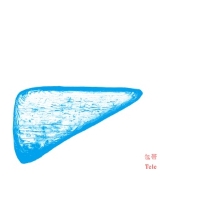Special
<インタビュー>Tele、運命的な初ドラマタイアップ「包帯」完成――転換期を迎えて向き合う“俗っぽいもの”との距離感

Teleの新曲「包帯」は彼にとって初のドラマタイアップとなる『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ!』(テレビ東京)のエンディングテーマ。しかし書き下ろしではなく、なんと楽曲自体は2年ほど前から存在していたものだという。谷口喜多朗の極めて個人的な記憶と感情から生まれた曲が、時を経て、彼自身も好きで観ていたという『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの初連続ドラマと邂逅する――なんとも運命的だが、このインタビューを読めば、そこにはTeleの物語としての必然が間違いなくあったのだとわかってもらえるはずだ。今年、初の武道館公演を成功させ、来年4月にはさらにスケールアップして横浜アリーナのステージにも立つTele。アーティストとして大きな転換点にいる今だからこそ、この曲に刻まれた孤独と苛立ちは大きな意味をもつ。(Text:小川智宏 I Photo:久保寺美羽)
武道館やってみて「何かを演出する」っていうのが結構好きなんだなって
――6月の武道館公演、素晴らしかったですね。ステージとお客さんの間に生まれる空気も、それまでのTeleのライブとは違って、より近いというか、交差している感じがしました。
喜多朗:そうですね。ツアーも本当に各地、すごい熱量の人たちが多かった。なんか「うわーっ!」みたいな。それが嬉しかったですね。
――それに引っ張られるようにして、喜多朗くんの感情もより表に出ているような感じがしました。
喜多朗:世の中の人に聴いてもらうためにはそういう部分は曲に出さない方がいいんじゃないかと思っていたんですよ。でも僕は昔からパンクスとかも好きだし、いわゆるロックの中でも、そういう自分の中の非合法なパッションというか、倫理的じゃない部分を解放するみたいなところにずっと憧れていたし、それでスリーピースのバンドをやったりしていたんだけど、でもそれがまったく人に受け入れられなくて日の目を見なくて。だからそこは音源には入れないようにしよう、自分のそれ以外の部分を人に見てもらおうと思っていたんですけど、それが意図せずしてお客さん側から出てくるっていうのがすごく嬉しかった。
――それによって「箱庭の灯」というテーマも、そもそも考えていたときはおそらく違うものになっていったんだろうなって。
喜多朗:武道館やってみて「何かを演出する」っていうのが僕は結構好きなんだなって思いました。ゼロから1を作るっていうのと同じくらい、作られたものをどう飾り付けてあげるかというか、どう見せてあげるかみたいなものが、僕は結構好きなんだなって。ライブの何かをきっかりデザインする、編集する能力は僕にはなくて……演出と編集の違いは何だろうと思うと、編集は最終的にきっかりプラン通りにいくことが理想で、演出っていうのは余地を残すっていうか、「この人はこう思うかもしれない」みたいなものも含めて置いておくというものだと思うんです。「箱庭の灯」というテーマで、こういうものにするっていうのはざっくり決めていたんですけど、それが当日、いろんな人がいる中で全然違うものになっていくというのも含めて、これはたまんないなって。思い通りにならない方が楽しいっていう喜びを感じたのかなと思います。
――うん。もちろん自分だけの箱庭を作るんだけど、ライブを通してそこにちゃんとヒビが入ってくっていうか、光が漏れ出していくっていうか。そういう感覚があった。
喜多朗:本当におっしゃる通りです。こんなにもみんな有機的で、素晴らしいねって。
――Teleは今までツアーやったりワンマンライブやったりすると、その度にまだやり残していることというか、積み残しみたいなものを感じながら次に行くみたいなことを繰り返してきたじゃないですか。今回はそれとは違う感覚で終われた?
喜多朗:そうですね。なんか、みんな観てておもしろかっただろうなって思った。武道館のあんなステージ、みんな見たことないだろうし。もちろん、ミュージシャンのアスリート的な観点からすると100点ではなくて、そこはもっとトレーニングを積んでいきたいんだけど、「これはおもしろいぞ」みたいな。じゃあ、次やるんだったら何がおもしろいかな、みたいな感じで終わりました。次はこれやりたくて、あれもやりたくてみたいな感じですね。
――おお、なんかライブをやるモチベーションが少し変わった気がしますね。
喜多朗:「これをやらないと誰からも受け入れられないんじゃないか」みたいな切迫感から頑張ってきてたんですけど、これからは切迫感じゃなくて、もうちょっと……なんて言ったらいいんだろうな、切迫感はあるんですけど、その切迫感を上回るくらい、自分がやりたいものに対する欲望というか下心が増えた。今までちょこちょこ出していたものが、いいものにまとまって、「じゃあ、あれもできるんじゃないの」みたいな。よだれをだらだら垂らしてるみたいな感じです(笑)。

リリース情報
公演情報
【Tele Tour 2025】
2025年3月1日(土)香川:高松Festhalle
2025年3月7日(金)広島:BLUE LIVE HIROSHIMA
2025年3月15日(土)宮城:SENDAI GIGS
2025年3月21日(金)、22日(土)大阪:Zepp Osaka Bayside
2025年3月28日(金)、29日(土)福岡:Zepp Fukuoka
2025年4月2日(水)、3日(木)名古屋:Zepp Nagoya
2025年4月6日(日)新潟:NIIGATA LOTS
2025年4月13日(日)札幌:Zepp Sapporo
2025年4月20日(日)神奈川:横浜アリーナ
チケット情報はこちらから>>
関連リンク
下世話さみたいなものに対しての自分の中の答えが出た

――本当そうで、欲望が見えてきたというか、人間の生々しい部分っていうのがより見えるようになってきたと思うんです。Teleのライブって、もちろんエモーショナルだし盛り上がるんだけど、一方で今まではそれをちょっと傍観者として楽しむみたいな感覚があったんだけど、なんかもっとお互いにさらけ出せるものになってきたなあと。
喜多朗:下世話さみたいなものに対しての自分の中の答えが出たというか。俗っぽいものに対してそこでうまくやれる自信がなかったんです。俗っぽいものに取り込まれてしまうか、完全に水と油で跳ねつけてしまうかのどっちかなんじゃないかと思ってすごく遠ざけてたんですけど、そこに対する自分との距離感が見えてきたのもちょうどその時期だったのかなって。
――俗っぽいものに対する距離感?
喜多朗:そう。最近、いろんな人と話すことが増えて。その人たちから感化されているみたいなこともあるのかもしれないです。最近めっちゃ仲いい友達でいうと青松輝っていう、「ベテランち」っていう名前でYouTuberをやってるんですけど、YouTuberなんていうもの、この世で一番くだらんもんだと僕は思ってたんですよ。彼なんか東大の医学部行っていて、それでYouTuberやってるなんてアホだろって思ってたけど、彼がやってる短歌を見たら面白いなと思って仲良くなったんです。YouTuberって、冒頭何分かで興味を示さなきゃいけないとか、数字をどれだけ稼がなきゃいけないとか、他の人の企画を当たり前のように持ってきていいとか、俗っぽさの最たるところにいる人間なのに、短歌の部分では僕と響くような感じがあって、人間的にもすごく分かるところが多い人間だったんですよ。そんな人間が俗っぽさど真ん中のところでどうやってるんだろうみたいな話を聞いているうちに、これは清廉潔白だと思えるような場所よりも、自分に対して決めた所作がないと生き抜けない場所だなと思った。
――なるほど。毛嫌いしていたけど、そうじゃないかもしれないと思ったわけですね。
喜多朗:俗っぽさとの距離を作るには、俗な世間をまずちゃんと愛さなきゃいけないし、同時に卑下しなきゃいけないし、その上で向き合わなきゃいけないっていうところをやってるやつなんです。これは僕にはできないと思ってたけど、できるできないじゃなくて、どれだけその中に自分が頭や顔を突っ込んで鼻から吸い込んで自分の中に流し込むか。流し込んだ先で自分の性質が大幅に変わるとしても、体自身は僕のものだから1回やってみるかみたいな。あと一度、とある先輩ミュージシャンとお話しする機会があって。その時ちょうど、それこそタイアップとか僕には無理だなとか思っていたんです。何でかっていうと、僕は時間も守れないし、何かに対して臨機応変に心を動かせるか確証が持てなくて。でもその先輩はそこで当たり前のように戦っている人なんですよね。そういう人は僕とは全然違うタフさをもっていて、それこそアンドロイドと生身の人間ぐらい違うと思っていたんですけど、お話を聞くとこれは生身の人間が血を吐きながら耐えているんだっていうのがわかった。僕が「結局いっぱい考えていっぱい作るしかないんですよね」って聞いたらその先輩も「そうだよ。いっぱい考えていっぱい怒って、いっぱい作るしかないんだよ」って。それを「そうだよ」って言える人が表立って血を吐きながら戦ってるんだったら、僕がちょっとした切り傷みたいなのをビビって戦わないのは、これは卑怯だなと思ったんです。
――そのお二人なんて、それこそ喜多朗くんの言葉を借りれば俗世間にまみれながらものを作っているわけですからね。
喜多朗:しかも、ベテランちは完全にインディペンデントでやっていて、かたやその先輩は僕と同じように事務所とかレーベルがいるアーティストなんだけど、僕より遥かに上にいるっていう。どこかのひとつの軸は二人とも一緒なんだけど、どこかが少し横にずれてたり上にずれてたりするっていう。そういう人たちに対して僕は勝手に性質というか、質感は似てるなって思ったんです。彼らに武道館の直前に出会えたっていうのは、俗っぽさに対する向き合い方を決めるきっかけになったなと思います。

――たとえば「カルト」という曲は、ある種開き直りのように「カルトなんだよ、バーロー」みたいな感じだったじゃないですか。それはそれでひとつの態度なんだけど、武道館でのTeleはそれとは違うところにいる感じがしたんですよ。
喜多朗:俗っぽさの中で生きていくためには、愛に振り切って奉仕の人間になるか、世間というものを見くびって逆張りしてしたたかに生きるか、どっちかだと思うんです。優しく生きるか正しく生きるかの二択。でも僕は本当に中途半端な人間だから、たぶん性質としては俗っぽい世間を愛していたいし、「こんなもんだよ、世間なんて」なんて思いたくないんですけど、そこに振り切って潰れていって、消えていってしまった人たちもたくさん知っているし。そうではなくて、その自分の中でのちょうどいい間っていうものを、これからあっちに引っ張られて、こっちに引っ張られて決めていくんだなっていう。そのフィールドにようやく立てたというか。自分がカルト宗教の教祖みたいな感じである種のエコーチェンバーの中で「言いたいことだけ言うんです」っていうふうにしない。そうなるために、ひとつ必要なことができたのかなと思いますね、武道館は。
――そういうタイミングで今回、ドラマのタイアップっていうのも、巡り合わせとしてはすごく運命的なものがあるなと思います。
喜多朗:そうですね。本当にいろんな人から「そんなにうまくいかないよ、普通」って言われて。この「包帯」という曲、書き下ろしではないんですよ。
――2年前からあった曲だそうですね。
喜多朗:そう。本当に個人的な曲で。僕、前に鶯谷っていう町のわりと荒川区寄りのところに住んでいたんですけど、よく荒川を見に行っていて。荒川って、結構ホームレスがいっぱいいたり、あまり素行のよくない学生たちがいたりするんですけど、その感じが僕にはすごく落ち着く感じがしたんです。この曲はその荒川を見ながら書いてたんです。僕はよく家出をする人間だったんですけど、あるとき川原のススキの中を歩いて行ったら、歩いた先にホームレスの人が寝転がってて、それを踏んじゃって逃げて帰ったことがあるんです。川を見る度にそれを思い出して、そこから広げていって書いたというか、その川から連想する僕の記憶みたいなものを振り返りながら、本当に散文詩みたいに書いたんですよ。だからその曲が人の作品というか、ドラマと合わさるというのはすごくびっくりしました。
――結果すごく合っているし、奇跡的ですよね。
喜多朗:本当に「これは配信シングルにはできないよね」っていう話もあったんですよね。配信にする曲じゃないよねっていう。アルバムの中にひっそりといるような曲だと思ってた。それくらいすごい個人的な曲なんです。僕の友達に底抜けに明るい女の子がいるんですけど、その子、実家が葬儀屋で。今は公務員をやっているんですけど、市役所で生活保護の仕事をしていて。生活保護を受給している人の家に行って、受給資格をチェックするっていう。そうすると当たり前のように孤独死している人とかがいるそうなんです。歌詞の冒頭に〈君からする死の匂いは〉ってあるんですけど、その子はずっと生活に人の死がつきまとってて、なのに明るくて、僕にはそれが本当にずっと溢れそうなコップに水滴を落としているようで、「どうか頼む」っていう気持ちで見ているんです。最終的に僕はその子の根幹のしんどい部分の話は聞けなくて、それがそのさっき言った、荒川のところでホームレスの足を踏んで逃げて帰った自分と同じような感じがして……だからこの曲はずるい曲というか、最後まで踏み込めていない曲ではあるんですけど。

リリース情報
公演情報
【Tele Tour 2025】
2025年3月1日(土)香川:高松Festhalle
2025年3月7日(金)広島:BLUE LIVE HIROSHIMA
2025年3月15日(土)宮城:SENDAI GIGS
2025年3月21日(金)、22日(土)大阪:Zepp Osaka Bayside
2025年3月28日(金)、29日(土)福岡:Zepp Fukuoka
2025年4月2日(水)、3日(木)名古屋:Zepp Nagoya
2025年4月6日(日)新潟:NIIGATA LOTS
2025年4月13日(日)札幌:Zepp Sapporo
2025年4月20日(日)神奈川:横浜アリーナ
チケット情報はこちらから>>
関連リンク
僕がTeleを続けることで、
川の底に行ってしまった人たちにみんなの目が向けば

――踏み込めない自分を書いた曲という意味では、さっき話してくれた心境の変化みたいなものに至る以前の、少し過去の谷口喜多朗がここにはいる感じがして、それがおもしろいんですよ。
喜多朗:確かに。この曲、1番のサビが終わるまで書いて、僕からすると、その友達の女の子のことを脱がしてるみたいな感じになっちゃったんですよ。それは卑怯かもしれないと思って、2番で自分の服を脱がしたみたいな感じで小さい自分のことを書いたんですけど。だから最初この曲がもしかしたら『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ!』に合うかもってなったときも、僕も『ベイビーわるきゅーれ』の映画は好きで観ていたので、人間の死に対する向き合い方が全然違うよなとは思っていたんです。あの作品はなるべく死っていうものを重く受け止めない感じに描いていると思うんですけど、僕の場合はこの死っていうものをずっと眺めて、それをコンテンツにする勇気もなくて、なのに曲にはしてるみたいな。僕には『ベイビーわるきゅーれ』の方が潔く思えたから、この曲でいいのかなって。でもこの曲はずるい曲というか卑怯な人間の曲なんで、潔い人の作品にくっつけて「公開処刑」に遭うべきだと思って。卑怯な曲だってバレた方がいい。
――というか、逆にいうと『ベイビーわるきゅーれ』という作品と巡り合ったことで、この曲を世に問う意味が出てきたということですよね。
喜多朗:そうですね。一個の作品の奥行きに寄与できればいいなと思って。まあ、今はしっかり役立てればいいなって思いますけど。
――とはいえ、『ベイビーわるきゅーれ』は映画のときから好きだったわけですよね。ということは何かしら自分に通じるものを感じていたのかもしれないし。
喜多朗:確かに俺は結構勝手な親近感を持っていて。それこそ一作目の舞台は鶯谷で、二作と出てくる場所とか「ああ、知ってる知ってる」って思うし、あと阪元裕吾監督がこの間サマソニ(SUMMER SONIC)のライブを観に来てくれたんですけど、会った時に「あれ? この人同じ匂いがするぞ」って思ったんです。すごく作品を大事にしてるけど、別にこの作品がどうなってもいいとも思っている感じというか。勝手にこんなこと言っちゃいけないけど、『ベイビーわるきゅーれ』という作品に対する愛ゆえに、この作品がどこへ行ったって、俺らは成立させるぜ、だからどうなったっていいんだっていう。作り手に自信があるがゆえの退廃的な思想というのがある気がしたんです。僕もTeleに対して、いろんな人に聴いてほしいしいろんな人の音楽になってほしいし、大きいところでやりたいっていう目標はあって、そのために必要なもの全部やるぞって思うんですけど、同時にどこかで「どうなったっていい」っていうのを同じくらい思ってるんです。そういうところに親近感を覚えてたので、その作品で自分にとって初めてエンディングをやるっていうのは、結構ラッキーではありますね。
――今の話って、それこそさっき話してくれた「俗世間との距離」みたいなことに近いと思うんですよ。どこまでいっても逃れられないんだから、そこでやるしかないんだよ、みたいな。
喜多朗:うん。


――たとえば喜多朗くんが家出をして河川敷に行くというのも、人間関係とか社会から解脱したいと思っていたんだと思うんです。でもそこにもホームレスがいて、それを踏んづけちゃうわけじゃん。「あ、逃げられないんだな」っていう。
喜多朗:で、慌てて帰る(笑)。本当にそれが結構僕の全てを表していて、結局川の底にはいけないんです。
――そうそう、「そこ渡れないんだ」っていう感じ。
喜多朗:でもTeleっていうものを続けていくモチベーションには、川の底に沈んじゃったものを忘れないでいたいっていうのがあって。もう辞めてしまったバンドとかっていうものが本当にゴロゴロいて、そういうのを僕は忘れないでいたいって思うし、アンダーグラウンドに居続けてしまう人たち、そこに居続けることは悪いことじゃないんだけど、僕はやっぱりそういう人たちを評価してほしいって思う。僕がTeleを続けることで、川の底に行ってしまった人たちにみんなの目が向けばいいなと思うし、それは社会に対してもすごく思う。社会的弱者の人たちに対して救いを差し伸べる時って、同じになって沈んでいくか、ものすごく遠くから見て「そこは暗いから近づかない方がいいよ」って言うか、どっちかしかないんです。本当はもっとフラットに川の底に対してアクセスして見に行った方がいいのに。それは寂しいので、Teleを続けていって、そこに対する答えが出たらいいなと思います。
――それこそまさに「包帯」って曲だと思うんです。この曲には強烈に死の匂いがあるけど、同時に〈未来は、生き延びた灰の溜り場じゃないんだ。〉と怒ってもいる。じゃあどうするんだ、っていうのはこれからなのかなという気がする。
喜多朗:まだたぶん、次のアルバムとか今書いている曲には「答えが出ないぞ」っていう曲しかない。それこそ、いっぱい考えていっぱい怒っていっぱい作ればその答えが出るのかなと思うと、続けていくしかないなって思いますね。
▲「包帯」MV
――今はアルバムを作っているところ?
喜多朗:今はアルバムのコンセプトがまとまってきているところで、それに来年のツアーも引っ張られていくのかなっていう感じがありますね。今までいっぱい曲を出してきたがゆえに、アルバムが配信曲まとめみたいになっちゃいそうなので、それに対してどう答えを出すかみたいな感じで、今作ってるって感じです。
――ツアーも、さらにスケールアップして横浜アリーナをやります。
喜多朗:本当にね、みんな好きなんだと思います。俺が切羽詰まってるのを見るのが(笑)。でも自分の身を削って自分の過去を削いでやるみたいなのは、前回のツアーでいったんおしまいだったと思っているので、今度は自分が感じていること、考えていることっていう「今」をちゃんと削いできたらいいなと思っています。

リリース情報
公演情報
【Tele Tour 2025】
2025年3月1日(土)香川:高松Festhalle
2025年3月7日(金)広島:BLUE LIVE HIROSHIMA
2025年3月15日(土)宮城:SENDAI GIGS
2025年3月21日(金)、22日(土)大阪:Zepp Osaka Bayside
2025年3月28日(金)、29日(土)福岡:Zepp Fukuoka
2025年4月2日(水)、3日(木)名古屋:Zepp Nagoya
2025年4月6日(日)新潟:NIIGATA LOTS
2025年4月13日(日)札幌:Zepp Sapporo
2025年4月20日(日)神奈川:横浜アリーナ
チケット情報はこちらから>>