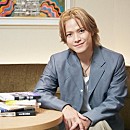Special
<わたしたちと音楽 Vol.41>児玉雨子 アイドルやアニメのために綴る言葉に込める思い

米ビルボードが、2007年から主催する【ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック(WIM)】。音楽業界に多大に貢献し、その活動を通じて女性たちをエンパワーメントしたアーティストを毎年<ウーマン・オブ・ザ・イヤー>として表彰してきた。Billboard JAPANでは、2022年より、独自の観点から“音楽業界における女性”をフィーチャーした企画を発足し、その一環として女性たちにフォーカスしたインタビュー連載『わたしたちと音楽』を展開している。
今回のゲストは、作詞家であり小説家の児玉雨子。これまでにアンジュルムを始めとしたハロー!プロジェクトの楽曲からアニメ・ゲーム関連まで数多くの作品を手がけ、文芸誌などでもその筆を評価されてきた。10代の頃からエンタテイメント業界で言葉を紡いできた彼女が、今大切にしていることとは。(Interview:Rio Hirai[SOW SWEET PUBLISHING] l Photo:Megumi Omori)
話すよりも書くことのほうが、
言葉に打算が混じらない

――高校2年生のときに、集英社の【すばる文学賞】に応募して、2011年には情報番組『コピンクス!』の主題歌「カリーナノッテ」の作詞を担当したのが作詞家としてのキャリアのスタートだそうですが、言葉を使ったお仕事を意識したのはいつ頃からなのですか。
児玉雨子:本当は、絵を描くのが好きで漫画家になりたかったんです。漫画を描くためにプロットを書いていたら小説のようになって、それをそのまま賞に出してみた感じですね。それまでも文芸は好きだったけれど、音楽も美術も漫画も並列で同じくらい好きでした。作詞の仕事の依頼をいただくようになってからは、「なんか私、作詞の仕事だけは来るな」と思いながらも続けていました。
――言葉を書くことは、それまでも自然にやってきたのでしょうか。
児玉:そうですね。学生のときもグループ行動が苦手で、みんなとは知り合いだけど、下校した後も電話をするような距離感の友達もいなかったし、おしゃべりするよりもガラケーに思ったことを打ち込んでいることのほうが多かった。自分にとって話すのは後天的に身につけた手段という感じがして、書くことのほうがより打算なく自然に言葉が出てきている気がします。それでもそのまま作詞家になるなんて、思ってもいなかったですけど。
――それからもお仕事を続けて今に至ると思うのですが、アイドルと同世代の作詞家というのも、当初は珍しかったのではないでしょうか。
児玉:自分では、歌詞を提供し始めた当時から同世代という意識はあまりありませんでした。アイドルって、レッスン期間中の小学生の子たちもいたりするし、16歳の子からしたら21歳でもすごく大人に感じるじゃないですか。ティーンのときって1歳差でもそのギャップはすごく大きいと思うんです。だから、自分が「同世代の作詞家」「若い作詞家」と言われてもあまりピンと来ていなかったですし、むしろ同世代の気持ちでいちゃいけない、自分は“汚ねぇ大人側”だと思っていました。
大人側として、歌詞を書く相手に
“書きつけない”ようにしたい

――そうだったのですね。ハラスメントは、年齢や立場などギャップがある間に生まれやすいと思うのですが、当時からそのご自身の権威性を意識していらっしゃったんですね。自分が書いた言葉が他人の口から発せられる作詞という行為は、とてもデリケートなものでもあると思うのですが、児玉さんは作詞をする際にはどんなことに気をつけていらっしゃいますか。
児玉:さすがに権威性とまでは思っておらず、「私はオタク的感性が強いから」という引け目のようなものでしたね。あまり20代の頃は強く意識してはいなかったのですが、女性から女性のセクシャルハラスメントもきっとあるじゃないですか。それに、自分はそうは思っていなかったとはいえ、昔は“同世代の女性”が書いていることで評価をされたりもしました。特に今、作詞でご一緒しているアイドルの子たちはもう明確に違う世代の人間なんですよ。セクハラまでいかなくとも、大人側の人間として“書きつけちゃう”ことはあると思っていて。だからこそ、恋愛にまつわる歌詞を書くのは今すごく難しいですね、手探りです。あとは、差別的に受け取られやすいだろう表現にはここ数年はより気をつけているかもです。それ以外は、昔よりもさらに自分の書きたいことを自由に書くようになった。以前より気にする領域が変わったのを感じています。
――それはご自身の経験が積み重なって? それとも社会が変わったからということなのでしょうか?
児玉:両方ですね。
――児玉さんの書く歌詞には、“強い女”や“若い女”といった外圧的なカテゴライズから“ウチら”を取り戻す、という意思を感じますが、どうしてそういう考えに辿りついたのでしょうか。
児玉:まぁ単純に、なんでもかんでもそういう表現で片付けられることに違和感を抱くようになった、という感じですね。K-POPのガールクラッシュを「流行ってるから」とモノマネしてかえって女性を侮辱するくらいなら、しないほうが良いんじゃないかなぁと思っているし。あとは、自分が書けるのはもっと小さな語りだったり、社会的なことは大事だとは思うけど、本当に好きなモチーフは建造物やつやつやの石や宇宙にまつわることだったりして……とか言って、逆張りしたいだけなのかもしれないですけどね。
――ご自身のパーソナルなモードとしては、どういう状態なんでしょう?
児玉:まず、強い女っていうものがよくわかっていないですよね。何を持って強いというのか……。今の私は「とりあえず、書きたいことを書く」って感じです。
幼い頃に何気なく聴いていた曲が、
時を経て心の奥に届くこともある

――児玉さんが書くもの、例えばアイドルやアニメの楽曲は、こういうインタビュー記事よりも幅広く多くの人に届くと思うんです。「この文章を読もう」と思わずとも、日常の中で耳に入ってくる言葉だったりするじゃないですか。そういう特性のある“歌詞”を通して、伝えられることに期待はしていますか?
児玉:初めて歌詞が耳に届いたそのときに心が揺れてくれたらいいなという気持ちはもちろんあるけれど、今聴いてくれている小学生の子が、高校生や大学生になって、ふと「あの曲、実は良い曲だったな」って思い出してくれればいいとも思います。自分自身、子供の頃に単に耳当たりが良いから聴いていたとか、みんなが聴いてるから聴いていたという曲を、大人になってから聴き直して、噛み締めた経験が幾度もあるんですよね。今現在の救済にはなっていなくても、いつか誰かの好きな歌になればいい。もちろん、自分が発信したものが今すぐ世の中に広くリーチしてほしいって気持ちもあるんですけど、5年後くらいに急に火がつくこともあるのも知っている。おかげさまでそれを知ることができるくらい仕事を続けられてきたから、もう少し世の中を信用しようという気持ちになりました。
――作詞家としてのデビューが早かった児玉さんは、“若手女性作詞家”や“美人作詞家”と冠をつけて語られることも多かったかと思うのですが、そのことについてはどう感じていましたか。
児玉:今はもうそれらに怒るというわけではなく、わきまえて黙るでもなく、「はいはい、また出た」と思ってますね。言われるたびに「まだ、それ言ってるんですか。いつの時代ですか?」と釘を指すように意識はしてきましたが。最近はもうそんなこと言うひとも、めずらしい気がします。
業界の“ネガティヴマッチョ”精神への
オリジナルな反抗方法

――このインタビューを続けてきて、女性がエンタテイメント業界で長く活躍するためには、女性自身の問題だけではなく、社会の眼差しや構造も含めて乗り越えなくてはいけない年齢の壁があるのを感じました。経験を重ねることよりも若さが重要視される価値基準や、妊娠・出産を含む体調の変化に対応しづらい労働環境が関係していると思うのですが、児玉さんは、女性がエンタテイメント業界で活躍しやすくなるにはどんなことが必要だと思いますか。
児玉:いろいろなことをやるのは意識していますね。業界ってひと言で括れないくらい細分化しているじゃないですか。私がやっているものはポップカルチャー的なジャンルが多いけれど、たとえばアイドルだけじゃなく、アニソン、VTuberのお話も積極的に取り組んでいて、ポップカルチャーの中でどんどん越境しています。「ひとつの場所にとどまらない」という姿を見せることは、この業界を働きやすい環境にする一つになる気がするから。あとはスケジュールもかなり気をつけていて、急すぎるものは受けない。若くてやる気がある人を使い潰しているのは、社会全体の問題ですよね。
――高度成長期の“寝ずに頑張る”の精神が、エンタテイメントの業界ではまだ受け継がれているような印象もあります。
児玉:学生の時に「女が何かものを書いたり作ったりしていて、幸せなんて望めるわけない」って言われたりもしました。未だにそういう考えを引きずっている側面があるのを感じますね。いかに自分の心身をセルフネグレクトしたかを自慢するものを、私は“ネガティヴマッチョ”って呼んでいます。当時はそれに対抗する語彙を持っていなかったけど、もし私が体を壊したとして、無茶頼んできた人たちが身代わりになってくれるわけじゃない。無理なスケジュールには「ごめんなさい、できません」とお断りして、ジムと睡眠の時間はかなり確保しています。
プロフィール
作詞家、作家。アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリーなどハロー!プロジェクト関係を筆頭とするアイドルや、声優、テレビアニメ主題歌やキャラクターソングを中心に、VTuberから近田春夫まで幅広く歌詞を提供。小説やエッセイ執筆も行う。著書に『誰にも奪われたくない/凸撃』(河出書房新社)、『##NAME##』(河出書房新社)、『江戸POP道中文字栗毛』(集英社)がある。