Special
Tele「鯨の子」インタビュー 「生まれたときから最悪だから、あとは上がるだけ」

昨年11月に初のワンマンライブ【東京宣言】を成功させ、そこから次のフェーズへと突入していった谷口喜多朗によるソロプロジェクト・Tele。彼から届いた2023年最初の新曲「鯨の子」は、これまでとは一味違うシンプルなサウンドと、友達に語りかけるような歌詞のニュアンスが印象的な1曲だ。ワンマンライブで自分の音楽を求める人と面と向かったことが、表現者としての彼に与えた影響とはどんなものだったのか。そしてその実感は、歌詞やサウンドにどのように反映されていったのか。彼自身が今抱いている意思がはっきりと語られた今回のインタビューからは、Teleがこれからますます時代にとって、世代にとって、重要なアーティストになっていく予感がする。(Interview & Text:小川智宏)
自身初のワンマンで感じた「生々しい実感」
――前回のワンマンライブ【東京宣言】から数か月が経ちましたが、あのライブを経たことで考え方や意識の面で変化は感じますか?
Tele:ワンマンで自分だけを観に来る人が目に入ったというか、どういう人が観に来るのかがわかって。それがいい意味でも悪い意味でも何か変な欲みたいなものをかき立てちゃっていたのかな。
――変な欲?
Tele:考えていること自体はあまり変わっていないんです。いい曲を書いて、MVとかアートワークも含めて、周りの協力を得ながら自分が納得するものを作って、それをライブに向けて仕上げていくことは変わらないんですけど、向かう先がわかっちゃったぶん、「そういう人たちはどう思うかな」みたいな変な欲求が出てきちゃったんです。でも、僕が元から、人間関係でも親しくなるとうまくいかないタイプだから(笑)、それはやめたほうがいいなって最近は思っています。それは全然観に来てくれた人のせいではなくて、僕の性質なんですけど。自分の中で変な打算みたいなものが生まれちゃっていたということがここ2か月くらいあって、そういうのと折り合いをつけていってたみたいな感じですね。
――要するに、自分の音楽を受け取ってくれる人が、たとえばライブのお客さんという形ですごく具体的に見えたわけですよね。「この人たちに届けるんだ」というのがわかった。
Tele:それはすごく嬉しかったんですよ。でもリリースを始めてからそこまではあまり実感のないまま過ごしてきた感じもあったので、ワンマンで本当に自分だけ観に来てくれてる人たちを目の当たりにして、ちょっと生々しい実感みたいなものが生まれてきたんですよね。だから自分の中でうやむやにしていた部分を見なきゃいけなかったし、はっきり見た上で「じゃあどうしようか」って。それは……僕がそんなにお金持っている家ではなかったというのもあって、やっぱりアーティストのライブのチケットは高いなって思うことが多かったし、本当に高校生のときはお昼ご飯を食べないでお金を貯めてCDやチケットを買ったりということもあったから、このお金を出してもらってるぶん、ちゃんとやらなきゃいけないなっていうのと、「でもそれにしてもやっぱり高くないか?」ということとか。でもそれをやっぱりちゃんと背負ってやっていかなきゃいけないし、その自信はつけていってるし、ちゃんと舵を切ってやらなきゃいけないんだろうなってことを思いましたね。
――でもそこでジレンマを感じているのはある意味で誠実なことですよね。そこから降りるつもりはないよって前提があるからこそ、そう感じるんだと思うから。
Tele:そうですね、もちろん。ここまで話したのは、そのお金に値するほどのパフォーマンスをしたくないって意味ではなくて、するのは当たり前にやらなきゃいけなくて、そのために向き合っていくのがアーティストをやる上で当たり前なんだけど、「だけどそれにしても高くないか?」っていう(笑)。ちゃんとお金をもらわないといけないのはしょうがないことだと思うんですけど。なんか5、6年前とかにイギリスとかでも同じような感じになったじゃないですか。音楽大学とかを出ている、中流階級以上の人じゃないとロックンロールの世界に参入できなくなっちゃったっていう。僕はギターを買って音楽を始めたし、ロックってジャンルがポップスも含めて好きなんですけど、仮に今僕が14歳だったらやるかなって思ったらたぶんやらない気がするんです。楽器だってどんどん高くなってるし。それってどうなんだろうって。チケットも高くなってて、楽器もスタジオ代も高くなってて……それでも始める人は始めるんだろうけど、たぶん、今はヒップホップがそういう人の受け皿になっているんだろうなって。あんまり関係ない話になりましたね(笑)。
――それをどうにかしていきたい。
Tele:うん。だから、去年までのアレンジとかで反省したのは、結構自分が複雑なアレンジが好きだし、ストリングスとかも含めて好きなので結構いろいろとやっていたんですよ。でもこの曲を聴いて真似しようって思ってもできるかな、みたいな。真似してもらうことが主目的じゃないし、その責任を僕が担うかっていうと、まだまだそんな段階じゃないし、自分がまずどうやって人に聴いてもらえるかっていうことが大事なんだけど、飽和していくアレンジみたいなものに対して「これを聴いて俺もやろうって思えるか?」って。それは結構大事な部分な気がしていて、新曲を作る上でもすごく考えていました。
音楽には“祈り”があってほしい
――じゃあ「鯨の子」もそういう中でできてきた曲なんですか?
Tele:そうですね。これは歌詞の部分で平坦な言葉を使おうっていうのがまずあって。それまで僕は何も意識せずに、自分の好きな言葉とかきれいだなと思う言葉を使っていたんですけど、結局それって読んできた本の量とか、生まれ持った環境と経験に依存するものだから。僕が実体験に基づいた生々しいラブソングがあんまり好きじゃないのは「結局これって経験値のゲームじゃない?」って思っちゃうからなんです。人生経験を作品に昇華することは素敵なことなんだけど、あまりにも経験値バトルすぎるというか。そんなに悲惨な恋愛の経験をしていないと曲って書いちゃいけないの?みたいな。それと難しい言葉を使う自分のやり方というのは、実は骨組みとしては同じなんじゃないかと思ったんです。それで平坦な言葉で歌詞を書けるようにしようと思って書いた部分はあります。それによって聴いたときにとっつきやすくなって、さっき言った「音楽始められるな」って部分に繋がったらいいなって。
――「鯨の子」は確かに、今「平坦」と言っていましたけど、音にも言葉にも余白がすごくある感じがしますよね。サウンド的にもループが基調になっていてシンプルだし、そこに今言ったようにすごくわかりやすい、語りかけるような言葉で歌詞を書いて歌っている。その意識はすごくビビッドに出ていますよね。
Tele:そうですね。でもその意識だけに持っていっちゃいけないし、あまりにも自分が大義を背負った気になるのはよくない。なんか、自分にとっては大義というより祈りなんですよ。世の中の音楽がそうあってほしいっていう。もちろんいろんなアーティストが野心とか決意とかをもって作っているけど、どこかにそういった祈りみたいなものが含まれてほしいというか。だけどそれを含ませながら作るのって結構難しくて、全然できないじゃんみたいなことも考えながら、でもやらなきゃダメだよねって。
――たとえば「ロックスター」という曲はそれこそ祈りというものをストレートに注ぎ込んだ曲だったと思うんです。そういう意味ではあの曲を書いた気持ちと、この「鯨の子」を作ったときの気持ちは繋がっているものではありますよね。
Tele:そうですね。同じ人間なんで、そう簡単には変われないから。だから根本の部分は同じなんですけど、「鯨の子」に関しては音もそうだし言葉もそうだし、1個1個丁寧に置いていったみたいな感覚がありました。リズムはアレンジを作る段階では完全にループで作っていて、レコーディングのときにドラマーに再レコーディングしてもらったんですけど、そのドラマーが椿三期って僕の友達で、ちゃんとしたレコーディングスタジオで叩くのは初めてでめちゃくちゃ緊張してたんですよ。僕がどうしてもそいつとやりたいって言って連れてきたので、エンジニアさんとかにはちょっと迷惑かけちゃったんですけど(笑)。でも緊張してる人間って過剰に1音1音を丁寧に演奏するんですよ。その感じがドラムの音に出ていたのがよくて。
――逆に言うと、彼に叩いてほしいと思ったのはそういうニュアンスが欲しかったから?
Tele:そうです。もともと彼がやっているバンドのファンでやってみたいなと思っていたんです。でもライブも一緒にやっていただいてるドラマーの森(瑞希)さんが本当に素晴らしいドラマーで、僕が作る曲をすごく理解してくれるので、この人にお願いしない理由がなくて、なかなかタイミングがなかったんですよね。でもこの曲だったら面白くなるかもしれないって思って。結果的に、かなりいいドラムの音になったなと思います。
――その半分ビビリながら叩いている、でもそれを超えていくようなパッションもあるみたいな感じって、この曲で描かれている風景そのものですよね。それも含めてこの曲の世界観というか、イメージが喜多朗くんの中にはあったわけですね。
Tele:それがどこまで有効打になったかはわからないけど、そもそも前提として本当にセンスのあるドラマーだし、その緊張感みたいなものってまだ歴の浅い人間にしか出せない唯一の強みだと思うから、それがこの曲を下から支えてる感じはあります。
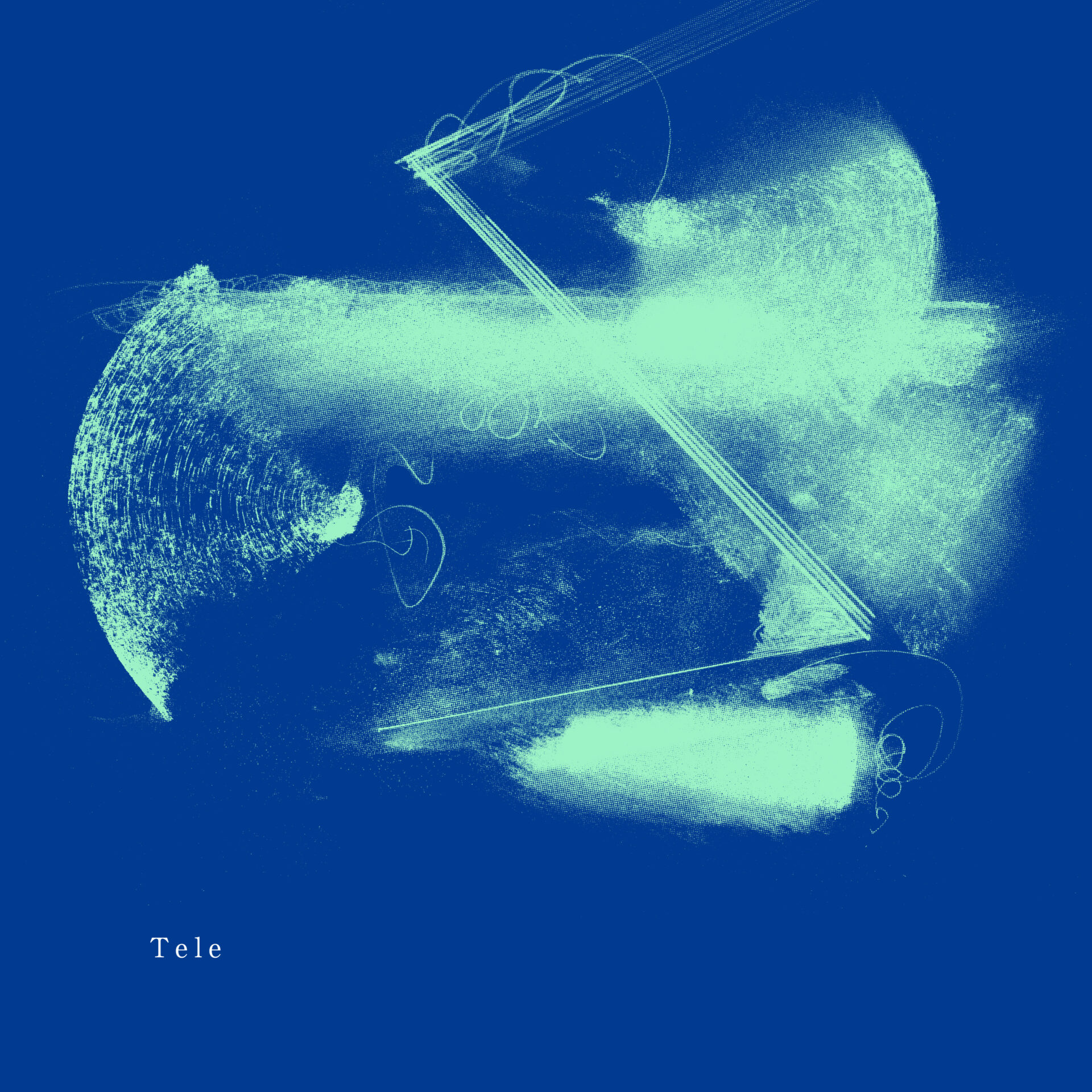
――単純に同世代であるってことも大きかったのかな。
Tele:うん、同世代のミュージシャンがどういう感覚で僕の曲を叩こうと思ってくれるか。これまでは年齢が一回り上くらいの方とレコーディングしてきてたから、かなり広いレンジで僕の曲を捉えてくれたし、そうすることによって僕の曲がちゃんと仕上がってきたというのもあるんですけど、狭いレンジで僕の曲を捉えたときにどういう捉え方をするんだろうなって好奇心があって。そしたら当日、なんかよくわからない金物類みたいなのをガチャガチャ持ってきて、「これも叩いたら面白いと思うんだ」とか言い出して(笑)。「面白いけど使わないな、これは」とか言って。そういうのも含めて「もっとこうしてほしい、ああしてほしい」みたいな微調整は今までのレコーディングよりもあったんですけど、自分がレコーディングのときにもっと意識したほうがいいこともわかったし、なるほど、そう叩きたいのねみたいな発見もあったし。面白かったですね。
――僕はこの曲はメッセージソングだなって思ったんですよ。世代論なんてバカバカしいかもしれないけど、今、喜多朗くんの世代が見ている世界とか、ものの見方とか感じ方とか、そういうのがすごく感じられたんです。そういう意識はなかった?
Tele:そんな意識はあんまりなかったかもしれないです。自分はわりと世代の中でアウト・オブ・カーストだと思っているし、世代の外に出されちゃった人間だとずっと思っていたから、「今の世代を表現してやろう」みたいな気持ちはそもそも僕にはないんです。でも僕の友達に対して書いた曲だからというのはあるのかもしれないです。結果的に、友達との間の狭い話を平坦な言葉で書くことによって抽象的にしたから、そうすることによっていわゆる世代論的な話に繋がっていくことになるのかもしれない。
――うん。だから世代というとちょっと大げさかもしれないけど、〈透明な僕らだけの暗号で話そう〉と書いているように、仲間同士の共通の感覚や認識、共通の世界観を持った人たちに対して歌っている感覚っていうのはこれまでの曲と比べても強いんじゃないかなって。
Tele:それは言われて気づいたかもしれません。〈透明な僕らだけの暗号で話そう〉っていうのはちょっと気取った歌詞だなって思うけど(笑)、昔はモールス信号とか、言ったらギャル文字とかもそうじゃないですか。いわゆる世代における暗号的なもの。それって今の時代にはないなと思って。それって、そもそもみんなが本音で話さなくなったから暗号が必要なくなったのか、ちゃんと隠して送れるようになったからなのか、それはちょっと僕にはわからないけど。だけど、暗号に近い何かってやっぱり友達の中で生まれるじゃないですか。目配せなのかもしれないし、共通のノリなのかもしれないし、「あれ」で伝わる感じっていうか。すごく根本的な話なんだけど、そういうものを大事にしようぜっていう。
お前はタフだけど、そのタフさで何でもできると思うなよ
――このあいだ喜多朗くんと同世代のあるミュージシャンと話していてすごく面白いなと思ったことがあったんです。今の世の中ってどんどん悪くなっていってるよねっていう言説があるじゃないですか。今の若い世代はそういう時代に生まれて不幸だ、的な。
Tele:はい。
――でもその人は「そんなの関係ないっすよね」って言っていて。生まれたときからそうだし、悪くはなってると思うけどこれ以上悪くなることなんてないと思うし、そういう状況でいろいろ言われてもそれはそれとして俺らは勝手にやっていけばいいと思いますよ、って。
Tele:びっくりした。それ、この間皿洗いしながら同じことを考えていたんです。今の30代の方とかって、日本が傾いていくときを見てきた世代じゃないですか。そうすると、世の中どんどん悪くなっていく、これから先は悪くなっていくんだみたいな考え方になるんですよ。けど僕たちにとっての悪いシチュエーションって生まれたときからだし、たぶんそろそろ底につくからあとは上がるだけっていう、希望がちょっとだけ見えているバッドなシチュエーションな気がするんですよ。この最悪なシチュエーションが沸騰直前の水みたいな、何が起こるかわからない感覚があって、そういう意味でいうと一回り上の世代の人たちの最悪と僕たちの中の最悪っていうのはちょっとだけニュアンスや意味合いが違うのかなって。だから本当に僕もそう思います。悪くなってるよねって言われてもピンとこないと思います。
――「鯨の子」を聴いていてそれを感じたんですよ。〈「こういうものだ!」〉って言ってるし、いろいろあるけどそれはそれとしてやっていくんですよ、僕らは僕らで生きていきますよっていう宣言のように聞こえてきて、面白いなと。
Tele:確かにそうなのかもしれない。ある意味諦めに取られちゃうのかもしれないけど、でもそのあと前に進めるんだったら理由は何だっていいじゃないですか。大義みたいなものにこだわらなくっていいよねって気持ちはあるのかもしれない。世の中がどうとかっていうのは考え続けるんですけど。そもそもそんなこととは関係なく生きていかなきゃいけないって気持ちはありますね、この曲には。ミクロで見るとただの酔っ払いの歌だけど、マクロで引いてみると、そういう意味になるのかな。
――でも〈君のタフさに全てを委ねないで。〉って始まるところは演説みたいな熱を感じます。
Tele:確かにそうですね。ここは何か本当に言葉通りのことを考えていたんです。結構しんどい状況だけど、僕なら大丈夫だから、私なら大丈夫だからみたいな感覚の人っているじゃないですか。友達で家庭のことですごく揉めている人がいて、その人の話を聞いていたときに、僕はその人にムカついちゃって。「お前はタフだけど、そのタフさで何でもできると思うなよ」みたいな。曲を作っていく中でその感じがすごく生まれて、無理やりこの部分をねじ込んだんですよね。だから後ろのトラックも含めてここの部分ってすごく暴力的な快感になってるなと思うんですけど、無理やり入れてよかったなっていうか、この部分があることによって曲全体の意味合いも変わってくるし。この部分は本当にムカつきながら書いてた。僕らは結局タフじゃなきゃいけないし、それが前提になっている歌詞ではあるんですけど、そこまで過信しなくていいんじゃないか、君のタフさを、っていう。
――だからここにはすごく感情が溢れているんですよね。それがあることで血が通った気がするし、これに救われる気持ちになる人もきっといると思う。
Tele:説教くさくならなかったかなって心配もあるんですけど(笑)。
――いや、だって説教じゃないですか、これは。
Tele:うん。怒ってたからしょうがない。たまに「休みがしんどい」って言う人いるじゃないですか。休んじゃったらもう無理だから、みたいな。僕はちょっとあんまり全然共感できないんですけど、もうちょっと肩の力を抜いた方がいいぜって。そして、楽しむことをサボらない方がいいよって。この曲だって朝まで踊ってるんですよ。しんどいですよ、朝まで踊るのは。どうせしんどい毎日を過ごしてるんだったら、たまに1日ぐらいはそういうしんどさでもいいんじゃないのっていう気持ち。どうせしんどいんだから。そういう歌ではあります。
――それこそTeleの音楽の1個の存在理由なのかもしれない。
Tele:そうなっていったらいいですね。それがちゃんと意味になっていけばいいなって思います。なるだろうなとも思うし。僕の考えることは、偏屈な人間なんで変わらないから。
――そういう意味でも【東京宣言】のワンマンまでのTeleからさらに一歩進んだところでこの曲は生まれていると思うし、そう受け取られていくと思うし。今度のワンマンライブ【nai ma ze】にも繋がっていくんだろうなというふうに思います。
Tele:はい。大阪は初めてライブしたBIG CATってライブハウスだし、東京は前回の倍のキャパシティの会場なので、何かそれぞれの会場が持っている意味というのがライブを通して混ざっていって1つになってくれればいいなって思っています。大事にしていきたい場所である大阪と挑戦していく対象であるO-EASTがちゃんと同列の意味を持つライブに成り立っていけばいいなって思いますし。何より来てくれた人が楽しんでくれるようなライブになればいいなと思っています。



























