Special
<インタビュー>伊根に聞く、ボカロPとしての自分、Adoをはじめとするアーティストらへの楽曲提供、そして“ボカロ文化の魅力”
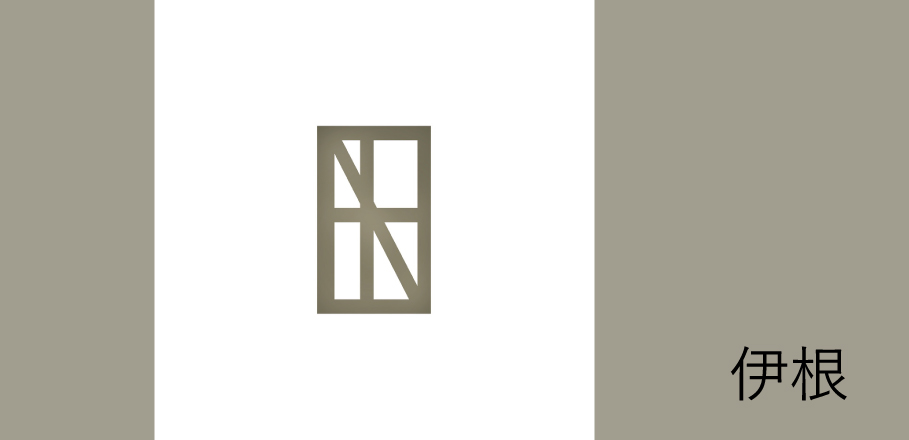
Interview:天野史彬
Text:Maiko Murata
ボーカロイド、いわゆる“ボカロ”楽曲や同シーン出身のアーティストが、各種チャートを席巻するようになって久しい。Billboard JAPANチャートにおいても、総合ソング・チャート“HOT 100”をはじめ、毎週各チャート上位にボカロP出身アーティストや歌い手出身アーティストが数々登場している。
そんな中Billboard JAPANにて、動画配信サービス『ニコニコ』上におけるボーカロイド曲(※)の人気を測る新チャート”ニコニコ VOCALOID SONGS TOP20”が12月7日よりスタートした。なぜ今「ボカロシーン」が熱いのか――それを探るインタビューとして、2022年には1stアルバム『Direct-View AR』をリリースしたほか、AdoやKing & Princeらへの楽曲提供もおこなうボカロP・伊根に、自身の音楽歴や楽曲への向き合い方を通して、彼が観て触れてきた“ボカロ文化”とその魅力について聞いた。
「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。
今のボカロを取り巻く状況から感じること
――まず伊根さんは、ボカロやボカロを出自に持つアーティストたちがオーバーグラウンドのJ-POPシーンでも活躍されている状況を見て、どのように感じますか?
伊根:僕自身、聴き手としては垣根なくいろんな音楽に触れてきたなと思っていて。同じプレイリストの中にメジャーなJ-POPもあれば、自分の好きなボカロ曲もあれば、バンドの曲もあれば、中学校で歌った合唱曲なんかも入っている(笑)。そのくらい混在しているので、今の状況はむしろ自然な感じがしますね。ボカロ生まれとか、J-POP生まれとか、出生にはとらわれずに「面白いものが面白い」という評価をされる流れになっていると思うんです。そういうところは嬉しくもあり、ただ、少なからず恐ろしくもあるというか。
――恐ろしさもありますか。
伊根:作り手の人はわかると思うんですけど、評価される可能性があるということは、評価されない事実が強調されることでもあって。ボカロって、趣味で作っている人もいるし、「好きだから」という自分なりの動機や探求心をただただ愚直に掘り進めている人もいる文化なんです。“評価”という尺度が強調されることによって、いろんな影響があるだろうなとは思います。人によっては悩んだりすることもあるかなって。ボカロ文化って、オープンじゃないからこその良さを含むと思うんです。自分の家の裏庭とか、みんなの砂場みたいな場所で、純粋に“作る楽しみ”を受け入れてくれる側面が昔のボカロ文化は強くあったし、僕個人としては、そこを忘れないようにしたいなと思います。僕も評価のためだけでは作れないタイプなので、バランスを取りたいな、と思っています。
音楽、ボカロを始めた経緯
――伊根さんはどのような経緯で音楽を始められたのでしょうか?
伊根:中学生の頃に親にギターを買ってもらったのが、始まりと言えば始まりですね。基本的にはずっとひとりで、独学で遊んでいた感じでした。ギターと作曲関連の機材を揃えて、趣味でそれをいじっている感じで。一度バンドを組んだこともあったんですけど、それは、ちゃんとした活動には繋がらなくて。
――ボーカロイドを使い始めたのは、どういったきっかけがあったんですか?
伊根:まだここまでメジャーな文化ではなかったですけど、聴く側としては小学生か中学生くらいの頃からボカロには触れていたし、作り手側をやりたいとなったときに、自然と「ボカロから始めるんだろうな」とは思っていて。僕がボカロを買ったのは社会人になってからなんですけど、当時は周りで音楽をやっている人も少なかったですし、ボカロならひとりで全部完結できるというのもよかったんだと思います。
――作り手になることを決意したきっかけなどはあったんですか?
伊根:そういうのは、あまりなかったんです。趣味でギターを触っているときに、既存の曲を模倣したり、アレンジしたりして遊んでいたんですけど、その流れで「なんでこの音は気持ちいいのかな?」みたいなことを考えて、感覚と理論の擦り合わせみたいなことを無意識にし始めたんです。そうやって遊んでいたことの延長として、自然な流れで作る側になり始めた感じでした。その意味では、最初から作り手をやりたかったのかもしれません。
――そこから今に至るまでずっと、ご自分は何を求めて音楽作りをしてきたのだと思いますか?
伊根:そうですね……これは昔から共通していることなんですけど、僕は、人に何かを伝えることが不得意というか、自分の感情や伝えたいことを言語化するのがすごく苦手なんです。語彙力の問題というよりは、言葉じゃ全部伝わらないとわかっているがゆえに、「じゃあ伝えなくてよくない?」と拗ねてしまうことが多くて。昔から、自分の中にある“言葉に翻訳する前の原石”みたいなものを伝える術がほしかったのかなと思うんです。言葉や身振り手振り以外の何かで、なるべく解像度高く、自分の中にあるものを伝えたかったんだと思います。
――なるほど。以前、伊根さんが「研究者」になりたかったとおっしゃっていた記事を読んだのですが、そういうご自身の探求精神というのは、音楽作りにも反映されていると思いますか?
伊根:たしかに、音楽を作る過程は実験とか研究みたいな感じだし、サイエンスに繋がっていることをしている気はします。たとえば、量子力学って、最先端でも未解明な謎が多い分野じゃないですか。昔からああいう世界には夢があるなと思っていましたね。科学っていちばん現実的で、問答無用で信じることができる論理的なものだけど、そのわりに、最先端の部分では「そんなことありえないでしょ」と直感では判断してしまいそうな理論が、正しいものとされていたりする。そういう“驚き”と“納得”があるものというか、「筋は通っているけど脅かされる」ものに惹かれるし、そういうものを自分も作ってみたいという気持ちがあって。実際に、自分は量子力学の研究者になれるほどの頭はないけど、音楽はたまたま自分にもできた。音楽で、研究者と同じようなことがしたかったのかなと思っています。
――“驚きと納得”を求めることに、伊根さんの根本的な資質があるんですね。
伊根:音楽でも、「音を楽しむ」という意味での魅力と、何かを伝える手段としての納得感のバランスがいいもの……“驚きと納得”が両立しているのが好きです。僕自身、元々ものを作るのが好きでしたし、自分の知らない世界を探りたいという気持ちがずっとあったと思います。小さい頃は図工や科学が好きな教科だったし、今でも本や映画に触れるときはSFが結構好きだったりするんですけど、そこに通じるものは、子供の頃から持っていたと思います。学校から帰ってきてニコニコ動画でボカロ曲を探している時間も、旅をしているような気分でした。Nintendo DSのソフトで二次創作が上がっていたのを聴いたことをきっかけにボカロを知って、人の声じゃないことに最初は衝撃を受けて。そこから興味を持って、源流のニコニコ動画の方に行って……最初は、ランキングから聴いていったのかな。当時はギターをやっていたこともあって、「ロック」とかのタグから検索をしたりして。いろんな曲を聴いていくと、再生数と自分の“好き度”は全然比例していなかったりするし、そこが面白いなと思っていました。
――今回、Billboard JAPANに立ち上がった“ニコニコ VOCALOID SONGS TOP20”には、どのようなことを期待しますか?
伊根:僕がボカロにハマっていった当初のことを思い出すと、自分で掘って好きなボカロ曲を見つけたとき特有の感動や驚きがあったと思っていて。今までボカロにハマったことがある人には、きっとそういう経験がある人が多いと思うんです。チャートができることで、そういう体験ができる機会が増えたら嬉しいなと思いますし、驚きを見つけやすくなったらいいなと思います。「今、これが有名だから聴いてください」というのもあるとは思うけど、「そこだけじゃないよ」ということも見えると嬉しいです。有名なものには理由があるし、そういうものも聴いてほしいけど、それだけじゃないよって。ボカロって自由な文化だし、「君も作ったりできるんだよ」ということがよくわかると、さらにいいのかなと思います。
Adoへの提供曲「過学習」
――2022年は、伊根さんはご自身初のフルアルバム『Direct-View AR』をリリースされましたし、Adoさんや栗林みな実さん、King & Princeといったアーティストへの楽曲提供も行われていました。伊根さんにとって、2022年はどんな1年でしたか?
伊根:今年は、住む場所も、関わる人も、時間の使い方も全部が変わって、濃密で速かった1年だったと思います。音楽をいろんな動機で作ったり、作らせてもらったりした年でもあって。作り手として認識され始めたことの悩みや葛藤もあったのかなと思います。曲を作ったり、悩んだり、解決したり、諦めたり、苦しんだり、面白がったり……目まぐるしい感じでした。なので、アルバムが出たとか、楽曲提供をしたとか、そういう字面だけを見ると、知らない人の人生みたいにも感じます。
――Adoさんに提供された「過学習」はどのようにして生まれた楽曲だったんですか?
伊根:突然、依頼をいただいて。非現実的な出来事で、驚きでしたね。曲に関しては、繫がりすぎる現代社会の境界のなさがテーマとしてあって。どこからが自分で、どこからが自分じゃないかという境界線がなくなっているような感覚……自己の喪失というか。そういう現象が僕にも、規模が小さいなりに起きたりするんです。「伊根」という概念が、僕なのか、僕とは別なのか、自分の本名を見たときに「こっちが自分なのか?」と考えることもあって。どこからが自分で、どこからが聴き手のものなのか、聴き手が「伊根さん」と呼んでくださった伊根さんは本当に僕なのか?とか……たまに考えたりします。そういう現象に対する皮肉とSOSを込めた曲です。
――今の社会や時代性に対して、非常に批評性のある曲ですね。
伊根:未知の状況に対して自分は何をしたくて、何をすべきで、何ができて、今どこで何をしているのか……そういうことがわからなくなってしまう。それでもなんとかして進んでいくけど、総じて正解が出せないし、そもそも、正解なんてないし。皆の見ているものが違う分、集団や社会が実際にそういう状態になっていることも多いと思います。今までの経験にがんじがらめになってしまうというか。タイトルの通り、そういう未知に対応できない皮肉さと足掻きみたいなものを書いています。
「過学習」 / Ado
――Adoさんの歌声や、彼女の存在に対してはどのような印象を持っていますか?
伊根:あれこれと言葉を選んで説明するというよりは、シンプルな言葉で「かっこいいな」と言ったほうがしっくりくるかもしれません。色々含んだ感嘆として「かっこいいなぁ」と。あと、Adoさんはメジャーデビューする前からずっと歌い手として「歌ってみた」動画をアップされていましたし、この間も【超パーティー2022】でカバーを歌われているのを見たんですけど、Adoさんの歌を通して、自分が好きだった歌のかっこよさを再確認したり、知らなかった曲を知ることができたりする。それって、すごいことだなと思います。Adoさん自身のかっこよさも見せてくれるし、Adoさんが伝えてくれるかっこよさ、伝えたいもののかっこよさもAdoさんと掛け合わせて見せてくれる感じがする。少年漫画で、めっちゃ強いキャラが主人公と共闘してくれる時の高揚感に近いものがあるというか(笑)。
――なるほど(笑)。でも、しっくりきますね。
伊根:本人もかっこいいし、いろんな人を巻き込んで、巻き込まれた人のことも主人公にして、全部をかっこよくしてくれる。そういう心強い存在感を僕は勝手に感じています。
――「過学習」のお話の中で、伊根さん自身と聴き手との関係性の話もあったと思うのですが、自分の音楽のリスナーとの関係性というのは、どのように考えられていますか?
伊根:大前提として感謝は絶対にあるし、言及してくれる時点で、それがイマイチな評価でもなんでも、名指ししてくれるだけでありがたいことだと思っているし、評価してもらえた時はなおさら、嬉しいです。でも、そこで僕が「自分の音楽はこう受け取ってほしい」とか「こう評価してほしい」みたいな欲を持ちだすと、聴いてくださる方に責任まで投げつけているような気がしちゃうので……難しいですよね。自分で船を漕いでここまで来たことは事実だし、聴いてくれる人や関係者の方たちに助けられてここまでのことが実現できたのもまた、事実なので。作り手として、恵まれているなと思います。恵まれているからこそ、自分のやりたい活動でそれに報いることができているなら、幸せなことだなと思います。それが今、作り手と認識され始めた人間として、感じていることですね。
King & Prince「TraceTrace」を振り返って
――King & Princeに提供された「TraceTrace」はどのようにして生まれた曲だったのでしょうか?
伊根:(King & Princeは)第一線に立たれる方たちだという認識があったので、自分が何をやるべきなのか、何ができるのかという部分は結構悩みました。でも結局は、あれこれ考える前に全力を尽くすしかないかなと思って作りましたね。編曲を自分が担わない楽曲制作は今回が初めてだったんですけど、メロディやリズム、コード進行に関しては、僕自身のエゴになりすぎず、タイアップのドラマ(『新・信長公記 ~クラスメイトは戦国武将~』)の雰囲気や、5人の歌とダンスにうまく使ってもらえることを要所要所で考えながら、でも自分が担う曲でもあるという、そのバランスのいいところを探り探り作っていきました。歌詞については、ドラマを念頭に起きつつ、いろんな受け取り方ができるような普遍的なものにしたいなと思っていて。ドラマ自体が特別な状況を舞台としていたので、非日常から生まれる普遍的なものを作ることができればいいのかなと思って。なので、あまり普段は聞かないような文章が並んでいる歌詞になっていると思うんですけど、単語自体は難しいものを使わないようにしました。そうすることで、非日常的だけど普遍的であるということを表現できればいいなと思って。ラスサビの前の歌詞は特に、それを体現できたのかなと思っています。
「TraceTrace」YouTube Edit / King & Prince
――“非日常から生まれる普遍性”というのは、伊根さんの根本姿勢である“驚きと納得”にも通じる気がしますね。実際にKing & Princeの皆さんが自分の作った曲を歌い踊っている姿を見て、どんなことを思いましたか?
伊根:こういう、見方によっては非現実的なことって、この活動を始めてから度々起こるんですけど、未だに何を思えばいいのかわからないんですよね(笑)。「本当にドラマで流れているな」とか、「本当に歌ってもらっているな」とか……そういう自覚があった方がいいんだろうなと思いつつ、まだまだ非現実的な感じはあります。「本当に自分が作ったんだよな」と改めて感じることが多いです。あと、自分の関わったものに対する感想は、ちょっと語彙が追いつかないです(笑)。“感動”したんだと思います。一歩引いた聴き手として「かっこいいな」と思いました。歌も踊りも、MVの色の使い方とかもすごくかっこよくて、一視聴者として見入っていました。この“かっこよさ”に携われてよかったなと思います。
1stアルバムの裏側にあった思い
――ご自身の1stフルアルバム『Direct-View AR』は、「ルーセ」などの代表曲も収録しつつ、伊根さん自身が執筆された小説も同梱されているコンセプチュアルな作品というイメージもありましたが、本作はどのようなテーマをもとに作られたんですか?
伊根:この『Direct-View AR』というタイトルは数年前に考えていたもので、「この名前で何かを作ろう」とずっと思っていて。その人――それは僕かもしれないですけど――しか見ていないようなフィクション、夢物語、ともすれば幻覚の暗喩として、このタイトルはイメージしていました。技術チックな名前にしたのは、何かを伝えるときに完全に伝わり切らないこと、言葉で伝えようとするけど上手く切り出せないこと、言葉に翻訳しづらい概念……そういう言葉になる前のことに、実在する物と同等の確かさや尊厳を持たせることができたらいいなと思ったからで。それが、アルバムを作るに当たって一貫したものだったと思います。
「DiVAR」IA ― Science ver. / 伊根
――音楽アルバムとリンクするように小説を執筆されたのは、なぜだったんですか?
伊根:まず、僕が文章を書くのが好きだったというのはありますね。話すことほどリアルタイムではなくて済むので、より伝えたいことを翻訳しやすいというか。時間もかけられるし、より正確性を持たせることができるので、それを手段として使ってみたかったというのがひとつ。あと、さっきから言っている“驚きと納得”を軸にしているからかなと思います。驚きだけだったら、わりと僕は音楽で作りやすいんです。ひねくれたことや変なことをするのが大好きなので。でも、納得させることができるものや、共感できるものを作ることが苦手で。その“納得”の部分を表現するために文章を書いたのかなと思います。僕が作る音楽は無機質なものになりがちだし、歌詞も、誰かへの思いというよりは無機的な言葉選びに寄りがちだけど、それだけだと僕自身、納得感が足りなくて。もっと共感できるものを作りたいと思ったし、共感するのは人なんだから、人を描きたかった。得意ではないことだけど、自分の世界観に“人”を持ち込むために、文章を書いたんだと思います。
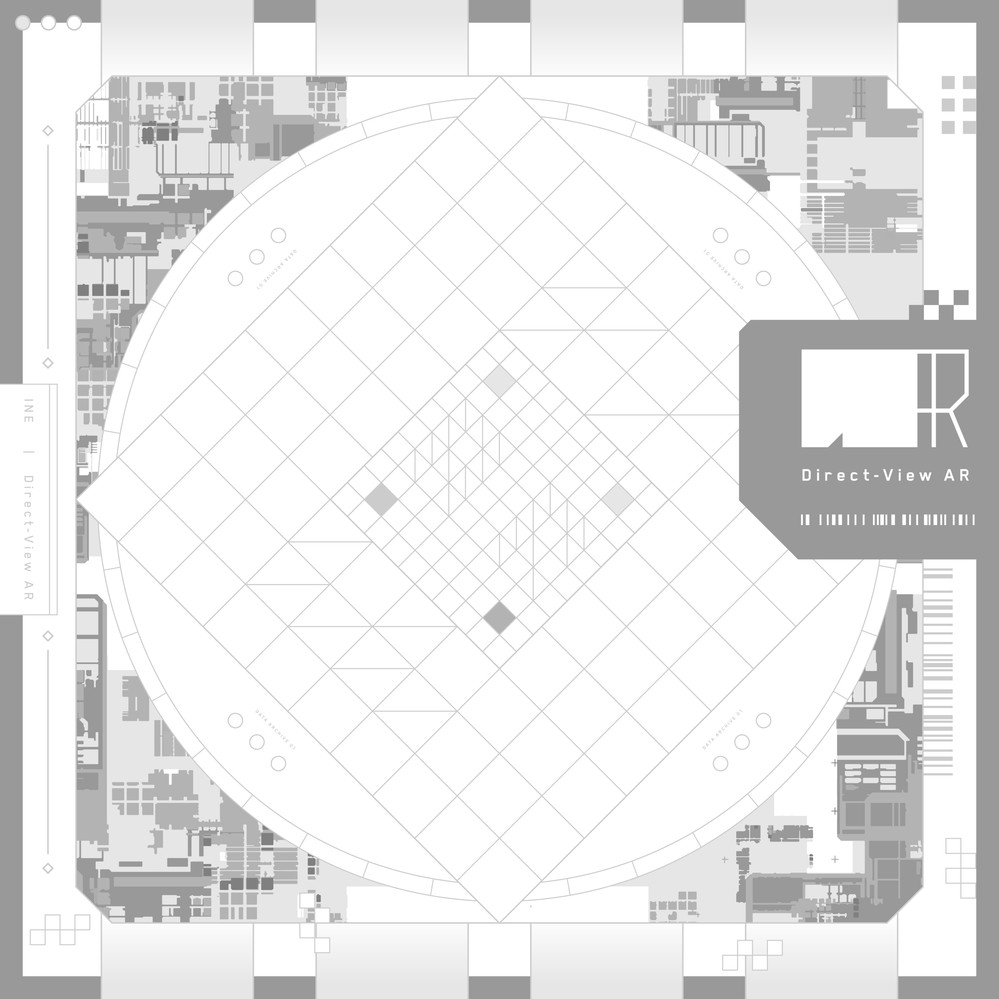
――『Direct-View AR』の最後を飾る楽曲のタイトルは「パーソナリティ」ですが、伊根さんがボカロPとして最初に投稿した楽曲は、「回避性パーソナリティ」でしたよね。歌詞の内容は非常に対比的になっていると思うのですが、どういった意図で、今作の最後に「パーソナリティ」という楽曲を収録したんですか?
伊根:「回避性パーソナリティ」は、あの曲を作った時の自分を書いている部分もあったんですよね。作り手を始めたばかりで、当時はサラリーマンをやっていたんですけど、あの時のすごくクローズな自分だけの思いが書いてある曲で。「回避性パーソナリティ」を投稿したことは、自分の中の、人に伝えることができていなかった部分を初めて世に出したというか、オープンな場に置いておいたような感覚があることだったんです。振り返ると、ずっと趣味で音楽に触れてきていて、「いずれ、投稿するんだろうな」とは思っていたんですけど、それがいつになるのかはわかっていなくて。音作りが上手くいっていないからとか、動画が作れないからとか、いろんな理由をつけて投稿するのを先伸ばしにしていたんです。実際になんで投稿したのかは、今振り返ってもちょっとフワッとはしているんですけど、コロナで在宅勤務になって、家にこもって、時間が増えて、「今が自分の外に出るタイミングなのかな」と思ったのかもしれません。あの時、ちょっと勇気を出したと思うんですよ。それから2年経って今の自分が振り返ってみた時に、誰かに何かが伝わることがあったし、自分が思っていた以上のことが起こることもあったし、結局人に助けられたりしながら、ここまで活動ができていて。あの最初の曲に対して、今振り返ってどう思うかを表現したかったんです。歌詞にはそういう部分がありますね。トラックはほぼ一緒で、実は「回避性パーソナリティ」ができた次の日くらいには、「パーソナリティ」のメロとかはできていて。いつか、どこかのタイミングで振り返って世に出したいなとは思っていたんです。自分にとって確認しなければいけないことだったんだと思います。
――この2年間で、ご自分は変わったと思いますか?
伊根:2年前はプロでもなければアマでもない、なんでもない立場だったけど、今は人から見ても「プロ」と呼ばれるようなことをしていて。いちばん変わったのは、自分が何かをすることによって自分以外の何かが動く、こんなにも動いてしまうということですよね。それに、自分がやってきたサラリーマンの仕事だと、わりと正答があるというか、明らかに求められていることがわかるけど、今は正解の存在しない問題が並んでいることが多くて。そこに困惑はしつつ、でも周りを見た時に、そこに向き合うアーティストやクリエイターの方々がいて。そういう人たちをもっとかっこいいと思うようになりました。僕はまだまだプロとしての姿勢や考え方が幼稚な部分もあると思いますけど、向き合う姿勢そのものについて考えることが増えたのは、変わった点だと思います。まだまだこれからも、いろんなものを見て学んでいきたいです。
――最後に、伊根さんにとって、ボーカロイドという文化の魅力とは、どういったものだと思いますか?
伊根:まとめて言うと、関わっている全員が地続きにあるところですね。僕の経験として、聴き手をやるにしても、作り手をやるにしても、障害が一切なかったんです。ボカロを買うこと以外の障害がほとんどない。「作り手をやろう」と思い立ったら、すぐにできちゃう。僕自身、自分がいつ「ボカロPをやろう」と思ったのかはあまり覚えていなくて、当たり前の様にやりたいことをしていたら、気づいたら作り手をやっていたというくらい地続きにあるものだったんです。なので、ボカロPは憧れた瞬間にほとんどを始めることができるし、「いつかなれるもの」じゃなくて、「今やれること」。その障害のなさは魅力だと思います。だからこそいろんな人たちが集まってきて、幅広い音楽が生まれている文化になっていると思うんですよね。僕は『マインクラフト』みたいなゲームが好きなんですけど、ああいうオープンワールドなゲームで旅をしている気分に近いんですよね。有名な都市部に行ってもいいし、知る人ぞ知る穴場に行っていいし、ガイドさんをやるのもいい。何をやってもいいし、冒険し放題。そこが、僕としてはボカロ文化の魅力だと思います。
関連商品































