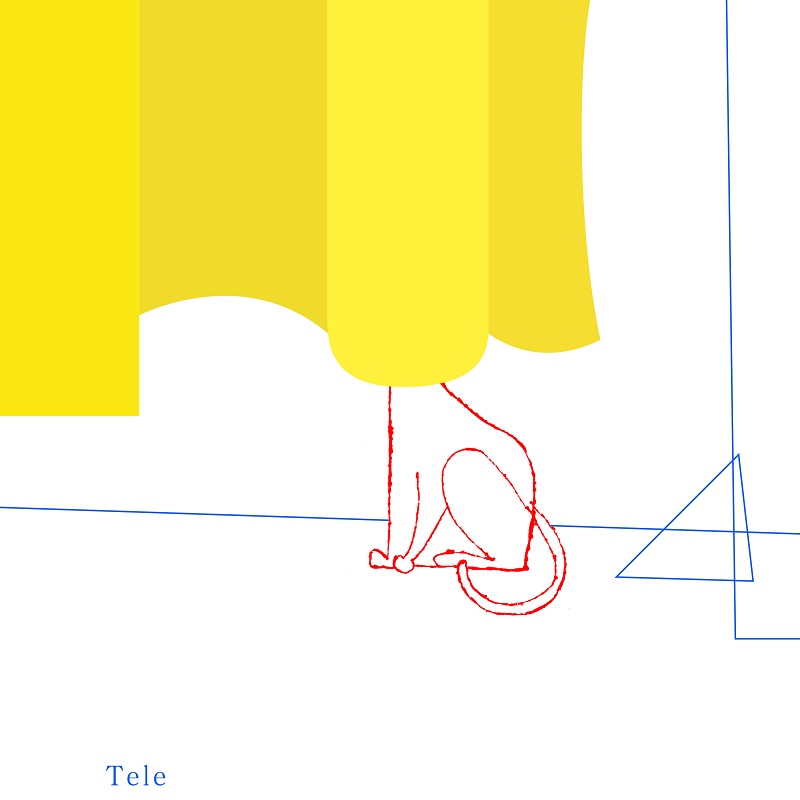Special
<インタビュー>Teleが眼差す新時代のポップス、ラブソングの美学

2022年1月から楽曲のリリースを開始し、6月には初のアルバム『NEW BORN GHOST』も発表した谷口喜多朗のソロプロジェクト・Tele。いまだその全貌が見えない不思議なアーティストだが、その音楽は確実に多くの人の心に届き始めている。世の中に溢れるポップミュージックとは一線を画した独特の視点と感性で人間の本質を綴った歌詞と、それをまっすぐど真ん中に打ち込んでくるメロディ。その音楽は控えめに言っても革命的だと思うし、聴けば聴くほどいろいろな感情が呼び起こされていても立ってもいられなくなる。底知れないポテンシャルを秘めたニューカマーだ。
そんなTeleがアルバム後初となる新曲をリリースした。9月21日に配信された「Véranda」は、これまでの彼の表現と通じ合いながらもさらに一段高い解像度でリスナーに訴えかけるラブソングである。この曲で彼が歌った「愛」のありかたには、Teleというアーティストの哲学やスタンスがはっきりと表れている。
11月2日に東京キネマ倶楽部で開催される初のワンマンライブ【東京宣言】への意気込みと合わせて、Teleというアーティストの正体に迫った。(Interview & Text:小川智宏)
Teleの音楽が「ポップ」であるために
――2022年も残すところ2か月ですが、Teleにとって今年は本当にいろいろなことが変わった1年でしたよね。
Tele:今年1月に初めて楽曲をリリースしたんですけど、それ以前に3年近く、僕はTeleという名前で3ピースのバンドをやっていたんです。その後2020年からコロナと並行してメンバーがいなくなってひたすら曲を作り溜めるだけの時期があったので、「ようやくか」という気持ちです。ようやく人の耳に届くところに自分の作品を置けるっていうのと、あとは「まだまだ足りないな」という気持ちもあります。もうちょっと薄れるかと思っていたけど、余計に「もっと早く、もっと早く」って思っていますね。
――なるほど。すごく内圧が高い状態でずっとやってきて、ようやく地上に出てきたというか。その開放感みたいなものもありました?
Tele:ありました。本当に初日のセミみたいな気持ち。地面がアスファルトで舗装されてなくてよかったって思いました(笑)。ただ、1週間で死ぬにはちょっと惜しいので。そのためにはセミのまんまじゃなくて、もっと遠くまで飛べる体力とか技術とか、いろいろなものが必要だなっていうことがわかりました。今までは何かわからない状態で壁にぶつかっていたみたいな感じだったんですけど、その壁の全貌がわかって、じゃあこれをどうやって越えていこうかっていうことを考えた1年だったなって。
――Teleの音楽に触れた人たちからはすごく熱烈な反応もあったと思いますが、それに対してはどう感じますか?
Tele:これはアルバム(『NEW BORN GHOST』)の話なんですけど、アルバムのジャケットのデザインをお願いするときに、デザイナーの方にいろいろな案を出していただいたんです。でも自分の中では案を出していただく前に明確に決まっていたことがあって。それは初めてCDを買って手に取ったときに一生焼き付くものにしたいということだったんです。一生焼き付いて、そのCDがその人と一緒に年月を経過できるようなジャケットがいいって思いがあった。特にこの1年リリースしてきた曲、その1年にリリースした曲がまとまっているアルバムも「Véranda」も、音楽に初めて触れる人にちゃんと届けたかった。だからアルバムを出したときに実際に「初めてCDショップに行きました」ってメッセージをくれた人もいて、それは僕が願った通りの反応ですごく嬉しかったです。配信がメインの今、CDでしかアクセスできない曲も一定数あって、CDを聴いてもらうことをアーティストがお願いしないとそういう曲たちって誰にも聴かれなくなってしまう。そういうことを思っていた自分としては、いろいろな人の「初めて」になれたっていうのは一番嬉しかったし、驚きも少なからずありました。

――実際にTeleの音楽が「CDを買う」という行動に繋がっていった。それはまさにTeleの音楽がポップソングとしてのパワーを持っていたということだと思うんですが、じゃあ、自分の曲のどういう部分がポップなんだと思います?
Tele:なんだろう。たとえばメロディだったりコードだったりアレンジメントの部分でいうと、僕はかなり、いわゆる往年の名曲的なポップソングからすごく引用しているし、影響を受けている。でも僕の歌詞って、基本何言ってるかわからないんですよ。それは書き手とか創作する側の言いたいこととか、真意みたいなものはなるべく隠したほうがいいと思っているからなんです。言いたいことがあるじゃないですか。それを思ったときの時間があって、場所があって、その場所にいる人たちがいて。そういうことを綿密に書いていったら、必然的に言いたいことって最後の最後、奥のほうに隠れていっちゃう。僕はそれが自然だと思うから、隠れるべきだって思う。だけど強い感情ってそこから漏れ出てくるんです。僕の歌詞は終始何を言っているのかわからないかもしれないけど、やっぱり僕の感情が漏れ出ている瞬間があって、そこでたぶん僕っていう人間の感情に触れてもらえているんじゃないのかなと思います。感情が漏れ出す瞬間のエネルギーはみんなわかることで、それをいいと思っていただいてる……んじゃないでしょうか。
――言葉の部分でいうと、おっしゃったようにTeleの歌詞は必ずしもポップス的ではないと思うんですよね。ポップスの言葉というのはある1個の感情を切り取って、それをデフォルメすることによってわかりやすくしていくじゃないですか。それが共感に繋がったりとかするんですけど、Teleはそうしない。誠実だなと思うんです。
Tele:まあ、それが得意じゃないのもあるかもしれないけど。自分の感情をデフォルメした状態がちょっと気持ち悪くて、怖くて。それを結果的に誠実だと捉えてくれるのは嬉しいんですけど。ただ、デフォルメした感情を歌った曲も僕は素晴らしいと思っているし、1つの作品のあり方としては間違っていないと思う。僕ができないだけですね、単純に。
――実際にできるかどうかはわからないですけど、少なくとも谷口さんはそれは得意じゃないなって思っているわけですよね。でもその認識に対して「自分なりのやり方でやってみよう」ってところに真っ直ぐ向かえる。で、そのやり方においてあくまでポップであることを目指すことができる。わかる人にだけわかればいいやとはならない。それは逃げていないということだと思うんですよね。まさに漏れ出ているものは届くでしょってピュアに信じているというか。
Tele:ああ、届くでしょって根拠のない自信は14歳とか15歳の頃からずっとあるんです。世の中に対するものすごい不安と同時に、だけど俺はこのなかで生きていけるなって。僕、14歳くらいのときに家出とか野宿とかいっぱいしてたんですよ。今は違うんですけど当時は親とあまり仲良くなくて、これ以上いるとギスギスしちゃうかもしれないと思ったから、そっと「行ってきます」みたいな感じで家出して、近くの広い河川敷で3日間くらい寝泊りしてみたりしたんです。そうしてみたときに「最悪生きていけるな」って思っちゃったんです。もちろん体はそんなに強いほうじゃないから、それを3年とか続けたら死ぬと思うんですけど、この状況からより良く生きていくためにはどうしたらいいんだろうってエネルギーが自分の中にあることは把握できた。だから、根拠はないかもしれないけど、現状自分の矢印がちゃんと前に向いているということがわかれば大丈夫だと思ってる。だから僕は歌詞では自分の感情をデフォルメしないし、聴いてくれる人はこういう人だろうというデフォルメも絶対にしないと決めています。
リリース情報
シングル『Véranda』
- 2022/09/21 RELEASE
配信リンク:
https://tele.lnk.to/Veranda
公演情報
【Tele 初ワンマンライブ「東京宣言」】※SOLD OUT
2022年11月2日(水)
東京・キネマ倶楽部
OPEN 18:30 / START 19:00
【CONTACT!!Vol.22 -MINAMI WHEEL EDITION-】
2022年11月16日(水)
大阪・心斎橋BIGCAT
OPEN 18:30 / START 19:00
出演:Tele/chilldspot/リュックと添い寝ごはん
【Spotify Early Noise Night #14】
2022年11月25日(金)
東京・Spotify O-EAST
OPEN 17:30 / START 18:30
Tele 関連リンク
ラブソングの定義からは外れたかった、だけどラブソングを書きたかった
――そういうTeleの基本スタンスというか哲学を感じながらアルバムを聴いたわけですけど、「ghost」という最後の曲を聴いたときに、それまで出してきた曲たちとは違う感覚を覚えたんです。他者との距離感や関係性がまた変わってきた感じがしたというか。
Tele:あの曲は本当にコロナで家から出れない時期に作った曲で。深夜3時くらいに自転車で東京を走り回っていたんです。新宿の歌舞伎町に行ったんですけど、まだコロナが始まったばっかりの時期だったからものすごく人がいて、そのとき僕は「この溢れてる人の中に僕を知ってる人は1人もいないな」って思って。ものすごく当たり前のことなんですけど、その当たり前のことがものすごくしんどく感じちゃって、書き始めた曲なんですよね。ただ、昔から歌詞を書くことが僕にとってはある種のカウンセリングみたいな面があって、あの歌詞を書いていく中でも、でも今このときにでも何回でも僕の曲を聴いてくれる人はいる、そこまで1人ではないんだということに気づいたんです。それまでは孤独が大前提で、孤独な人間がどうやって生きていくかっていうことにものすごく注視して歌詞を書いていたから、そもそも自分の孤独を疑わなかったんですよ。だけどコロナになってメンバーもいなくなって、ただ孤独であるという状態でその孤独を疑うことになったから「孤独ではないな」って気づいた。それで、そういう人たちから流れ出た感情が凝り固まった僕を変えてくれるんだろうなってある種の祈りみたいなものを書いたんです。
――そういう意味ではこの10か月ぐらいというのは、そこで感じた祈り、予感みたいなものが実体化していくっていうか、より補強されているような日々でもあった?
Tele:そうですね。その通りだと思います。
――そうなることによって何かまた自分の中に変化は生まれましたか?
Tele:それは生まれちゃいけないなとは思っているんですよ。とくに歌詞に関しては、人に聴かれたからといって過剰に何かが変わっちゃったりしたら、それはどんどんずれていっちゃうと思うから。だけど、余計に丁寧に作らなきゃいけないというか、中途半端なことはできないなって気持ちはやっぱり強くなりましたね。すごく若い人というか……僕が「若い人」って言うのはあれなんですけど(笑)、本当に14歳とか15歳の少年少女が聴いてくれているわけで、そういう、僕より若くて僕よりも可能性持っている人に対してどういう音楽をそばに置いてあげるのが僕にできることなんだろうというのは、今も考えています。あとは、ライブに対する考え方も変わりました。僕はサーカスとか動物園と一緒だと思っていたので、お客さんがビビればビビるほどいいと思っていたんですよ。でもそうじゃないなって。すごく偽善的だけど、ライブを観にきてくれるお客さんのことをすごく瞬間的に愛せるようになったというか、僕のことをわかってほしいし、僕もわかっていたいっていう感情が生まれたなとは思いますね。
――うん。それがつまりポップっていうことなんだと思うんですよね。使っている言葉がどうとか、わかりやすさがどうとかではなくて、そこで相手とチャンネルを合わせようとしているということ。そういう意味ではTeleはどんどんポップになってきているなと思います。
Tele:そうですね。今の「チャンネルを合わせる」というのはその通りだなと思う。結局聴いてくれる人はいろいろ探すわけじゃないですか。もちろんふっと目に入った、たまたまチャンネルが合ったということもあるけど、お互いに周波数を合わせていかなきゃいけない。お客さんたちは常に周波数を合わせてくれているんです。ラジオだったりとか、YouTubeで探したりとか、プレイリストを聴いたりとか。それがたまたま合うのが一番美しいことだとは思うんです。だけどそれってすごくはかなげな美しさであって、アーティスト側がそこのチューニングを合わせようとするという健気な美しさもあっていいんじゃないかっていうふうに僕は思いますね。
――「Véranda」も今話してくれたことにつながるような曲だと思ったんですが。これは谷口さんにとってどういう曲ですか?
Tele:これは……ラブソングってすごい不思議だなって思うんです。人が人を好きになるって、いろいろなルートはあるけど、そのルートを繋いでいる糸って全部同じじゃないですか。ラブソングにもいろんなパターンはあるけど、結局「ここ」のことを歌っているという意味では全部一緒で、そうなるとラブソングにおける「定理」みたいなものが歌詞にはあると思うんですよ。それって作品数が増えていけばいくほど明確になっていっちゃってて、「いつまでもセックスの後にタバコを吸うエモささみたいなものを書いているんじゃないよ」って怒りみたいなのが生まれてきて(笑)。だからそうじゃない方の人のことをまず書こうって思ったんですよね。ラブソングの定義からは外れたかった、だけどラブソングを書きたかった。だからその関係性の愛の捉え方もものすごく適当にしたんですよ、あえて。〈愛はここにあって〉って、どこなんだよそれはって。そんなの言わなくていいんですよ。みんな人を愛することに理由を考えたりとか、普段無責任な人が人を愛することについて急に責任を感じたりとか、そんな必要ない。聖書を読んでも「汝の隣人を愛せよ」ってきっとこれくらいのテンションで言ったんじゃないのって思うんです。
――すごくよくわかります。僕もこの曲はラブソングだと思うんです。だけどそれは類型化された恋愛ソングではなくて。「付き合って嬉しい」「愛し合えて幸せだ」だけじゃなくて。「別れて悲しい」とか「寂しい」だけではなくて、その奥底、その先に何かあるんじゃないのというのを一生懸命探しているような感じがする。
Tele:そうですね。「私小説」という曲もそうなんですけど、若干ラブソングって捉えられるかもしれないって思ったときには、絶対僕は男女を決定するような言葉を使わないんです。それは別にポリティカル・コレクトネスみたいなことを意識しているわけではなくて、たとえば「私小説」の歌詞で〈誰かの視線が気になってボタンの一番上締める〉っていう歌詞があって、これって別に、男も女も言えることだと思うんです。そうやってその人を決定的にしないっていう。それは「Véranda」でも意識して書いていました。でも不思議だなと思います。僕はここに恋人だなんて一言も書いてないし、言っていないけどじつは僕は結婚していて、これは奥さんの歌かもしれないし、僕が高校生から付き合っている男性のパートナーのことかもしれないし、友人たちと集まって飲んでいるときのことかもしれないし。だけどそうやってラブソングだって捉えてもらえるっていうのは、やっぱり何かあるんだと思うんですよね、奥底に。
――ただこの曲、最後で〈ザマアミロ!〉って歌うじゃないですか。ここは感情が溢れている部分だと思うんですけど、この〈ザマアミロ!〉は一体誰に向けられているものなんですか?
Tele:あんまり特定個人に向けてはいないし、特定個人に言っていたとしてもこんなところでは言えないけれど(笑)、なんだろう、「愛はここにあるぞ、ないと思ったろ? ザマアミロ」みたいな。その言葉が単純に好きというのもありますけど、僕が〈愛はここにあって〉って歌にしたのは、そんなものまるでないような顔をして生きる人がいるじゃないですか。しいて言うならそういう人たちに向けてなんです。あと、よくわからない性欲とか、お金とか、個人的な都合で愛を邪魔してくる人たち。そういう人たちに〈ザマアミロ!〉って。ほら見たことかって言って、手を繋いで街を歩いていく。そういう意味でもこれは他の曲より具体的だなと僕は思っています。

――そして11月にワンマンライブ【東京宣言】があります。東京キネマ倶楽部でやるというのは念願だったそうですね。
Tele:高校生のときからキネマ倶楽部でやりたいと思っていました。実際にライブを観に行ったんじゃなくて、神聖かまってちゃんのライブ動画を観て、めちゃくちゃよくて。その瞬間に「このステージに立ったらすごいだろうな」と思って、ずっとやりたいと思っていたし、周りにも言っていたので。初めてのワンマンがあの場所でできるのはもう、願ったり叶ったりです。
――すでにフェスやイベントには出ていますけど、改めてワンマンライブに向けてはどういうイメージを持っていますか?
Tele:今、全体のプロダクションみたいなものをいろんな人と話し合って決めているところなんですけど、楽しいですね(笑)。どうしてもフェスだったりイベントだったりすると僕を観に来ていない人たちもいて、その人たちにどうやって届けるかってことも考えなきゃいけないんですけど、ワンマンってなると当たり前だけど僕を観たくて来た人ばかりで。じゃあその人たちに何を見せようか、どうやってこの人たちの予想や期待を裏切ってやろうかって。大規模な前提条件があるから、その前提をどうやって覆してやろうかというのが楽しみです。「東京宣言」というタイトル通り、自分がこれから進んでいくにあたっての宣言を打ち立てられたらいいなって思っています。
リリース情報
シングル『Véranda』
- 2022/09/21 RELEASE
配信リンク:
https://tele.lnk.to/Veranda
公演情報
【Tele 初ワンマンライブ「東京宣言」】※SOLD OUT
2022年11月2日(水)
東京・キネマ倶楽部
OPEN 18:30 / START 19:00
【CONTACT!!Vol.22 -MINAMI WHEEL EDITION-】
2022年11月16日(水)
大阪・心斎橋BIGCAT
OPEN 18:30 / START 19:00
出演:Tele/chilldspot/リュックと添い寝ごはん
【Spotify Early Noise Night #14】
2022年11月25日(金)
東京・Spotify O-EAST
OPEN 17:30 / START 18:30