Special
<インタビュー>KUMIと深沼元昭が明かす――“大人ガレージバンド”Uniollaを結成した理由とバンドが目指すもの

LOVE PSYCHEDELICOのボーカルKUMI、深沼元昭(Gt.、PLAGUES/Mellowhead)、林幸治(B.、TRICERATOPS)、岩中英明(Dr.)の4人によるバンド「Uniolla」が本格的に活動をスタートした。ユニオラと読むこのバンド名はKUMIが命名したもので、気のおけない4人が青春を具現化したナンバーは、幅広い世代に受け入れられることだろう。キャリアの長い彼らがあえて原点に戻り、手作業で作り上げた1stアルバム『Uniolla』は11月24日に発売。KUMIと深沼元昭がレコーディングの様子や言葉を交わさずとも共有されたバンドの核を教えてくれた。
――まず、バンド結成の経緯から聞かせてください。
深沼元昭:元々、僕がMellowheadというソロ・プロジェクトをやってて、佐野元春さんや及川光博くんとか、いわゆるフォーチャリング・ヴォーカルとして、いろんな方に歌っていただいてきたんですね。「その人が歌ったらどうなるかな?」と曲を書いて、歌ってもらうことを自分のチャレンジにしていて、KUMIに歌ってもらおうかなと思って、何曲か書いたんです。
KUMI:最初に持ってきてくれた曲は3曲くらいあったかな。
深沼:そうだね。歌ってもらったんですけど、ソロ・プロジェクトのフィーチャリング・ヴォーカルという感じにならなかったんですよね。「これは違うものだ」と思ったのが、最初のとっかかりでした。僕のソロ・プロジェクトは、サウンド的に割と凝ったモノが多かったんですけど、KUMIの歌声を脳内で鳴らしてみたときに、どんどんバンドサウンドになっていて。これを無理に自分がソロでやってきたサウンド・プロダクトに仕上げていくのは違うって相談して、バンドを始めることにしたんです。
KUMI:私は自分が書いていない曲を歌うのが初めてだったから、どういうふうになるのか、とりあえず全部歌ってみたいと思って。一緒にレコーディングをして歌ってみたら、どの曲も素敵で、すごくいいものになった気がしたんです。「これはもう、バンドだね」って、私も思いましたね。
深沼:「これはバンドだと思う」って、KUMIのほうが強く言ってた。
KUMI:そうだっけ?
深沼:そうだよ。
KUMI:(笑)。
深沼:まだその頃は、知り合ってそんなに時間が経ってなかったから、そこまで強く主張したわけじゃないけど、割とそういう感じだったね。
――改めてお二人の出会いもお伺いできますか?
KUMI:2015年に、LOVE PSYCHEDELICOの夏のフェスやイベントに、いつも一緒に演奏していたキーボードの堀江(博久)くんが出られない時があって。堀江くんが「俺の代わりはキーボードじゃなくて、きっとギターがいいと思う」って、深沼くんを推薦してくれたんだよね。LOVE PSYCHEDELICOの楽曲は多くがギターサウンドなのに、それまではギター一本で演奏していて、NAOKIも「いつかツインでやってみたい」という思いがあったから、そこで初めて深沼くんを呼んで、ツインギターでLOVE PSYCHEDELICOの音を奏でました。それが知り合うきっかけ。そこで、改めて、PLAGUESやMellowheadの音源を聴きました。特によく聴いたのはMellowheadで、彼のプロダクトを聴いていくうちに一緒に何かできたら面白いなと思うようになりました。
深沼:沢山のアーティストに歌ってもらえて、こんなに運のいいやつ、そうはいないと思ってます。ミュージシャンとして、いつもありがたいなと思ってましたし、曲を作る時も否が応でも気合いが入りましたよ。「LOVE PSYCHEDELICOのKUMIが、違うバンドで歌うときは、どんな曲を歌うんだろうか?」と考えた末に出てきたものが、結果的にもっとバンドサウンドだったんですよね。
――そこからバンドメンバーをどうやって集めていったんですか?
深沼:一番仲のいい人に頼んだっていう感じですね(笑)。特にまだどうやっていくかも決まってなくて、「本当にバンドできんの?」みたいな感じもあったし、すごく曖昧だったから、仕事的にお願いします、みたいな感じでもなくて。TRICERATOPSの林くんは、僕のほとんどのプロジェクトで弾いてくれる相棒というか、友達みたいなものなので、「どうすればいいと思う?」っていう相談から始めました。ドラムのヒデくんは、今は活動休止中のJake stone garageという3ピースバンドをやっていて、僕がプロデュースしていたんですけど、そのうち僕のプロデュース作品で叩いてもらうようになったんです。自分が考えたアンサンブルを具現化するときに、いい形でやってくれるし、彼自身、ドラマーとして、どんどん自分の引き出しを増やしていきたいっていう意欲的なところがあって。まぁ、単純に仲がいい二人ですね(笑)。
――KUMIさんはバンドになっていくことをどう感じていましたか?
KUMI:NAOKIと二人でやっているLOVE PSYCHEDELICOは、バンドではあるけれど、自分たちのサウンドを二人きりでは再現できないわけで、そういった意味で、せーので演奏ができて、それがそのままバンドの音であるというものは楽しいだろうなと思っていました。最初に歌ったときに、バンドでの広がりが見えたし、それは深沼くんが作るサウンドだろうね。
深沼:最初はもっと自分のソロ・プロジェクトに近い音だったんだけど、進めていくうちに、「これはバンドでやるべきだな」って確信して。「どうせなら徹底的に生で行こう」って、タンバリンとかパーカッションまで、自分たちの手で演奏しました。タンバリンやシェイカーは全部KUMIがやっています。僕、パーカッションが本当にダメで、シェイカーを振れる人を本当に尊敬するな。
――エレキギターで刻めるのに?
KUMI:ねぇ?
深沼:全然ダメなんですよ。とにかく、人数以上のことをなるべくやらないでおこうと決めてます。もちろん、レイヤーが薄くなるのでスッカスカなんですけど、大袈裟に言えば、そういうアートだから。
KUMI:音を詰め込むよりも、そのほうがバンドらしさが出るよね。みんなの個性がハーモニーになるし、この4人がいれば、Uniollaの音になるっていう。
深沼:正しいものをやりたいわけじゃないからね。足りなかったりすることが、一種の表現であればいいのかなと思います。KUMIのボーカルを考えたときに、自分がやりたい音の答えがそれだったとも思います。ある意味、途中まで考えていたものは、音楽的にプロの仕事だったんですよ。しっかり音を重ねていたけど、今までやってきたプロのキャリアではないものを作りたいと思ったし、メンバー同士で演奏する楽しさを味わいたいし、ライブに来てくれるお客さんと一緒に分かち合いたい。徐々にKUMIの歌にそう導かれていったと思いますね。
――バンドで演奏する楽しさが最初に伝わってきますよね。
KUMI:私がバンドで楽しいだろうなと思っていたのは、音で遊べる仲間といつでも集まってセッションができて、そのままライブもできるという在り方なんだよね。そういう日常がいいなって。幸い、こういう場所(取材はLOVE PSYCHEDELICOのプライベート・スタジオで実施)もあるし、レコーディングもここで一発録りしました。
深沼:大人が集まってやるガレージバンドなんですけど、ガレージにしては(これは)ちょっと贅沢です(笑)。なおかつ、LOVE PSYCHEDELICOにはもう一人、優秀なエンジニアであるNAOKIくんがいる。NAOKIくんは、いわゆる今の普通の録音のフォーマットを全く気にせずに、「こういう音はこう録るべきだ」っていう信念を持ってやってくれたので、彼の力もすごく大きいです。後で加工することを前提にせず、今、ここで鳴ってる音をちゃんと録る。1曲1曲、曲に合わせてマイクを立て直したりして、超DIYで大変だったけど、そういうのも面白かったし、楽しかったですね。
――4人でどんなバンドにしようという話し合いはあったんですか?
KUMI:なかったね。なのに、最初に集まって演奏したとき、なんの説明もしてないのに、みんなしっくり来ていて。それがUniollaの誕生だったね。
――ちなみにバンド名は誰の発案ですか?
KUMI:私かな(笑)。私、ユニコーンが好きで。響きとイメージから、ユニコーン達という意味でユニオラ。
深沼:“ラ”は“等”なんだよね。ふわっとしてる感じがいいと思う。
リリース情報

「絶対」
- 各音楽サービスで配信中 https://jvcmusic.lnk.to/zettai

『Uniolla』
- 2021/11/24 RELEASE
- VICL-65577 3,000円(tax out.)
ツアー情報
【Uniolla 1st Tour 2021】
- 2021年12月7日(火)開場18:00/開演19:00
- 東京・LIQUIDROOM
- 2021年12月8日(水)開場18:00/開演19:00
- 大阪・BIGCAT
- 2021年12月10日(金)開場18:00/開演19:00
- 愛知・THE BOTTOM LINE
- チケット:前売6,900円(税込、整理番号付き全自由)
- 11月6日(土) 10:00~、各プレイガイドにてチケット一般発売スタート
- ※未就学児入場不可
- ※各会場ドリンク代別途必要
関連リンク
年齢やキャリアを重ねても
バンドや音楽に対する気持ちは変わってない

――9月29日にはUniollaの始まりの曲として、アルバムの1曲目に収録されている「A perfect day」が配信リリースされました。
KUMI:とてもオープンなサウンドだから最初のあいさつにはぴったりだなって。
――歌い方や声のトーン、色が違いますよね。そこは意識的なものでしたか?
KUMI:意識的に自分の中で新たなキャラクターを模索するということはなかったですね。
深沼:そこの試行錯誤はなかったよね。最初からこの歌い方だった。LOVE PSYCHEDELICOの楽曲にいる主人公よりも圧倒的に弱くて儚いですね。
KUMI:それはたぶん、深沼くんが曲を作るときにそういう歌い手のイメージがあったからだと思う。私は素直に歌うだけでキャラクターができあがっていったから。
深沼:特に説明もしなかったんだけどね。なんとなく描いた朧げなビジョンが、音と一致した感じがしますね。「A perfect day」は、すごく明るい曲調なんだけども、歌詞は憂いがあって。
――夕方ですしね。
KUMI:切ない気持ちになるよね。
深沼:それに、Aがついて単数だしね。そういうところも切ないんですけど、そういったことを全部KUMIが感じ取って、歌ってできたキャラクターなのかなって。
――青春も感じるんですよね。
KUMI:そう、Uniollaのキーワードの一つに“青春”があると思う。
深沼:なぜかそうなった。それが不思議なんですよね。
▲「A perfect day」
――今日が楽しくて仕方がなくて、明日が来なければいいのにっていうくらいの青春を感じます。
深沼:自分ではなかなか「青春です」とは言い難いけど(笑)、みんなに言われるよね。
KUMI:メンバーもみんな感じていたと思うよ。
深沼:年齢やキャリアを重ねても、バンドや音楽に対する気持ちは全然変わってないなと思ってて。今、こうして新しいことを始めて、言うなれば、リアル青春なんですよ。そういう気持ちだから、楽しみでしょうがない。新しいバンドで楽しく演奏ができて、いいアルバムが作れて。次はもっと良いものを作りたいって思うし、そういう単純なことに夢中になれることがすごく楽しいと思ってます。
――バンド活動が始まって、KUMIさんはどう感じてますか?
KUMI:今は思うように集まれなかったり、ライブをやったりすることが簡単ではないけど、これからはそういう日々になるといいよね。それから、私にとってこのバンドの魅力の一つは自分がいち歌い手でいられることかな。
深沼:ただ、(KUMIの)ギターの負担は大きいんですよ。LOVE PSYCHEDELICOよりも、やることがたくさんあって、ライブまでに練習しないといけない。歌いながらエフェクターを踏むなんてデリコではないからね。
KUMI:そうね。エレキギターを弾く曲も多いね。リハーサルで実際に自分で足元を操作してみたけど、こんなに難しいのかと。
――11月3日配信の第2弾「絶対」ではKUMIさんがリフを弾いてますね。
深沼:最初からリフをKUMIに弾いてもらおうと思ってました。この曲は、よりこのバンドのことを思って書いた曲です。さっき“青春”というキーワードが出たけど、自分が20代前半くらいに聴いていた音楽の影響が色濃く出てます。僕のデビューはPLAGUESという3ピースバンドで、どっちかと言うとルーツ・ミュージックに近い、60〜70年代のロックを踏襲していたんですけど、20代前半はもっと怪しい音楽もいっぱい聴いてたんですよ。来日公演を見に行って、「え!? こんなに下手なんだ」って思った人たちもいて(笑)。でも、彼らが作っていた音楽から感じた「自分たちでやってみたい、いい曲を作りたい」っていう情熱は、今でも鮮明に残ってるんですね。
――80年代後半〜90年代前半のUKインディーポップやネオアコ界隈には、ヘタウマと言われる魅力的なバンドがいっぱいいました。
深沼:ミュージシャンとして技巧的に優れているわけではないんだけども、だからこそ伝わってくるものがあったんですよ。具現化する力はないけど、「俺はこれが最高だと思う」っていう情熱だけはあるっていう。そういう初心に立ち返ってます。「絶対」は、バンドで、全部生音にして、自分たちが演奏する姿が見える音にしようって思ってから作った曲なので、Uniollaのコンセプトがすごくわかりやすい曲だし、歌詞の主人公もよりはっきりと弱々しく、よりはっきりと儚い感じになってる(笑)。このバンドのキャラクターやビジョンが定まってきたときに書いた曲でもあるので、バンド演奏にしても、歌詞のキャラクターにしても、「よりしっかりと、しっかりしないもの」が表現できてる。確信を持って、ふわふわしてますね。
KUMI:確かにバンドのイメージができてきた頃だったかもね。80年代後半〜90年代前半の女性ボーカルのインディーポップというか。「名前も覚えていないし、アルバムを聞くと割と退屈だけど、この1曲は大好きっていう音楽あったよね?」っていうイメージ。
深沼:そういう人たちのその1曲の破壊力がすごかったんだよね。その情熱みたいなものに自分が当時揺れ動かされていたことを思い出して作りました。ただ、“大人のガレージバンド”なので、アルバムは全曲いい曲にしたいと思ってましたし、20年以上のキャリアで両立させたいなと思いますね。
――ヘタウマじゃないですからね(笑)。音もいいです。
深沼:彼らが輝いていたコアをいただきたいというか、その素晴らしさを自分たちでも一回表現したいところはある。
KUMI:そのピュアさは大事にしたいね。
深沼:20何年やってるから、なおさらだと思うんですよ。もう一回バンドをやるっていう行動の“青さ”みたいなもので、同じような気持ちになれるんじゃないかなと思いましたね。
▲「絶対 (Short Teaser)」
――「絶対」の女性像についてKUMIさんはどう感じましたか?
KUMI:とても魅力的だよね。すごく繊細で、傷つきやすいんだけど、キラキラしたものが好きで、今を生きている。歌うことで光を増やしていきたいというイメージは共感するところもありますね。
深沼:曲ごとに微妙な違いはあるけどね。
KUMI:そうね。もっと図太いところもあるからね(笑)。
深沼:ただ、そういったキャラクターが、歌っていて自然と、無理して演じずともKUMIの中から出てきてて。何曲かやっていくうちに、このバンドのキャラクターがはっきりしていったんですよ。だから、もともとあるのかもしれない。
KUMI:歌っていて自分の中に違和感がないのは、きっとそういうことなんだろうね。
――当時のネオアコやギターポップの中にも、不器用でナイーブだけど、意地っ張りな女の子がいましたね。この2曲が収録されたアルバムがリリースされますが、完成してどんな感想を持ちましたか?
深沼:ミュージシャンがバンドを結成して、それぞれが音を出し、合奏した音を集めたアルバムになってる。ごくごく当たり前のことなんだけど、実はそんなに当たり前じゃなくて。集まって生で演奏して、それがレコードになるっていうのは、その時に起こった奇跡みたいなものだと思うんですよ。コロナがあって余計にそう思った。集まって演奏できただけで楽しいんですよね。いろんな困難を乗り越えて、仲間が集まって、アルバムになって、みんなに聴いてもらえる。キャリアがあって、いまさらかもしれないけど、「バンド演奏ってすごく楽しい!」っていうことが伝わるといいな。いまさらながら「バンドやろうぜ!」っていう気分がすごく出ているアルバムになったと思う。びっくりするほど純粋なものが詰まってる。長年ミュージシャンをやってきて、そういう気分にさせてくれるのがバンドの面白さであり、ある意味、恐ろしさでもあるよね(笑)。長く音楽をやってる人を、こんなにも簡単に青春に戻してしまうんだから。
KUMI:(笑)。そういった意味でも、とてもいいエネルギーが集まった作品になったんじゃないかな。きっと優しいとか、温かいとか、心地いいとか、そういうものを感じてもらえたら。
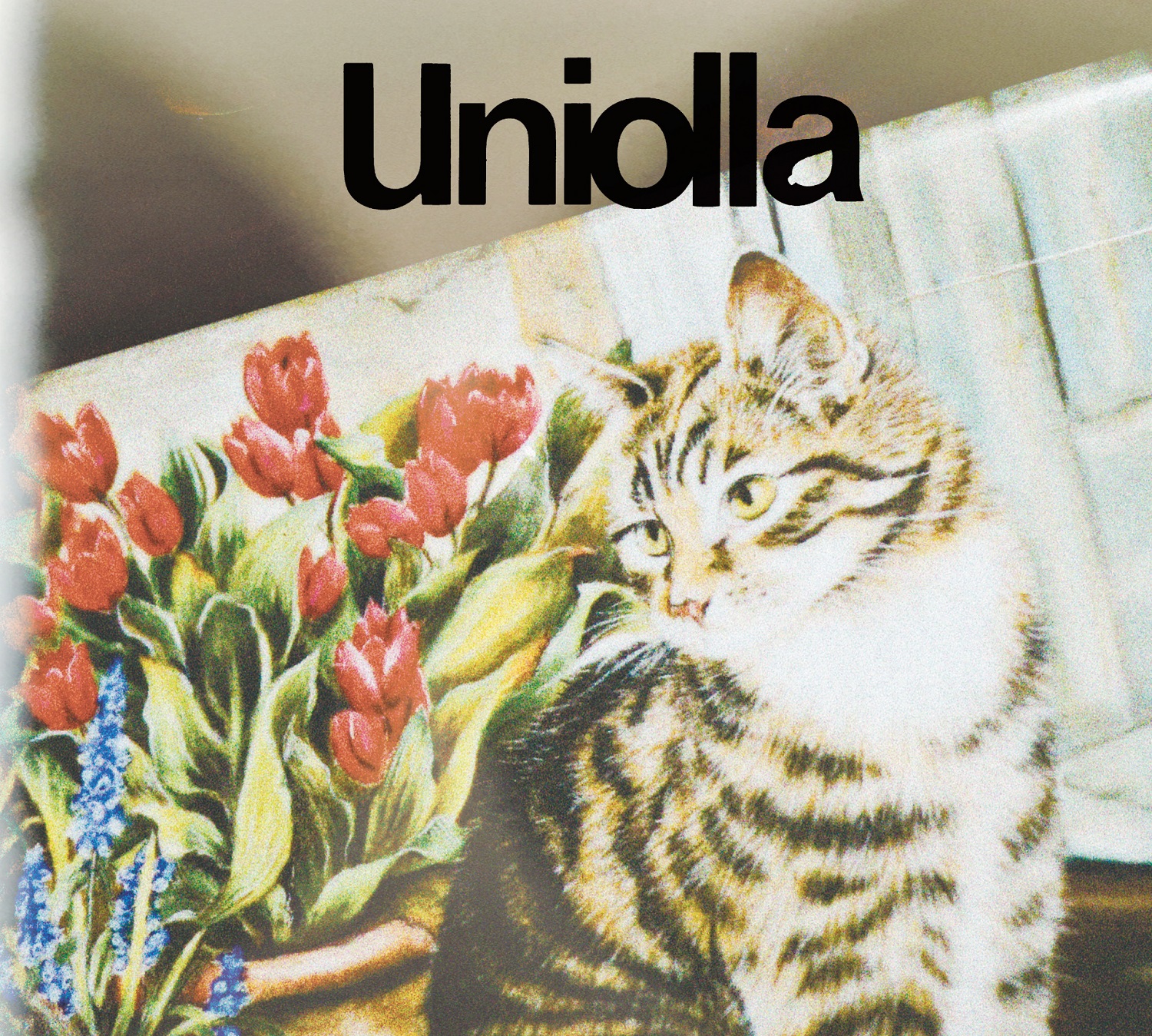
▲スタジオに置いてあったトレーをジャケット写真に起用したという
――できればアルバムは曲順通りに聴いて欲しいですね。特にメロトロンで歌うバラード「果てには」と最後のエールソング「あしたの風」は、この流れで聴くとよりグッと来ます。
深沼:アルバムってドリーミーな存在だからね。
KUMI:1曲目は「A perfect day」で始めようっていうイメージがお互いにあって、私はラストに「果てには」が来て、最後は「あしたの風」にしたかった。柔らかい気持ちになって、最後に力強さというか、生命力を取り戻すというか。情熱をもう一回しっかり持つという感じで終わりたかった。
――バンド演奏が激しさを増すところで興奮しました。
深沼:生命力がありすぎてテンポが速くなるっていう。
KUMI:そうそう。ドラムが最後、走っていっちゃう。まさに青春だよね。みんなに聴いてもらえたら嬉しいな。
リリース情報

「絶対」
- 各音楽サービスで配信中 https://jvcmusic.lnk.to/zettai

『Uniolla』
- 2021/11/24 RELEASE
- VICL-65577 3,000円(tax out.)
ツアー情報
【Uniolla 1st Tour 2021】
- 2021年12月7日(火)開場18:00/開演19:00
- 東京・LIQUIDROOM
- 2021年12月8日(水)開場18:00/開演19:00
- 大阪・BIGCAT
- 2021年12月10日(金)開場18:00/開演19:00
- 愛知・THE BOTTOM LINE
- チケット:前売6,900円(税込、整理番号付き全自由)
- 11月6日(土) 10:00~、各プレイガイドにてチケット一般発売スタート
- ※未就学児入場不可
- ※各会場ドリンク代別途必要
関連リンク
関連商品






























