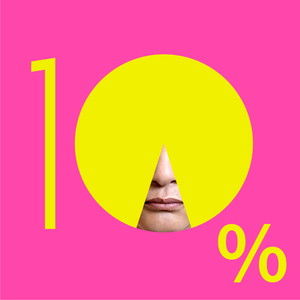Special
<香取慎吾「10%」レビュー>みんなが同じものを見ているわけではなくなった時代における“仲間づくり”のアンセム誕生

あらゆる人の自分事として発信できる自由さ
今年の3月から6月にかけて開催した自身の個展【BOUM!BOUM!BOUM!】を成功させたばかりの香取慎吾だが、2019年10月1日0時、事前告知なしに新曲「10%」を配信リリースし、大きく話題を呼んでいる。
無論この日から消費税率が8%から10%へと変わるタイミングを意識してのタイトルではあるはずだが、楽曲自体は非常にアッパーで軽快な仕上がり。言葉遊びがたくさん散りばめられた歌詞ではあるものの、よく聴かないと一瞬何語で歌っているのかも分からないぐらい、トラックのビートによる楽しさのほうにまずは耳が引っ張られる。その上、サビに明確な意味のある言葉は置かれておらず、誰もが気軽に口ずさめ、なんともユニバーサルな設計のポップ・ダンス・チューンだなと、初めて聴いた瞬間には唸った。しかも、詞中で何度も繰り返される“テンパーセント”というフレーズだけは非常にキャッチーに響き、自然と、世の中の様々な“10%”という数字について感じ取るような仕組みになっているのだ。
増税という社会的なメッセージを固苦しくなく、あらゆる人の自分事として発信できる自由さは、今の香取慎吾の立ち位置ならではだろうし、0時ちょうどにリリースするという仕掛けも配信ならでは。とはいえ、増税に反対 or 賛成というメッセージを打ち出すというよりも、むしろ「一度みんなでいろいろ一緒に考えてみない?」と、テーブルに多様な話題を並べ、ディスカッションに気軽に誘ってくれているかのような親しみをも感じる。
楽曲をサプライズでリリースしてしまうくらいのフットワークの軽さも、現在のデジタル時代においてはとても重要なものだろう。サンプル盤を一足早く音楽関係者が聴き、事前に専門家によるレビューが出て、そこからプロモーションを通じて世に音楽が知られていく、という長らく音楽業界で続いてきた流れすら、配信の時代には変容していく。これからの最初の“レビュワー”はファン=新しい地図でいうところの“NAKAMA”であり、SNSのコアなユーザーの意見がその後の流れに大きく影響を及ぼす。このSNSのコアなユーザーというのも、もしかしたら世の中における“10%”くらいなのかもしれないが。
ともに楽しみながら人々を動かしていく
とはいえ「ネットの自分のタイムラインで熱く話題になっていることでも、ちょっと違うコミュニティに行くと誰も知らなかったりする」そんな経験を、近頃は誰もがしているのではないだろうか?
ご存知の通り、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による新しい地図は、自分たちのチャレンジするフィールドにユーザーも巻き込み、ともにシェアして参加できる、ユーザー参加型プラットフォームとしての活動を拡大させている。そこには、一方的に“エンターテイメントを供給する側としてのアーティスト”ではなく、ともに楽しみながら人々を動かしていく熱量ある伝道師のような愛が感じられ、だからこそ、例えば配信番組にも錚々たるゲストが参加するし、SNSユーザーたちのハッシュタグによる参加も止むことがない。
つまり、「慎吾ちゃん、吾郎ちゃん、剛くん、あんまりテレビで見てないな、なんだかかわいそう……」なんて言う人も世の中にはいるのかもしれない。ただ、今は生配信やソーシャル・ネットワークなど、新興のメディア・プラットフォーム側で楽しみながらチャレンジしているわけで、「本当にやりたいことを伸びやかに楽しめていて最高だなぁ」という風にしか、個人的には見えないのも事実なのだった。香取慎吾がスタートさせたファッション・ブランド『ヤンチェオンテンバール』や、前述の個展について、たとえテレビで大きく取り上げられていなくとも、インターネット上での情報や議論によって人は動き、そこに熱狂は生まれ続けている。
熱く強い“仲間をつくる”ためのアンセム
「ここ数年、地上波テレビをほとんど見なくなった人のパーセンテージってどのくらいだろう?」「新しい音楽は今まで通りたくさん聴いているけれど、今やCDはまったく買わなくなってしまったなという人のパーセンテージって?」など、配信されたばかりの「10%」を繰り返し聴きながら、私自身、いろいろなことに思いを馳せさせてもらった。
そのくらい、ポップな言葉遊びの中に多様なメッセージを忍び込ませつつ、むしろ歌詞のことなど全く考えなかったとしても楽しめてしまう点が、この楽曲の香取慎吾らしいポジティヴな魅力だ。
世の中のすべての人に理解されること、賞賛されることなんて現実的にはないのだから、ならばそのうち10%くらいの支持者である“NAKAMA”とともに強く確かな手応えをともに分かち合いたい!という熱量もこの曲からは感じられる。
香取慎吾が世に放った「10%」は、みんなが同じものを見ているわけではなくなった時代における、熱く強い“仲間をつくる”ためのアンセムと言えるのかもしれない。
Text by 鈴木絵美里
関連商品