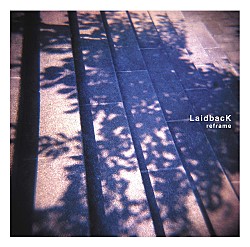Special
井筒香奈江インタビュー「音へのこだわり方で、こんなに音楽って変わるんだ」

ソロ・シンガーとして、また2002年よりLaidbackのヴォーカルとしても活躍する井筒香奈江。2008年にリリースしたLaidbackの2ndアルバム『reframe』が『Streo12月号』でディスクコレクション優秀録音盤を獲得するなどオーディオ雑誌にて高い評価を得たことをきっかけに、自身のソロ作品『時のまにまに』シリーズでも、各誌で優秀録音盤を獲得し、オーディオ界で特に高い人気を誇っている。そんな彼女が、16年来のメンバーとともに2018年にリリースしたのは『Laidback2018』。5月にリリースするとe-onkyo musicハイレゾ配信ランキングやamazonジャズランキングなどで1位を獲得、そして10月にはアナログ盤がリリースされた。オーディオ界ともかかわりの深い彼女が思う、音とオーディオの関係そして音作りへ込めた思いとは。
聴いてくれている人だけのために歌っているかのような空気感が伝えたかった
−−今日はシンガーソングライターとしての井筒さんってどんな方?というところをしっかりご紹介したうえで、プラス、音や録音といったところもフォーカスできたらいいなと思っています。今回、Laidbackは10年ぶりのリリース、録音にも大変こだわられていますね。
井筒香奈江:Laidbackとしては2002年に結成した後、2004年にファースト、2008年にセカンドを出してきました。その後、2011年に初めて私がソロをリリースして。2011年からは年に1枚のペースでソロ作品を出し続けてきて、ここまで6枚のアルバムを出してきました。2011年に出したきっかけは、やはり震災が大きかったかもしれません。その少し前にはリーマンショックがあったりしていて、音楽業界が辛い時期に差し掛かっているなと感じていて。それまでの私はピアノバーやラウンジバーとかホテルのような場を中心に歌っていたんですが、徐々にそういった仕事が無くなってくるのを感じていました。「このままでは歌う場所もなくなり、歌手ではいられなくなっちゃうのかもしれない」というような危機感もあって「だったら自分で何かを作ろう」ということで、震災前からレコーディング自体の計画はしていたんです。そうしているうちに、レコーディングに入る前に東日本大震災があって。その時期、歌の仕事は本当にゼロになってしまったんです。
−−あの時期はいろいろなコンサートやライブも軒並み、中止になっていましたね。
井筒:ええ。そうやって、やることなく家の中にずっといて、テレビもずっと震災関連。自分は東京にいたから被害もほとんど被っていない、だから「辛い」とか「悲しい」とか言ってはいけない。言えない、ですよね。自分より辛い人なんて山ほどいるし、こういう状況の中で辛いなんて言っちゃいけない、と。でも実際は将来の不安とか、みんな抱えていて、本当に辛さを感じていたと思うんです。でもテレビからは「がんばれ、がんばれ」とメッセージが流れてくる。そういう狭間で「自分は、もうどうしていいかわからない」となってしまいました。辛かったですね。で、きっと震災でなくとも、自分と同じように辛いことを辛いって言えない、悲しいことを悲しいって言えない、そういう人は山ほどいるんじゃないかとその時かなり考えました。応援する歌はたくさんあるし、有名な方は被災地へすぐに行ってコンサートを開くこともできたけれど、私なんかはそういうファンの方がいるわけでもない。そんな中、何ができるか……というか、そもそも「何がしたいかな?」と考えた末、「そういう感情を、分かっているよ」と伝えられるような作品を形にしたいと思いました。「がんばって!応援しているよ!」ではなく。 今思えば私が一番欲していたんだと思います。
−−そのままでいい、と、寄り添うような音楽ですね。
井筒:「辛いって言ってもいいし、言えなくてもそばにいるよ」ということが伝わるような音楽を作りたいと、当時のエンジニア、Gumbo Studioの川瀬さんに伝えました。聴いてくれている人だけのために歌っているかのような空気感が伝わるようなもの。すると川瀬さんが「わかりました。では音もそういう風にしましょう」と言ってくださって。出来上がったものは、それまでのLaidbackでの2枚とも、全く音像が違いましたし、本当に、聴き手と私が対峙して目の前で、耳元で歌っているかのような音楽にしていただきました。 もちろん歌い方もかなり意識してチャレンジしてみましたが、そもそも作り方がまったく違ったので「音へのこだわり方で、こんなにも音楽って変わるんだ」と感じたのはその時でしたね。それまでは川瀬さんに任せきりだったけれど、そこからは自分でも「音ってこんなにも面白い一面があるんだ」と興味を持ち始めて。
−−震災以前と以降の変化が本当に大きかった、と。届けたい人というのがより具体的になったともいえるのでしょうか?
井筒:振り返ってみると、最初2004年にLaidbackでのファーストを制作した時は、“誰に届けたいか”という具体像はなど、全くといっていいほど無かったかもしれないです。ユニットを2002年に組んで、それがすごく楽しくて純粋に「これを形にして残しておきたいなあ」くらいの感じでしたから。
−−音質や1音を作ることへのこだわりに気付いたのは震災きっかけの部分も実は大きかったということですね。
井筒:私の中では大きかったですね。それまでは歌うのも洋楽のみでしたが、そこからは、もともと大好きだった70年代の日本のポップスも歌い始めました。やっぱり自分は日本の曲で育っていて身体に染みついているのはそういう歌だし、たとえば鼻歌を歌うと小さい頃に覚えた曲などが出てきますから。同時に、日本語ってとても美しいなとあらためて感じました。比喩なども豊かで、想像のできる歌詞が生まれやすいな、と思います。私は押し付けないあり方が好きなので、荒井由実さん、井上陽水さん、玉置浩二さんなどの詞が、自分のなかでしっくりくるのでよくカバーもさせていただいています。
−−それまでライブでも披露していなかった日本語詞を歌うようになったというのは、かなり大きな転換点かなと思います。
井筒:若い頃ってなんとなく「英語の曲歌っているのがかっこいい」って思っちゃってたのかもしれません(笑)。ジャズのスタンダードはもちろん、70年代のキャロル・キングやジャニス・イアンが大好きなので、ああいった曲は見よう見まねで歌ってました。また、仕事場では英語詞での歌を求められることが多かったのも理由のひとつかと思います。
リリース情報
関連リンク
Text: 鈴木絵美里 Photo: Kumi Watanabe/Mariko Ikitake
音楽の世界にいる時は素直になれたし、素直に楽しめた
−−先ほどもお話しいただいたように、ホテルのラウンジやジャズクラブで歌われていたんですよね。
井筒:そうです。Laidbackを結成するまで、ジャズクラブなどで歌ってきました。でもスタートはすごく遅かったんですよ。そもそも私はインテリアデザイナーを目指して仕事をしていて、音楽を自分がやるというのとは無縁の生活をしていました。でも、同じ職場にいた女の子がオールディーズ好きで、あるライブハウスでアルバイトを始めて。ちょうど自分がデザイン事務所から別のデザイン事務所へと転職する際に「人が足りないから手伝ってくれないか」と誘われまして。ちょうど時間もあるタイミングだし行こうかと向かってみたところ、そこは接客をする子たちがみんな音楽の道を目指しながら働く感じのお店だったんです。で、そこに行くなり課題曲を与えられて自分も歌うようになった、というのがきっかけ。そこでは、お客さんたちもその音楽家の卵である店員さんたちの成長を楽しむ、というちょっと変わったシステムのお店でした。
−−学生時代からずっとジャズシンガーをされていた、ということでもなかったとは意外です!
井筒:ええ。姉の影響で子供の頃はバイオリンも習わせてもらったりしていましたがクラシックだけではどうにも飽きてしまって続けてはいなかった。なので、まさか自分が歌うことになるとは思ってもみなかったし「まあ転職の合間にちょっと手伝いに……」というくらいの軽い気持ちで入って行ったんですが、知り合いのシンガーさんに「やるならちゃんとやらないとダメ!」と叱咤されまして。それで発声なども教えてもらい、気づけばシンガーとしての活動を始めていた。段々とインテリアの仕事ともウエイトが逆転していって、ここまでずっと続けてこれてしまった、という。
−−インテリアデザインの仕事よりも熱を持って臨むようになっていった、ということですね。
井筒:そう。同時に、デザインをやっている時の自分はちょっと天狗になっていたので。わりといい成績を修めてデザインの学校を出たら、すぐにいい仕事も任せてもらえて。でもプライドばっかり高くなっちゃって、転職したら心がポキっと折れてしまった。自分ができると思っていたインテリアのこと,実は全然できないって気づいてしまったのと、音楽を自分でやって楽しみ始めた時期が重なっていたのは、ラッキーだったのかも(笑)。
−−音楽によって救われたし、人生の転機にもなった、という。
井筒:既にその時点である程度、年齢もいっていたけれど、音楽の世界にいる時ならば自分はまだ初心者でいられる。自分と同じくらいの年齢の人のほうが自分よりキャリアがあって当たり前なわけです。だから誰かをライバル視をする必要が全くなかったし、自分より年下の人でも、私のほうが下の立場で当たり前。だからこそ、素直になれたし、素直に楽しめたんです。
−−気負いなくいられたのが音楽の場だったということですね。
井筒:本当に、いい人たちに巡り会えていたのだと思うんですよね。全然歌えない頃から「ここで募集しているよ」って教えてくれる人たちがいたり。Laidbackも、私が勝手に引き合わせて勝手にユニットにしちゃったんですけど、ふたりとも嫌がらずに、もう16年も続けてくれています。でも、プライベートとかも全く別々で、打ち上げとか、3人で食事したこともたぶん数える程度です。でもその距離感が16年こういうペースでできている秘訣なのかもしれない。そうやってなんとか続けて、遂にこのユニットとしても3枚目が出せました。
−−今回の3枚目は、井筒さんがソロ活動を始めてさまざまな変化を経て以降初めて、10年ぶりのLaidbackとしてのリリースになりますね。
井筒:はい。そのソロでずっと作ってきたシリーズも少し気分を変えたい、何か変化を求めていた頃に、今回の新作の一番のキーマンとなるエンジニアの高田英男さんと出会いました。元はビクターでスタジオ長をされていた方で、「日本音楽スタジオ協会」の会長でもいらっしゃる。その高田さんとの出会いがあったことで、今までの音づくりとはまた違うものを、是非高田さんに作っていただけないかとお願いをしたところから始まっています。
−−変化を求めていたところにまた、出会いがあったわけですね。
井筒:実際には、今回のアルバムを制作する3年前くらいには出会っていて、私の音源も聴いていただき感想を頂戴していました。その後、ちょうど私が「次のアルバムをどうしよう」と悩んでいた時期にオーディオのイベントでお会いすることがありまして。何を悩んでいたかというと、もうソロを年に1枚出すというのが当たり前になってきていて、聴いてくださる方もそれを前提に、待ってくれている。でも、どうしてもできなくなってしまって。どうしていいかわからない、どう変わればいいかもわからないから、今年は出さない、と一旦は諦めたんです。でもそうやってモヤモヤしている時にイベントの会場で振り返ったら高田さんがいらっしゃって、思わず「私を録っていただけませんか!?」とお願いしてしまった。「可能でしょうか!」と思いをぶちまけました。……何か、とにかく突破口を求めていたんですね。 私はフリーでやっていますし、本来ならこんなメジャーな偉い方にお願いをできるような立場ではないのですけども、ここが私のまあ……性格ということで(苦笑)。
−−なるほど。つまり“諦めた”とはいえ、どこかでやはり想いが残っていたということですね。
井筒:ずっと悩んでいました。そうしてお願いをしたら、高田さんはとても優しい方で「僕は今フリーだからお受けすることはできるけど、いろいろお金もかかったりするでしょうし、ちゃんと話しましょう」と言ってくださり、そこから始まりましたね。Laidbackのライブも来てくださり「このままでいいじゃない、このまま録ろうよ!」と言ってくださって。
リリース情報
関連リンク
Text: 鈴木絵美里 Photo: Kumi Watanabe/Mariko Ikitake
音楽を最大限に活かしいいものにするための音作りができた
−−今回は乃木坂のソニー・ミュージックスタジオでのレコーディグということですね。これだけの環境で録音するというのは初めてのことだったそうですが、いかがでしたか?
井筒:これまでは個人のスタジオや、お寺、喫茶店などで録っていたものもありました。本当に手作り感あるところで録っていたんです。なので、急にこれだけの環境でやるということで、もう本当に、内臓が全部出ちゃいそうでした。身の丈の生活から突然「六本木ヒルズの最上階に住め」と言われているようなもの。もうどうしていいかわからないから、すごく広いのに隅っこのほうばかり使っちゃう、家賃払えないしみたいな(笑)。最初はそういう感じで、見学に行った時はまったく落ち着きませんでした。「大丈夫かな……」と不安が募るばかり。
−−その環境は高田さんが用意してくださった、ということでしょうか?
井筒:そのソニーの乃木坂スタジオで録らないか、と提案してくれたのは、日本オーディオ協会の方なんですね。エンジニアの高田英男さんと私が録音をするということを聞きつけてくれて、その協会さん側から「ぜひその作品で一緒に何かやらせてもらえませんか」と言ってくださいました。その際、乃木坂のソニー・ミュージックスタジオを使う、というのが条件の1つにありました。そういう流れでしたね。高級なスタジオなので、レコーディング日程は2日間のみ。あれだけすごい環境のなか、しかもその2日間でしっかり決めなくちゃいけない、というプレッシャーを半年間くらい抱えていたので、レコーディングの2か月くらい前にはもうおかしくなる寸前。できないと期待を裏切ってしまう、周りに迷惑をかけてしまうし、しかもその迷惑をかけるメンツがあまりにもすごいから……と、精神的に追い詰められました。でも、スタジオに入り、ヘッドホンをつけ、マイクの前に立ってしまうと、いつも通りになれたのが本当に不思議でした。
−−本番ではリラックスしてできた、と。
井筒:あとあと分かったのは、その雰囲気も含め、高田さんのおかげであったということ。いかにミュージシャンが本領発揮できるかということを第一に考えて、ものづくりや雰囲気づくりをしてくれたので、我々はまんまとそれに乗っかって集中して演奏させてもらえたんです。私は、あのイベントで高田さんにお会いした時の自分の勢いだけは褒めたいですね(笑)。よく言った、と。
−−やはり仕上がりの感じはまったく違いましたか?
井筒:作品を聴いた時に、今まで個人名義で出してきたアルバムとは確かに違うものでした。それは、どちらが“いい”っていうことではなく、コンセプトに基づいた音作り、という意味です。今回はバンドらしさを出すというコンセプトの基、スタインウェイのピアノを使わせてもらって、何もかも最高級の設備のなかでやらせていただいた。関係者はメジャーで活躍されている匠達、そのエネルギーが詰まっているアルバムになりました。音づくりの違いもとてもよく分かり、本当に興味深い一作になりました。
−−本当に凛としていながら、暖かい雰囲気に満ちていると感じました。
井筒:嬉しいです。広いスタジオの静けさや緊張感も、とにかくよく出ていると思います。ピアノの1音弾く音、息遣いなども。でもそれが音音音って音メインなものではなくて、本当に音楽を楽しんでもらうための音づくりだったので。 “音がいいものを作るため”ではなくて“音楽を最大限に活かしいいものにするための音作り”なんだなと。いつもそうですけども、今回もそこは変わらずさらに強めてできたのではないかな、と思います。
−−今後、ご自身の作品をよりどういう方に聴いてほしい等、希望などありますか?
井筒:もう本当に、音楽がお好きな方にも聴いていただければ、と思うんです。 私も元々は普通の歌い手・シンガーなので、音楽を届けたい。Laidbackの1、2枚目や井筒香奈江ソロ名義で出した『時のまにまにシリーズ』の5作とその後に出した『リンデンバウム』という作品もずっと音にはこだわってきて、オーディオ業界の方にも高く評価をいただきました。そんなわけで、今はかなりオーディオの業界にいるけれど、オーディオマニアの業界で言われている感想には小難しい印象もあると思いますし、一般の方が受け入れにくい世界になってしまっているのかもと感じたりしています。今って、オーディオと音楽があまりリンクをしていないような気がしてしまうんです。
−−確かに。オーディオについては、知識が無いと言及してはいけないことのような感じも、少ししますよね。
井筒:でも、私自身がかつてはオーディオのことはわからなかったところからスタートしていますし「いい/わるい」じゃなく「好きか、嫌いか」でもいいと思うので。全然難しくとらえていただかなくていい。良い悪いの判断なんかわからなくてもいいんです、と。でも、たとえば、これまで聴いていた音楽をもっと違う音で聴けるようになって、それが発見や楽しさに繋がったら、より一層その音楽を好きになったりするはず。「こんなところで息遣いをしているんだ!」とか「こんなところで声を出しているんだ」とか。強弱で感情がこもっているんだ、とか。
−−何度も聞いていた音楽のはずなのにこんな音が…!!っていう気づきは、確かにヘッドホン(イヤホン)の違いでもあったりしますよね。何度も聴いていたはずの音楽でも、時代や、自分の状態によっても違いがわかる瞬間があるとは思います。
井筒:オーディオがなかったら音楽は聴けないし、音楽がなかったらオーディオなんてただの箱だし。もっとそこが密接である面白さを、この作品を聴くことで味わってもらえたらいいな、と思っています。このLaidback3枚目では、バンド感、空間、ライブ感を活かせる形に仕上げていただいていますが、録音機材によってもそういう違いが出るし、ハイレゾCD、DSD、アナログレコードというフォーマットによっても違うということが、まず体験して面白がってもらえれば。その上で、やっぱり自分はCDが好き、とかアナログが好きとか、そういう風に楽しく聴ける形を、オーディオマニアだけでなく、普通の音楽好きの方たちにも選んでもらえたら、と思っていたりします。音楽とオーディオの関係が密だっていうことを、音源を通してもう少し伝えていけたらいいなって思います。
−−今後、井筒さんのビジョンなどあれば最後に教えていただきたいです。
井筒:作る側としては、より一層、そういう音作りの部分を疎かにしてはいけないと思っていますね。こだわれる限りのところは十分に凝って、その先どう評価されるかは、もう聴いてくださる方たちにお任せするしかないですから。だからまあ、やるだけやるっていう。10月にはアナログ盤が出ましたが、これまた匠の技が結集されたものです。ディスクユニオンのJazzTOKYOさんが、私のこれまでの作品をじつは一番売ってくれているところなんですが、そこの店長の生島さんが先のCDを聴いて「ぜひアナログをつくろう」と持ちかけてくださったところから、アナログの発売に至りました。それと同時に各社配信も始まっています。是非こちらも、5月に出ているCD(UHQCD)と比べたりしていただきたいです。
 Photo: Kumi Watanabe
Photo: Kumi Watanabe
リリース情報
関連リンク
Text: 鈴木絵美里 Photo: Kumi Watanabe/Mariko Ikitake
関連商品