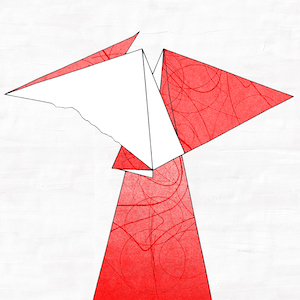Special
<インタビュー>武道館ワンマンを控えるTele、新曲「カルト」を語る――自分自身と向き合った先に見つけた答えとは

谷口喜多朗によるソロプロジェクト・Teleから久しぶりの新曲が届いた。その名も「カルト」。理屈ではなく直感で自分を信じ、Teleを信じろと、この曲は訴えている。〈僕が愛になってやる。〉という力強いフレーズは、アーティストとしてTeleが新たなフェーズに突入したことを証明するかのようだ。6月には初の日本武道館ワンマンも控える彼に、この曲ができた背景を語ってもらった。(Interview & Text:小川智宏 Photo:小野正博)
ツアーそのものに関しては、すごく反省が要所要所であった
――2024年も4月に入りまして。2023年は【祝 / 呪】というツアーで幕を閉じましたが、そこから3か月ほど、どんな心持ちで過ごしてきましたか。
喜多朗:今年の始まり方が、世の中的にあまり幕開けって感じられない始まりだったから、すごい嫌気がさしちゃったなかでのスタートでした。よく考えたら今年の1月2月は、コロナから開放されたことによって目を瞑ってたことのツケが回ってきたなっていう。ロシアとウクライナのこともそうだしガザのこともそうだし、日本が地震大国だっていうことも含めて、そういうことが個人的な人間関係とか生活の部分でもあって、この3か月くらいは結構へこんでましたね。
――でもツアーはすばらしかったじゃないですか。
喜多朗:ありがとうございます。ただ、ツアーとしてはすごくいいものをみんなにやらせてもらったっていう感覚はあるけど、その真ん中に立つ人間としてもっとタフじゃないとなっていう反省はすごいあって。それはフィジカル的な問題とそれに応じたメンタルの問題で、タフであれば乗り切れたことっていうのがツアー中にも何個かあったんです。12月の頭にZepp DiverCityでツアーの追加公演があったんですけど、そこから年末のフェスにかけての1か月はそれを回収していくみたいな感じでした。その12月の追加公演、僕は「葬式」のつもりでやってたんですよ。それは「供養してあげなきゃいけない」みたいなことだったんですけど、なんかこれじゃ供養しきれねえなって。だから、ツアーそのものに関しては、すごく反省が要所要所であったかな。


――その「供養しきれねえ」っていう思いは、この「カルト」という曲につながっている感じがしますね。
喜多朗:そうかも。この曲はタイトルから作ったんですけど……ツアーの後フェスに何本か出るなかで感じたのが、これはもしかしたらあんまりいい響きに聞こえないかもしれないけど、ああいう場におけるすごく儀式的な盛り上がり方のことで。あれを見て「音楽って本当に宗教みたいなもんだよな」と思ったんですよ。たぶん供養する前の、幽霊だった僕はそこにあまり肯定的ではなかったんですけど、カルトならカルトらしくドンと構えてやることが、今僕がやれる誠実さなんじゃないのかなと思って。それでこの曲を弾き語りでぱっと作ったんですよね。
――なるほど。
喜多朗:自分で自分のことを考えたらすごい宗教チックだし、そこは背負っていかなきゃいけないなって思ったっていうのと、他のアーティストを見たときに、僕には理解できないけど、そのコミュニティの中だけで通用したりするっていうことがすごく増えているっていう。それもすごく宗教みたいだと思ったんです。そうなったときに、いわゆるヒップホップとかクラブシーンの界隈にいる人たちと会話して、「僕のスタンスとしてこっち側で友達と仲良くして、そうじゃない側を否定するのは誠実じゃない」と思って。であれば、僕がステージの上で立つ在り方を決めたように、そのカルト化しているJ-POPに対しての答えは僕の中で決めようぜっていう。
――それがこの「カルト」という楽曲である、と。
喜多朗:曲の中で〈君が君に用意してんだ。/ほらカルトなんだよ。〉って書いてますけど、ガーッと信仰していくみたいな感じでアーティストを追いかけている人がいて、そういう人には若い人が多くて、そうなれるということは自分のことをまず全面的に信じているっていうか、絶対的な無敵感があるんですよ。そういう無敵感をもった人と僕は対峙するわけで。ということは、お客さんが僕を信じるというカルトでもあるけど、僕がお客さんを信じているっていうことでもあるのかもなと思って。その鏡合わせのような関係にだんだん気づいていった。だからこれは最終的に自分に対して言っているし、でも僕からしたら小さな神様である、聴いてくれている人に対して言っている言葉でもあるんだと思います。
――そうやって考えていく上で、たとえば6月に武道館でワンマンっていう大きな舞台が決まっているというシチュエーションは影響しましたか?
喜多朗:あんまり考えないようにはしたんですよ。そこがピークになっちゃったら悲しいじゃないですか。でも、やっぱりビビってはいたから(笑)。やるしかないよね、腹くくんなきゃダメだよねみたいなきっかけにはなったし、そのきっかけが必要なタイミングではあったから、いいほうに働いている気はしています。でもすごく最悪(笑)。
――そうだと思う。最悪だけど腹をくくらなきゃっていう。その気持ちはこの曲に出ている気がします。いろいろ歌ってきて〈カルトなんだよ!〉〈愛になってやる。〉って言い切ることって、一見希望のようにも見えるけど、追い詰められて崖から飛び降りてる感じもするんですよ。
喜多朗:少なくとも飛ぶきっかけにはなってる。飛ばなきゃダメなタイミングで飛べたのはすごくいいことだと思いますよ。「カルト」のミュージックビデオは「鯨の子」や「Véranda」を撮ってくれたhamaibaさんに撮ってもらったんですけど、最初はすごく抽象的な案であまりハマってなかったんです。でもその中の1シーンで、撮影スタジオでエアコンの室外機と僕が立っているというカットがあって、「これだよ」ってなって。結局、室外機が50個近く並んでる壁を作ったんです。部屋の中の空気を外に叩き出して代わりに涼しい風を当てるっていうのが、この曲とぶつかった感じがして。ファンが回っているのも飛ぶっていう感じだし、でも回っているから続いていくっていう感じもするし……なんか「俺らは結局室外機なんだよ」って(笑)。世の中からきれいなものを摂取して吐き出していて室内機の面をみんなに見せてはいるけれど、室外機の面もちゃんとあるし、風が吹く感じとかも含めてこの「カルト」っていう曲にも合ってるし、これを出すタイミングの僕にとって合っていたなと思います。
Tele「カルト」 - Music Video
リリース情報
ツアー情報
【Live Tour 2024 箱庭の灯】
2024年6月1日(土) 東京・日本武道館
2024年6月14日(金) 新潟・新潟LOTS
2024年6月16日(日) 宮城・仙台GIGS
2024年6月21日(金) 広島・広島クラブクアトロ
2024年6月22日(土) 香川・高松オリーブホール
2024年6月27日(木) 福岡・Zepp Fukuoka
2024年6月29日(土) 愛知・Zepp Nagoya
2024年7月 9日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside
2024年7月15日(月・祝) 北海道・Zepp Sapporo
チケット一般発売中
https://eplus.jp/tele/
関連リンク
自分にとって必要な曲が必要なタイミングで出てきた

――歌詞では〈僕は愛を待っている。〉というフレーズが、最後には〈僕が愛になってやる。〉って能動的な表現に変わるところがすごくドラマティックなんですけど、これを書いたときの気分はどういうものだったんですか?
喜多朗:もう「仕方がないよ」っていう気持ちですね。愛を待ってもどこにもないんだから仕方ない、僕が愛になってやるしかないよって思ったし、これは自分に対するカウンセリングみたいなものだとも思ってるから、そうやって自分に対して言葉を書いていく中で見えた、きっとどこかにいる僕みたいな人に対しても言ってあげたい言葉っていうのが〈僕が愛になってやる。〉っていう言葉だった。
――うん、だからもうこう言うしかなかった感じがするんですよね。世の中の状況、自分の状況、お客さんというか、Teleの音楽にある種宗教的に向き合っている人々、そのすべてに対してちゃんと答えを出すんだとしたらこう言うしかなかった。
喜多朗:そう、仕方ないよっていう。でも「仕方ない」って僕にとっては全然マイナスな感じではないんです。仕方ない、生きていくんだからっていう。
――サウンドはすごくストレートなロックになってますけど、これはどういうイメージだったんですか?
喜多朗:サウンドイメージは曲を書いた段階からあって。今回、レコーディングを完全に【祝 / 呪】ツアーを回ったサポートメンバーにやってもらったんで、流れ自体はすごくサクサクいきました。なんか、もうそこに必要な音はあったって感じ。このメンバーを集めて叩けば出る音が今必要な音だなっていう感じでした。ツアーでもギュッと高まった瞬間があったし、それを今録らなきゃっていうのがありました。ツアーも楽しませてくれたというか、ライブ終わった後はみんなでわーって飲みに行ったり、遠征先の都市の行ったことのないドンキに行ってみたりして(笑)。そういうのも含めてツアーはすごく楽しかったんです。みんな人間の部分も出してくれたから、それを1個にまとめたかった。よく聴けば結構シンセとかも入れていて、そこは僕の理屈の部分なんですけど、それ以外はもういったんやっとこう、みたいな。
――この、いかにもシンガロングを求めるようなコーラスはどういうことだったんですか?
喜多朗:イントロで迷ってたんですよ。最初はすごくしっとり入ってたんですよね。アコギと歌だけで。そのときはトラックもドラムマシンみたいな音が入ったりとか、複合的な感じで作ってたんですけど、「違うわ」って思って。「人間叫ばなきゃだめだよ、だって僕たち今待ってるんだから」っていう。鳥のヒナもそうだけど、待ってるなら口開けてなきゃだめでしょって。そういう感じ。
たとえば「花瓶」に入れたコーラスは「歌わせよう」っていう気持ち、作為があったんです。それは作ってたときがコロナ禍で誰も声を上げられないっていう感じだったから。だけど、これは声で歌わせようっていう気持ちはさらさらなくて、だから、同じようなコーラスが箇所箇所にまた出てくるんですけど、歌わせようって気がさらさらないくらいギターを鳴らしてもらって、「歌えるもんなら歌ってみろよ」っていう。だから同じように声が入ってるけど、自分にとっては違うんです。

――今「花瓶」と比較してくれましたが、僕は「花瓶」も「ロックスター」も「ことほぎ」も同じことを言おうとしていると思うんです。どの曲も「こういう存在でありたい」という思いのもとに作られた気がする。
喜多朗:ああ。
――でもその願いは現状と乖離してるから、そこをどうにかして丁寧に埋めていくという作業を繰り返してきたんだと思うんです。ところがここに至ってはそういう作業がなくなってる感じがするんです。
喜多朗:ああ、そうですね。今まで見上げてきたものが、今は横並びになってるっていうか。それは音楽的な部分で最初手探りでやったところが、ある程度自分の中で理屈ができあがってきたっていうのもあるし。だからすごい自分にとって必要な曲が必要なタイミングで出てきたような感じがあるんですよね。
――わかりました。そしてこの曲を経て、武道館とツアーが始まっていきます。今回のツアーのテーマはどういうものになりそうですか?
喜多朗:今回は「箱庭の灯」っていうテーマがあって。僕はずっと箱の中にいるなっていう感覚もあるし、箱庭療法という、砂場にいろいろ物を置いていくという治療法があるんですけど、僕はそういうことをやってるなと思ったんです。1枚目のアルバム作ったときに僕のカウンセリングが終わりかと思ったけど、意外と人間っていうのはなかなか安定してくれなくて、僕のカウンセリングは終わらないぞと思って。であれば、これは今話してて気づいたことですけど、やっぱり何か答えを出さなきゃいけないと思ったんです。あと、ライブハウスとかって「ハコ」っていうじゃないですか。でも箱っていうよりは、すごくそこに生態系みたいなのがある感じがしたんですよね。あと、今までは箱の外に明かりを求めてる感じがしたけど、結局中に明かりはあるんだよなっていうことにも気づいたので。そこも含めて来てくれる人と自分が納得のいく答え合わせができたらなって。箱庭の中にいながら、箱庭の外に行きたいっていう気持ちもあるから、それも含めて「自分、さあどうしましょう」っていう。全国各地の箱の中でお客さんに見せてそれに対する反応とやったことによる僕の変化がちゃんと答えになればいいなと思ってます。

リリース情報
ツアー情報
【Live Tour 2024 箱庭の灯】
2024年6月1日(土) 東京・日本武道館
2024年6月14日(金) 新潟・新潟LOTS
2024年6月16日(日) 宮城・仙台GIGS
2024年6月21日(金) 広島・広島クラブクアトロ
2024年6月22日(土) 香川・高松オリーブホール
2024年6月27日(木) 福岡・Zepp Fukuoka
2024年6月29日(土) 愛知・Zepp Nagoya
2024年7月 9日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside
2024年7月15日(月・祝) 北海道・Zepp Sapporo
チケット一般発売中
https://eplus.jp/tele/