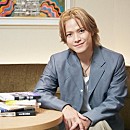Special
THE BACK HORN 栄純単独インタビュー

震災を経て完成した新アルバム『リヴスコール』が出来るまでの日々、栄純から見た各メンバー(山田将司(vo)、岡峰光舟(b)、松田晋二(dr)、自分)の特性、日本のロックやAKB48全盛のシーンに対する見解(SNE48=菅波栄純48プロジェクトの立ち上げ?)、2度目の日本武道館、3.11以降喪失感を持ちながらもサヴァイヴしていく為の提案など、魂込めて語ってくれました。
野性的に動けた3.11直後~世や人生に絶望しても
--2010年9月『アサイラム』から今作『リヴスコール』完成に至るまで、栄純さんにとってどんな期間になりましたか?
菅波栄純:まず『アサイラム』は「THE BACK HORNらしいアルバムが出来た」っていう充実感がすごく強かったんですよね。かなり完成度の高いデモを全員が作れるようになってきたこともあり、それぞれの個性が曲に反映されるようになってきて。また、あのアルバムのツアーは挑戦し甲斐のある曲が多かったんで、演奏面でかなり血となり肉となった。そこで得たグルーヴとか、エモーショナルな音のノリとかを音源にもっと込められないかと。あと、今まであんまりやってこなかった歌詞を先に作ることとか、そういうチャレンジをいろいろやっていこうと思って、去年の頭ぐらいから曲作りに入ったんですけど、3.11の震災があって。
--流れが一度止まったと。
菅波栄純:その日は俺らスタジオに入っていたんですけど、震災があって「あれ、音楽やってる場合じゃないのかな?」ってパッと思ったんですよね。それで、とりあえず2日ぐらいそれぞれ家にいて。で、取材があったんで集まったときに、まずちょっとホッとしたというか。この4人……やっぱりコイツらと一緒にいるとホッとする気がしたんですね。それから「まずは人として義援金を送るとか、足りていないものを送ることが正しいんじゃないか」みたいな話になったんですけど、ライブとかがどんどん中止になったりして。THE BACK HORNとしてどうするか考えたときに、まず自分らの中で決まったのは、ライブは主催者側がキャンセルしない限りは全部出ていこうと。
--実際、早い段階でライブは行っていましたよね。
菅波栄純:それでライブのリハに入ったとき、俺らはミュージシャンだし、やっぱり曲を作ってその曲を配信したりして、チャリティーを形に出来ないかっていう話が(岡峰)光舟(b)から出てきて。で、もうとにかく行動は起こしたかったし、震災以降に新たなアプローチをしたかったのもあって、『世界中に花束を』を手掛けることになるんです。そのときにマツ(松田晋二(dr))が詞先で書いた歌詞と、(山田)将司(vo)が曲先で作ってきた曲があって。ただ、それぞれ飛び抜けて良かったんですけど、結び付くとは思ってなくて。だけど全員の閃きで合体させて、将司が歌ってみたら「これはいける、その場で録ろう」となり、ライブリハのスタジオでノートパソコン広げて録って、すぐに配信することになったんです。
--それで、あれだけ早い時期に発表(2011年3月30日より配信)できたと。
菅波栄純:あの時期はひとつひとつのことに対して野性的に動けた。「このメロディで良いのかな?」とか「この歌詞で誰か傷付く人はいないかな?」っていう葛藤も出てくるんですけど、だけど「いや、今までの自分を信じよう」と思えたから凄いスピードでリリースできて。で、最終的に今回のアルバム『リヴスコール』が出来上がってみると、やっぱりあの時点でいろんな葛藤とか不安とかありつつも、震災に対して野性的にリアクションできたことは、バンドの信頼感を確かめる意味でもすごく大事だったし、音楽の力で聴いた人を元気付けたい気持ちは4人とも一緒なんだという確認もできたし、すごく大事な一歩だったなって。
--『世界中に花束を』を携えて被災地でライブも行いましたよね。
菅波栄純:東北のライブハウスの人たちとかイベンターの人たちとすごく協力できたので。逆に向こうから「THE BACK HORN来てくれたら、みんな元気になるんだけど」って誘ってもらえたり、今まで培ってきた人間関係の中でそんなに多くは語らずとも「ですよね」「やりますよね」ってなったり。事務所もチケット代をすごく安くしたり、『世界中に花束を』の配信ではレコード会社の人たちが、配信リリースするに当たっていろいろあったんですけど「いや、やりましょう」って応えてくれて、誰もが野性的だったんです。俺の言い方だと、野性的に全体が動いていた。
--その野性的なアクションとして敢行した東北ライブは、どんな印象だったんでしょう?
菅波栄純:「力になろう」と思って行ったのに、むしろ自分たちがすごく励まされたなって思った。いろいろありつつもライブに集まってくれて、ひとりひとり泣き顔やら笑い顔やらぐしゃぐしゃなんですけど、「おまえら、音楽を鳴らしてくれよ。悩んでねぇで。それでいいんだよ。それぞれが出来ることをやればいいんだ」って言ってくれている気がして、「よーし!」ってなったんですよね。今年の3月に発表した『シリウス』は、そうした葛藤から「やっぱりTHE BACK HORNらしく命の叫びのような音を込めていこう」って気持ちが変化していくドキュメンタリーになったと思う。
--ちなみに栄純さんは震災後、夏の野音で、自身が手掛けたバックドロップ(ステージ後方の画)について須佐之男命(スサノオのミコト)の話をしつつ「日本人はやられっ放しじゃねーぞ、この野郎!」と言い切ってくれました。やはり悔しさは強くあったんですか?
菅波栄純:最初はありましたね。でも、日本人って今までも自然災害に遭ってきている訳で、本とか読んでみると、過去の人はそういうときに何故か俳句を書いてみたりとか、黙々と家を建て直していたりとか、わぁー!っとなる訳でもなく淡々としているんですよ。無常観っていう考え方で、すべては流れて動いていくもんなんだっていう、ただの諦めとは言えない、もっと深い感覚。留まらないんだって思って生きていくところがあって。日本人ならではの、強固ではなく柔らかい、しなやかな乗り越え方をしている。でも俺はそういう境地までは辿り着いてないし、悔しいとか、悲しいとか、やっぱりすごくエモーショナルになっちゃうし、それはそれで全然あっていいと思ってはいるんですけど、そういうかつての日本人が持っていたしなやかさは、絶対ヒントにはなるだろうなって。
--4人が「やっぱりTHE BACK HORNらしく」って思えたのも、しなやかさのひとつですよね。
菅波栄純:そうなんですよ。音楽ではお腹が膨れる訳でもねぇ。人の命を蘇生させられる訳でもねぇ。でも音楽をやるっていうのは、そういう意味でのしなやかな戦い方のひとつではあると思うんですよ。
--その後もTHE BACK HORNは凄まじい熱量のライブでもって、多くのリスナーを鼓舞し続けています。そこで聞きたいんですけど、そうしたライブや音楽を発信していく側らで、この世の中だったり、人生に絶望することはないんですか?
菅波栄純:ありますね(笑)。でもあるのはしょうがねぇというか、日によって体調が悪かったりするじゃないですか。やけに頭が痛ぇし、腰も痛ぇしって。で、テレビとかでは「これの原因はこれだ。これの対処法はこれだ」ってよくやってるじゃないですか。でもひとつひとつの対処法はそれぞれ効果があるのかもしれないけど、もしかしたらすごく複合的な理由で体調が悪いかもしれない。気温とか、自分が操作できない部分も関わっての体調の悪さだとしたら、結局は「たまたま体調悪い」と思うのが一番良いのかなって。
--それ、いいですね。
菅波栄純:だから、ずーっと「原因は何なんだろう?」って頭悩ませたりするのは辞めたんですよ。「たまたまだな」って思うようにして、淡々と体調の悪さが過ぎていくのを静観しようって。そう思ったら少しラクになったというか。心の調子とかも同じで、自分のせいで心の調子が悪いと思う必要もねぇし、誰かのせいって訳でもねぇし、気温のせいかもしんないし、天気のせいかもしんないし。絶望っていうレベルまで落ちちゃうこととかも、ちょっとしたことの複合的な理由だとしたら、「たまたま今日は絶望してんのかもな」って思う手もあるというか。そう思うようになったら持続性が無くなったかもしれない。絶望の。押し込める訳でもなく、いなすというか。
--その変化は音楽にも影響してる?
菅波栄純:うん。今回のアルバムはネガティブなもんもポジティブなもんも、4人とも吐き出して。それが今まで以上に込められたと思うんですけど、どこかに開放的な感覚もあるというか。THE BACK HORNだから楽観的と言うほどのものではないかもしれないけど、やっぱり少し青空が頭上に広がってる。どんなに絶望的な気分でも、そういう部分も一緒にあるというか。共存してる。
暗黒時代を過ぎても~山田/菅波/岡峰/松田の役割
--ちょっと違う角度からもお聞きしたいんですが、随分昔の話ですけど、栄純さんはかつて彼女と別れてしまった罪悪感からダッチワイフとデートして、それをメンバーに撮影してもらったと話していましたよね。
菅波栄純:名作です。主演映画(笑)。
--完全に病んでるし、狂った行為だと思うんですけど、そうした向こう側に飛んでいってしまう自分というのは、今も生きてはいるの?
菅波栄純:もちろん生きてますね。それも一種の……吐き出しだと思うんですよ。吐き出すことで調整されることはあると思う。息を吸って吐くだけで少しラクになったりするし、会話もそうですよね。だからみんな愚痴言うし、それで何も答えは出ないんだけど、呑みながら話すじゃないですか。それと一緒だって言ったら「え?」ってなるかもしんないけど(笑)、ある意味では一緒なんですよ。音楽に吐き出していくこととも一緒で、巡回させないとハマっちゃうから。ちょくちょく吐き出すのか、溜めて溜めてドカン!って吐き出すのかでは、出てくるものの質感が変わってくるとは思いますけど。ま、俺に言わせりゃ、みんな頭おかしいと思う!
--(笑)
菅波栄純:何かを吐き出してるときって、どんな形であれ多少は狂気が宿ってるんですよね。うっすらと。呑んで「うわぁぁぁぁ!」って泣いている人とかいるじゃないですか。あと、自分もあるけど、呑んで「おめぇのこういうところがムカつくんだよ!」みたいな感じになってるときって、論理的には支離滅裂なことを言っていたりとか、目が血走っていたりする。だから吐き出す行為って狂ってるんだけど、狂ってるから気持ち良いというのもあって。ちょっと枠からはみ出るから気持ち良い。泥んこがあって、服汚したくないと思ってても、一回足まで泥の中に入っちゃったら「どうでもいいや!」って泥だらけになって遊ぶじゃないですか。あれってライブとか、絵を描いたりとかと近い気がしていて。表現って会話とかより一層泥遊び度が高い。もっと根っこのところからドロドロになる。そういうところがすごく引き出されるから、吐き出されるから、ちょっと見た目はマッドな感じなんだけど(笑)、それですごく浄化されていく。
--その浄化作業の効果か、栄純さんはダッチワイフと歩いていた暗黒時代は抜け出したじゃないですか。で、そうした暗黒に身を置いたり、追いつめられた状況にいる中で、その音楽やライブが自ずとヒリヒリしたものになるのは、他のロックバンドも証明してきたことだと思うんですけど。今の前向きで健全に見えるTHE BACK HORNが、ライブの後に4人でカラオケ行っちゃうぐらいの仲良し4人組が、ヒリヒリしたものを創造し続けられるのは何でだと思います?
菅波栄純:多分、4人とも全然違う人間なんですよ。それで、俺たちは一筋縄ではいかない方にどんどん行こうとしている。4人の作詞作曲のレベルも同じぐらいまで高め合って、全員が本気で思ってることを吐き出すということは、完全にカオス状態になるっていうことなんですよ。だって、いくらでもアルバムに収録できる訳じゃないし、だけど全員の想いはそれぞれ100%出てて、それをぶつけ合おうとしたらまとまる訳がないんですよ(笑)。それでも本気で4人が納得するまで突き詰めていくこと自体がマッドっていうか。そのやり方だとヒリヒリせざるを得ない。安心が何もねぇ状況でやってるし、人と何かを新しく作るって基本はそういうことじゃないですか。
--そうだと思います。
菅波栄純:答えの出ない問題……まぁ歌詞を書くこと自体、答えの出ない問題にわざわざ首を突っ込むようなもんだし、4人それぞれの真実をひとつにまとめることだって答えの出ない問題なんだけど、そういうことに取り組むって一番やり甲斐があるなって思いますね。なんだかんだでバンドで他の人とわーわー言いながら作るのが好きなのって、もちろん「なんで分かってくれないんだ?」って思うこともあるんですけど、思いがけないものが出てくるし、そういうヒリヒリした音が最終的に仕上がるのは、そのやり方ならではなので。
--では、今日は菅波栄純単独インタビューなので、他のメンバーがいたらなかなか答えづらい質問をさせて下さい。菅波栄純から見たメンバー3人はどんな風に映っているのか? まずリーダーの松田晋二(dr)から。
菅波栄純:マツは、THE BACK HORNのメッセンジャー。基本的にはスポークスマンだから、実はメッセンジャーの要素がすごく強い。言葉で伝えたいことがたくさんあるとか、元々そういう人なんですけど、今回はそれが歌詞という形に結実してる。今までも良い歌詞書いてたけど、より一層メッセージが伝わってくるし、マツという人間も見えてくるような、それと同時に普遍的であるようなものを書いてきたなって。今作『リヴスコール』の土台になっているのは、マツが書いた『世界中に花束を』と『ミュージック』の歌詞だし、曲を作れる状況がある有り難さとか、ライブができる有り難さとか、そういう音楽やれる喜びみたいなものをもう一回噛み締めよう。その喜びに溢れた音楽を鳴らすことが人の力になる。それが今回マツの辿り着いたメッセージであって、それがあって『リヴスコール』は出来たんですよ。だから本当にあの人はメッセンジャーだなって思う。
--続いて、岡峰光舟(b)。
菅波栄純:光舟は、THE BACK HORNの翻訳家。アイツが入ってくるまでのTHE BACK HORNってドロドロしたスープ、形の固まってない地球みたいなもんで、相当カオティックだったんですね。自分たちの音楽を紹介できる言語も持ってなかったし。でも光舟が入ってきて、「いや、THE BACK HORNってロックでしょ。ロックって言っていけばいいんじゃないの」って俺らが口ごもって言えずにいたことを発言した人で。「THE BACK HORNって抽象的な概念で曲とか作ってるけど、でも単純にライブバンドなんだよね」って翻訳したのもアイツだし。あと、アルバムの選曲でもアイツの意見って面白くて。ちょっと思い入れみたいなものを超越した意見が出てくる。「いや、これ、みんな待ってるから入れた方がいいよ」とか。すごく繋げてくれる人なんだと思う。で、プレイヤーとしてのプライドがあるんだけど、だからこそアーティストとしてというよりは、バンドマンとしてバンドを見られる。
--続いて、山田将司(vo)。
菅波栄純:THE BACK HORNのすべては将司に集約されていると思う。俺、ロックの本質って赤ちゃんの叫び声みたいなもんだと思ってて。ジミヘンのギターとかすげぇ赤ちゃんが泣いてるような音に聞こえるんですよね。そこに近いというか、将司が一番赤ん坊的な生命力みたいなものを持っている気がして。だからアイツの歌も赤ちゃんのような叫び声に聞こえるときがあって、それに勝るもんはないんですよ。そういうTHE BACK HORNの生命力の本質みたいなところ、心臓って言ってもいいかもしんないけど、存在自体がTHE BACK HORNだと思います。そこにプラスして運動神経も良くて。運動神経良い人って実は論理的だと思うんですよ。頭の中で動ける準備が整備されているってことだから。だからアイツは、例えばマツが「なんとなくやりづれぇ」って言っていたら「右手と左手の順番変えてみればいいんじゃない」って気付く。他にも未知数のところは沢山あって、底が知れない人です。
--では、自分ってどんな奴だなって思います?
菅波栄純:まず気分とか感じとかを一番重要視してる。だからすごく流動的なところがあって、今思っていたことが次の瞬間には変わっていたり、喋ってても飛び飛びなんですよ。さっきまで絵の話をしていたのに、気付いたら猫の話になっていたりして、いつもマツとかに「散らかすなぁ!」って言われる(笑)。跳躍しがちな人。でもその分、気分とか感じとかを掴むのは得意だなって。誰かが伝えたいことにすぐピンと来るとか。あと、その場の旬のネタで何とかやりくりしようと思う性格もあって。あんまり理想主義じゃないから、今旬のネタを一番美味しくするにはどうすればいいか考えるタイプかもしれないです。将司に完璧主義な一面があったりとか、マツに理想主義な一面があったりとか、光舟に歴史の文脈を大事にする性格があったりとか、それぞれ素晴らしいと思うんですけど、俺みたいなタイプが入ることでそのすべてが機能しやすくなるんだろうなって。
--では、規模をバンドの話からシーンの話へ広げていきたいんですけど、菅波栄純から見た日本のロックシーンってどんな風に映ってるんでしょう?
菅波栄純:簡単に言うと、めちゃめちゃ面白い。UKやUSのインディーとかもよく聴くし、クラブ系とかダブステップとかもちょいちょい聴くんですけど、その上で俺が思うのは、海外と連動している人はガッチリ連動しているんだけど、日本特有で進化しちゃってるロックが面白い。逆に「超進んでんな」って。J-POPとかJ-ROCKをバカにして“ガラパゴス化”してるって言う人いるけど、それって超進化してんじゃねーのって逆に思う。他の国の人とかみんなマネしたくなるんじゃねーのかなって。それは特に若手の曲を聴いてると思うんですけど、例えば、USのインディーでサイケとかフリークフォークみたいなのが流行ってるじゃないですか。それを日本のロックに変換すると、きのこ帝国とかになっていくんだ!?って。これが日本の力だよなって思う。ニューヨークからパンクが出てきたときに、日本ですぐ反応したアンダーグラウンドの人たちのパンクを聴いても「こうなるんだ?」っていう。だから「ガラパゴス化、バンザイ!」って俺は思っていて。このままガンガン行ったらもっと面白くなっていきますよ。
--それが=シーンの活性化になると。
菅波栄純:そう。それはもう初音ミクのシーンとか、ニコ動のシーンとか、アニソンのシーンとかもひっくるめて言えることだと思う。
SNE48立ち上げ!?~喪失した今をサヴァイヴする為に
--アイドル全盛であるシーンの状況にはどんなことを感じますか?
菅波栄純:SNE48、菅波栄純48みたいなこともやった方がいいかもしれないなって。それの投票1位が菅波栄純になる。俺以外の人もエントリーしていいんですよ。だから他の人が新たに菅波栄純になるかもしれない。楽しそう。「俺が栄純だ、俺が栄純だ」って盛り上がってくれれば。
--(笑)
菅波栄純:AKB48のゲーム感覚って面白い。最近注目している同年代の社会学者で、宇野常寛という人が言っていたんですけど、AKB48ってファンの投票が関係しているから、ファンがアイドルの物語を作っているとも言える。それって「機動戦士ガンダム」の話にも通じてて、ガンダムの中の宇宙世紀っていう歴史があるじゃないですか。ファンがそれに対して「こんなこともあったんじゃないか、あの時代には」とかワーワー言い出して、それを吸い上げてストーリーに戻してる。集合知じゃないけど、ファンがある意味クリエーターになってるんですよね。それは初音ミクにも繋がる話なんですけど、そういうのってバンドのシーンにはないじゃないですか。だからバンドマンでAKB48好きな人って多いし、俺らから見るとすごく面白いんですよね。あのシステムとか。
--じゃあ、SNE48も出来ることならやってみたい?
菅波栄純:やりたいですね。それ、エントリーしてもらえますか?
--分かりました(笑)。ちなみに誰が投票するんですか?
菅波栄純:THE BACK HORNのファン。
--そんなの、この栄純が良いってなるに決まってるじゃないですか。
菅波栄純:しょうがない。
--ゲームとして成立してないじゃん(笑)!
菅波栄純:今まで俺がやってきたんだから、それぐらい俺が有利じゃねぇと。食いっぱぐれる。
--話を戻します。では、そうした音楽シーンの中でTHE BACK HORNはどう在りたいと思います?
菅波栄純:THE BACK HORNって俺のイメージだと、昭和の男が未来都市にタイムスリップしたような異物感があると思っていて。それを昭和だけじゃなく、江戸時代の人とか、奈良時代の人とか、縄文時代の感覚、倭国ぐらい昔まで拡張していって、この日本で生きてきた人たちの記憶みたいなものが全部入っても面白いと思うんですよ。仏教的な要素とか、そういうものを取り込むことで異物感は研ぎ澄まされると思っていて。あと、古くはクラシックからこの先生まれてくる音楽の流れ中にTHE BACK HORNはあっていいと思うから、ブルースの匂いがするとか、今作で言えば『星降る夜のビート』はファンキーな感じがあるとか、そういう俺らがリスナーとして聴いてきた音楽の文脈と接続されているものもやっていきたい。異物感と、ちゃんと地に足ついている感じと、そういう相反したコンセプトを持っていいと思ってます。一見カオスなのに成立してるとか、カオス過ぎてシンプルとか、そういうバンドで有り続けたい。
--今の話はそのままニューアルバム『リヴスコール』にも当てはまると思うんですが、自身ではどんなアルバムに仕上がったなと思いますか?
菅波栄純:明らかにロックだなと思いました。歌も含めて演奏的にロックなグルーヴを今までより入れられた気がしていて。なんだかんだ言ってついつい体が動くとか、そういうことって最重要だと思うんですよ。ロックとして。それはここにあるなと。あと、俺はそう思わないけど、世の中的に「どんどん暗い時代になっている」という解釈があるとしたら、そういうときにこそロックって“踊れる化”していくから。他のバンドのライブとか観てても、みんなどんどんグルーヴィになってるし、直接的に踊れる感じじゃないバンドでも、音の絡め方がうねりのある感じにどんどんなっていて。THE BACK HORNもそうだと思うし、今回は腰が動くもの、よりグルーヴィなものになっている。で、そのグルーヴの上にメッセージがあって、4人が火花を散らしている。
--また、今作には『ミュージック』という曲が最後に収録されています。個人的には、THE BACK HORNなりの『上を向いて歩こう』なのかなと思ったんですけど、実際には……
菅波栄純:それいいな。それっすね! 他のところでも言っていこう(笑)。
--早速、流動的なところ出ましたね。
菅波栄純:(笑)。でもそれだわ。これは自分たちにとって大事な曲という側面もあるんですよ。「あ、俺らは音楽をやっていくんだな」っていう覚悟みたいな。で、俺らは「音楽を鳴らし続けるから」って呼び掛けている感覚があるんですよ。空気と溶け込むこともできるとか、それしか聞こえなくなるような強烈な体験をさせることもできるとか、音楽には流動性があって、言ってみればそれは柔らかさだと思うんですね。そういう音楽の柔らかさがすごくメロディとか音に出てるなと思っていて。マツの歌詞もすごく視点が優しいし、そういう曲を『ミュージック』って名付けられたのは、本当に良かったなって思う。
--『リヴスコール』リリース後には全国ツアーの開催も決まっています。そして、その最終公演は2008年6月以来2度目の日本武道館です。武道館で再びやりたい気持ちはずっとあったんですか?
菅波栄純:ありましたね。1回目の武道館はステージに登ってライブやってから「こんなに武道館って良いんだ」って思ったんですよ。それまでは「武道館? 通過点ですから」みたいなことを言っていたのに、大泣きして。だから今回は素直に「楽しみたい!」と言います(笑)。あと、武道館だから総合的な選曲にはなると思うんですけど、そう言っても『リヴスコール』のツアーファイナルという意味合いも強いし、このアルバムはライブでめっちゃ響きそうな曲が揃っていると思うから、本当に武道館でやるのが楽しみ。
--では、〆に入っていきたいんですが、これから俺たちはどこへ向かっていくんでしょうね? 3.11があり、原発の問題もあり、重い空気はだいぶ薄れた中で人々は生活するようになりましたが、それでもどれだけ寿命を削られてるか分からないようなこの国で、どう生きていったらいいと思いますか?
菅波栄純:うーん…………まず思うのは、行方不明の人がいっぱいいるじゃないですか。あれって辛いだろうなって。亡くなってしまったと分かってもラクなことは何もないけど、待っている側としてはまた別の苦しさがすげぇ続いていく。そういう意味では凄まじい状況が続いている感じがするんですけど、あれ以降、自分の気持ちも迷子になったり、行方不明になったりしているなと思っていて。それこそ表面的には、忙しいからとりあえず目の前のことに向かって頑張ってるだけなんですけど、ふと我に返った瞬間にポッカリ……あったはずのものが無くなったような、何か無くしたんだけど何を無くしたんだかよくわかんねぇような、行方不明の気持ちっていうのがある。
--それってどう埋めればいいんでしょうね。
菅波栄純:帰る場所をいっぱい持っていたら少しラクなのかなと思っていて。俺の話で言えば、実家が潰れちゃったんですよ。で、福島には母ちゃんしかいねぇんですけど、母ちゃんももしかして引っ越すかもしれないじゃないですか。そうすると、事実上、故郷に帰る場所が無くなってしまう。だけど、俺が思うのは、人と人との間に帰る場所はあると思えばいいのかなって。友達に会ったときに「ただいま」って思えばいいのかなって。母ちゃんと会ったときに「ただいま」って思えばいいのかなって。THE BACK HORNのメンバーとかスタッフと会ったときに「ただいま」って思える、そういう自分の中の帰る場所を確保していった方がいい。ただ、それがたったひとつだと俺は辛いと思う。これからの世の中は。そこで少なからずひとつ俺らが用意できるのは、THE BACK HORNの音楽という場所。それを帰る場所だとちょっとでも思ってもらえたら光栄だなって。ライブから帰るんじゃなくて、ライブに帰ってくる気持ちで来てほしいというか、「ただいま」と思って来てほしいというか、そういうことを思ったりするんですよね。
--なるほど。
菅波栄純:別にネット上で顔知らない人同士でも、すげぇ趣味が合うサークルみたいなものでも、それが帰る場所になってもいいと思う。だって、今やネット上の繋がりが多少は誰かの心の支えになったりするし。例えば将棋が大好きだったら将棋好きの仲間を探して、それがすげぇピンチになったときにセーフティーネットになる可能性はある。本当に思いがけない事態になったときに、その将棋のサークルが家族になる可能性もある。それぐらい帰る場所や家族というものを拡張して考えていってもいいよって俺は提案します。「いや、そうじゃねぇよ」って思う人もいていいと思うけど、心弱めの人間の代表として言えるのは、自分の経験上言えるのは、そういうことはこれからの世をサヴァイヴしていく為に必要かなと思ってます。
関連商品











![(V.A.) THE BACK HORN Ken gibkiy gibkiy gibkiy 氣志團 cali≠gari GRANRODEO 鬼龍院翔「TRIBUTE OF MUCC -縁[en]-」](/scale/common/80x80_img_noimage.png)

![(V.A.) THE BACK HORN Ken gibkiy gibkiy gibkiy 氣志團 cali≠gari GRANRODEO 鬼龍院翔「TRIBUTE OF MUCC -縁[en]-」](/scale/common/250x250_img_noimage.png)