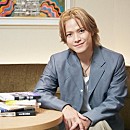Special
【Live Hackasong 参加企業インタビュー】ネストビジュアル

360VR、体験型インタラクティブ、HoloLensなどの企画制作を行うネストビジュアル。今回、Cip×ビルボードによる第二回ハッカソン【Live Hackasong】に参加する。今回、ネストビジュアルが提供するのはMicrosoft社のHoloLensだ。新たなインフラになり得る存在として現在注目されているMRデバイスのHoloLens。ネストビジュアルでもいくつかアプリの開発や研究が行われている。
MRの可能性、そしてハッカソンに期待することについて同社で代表取締役を務める植山耕成氏、宮崎隆二氏、高橋睦実氏にインタビューを行った。
MRはインフラになり得る
--今回、HoloLens https://www.microsoft.com/ja-jp/hololens
を使った新しいアプリ開発として、参加チームを募集されています。HoloLensとは、どんなデバイスですか。植山耕成(代表取締役):マイクロソフト社が開発したMR(Mixed Reality)のデバイスです。2016年3月にアメリカとカナダで開発者抜けに発表され、日本には2017年の1月に開発者向けに提供がスタートしました。
--VR(仮想現実)と、MR(複合現実)の大きな違いはなんでしょうか。
植山:VRは仮想空間に入り込む体験です。なので、どこにでも行けますし、誰にでもなれ、時間も飛び越えることができる特別な体験だと言えるでしょう。最終的には、人間が死んでも脳だけが残り、バーチャルリアリティではなく、それがリアルな世界としてずっと生き続けることができるような世界になるのではと思っています、一方でMRは、現実の世界も見えながら、仮想を重ねることができるというものです。
--AR(拡張現実)との違いはなんでしょうか。
植山:現実の世界も見ながら、仮想を重ねるという意味ではARと同じです。ただ、MRはデバイスにセンサーが付いているので、自分がいる空間を認識することができます。例えば、今この部屋でかけた場合は、どこに壁があり、床があり、そしてテーブルがあるかの位置や距離を認識することができるんです。そして、今僕らがMRコンテンツを制作するために使っているのがMicrosoft社のHoloLensです。これには Windows10のOSが入っているので、このデバイスがパソコンになります。ジェスチャーや声で検索もできますし、Wi-Fiと接続できるので遠隔地とのコミュニケーションも可能です。なので、VRのような非日常を体験するような特別なエンタテインメントではなく、MRはインフラになり得ると考えていて、数年以内にこれを付けながら生活し、仕事をする日が来ると思っています。iPhoneが発売されたのは2007年なので、今年でちょうど10年。そろそろ、新たなインフラが生まれても良い時代ではないでしょうか。
--御社がHoloLensと出会われたきっかけはなんですか?
植山:この会社を設立したのは3年半前の2014年です。その頃から世の中にVRコンテンツが生まれはじめました。僕らも、実際VRゴーグルを付けて実際に見た時に映像の革命だと思いました。今まで16:9の平面の映像しか見れなかったのが、全天球の球体の中に自分がいるというのは初めての感覚でしたから。さらに360度の映像の中にいながらインタラクティブもできる。その感覚は、本当に革命が起きたと思ったので当社でも開発に取り組むことを決めました。VRやAR、MRという分野はまだ色んな情報が氾濫しているような状況です。ただ、MRはVRと違った方向性を感じましたし、より大きいマーケットを感じたので、昨年アメリカの知人を通じて購入しました。
--御社でも既にアプリを開発されていますね。
植山:まだ自社開発の段階ですが、3つのアプリを作りました。まずは使う側も楽しめる内容が良いのではと思い、Voice Holder」、「Holo Tones」、「JK Bazooka」の3つを作りました。このアプリの中には、様々な技術が詰まっています。
宮崎隆二:まず、「Voice Holder」は、自分が発した言葉を具現化して空間に散乱させることができるというものです。このHoloLensには左右にマイクが2つずつ付いているので、それを使って音声認識をし空間に表示、それをさらに音声で上下に移動させたり、削除したりすることができます。Microsoft社からHoloLens用にSDKと呼ばれるツールキットが配布されていて、音声認識をアプリに取り込むためのキットも公開されているので、コードを読み取って解像し、部屋のどこにでも“言葉”を飛ばせるようなアプリを作りました。
VoiceBuilder from Nest+ Visual on Vimeo.
宮崎:「HoloTones」は、空間的に音を配置して空間音響を体感できる音楽アプリです。空間音響というのは、右で鳴った音は右のヘッドフォンから音が聞こえて首を動かすと、音も動くというものです。なので、救急車のドップラー効果も空間音響の技術を使って再現することが可能です。音の差し替えも可能ですし、シェアリングもできるので、もう少し改良を加えれば4名で1つのアプリを起動して離れた地点にいながらにして同時にセッションをすることも可能です。
HoloTones from Nest+ Visual on Vimeo.
--今後、MRはどのような分野での活用が考えられそうでしょうか。
植山:今は分かりやすいようにこういったゲームアプリを制作していますが、建設業や都市開発、不動産、あとは機械工学での活用が考えられると思います。例えば、熟練工ではない人に対して指示を与える際に、このHoloLensを通じて指示し、声で伝えることに加えて、空間上に数字などを表示させることで、熟練工と同じ作業ができるようにしたり。他にも、エレベーター点検や手術のシュミレーションなど、様々な活用が考えられるでしょう。Microsoft社自体も発表している通り、MRはまずBtoBから浸透していくと思います。教育分野とも非常に相性が良いので、今タブレットを使った授業が増えていますが、MRデバイスが配布される時代が間もなくやってくると思います。
宮崎:現実に見えないものを見せることができるのもMRだと思います。例えば、運転中の車のエンジンだったり、マンションが建設される前の空き地にマンションのホログラムを見せたり。なので、建築、医療、教育の分野と特に相性が良いと考えています。
植山:拡大したり、内部を見たりすることも可能なので、建築の分野であれば、クライアントと一緒に新しく建設予定のマンションを見るだけでなく、細部を拡大して表示したり、マンションの内部を見ることもできます。ありとあらゆる分野での活用が考えられるのではないでしょうか。
宮崎:MRの醍醐味は、現実空間を認識するスペーシャルマッピングにあります。壁を壁として認識したり、テーブルをテーブルとして認識したり。なので、ミサイルを床に打っても壊れないけど、壁に打つと壊れるというような現実世界の情報を反映させることができる強みがあり、だからこそインフラになる可能性がある技術だと考えています。
開催情報
【Live Hackasong】
アイディアソン
日程:2017年11月11日(土) 9:30開場 10:00~12:00
会場:ビルボードライブ東京
ハッカソン
日程:2017年12月10日(日) 10:00~18:00
会場:慶應義塾大学三田キャンパス内g-sec
※各チームの中間発表も行います。
最終発表&表彰式
日時:2018年1月30日(火)
会場:ビルボードライブ東京
参加受付(締切:2017/10/15): http://www.billboard-japan.com/hack2017
関連リンク
HoloLensのコンテンツ作りを体験してもらえれば
−−今回のハッカソン【Live Hackasong】では、参加者に対してどのような技術が提供されるのでしょうか。
植山: このHoloLensをお貸し出ししますので、HoloLensのコンテンツ作りを体験してもらえればと思います。
−−前回のハッカソンは「ライブ体験の拡張」をテーマに開催し、ライブのVR体験や、ライブを受動的に聴くだけではない新たな体験といった切り口の作品が発表されました。今回は「エンタテインメント体験の拡張」ですが、MRを使ってどのような開発が考えられそうでしょうか。
宮崎: エンタテインメントの分野で言うと、例えばMRは遊園地のアトラクションなどに非常に相性が良い技術だと思います。例えばアーティストの身振り手振りに合わせてホログラムを表示させたり、アーティストの前にCGを映し出したり。その空間をみんなで共有することも可能です。
−−今回のハッカソンに参加される1→10はインタビューで「ハッカソンに参加する時に、いつも審査基準としているのは「不自然さと手続きの煩雑さがないか」だ」とおっしゃっていました。
植山: そういう意味でもMRは、ハッカソンに適しているかもしれませんね。今、発表されているHoloLens以外にもこれから様々なデバイスが生まれるでしょうし、軽量化され、安価になっていくと思いますが、スマートフォンやPCに替わるデバイスになると思います。なので、今までスマートフォンやパソコンを持ち歩いていたという煩わしさから解放されるという意味で煩雑さは減りますし、間違いなく必要不可欠な存在になると思います。
−−MRが浸透するために必要なことはなんだと思われますか。
宮崎: BtoCとBtoB、それぞれ課題は異なると思います。BtoCの場合は、やはり現状のHoloLensにある小型化、軽量化、価格が一つの課題になると思います。そこが改善されれば、一気に広まるのではないでしょうか。
高橋睦実: 私は日頃メガネをかけていますが、今のHoloLensはメガネの上から掛けないといけないので傷が付いてしまって危険です。なので軽量化されるとともに、メガネと一体化されればより使いやすくなるでしょうね。
宮崎: 一方、BtoBで浸透するかどうかは費用対効果にあると思います。例えば、パイロットの訓練をするためには1回の訓練に数百万円のコストがかかるそうです。ですがHoloLensを使えば、一度コンテンツを作ってしまえば、ほぼ無料で訓練することができます。車のショールームなども同じですよね。なので、今までかかってきたコストを下げる為のソリューションとして提供することができれば、浸透していくと思います。
−−今回のハッカソンに期待することはなんでしょうか。
植山: VRの企業であるOculusがFacebookに買収されて、まだ3年しか経っていません。さらにMRで言うと、ようやく今年、日本でMRのデバイスも手に入れることができるようになり、まだまだこれからです。当社としてもハッカソンに参加するのが初めてです。今回のハッカソンを通じて、新たなMRのコンテンツを一緒に作れることを楽しみにしていますし、面白いアイディアが生まれたら、是非ハッカソン以降も一緒に開発を続けられればと思っています。
開催情報
【Live Hackasong】
アイディアソン
日程:2017年11月11日(土) 9:30開場 10:00~12:00
会場:ビルボードライブ東京
ハッカソン
日程:2017年12月10日(日) 10:00~18:00
会場:慶應義塾大学三田キャンパス内g-sec
※各チームの中間発表も行います。
最終発表&表彰式
日時:2018年1月30日(火)
会場:ビルボードライブ東京
参加受付(締切:2017/10/15): http://www.billboard-japan.com/hack2017
関連リンク
取材:高嶋直子