Special
「多くの人に届くように願いを込めて切磋琢磨するだけで充分」― 小林武史 インタビュー

1996年に公開された岩井俊二監督の映画『スワロウテイル』の劇中バンドとして誕生したYEN TOWN BAND。20年という時を経て、ニューアルバム『diverse journey』をリリースし、9月2日には京都市交響楽団と共演を果たす。YEN TOWN BANDのメンバーでありプロデューサーである小林武史に、この20年間で大きく変化した音楽の聴き方や、ヒットについて話を聞いた。
過去のCHART insightについてのインタビューはこちらから>>>
音楽が流れる場というのが多様化してきましたよね
−−小林さんは、日頃アーティストをプロデュースするのか、楽曲をプロデュースするのか、どちらを意識されていますか。
小林武史:その時の僕の立ち位置にもよりますね。たとえば「小林さんに好きにやってほしいんです」と言われれば、楽曲や作品に寄った形でプロデュースします。でも一曲だけ依頼されたとしても、このアーティストが今後どういうところに向かおうとしているのか、なぜ僕に連絡をしてきたのかということも聞くようにしているので、その場合はアーティストを意識しながらプロデュースしていきます。
−−私達は、楽曲の浸透度を測るためにセールス、ダウンロード、ストリーミング、ラジオ、Twitter、ルックアップ、YouTube、GYAO!といった8種類のデータを合算してチャートを作っています。日頃、音楽チャートはご覧になりますか?
小林:今は全然見ていません。経済という観点から音楽ビジネスを発展させていくためには、チャートを見て切磋琢磨していくべきだと思います。でも「この曲で、どれだけファンを獲得できるか」って思いながら作るのは、ちょっと違うんじゃないでしょうか。1万人のファンを作るんだって思って曲を作るより、多くの人に届くように願いを込めて切磋琢磨するだけで充分だと思っています。それに最近、音楽が流れる場というのが多様化してきましたよね。例えば、友達同士の間にも小さなメディアがあって、そこで音楽をレコメンドし合ったり。なのでセールスやダウンロードなど色んなデータをどれだけ数値化したとしても、メディアが入り組みすぎてチャートを作るのが難しい世の中になってきた気がします。
−−たしかに、昔のようにマスメディアを通じて流行を知るのではなく、SNSによって様々な人の意見を聞いたり、発信できたりするようになった結果、全員が共感できる「ヒット」というのを定めづらくなってきました。ただ、やはり今 最も世の中で聴かれている曲を表す指標というのは必要だと思います。そして、そのチャートを見て新しい曲と出会い、もっと音楽を好きになってもらいたいなと思っています。
小林:でも、新しい音楽と出会う機会はチャート以外にも沢山ありますよね。レコメンド機能が付いたサービスも沢山ありますし。
−−たしかにレコメンド機能があれば、より自分の趣味にあった曲を薦めてもらえますね。小林さんは、日頃どのように音楽を聴いていらっしゃいますか。
小林:一番多いのはアナログですね。
−−YouTubeを見ることはありますか?
小林:ありますよ。昔はレコード屋さんやCD屋さんに行って一枚ずつ探していましたけど、今は便利になりましたよね。大きい網をかけておいて、自分に引っかかったものだけをピックアップしていくみたいに。
−−YouTubeをきっかけに音楽と出会う人は、とても増えてきています。
小林:でもYouTubeで見た後、きちんとした音質でも聴いてほしいと思いますね。箱鳴りするくらいのスピーカーで聴くと、全然違うということが分かると思いますから。僕自身は、新しい音楽をどんどん知りたいというより、音楽を情報としてではなく“音”として聴きたいという考え方に変わってきました。音って、人間や楽器が媒介者になりながら嘘のない響きを伝えることで、人の愛しさのようなものが伝わってくるんですよ。それはたとえ生のライブではなくレコーディングで加工したとしても、きちんと伝わってきます。だからパーティーやその場を盛り上げるための道具として音楽を聴くのではなく、“音”を聴くために“音楽”を聴きたいし、そういう音楽を残していきたいと思っています。耳障りの良い音楽ばかりだと面白くないですしね。人間だって、見栄えが良くて人当りが良い人ばっかりだったら、どう思います?
−−面白くないですね。
小林:そうですよね。「面倒くさいから」という理由で、見たくないものに蓋をしたり、画一的で分かりやすい人ばかりになったら、すごくつまんないですよね。それに、こういうチャートとは無縁で活躍しているアーティストって、世の中にいっぱいいますよ。例えば、地方にも面白いものばっかり上演している会館も沢山あります。想いを持って活動しているアーティストをピックアップする目利きのセレクターがいて、その音楽がその街の日々の暮らしに溶け込んでいって。そんな街に住んでいる人は幸せですよね。聴く力もどんどん鍛えられていきますから。そしてミュージシャンも、地方の会館やライブハウスなどを回っていくことで、コミュニティが生まれていったりするんですよ。そういう交流を、SNSが助けてくれて。それって、すごく良いサイクルだなと思います。
−−7月には宮城県石巻で、【Reborn-Art Festival】のプレイベント【Reborn-Art Festival×ap bank fes】を開催されましたね。
小林:Reborn Artには、「生きる技」という意味を込めています。海の命があって、漁業があって、山や自然から循環するエネルギーがあって。そんな中で僕たちは生きていて、そういう循環を大切にしないといけない。会場となった石巻は、東日本大震災以降に一旦停止のボタンが押されたようなところです。5年経って表面的には綺麗になったかもしれませんが、内面にはすごく複雑なものを抱えたままです。僕の中のこのフェスのテーマは“出会い“なんですが、こんな場所だからこそ新しい出会いが起こり得ると思いました。地方って、経済や合理性から置き忘れられがちなんですよね。でも、実は地方にこそ本質が宿っている。都会でキラキラ光っているように見えるものって、勝てば官軍のような単なる合理性だけだったりしますから。でも労働=対価だけではないモラトリアムのような状態の人が、生きるとはどういうことなのかを探していく、そんな中で様々な出会いが起こるフェスにしたいと思っています。だから、何万人のためにこの音楽を作るって計算しているようなアーティストは呼びたくないし、生きるということのために、自分がやっていることを持ち寄ったフェスにしたいと思っています。経済を発展させるための合理的な社会には、以前からすごく危機感を感じていて、YEN TOWN BANDもそんな危機感から生まれたんですよ。
- < Prev
- 音楽の共振や共鳴、表現の可能性を捨ててしまうのって、すごくもったいない
- Next >
公演情報
【京都岡崎音楽祭「OKAZAKI LOOPS」前夜祭−SYMPHONIC EVOLUTION SPECIAL− YEN TOWN BAND ORCHESTRA】日時:平成28年9月2日(金)19:00開演(18:00開場)
場所:ロームシアター京都 メインホール
出演:
YEN TOWN BAND
Salyu
藤巻亮太
京都市交響楽団(管弦楽)
広上淳一(指揮)
チケット情報:オフィシャルfaceboookにて
【京都岡崎音楽祭 OKAZAKI LOOPS】
会期:2016年9月3日(土)、4日(日)※9月2日(金)前夜祭開催
会場:ロームシアター京都、平安神宮、みやこめっせ、岡崎公園、京都国立近代美術館、京都市美術館
INFO: http://okazaki-loops.com/
リリース情報
diverse journey
- YEN TOWN BAND
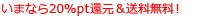
- 2016/7/20 RELEASE
- [初回限定盤[CD+DVD] :UMCK-9852 定価:¥ 4,536(tax in.)]
- 詳細・購入はこちらから>>
- [通常盤[CDのみ]:UMCK-1547 定価:¥ 3,240(tax in.)]
- 詳細・購入はこちらから>>
- [アナログ:UMJK-9064 定価:¥ 4,104(tax in.)]
my town
- YEN TOWN BAND
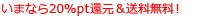
- 2016/6/22 RELEASE
- [初回限定盤[CD+DVD] :UMCK-9840 定価:¥ 1,620(tax in.)]
- 詳細・購入はこちらから>>
- [通常盤[CDのみ]:UMCK-5601 定価:¥ 1,080(tax in.)]
- 詳細・購入はこちらから>>
- [アナログ:UMJK-9061 定価:¥ 1,620(tax in.)]





























103