Special
フォール・アウト・ボーイ 来日インタビュー

無期限の活動休止宣言した2009年から約4年後にリリースされた『セイヴ・ロックンロール‐FOBのロックンロール宣言!』で奇跡のカムバックを果たしたフォール・アウト・ボーイ。リリース後にはアルバムを引っさげた大規模なワールド・ツアーを行い、2014年夏に行われたパラモアとのジョイント・ツアーの終了直後に新曲「Centuries」を突如公開。そして大ヒットディズニー映画『ベイマックス』のために書かれた「Immortals」、「American Beauty/American Psycho」と立て続けに新曲を発表し、2015年1月に待望のニュー・アルバム『アメリカン・ビューティー/アメリカン・サイコ』をリリース。アルバムは、米ビルボード・アルバム・チャート1位を記録した前作を上回るセールスで再び全米1位を記録した。異例の大ヒットとなった最新作を引っさげ、東京、神戸、名古屋で開催された【PUNKSPRING】でヘッドライナーを務めるために来日を果たしたフォール・アウト・ボーイ。約4年間のブランクを経て、より結束が強くなったFOBのベーシストを務めるピート・ウェンツが、新木場STUDIO COASTにて行われた単独公演の前に最新作や自身のレーベルについて熱く語ってくれた。
★『アメリカン・ビューティー/アメリカン・サイコ』リリース時のインタビューはこちら!
あくまでもFOBらしく、自分たちの道理にかなうやり方で、
トレンドを取り入れていくことが大切
――髪の色がピンクになったんですね!
ピート・ウェンツ:そうそう、日本に来るのに合わせて染めたんだ。今、ちょうど桜の時期でしょ。
――お~、なるほど。今回【PUNKSPRING】で名古屋、大阪、東京と回っていますが、オフの時間にはどこかへ行きましたか?
ピート:名古屋では少しショッピングして、今日もちょっとだけショッピングに行ったら、途中で東京スワローズのマスコットに遭遇したよ。
――え(笑)?
ピート:普通に道端にいたんだ。場所はよく憶えてないけど、バッチリ写真も撮った(笑)。明日は野球観戦に行って、お花見に行く予定なんだ。
――今まさにぴったりな時期ですしね。ではインタビューに。カムバック作となった『セイヴ・ロックンロール』リリースしてから約2年という短い期間で、最新作『アメリカン・ビューティー/アメリカン・サイコ』を発表しましたが、こんなにも早く新作が完成するとバンド自身思っていましたか?
ピート:新作は実験だったんだ。ラッパー、DJ、ポップ・スターとかって、ポップ・カルチャーの中で何か起ると、翌日にでも反応して、アクションを起こすことが出来る。今は、飛行機の中でもレコーディング出来るし、それをすぐさま発信できるような環境にあるから。そこで、僕らのようなロック・バンドがポップ・カルチャー史、ポップ・ミュージックにおいて同じことをできるか、っていう実験だったんだ。
――アルバムの方向性は、早い段階で定まっていたのですか?
ピート:そうでもないかな。「Centuries」は、結構早い段階で出来上がっていたから、それを中心に作品を作りたいと思って、作業をスタートした。とは言え、タイトル・トラックの「American Beauty/American Psycho」が出来上がったのは遅かったし、作品の骨組みとなった曲は、ほぼ作業の終盤で出来たものなんだ。
――確かに、タイトル・トラックとなる曲って、制作過程の終盤で生まれる場合が多い気がします。その曲が完成することで作品が繋がり、1つとなるというか。
ピート:うん、そうなんだよね。それと今作は、主にツアー中に書かれ、レコーディングされたものだから、“トラベル・アルバム”って感じもするね。それを可能にしてくれたのはテクノロジーだね。10年前とかだったら、デモとして録音した音をそのままアルバムに使うことは不可能だったけど、今はそれができるから、より速く、スムーズに作業を進めることができる。メールでも曲のアイディアやデータ自体も共有できるわけだし。それに俺とパトリックもお互いの機嫌を損ねないように、とか気を使うことがないから、その点においても作業するスピードが速いと思う。同時に、効率が上がったことで、より安易にトレンドを追いかけることも可能になって、そこばかりに執着してしまう場合もある。でも、現時点で起こってるトレンドを追っている時点で遅いよね。だから、あくまでもFOBらしく、自分たちの道理にかなうやり方で、トレンドを取り入れていくことが大切なんだ。

▲ 「Lost It To Trying」 / Son Lux MV
――前作では多数のゲストをフィーチャーしていましたが、今作はサンプリングを多く使っていますね。スザンヌ・ヴェガとモトリー・クルーは、なんとなくFOBらしいと思ったのですが、「Fourth of July」でサン・ラックスの曲を使っていたのは意外でした。
ピート:あれはパトリックのアイディアだね。セバスチャンと作った曲(「American Beauty/American Psycho」)で、モトリー・クルーを使ったのは俺のアイディアだったんだけど…。ちょっとカニエの「Bound2」っぽいよね。というのも「Bound2」がサンプルしている曲を聴くと、お互いすごく似ているんだけど、カニエの手に掛かることでまったく異なるフィーリングを持つ曲になった。それと似たようなアイディアで、サン・ラックスの曲を使ったんだ。サンプリングの醍醐味って、原曲とかけ離れた曲に使うことにあると思うんだよね。そこから面白いものが生まれるから。
――今の話を聞いて「Uma Thurman」に『ザ・マンスターズ』のテーマ曲をサンプリングしたのも納得できました。これはピートのアイディアですか?
ピート:あれはクレイジーだよね!誰のアイディアだったけな~?あの曲が面白いのは…テーマ曲のサーフ・ギターっぽいリフを色んな人に聴かせた時、みんなにクエンティン・タランティーノの映画に使われてそうって言われた。じゃあ、いっそタランティーノの作品でアイコン的存在のユマ・サーマンについての曲にしちゃうおう、って話し合って、完成させたんだ。
リリース情報
アメリカン・ビューティー/
アメリカン・サイコ
- フォール・アウト・ボーイ
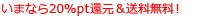
- 2015/01/21 RELEASE
- [UICL-1129 定価:¥2,376(tax in.)]
- 詳細・購入はこちらから>>
- レコチョクBESTでプレイリスト再生>>
関連リンク
サンプリングって、ロック界では
ちょっとしたタブーとして見られているから、
それをやってみることに意味があると思った
――これまでも詞の中で音楽、映画、文学やポップ・カルチャーに触れていますが、それに近い感覚でサンプリングを取り入れようと思ったのですか?
ピート:単純に試してみよう、って感じだった。実は「Save Rock and Roll」でも少しやっていて、元々はフォール・アウト・ボーイの曲をサンプリングしてみようというところからスタートしてる。あの曲には、俺たちの「Chicago Is So Two Years Ago」がサンプリングされているんだけど、自分の曲をサンプリングしたバンドなんて聞いたことないから面白いかな、と思って。で、アルバムがリリースされると「エルトン・ジョンやビッグ・ショーンとコラボしてるけど、次はだれとやるの?」っていう質問を受けることが多かったから、次回作はまた異なるアプローチを取らなきゃダメだ、って感じたんだ。しかも、ずっとツアーをしていたから、そんな時間もなかったし。それにサンプリングって、ロック界ではちょっとしたタブーとして見られているから、それをやってみることに意味があると思ったんだ。
――サウンド面においても、デジタルやエレクトロニック・ミュージックの要素をより取り入れた意欲作となっていますよね。こういったサウンドには、自然と辿り着いたのですか?
ピート:半々ってとこかな。たとえば「Centuries」なんかは、前作の「My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)」の延長線上にあると思うし、もっとさかのぼって「Sugar, We're Going Down」にも共通項があると思う。でもセバスチャンと作った「American Beauty/American Psycho」は、これまでの俺たちからは脱却したサウンドに仕上がってる。俺たちって、稀に“ポップ・アーティスト”っていうレッテルを貼られることがあるけど、そんな中でポップ・アーティストとして筋道が立った、妥当な方向へ進むことを期待されている時に、その反対に進む方がやり甲斐があるんだよね。それが賢明かと言われたら、そうじゃない場合の方が多いけど。あの曲は、そういうことなんだ。変った曲を無理矢理作ろうと思ってたわけではないけど、ぶっちゃけ変な曲だよね(笑)。
――(笑)。今おっしゃった通り、「Centuries」の次にリリースされたのが「American Beauty/American Psycho」で、あの曲に驚かされたファンも大勢いたと思います。
ピート:そう、その時点で「Irresistible」が出来上がっていて、ミュージック・ビデオも完成していたから、それが次のシングルになる予定だったんだ。でも、その間に「American Beauty/American Psycho」が出来たから、じゃあ次にリリースするのはこっちにしようって、話になったんだ。俺的にも「Irresistible」は難なく受け入れられると確信していたから、「American Beauty/American Psycho」をリリースしたことで、みんなを驚かすことが出来て良かったと思ってるんだ。
――ピート自身、これまでまったく聞かなかったような音楽から影響を受けることはありますか?
ピート:他人から見たら、結構意外なものを聴いてると思うよ。ヤング・サグとかドレイクは大好きだし…。
――確かに、ピートってヒップホップをよく聴いてるイメージです。
ピート:そうそう。後は、誰だろ。あ~、名前が思い出せないけど、UK出身のすっごくクールな子がいるんだよね。元々バンドにいたんだけど、今はソロでやってて…ザ・ストリーツをよりレゲエとヒップホップ風にした感じで…。ゴメン、Spotifyを確認しないと思い出せないや(笑)。
――では、映画『ベイマックス』のために書かれた「Immortals」が、どのように誕生したのか教えてください。FOBが初めて映画の為に書きおろした曲ですよね。
ピート:実は、これまで何曲か書いたことがあるんだけど、どれもうまくいったことがなくて…納得するものが書けなかったり、作った曲が気に入ってもらえなかったり、理由は色々あるんだけどね。今回は、監督と打ち合わせして、お互いすごく乗り気だったんだ。しかも監督は、俺と同じ通りに住んでて、隣人だったんだ!『ボルト』も監督してて…知ってる?
――犬が主人公の映画でしたっけ?
ピート:うん、俺の息子があの映画の大ファンでね。曲のアイディア出しをしていて、俺が一番クールだと思ったのが、オタクがスーパーヒーローになる起源を語るオリジン・ストーリーだったこと。しかも、俺たちの曲が起用されたシーンで、まさにその過程が描かれている。制作側からもたくさんのフィードバックをもらって、とてもエキサイティングなプロセスだった。こういうプロジェクトに携わると、完成するまでがまるで地獄みたいだった、とかいう話をよく聞くけど、まったくそんなことはなかった。こんなにも好きなようにやらせてもらえたのは、俺たち自身が映画のヴィジョンを信じて疑わなかったからだと思う。FOBは映画全体にとって、ほんの小さな一部分でしかない。でも自分たちが信じた小さなものが、【アカデミー賞】を受賞し、とても影響力のある作品になった―その一部になれたことは、すごくエキサイティングだし、光栄だね。
――映画は、息子のブロンクス君と一緒に観たんですか?
ピート:一緒に映画のプレミアへ行ったんだ。すごくクールだったよ。普段は…たとえば今日のライブに来てたとしてもステージ脇でニンテンドーDSをやってて、俺たちの演奏には特に感心を持たないと思う。もう何度も観てるし、俺がステージに立ってるだけのことだから。でも、クールな映画の一部だったということには、すごく反応してた。正直、あんなリアクションは初めてだったから、嬉しかったね。
リリース情報
アメリカン・ビューティー/
アメリカン・サイコ
- フォール・アウト・ボーイ
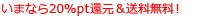
- 2015/01/21 RELEASE
- [UICL-1129 定価:¥2,376(tax in.)]
- 詳細・購入はこちらから>>
- レコチョクBESTでプレイリスト再生>>
関連リンク
若い世代のアーティストの手助けをし、
育成するという行為を非常に重んじている
――映画の世界観とFOBの持つアーティスト性を上手くバランスするのは大変でしたか?
ピート:もちろん。FOBの曲は、第一に…感情をさらけ出している―それも俺たちの視点から。とりとめもない曲もあるし、二重、三重の意味を持つものだったり…まぁ稀に意味不明なものもあるけど、曲の展開も一筋縄ではいかない。今回は、作品のキャラクターの視点から曲を書かなければならなくて、そこが今までとはまったく違っていて、俺たちにとっての挑戦だったんだ。
――先ほど映画の主人公がオタクだと言ってましたが、彼のキャラクターで共感できる部分はありましたか?
ピート:映画の後半で、彼が何度かあらわにした怒りは俺も感じたことがあるから、それらシーンを観た時にはグッときたね。怒りなんだけど、思いやりから生まれた怒り、っていうか。映画の宣伝マンかと思われそうなほど作品を絶賛してるけど(笑)、本当にすごくいい経験ができたプロジェクトだったんだ。

▲ 「Uma Thurman (Wiz Khalifa Boys Of Zummer Remix)」 (Audio)
――オタク=アウトサイダーという点ではポップ・シーンにフィットしないFOBと被る部分もあると思います。FOBは同期だったり、同世代の仲間のようなバンドが少ない孤高の存在ですが、そんな中、活動を続けていく上で葛藤ってありますか?
ピート:不思議な感覚だよね。去年リンキン・パークといくつかショーをやったんだけど、彼らと交流するのは興味深かった。彼らにも同期や同世代の仲間って呼べるバンドはいないよね。元々のジャンルを飛び越え、今は巨大な…まさに“モンスター”ロック・バンドと化したから。そんな彼らの姿勢、謙虚さ、俺たちに接する態度を目の当たりにして関心したね…とてもナイスガイなんだ。
同期がいないと、ツアーをセッティングするのもタフだね。去年は、運良くもこれまで一緒にツアーをしたことがない、俺たちと似た軌跡を辿ってきたパラモアとツアーできた。今夏のツアーの計画をしてた時、ウィズ・カリファがしっくりきたのは、彼はポップとヒップホップ界、俺たちはポップとロック界っていう、両方の世界で活躍するアーティスト同士だから。そういうのを組み合わせたりするのって、面白いと思うんだ。
それと、俺はアーティストが若い世代のアーティストの手助けをし、育成するという行為を非常に重んじている。たとえば、今日前座を務めるニュー・ポリティクスは俺のレーベルに所属している。彼らにしろ、今日ちょうどファイヴ・セカンズ・オブ・サマーのマイケル・クリフォードと話したんだけど…彼にしろ、若手と関係をはぐくんでいくことは大切なんだ。彼らが別にアドヴァイスを必要としてるわけじゃない…みんなクリエイティヴだし、頭も切れるし。でも、自分が20代だった頃に「大丈夫だ。小さいことでクヨクヨするな。」って言ってくれるような先輩アーティストがいたら、どんなに良かっただろう、って思うから。それがなかったから、今までFOBは自分たちだけで何でもやってこなきゃいけなかったんだ。
――話は変わって、アルバムがリークしたにも関わらず、前作よりも好セールスを記録したことには、ぶっちゃけ驚きましたか?
ピート:そうなんだよね(笑)。
――思えば『インフィニティー・オン・ハイ』も発売前にリークしてましたよね…。
ピート:そうそう!今回俺がリークについてブツブツ文句を言ってたのを、みんな勘違いしてて…。リーク音源を聴いてることについて俺が怒ってるって思ってるみたいだけど、そうじゃないんだ。現に俺だってリークされた作品を聴いたり、観たりするからね。まぁ、リリースされたら、そのアルバムだったり、映画を買うけど。何かを極度に好きだと、すぐに聴きたい、観たいって思うのはみんな同じだから。今回のリークについて俺が怒ってるのは、それがタブレットとかを売るのを商売にしてる会社によってリークされたからなんだ。奴らには音楽なんてどうでもよくて、リークしても自分たちの商売には関係ないから何とも思わない。それには、さすがに腹が立つ。自分が絵を描いたとして、それを運んだ業者が絵を真っ二つにして「俺たちは椅子を動かす業者なんだ。」って言ってるのと一緒ですごく苛立たしい。
でも、こういったことにも関わらず、ストリーミングやセールスで好記録を残せたっていうのは、すごくクールなこと。だからこそ、「音楽業界は死に絶えつつある。」なんていう話題が上がった時に、セールスの実数を含め、忘れずに伝えらなきゃ、と思ってることなんだ。世の中が変わっていくと同時に、音楽を発信していく新たな方法も見い出していかないといけないから。
――特にリークに関しては、もう日常茶飯事になってますからね。
ピート:だよね。ドレイクなんか、自分でアルバムをリークしたのも同然で、ミックステープと思いきや、普通のアルバムだったし(笑)。
リリース情報
アメリカン・ビューティー/
アメリカン・サイコ
- フォール・アウト・ボーイ
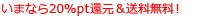
- 2015/01/21 RELEASE
- [UICL-1129 定価:¥2,376(tax in.)]
- 詳細・購入はこちらから>>
- レコチョクBESTでプレイリスト再生>>
関連リンク
彼らのような変わったバンドのためなら、
リスクを冒しても構わない
――ピートは10年前から音楽レーベルを主宰していて、去年<DCD2>として再ローンチしましたよね。今後はどんなアーティストのリリースが控えているんですか?
ピート:うん。ニュー・ポリティクスのアルバムがもうすぐ完成するよ。もう少しでトラヴィー・マッコイのニュー・アルバムも出来る。まだ名前は明かせないけど、すご~く有名な女性アーティストが参加してる(笑)。後は、ロロっていう子がいるんだけど…。

▲ 「Gibberish (feat. Hoodie Allen)」 / MAX MV
――パニック!アット・ザ・ディスコの新作にも参加してた子ですね。
ピート:そうそう、彼女も新曲をリリースする予定で、興味深い主観で曲を書くし、ジャンルに当てはまらないからすごく気に入ってるんだ。後、マックスがフーディ・アレンをフィーチャーした「Gibberish」ってタイトルのシングルをリリースしたばかりで、とてつもなくキャッチーな曲だね。それと、パニック!アット・ザ・ディスコのブレンドンも、曲作りに取り掛かってる。
――これほど移り変わりの激しい音楽シーンで、レーベルを経営することはピートにとってどんな意味合いがありますか?
ピート:確かに、ここ数年間だけでも色々変ったよね…。基本、俺とレーベルのスタッフで運営してるんだけど、これまではラジオ・プロモーションと流通はメジャー・レーベルを通してやってたんだ。その頃の悩みの種は、たとえば曲がバズってきても、まだラジオではかけられないとか、あれはダメだ、これはダメだ、って制約がたくさんあったこと。でも、最初にバズらせるところが一番のハードルで、それをクリアしたのに何でダメなんだよ、って感じじゃん?今は、全部自分たちでやってるから、曲がバズりはじめ、勢いがついたら、そのまま突き進むことが出来る。その点は気に入ってるね。
これまでもずっとそうだったけど、レーベルっていうよりは、仲間っていう感覚なんだ。しかもアウトサイダーばかりが集まった(笑)。業界的な目線からだと、すごく売れたものもあれば、そうじゃないものもある。ジム・クラス・ヒーローズだって、型にはまらないから売れるまで少し時間がかかったけど、徐々にみんながその良さを理解してくれビッグになった。それって、すごくクールなことで、俺は彼らのような変わったバンドのためなら、リスクを冒しても構わないと思ってる。そういうバンドやアーティストを、ポップ・カルチャーに浸透させ、いずれはポップ・カルチャーに影響を与えるまでに育て上げる。その為に様々な方法を模索するのは、やり甲斐のある仕事で、さっきの話にも繋がるけど、若手が抱くクリエイティヴな夢を守るっていうのは、すごく大事なことなんだ。
――そういった面で、FOBのファンはオープンだと感じますか?
ピート:興味深い質問だね。とにかく色々なファンがいるから。俺たちのサウンドが好きだから、パニック!アット・ザ・ディスコも好きって言う人もいるし。でも、俺が思っているよりオープンかもしれないね。そのアーティストが“本物だ”っていうのが理解できれば、チェックすることに抵抗がないんじゃないかな。さっき名前を挙げたマックスは、この前ランシドのティム・アームストロングと2曲ぐらい曲を書いたんだけど、彼はちょっと変わったポップ・アーティストで、まったくパンク・ロックじゃない。でも、このコラボからは、みんなをアッと言われるような、面白い作品が生まれると思ってる。
ただ、正直な話、俺が一つ気がかりなのは…たとえばシャーレの中で何かが育つためには科学反応が起きなければならない。でも、その元の何かがちゃんと育っていない場合、どうなるかってこと。バンドが自分らしらを見つけるまで、1、2枚の作品をリリースする必要がある時もある。ニュー・ポリティクスだってそうだった。でも、今の彼らのサウンド、個性、そしてイメージにはブレがない。これがニュー・ポリティクスなんだ、っていうのが確立されている。だから、そこまで辿り着いていないバンドを評価する時には慎重にならなきゃダメだ。FOBにだってそういう時期があったわけだから。それが確立された時に、つまらないとか、これからもっと聴いてみよう、って初めて判断することが可能になると思うんだ。

▲ 「American Beauty/American Psycho」 MV
――今の音楽業界は、デビュー・アルバムをリリースするタイミングで、アーティスト性がきちんと確立されてないといけない、というのが主流になってますからね。
ピート:そうなんだ!それってクレイジーだよね。だから、俺はインターネットと愛憎関係にあるんだ。だって、そうなったのはネット文化のせいで、バンドを始めたばかりでも、すぐさまオーディエンスがいる環境にさらされるわけだから。今考えてみれば、活動を始めて最初の1~2年間、誰にも相手にされなかったことは、FOBにとって一番の恵みだったのかもしれない。その間に実験して、俺たちはこういうバンドなんだ、っていうのを導き出すことができたから。今の時代、それをやるのは本当に難しい。人と違うことをやろうと思ってたら特にね。
すごく鮮明に憶えてるのは、初めてパニック!アット・ザ・ディスコに会うために、ラスヴェガスに行った時のこと。当時はジャージみたいなハーフパンツを着てて、その辺にいそうなガキみたいな格好をしていたのに、契約して、一緒にツアーをすることになったら、ペイズリー柄のスーツを着て、ステージに出てきた時のギャップ…。その時は「マジかよ?こんな恰好でステージに上がるのかよ。」って、ぶっちゃけ思ったけど(笑)。でも、それは彼らがバンドして作り上げた世界観の一部だった。普通のキッズだった2か月前と全く印象が違ったんだ。この時、アーティストの成長過程を見守るっていうのは、すごく大切なことだと気付いたんだ。
ゼロからスタートして、5000枚を売り上げるアーティストを育てるのは誰でもやれることだ。俺は、ゼロから1万枚売るアーティストを育て、そこから8万枚売れるようなアーティストを育てることを目指したい。ラジオのエアプレイなんかは、その後に考えればいいことだ。大切なのは、そのアーティストを継続的にサポートし続けること。ファレルだってそうだろ。もし彼を長年サポートし続けなければ、「Happy」やダフト・パンクの「Get Lucky」なんかの名曲は生まれなかったはずだ。面白いことを誠実にやるのは時間がかかるプロセスなんだよ。カニエについても、同じことが言える。孵化する時間が必要なんだ。そういったアーティストの成長に携わる人間として、彼らが孵化している間、守ってあげることが重要なんだ。
リリース情報
アメリカン・ビューティー/
アメリカン・サイコ
- フォール・アウト・ボーイ
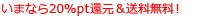
- 2015/01/21 RELEASE
- [UICL-1129 定価:¥2,376(tax in.)]
- 詳細・購入はこちらから>>
- レコチョクBESTでプレイリスト再生>>
関連リンク
関連キーワード
TAG
関連商品


































